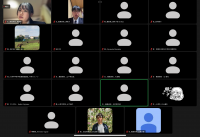AIと教師
地震から 442 日目
豪雨から 178 日目
エキュメノポリスさんの
AI英会話教材の開発に
生徒たちが関わらせていただいています
エキュメノポリスさんは
早大発の研究開発型スタートアップ企業
大学発ベンチャー表彰2024において
『科学技術振興機構(JST)理事長賞』を受賞
EdTech分野で世界から注目を集めています
現在AI技術を活用した英会話教材の開発に
携わっておられ
その教材を本校が活用しながら
改良のためのアイデアを出す
そういったお手伝いをしています
本日オンラインでミーティングが行われて
小津中学校の生徒の皆さんといっしょに
「AIと未来の教師のあり方」について
意見交換をしました
小津中学さんはかなり先進的な取組をしていらっしゃって
参考になることが多いです
本校は始めたばかりで
生徒達も話せる題材がほとんどありません
AIに対して「怖い」というイメージを持っています
それは教員がAIを取り入れた授業を
積極的にしていないからであって
生徒のせいではありません
学校の今後の努力が求められます
それでも自分達の考えをしっかり構築し
話し合いに参加していました
エキュメノポリスさんが開発した教材は
AIのアバターが英語で会話してくれるものです
人間相手だと文法的な間違いが恥ずかしいものですが
AI相手だとそれがありません
実際AIに
生徒の発話中の文法間違いを分析させると
学習が深まるほど
間違いが多くなってくるのだそうです
つまり間違いを恥ずかしがらずに
発話するようになっている証拠です
生徒に
「AI教材のいいところは?」
と尋ねると
「何を言っても不機嫌にならない!」
と答えてくれました
確かにAIは常に優しい笑顔で答えてくれます
でもものごごろのつかないうちから
それしか経験がないと
他人を傷つけてもわからない子が
育ってしまうのではないかと危惧します
人間かAIかという
二項対立ではなくて
両者のいいところを活かし合うような
使い方の研究が必要です
またある先生から
素晴らしいChat GPTの使い方を学びました
その先生は原稿を書いていて
構想に行き詰まったときに
「続き書いて」と
お願いするのだそうです
答えの文章はそのままでは使えませんが
「ああ!そういう視点もあるか!」
と突破口にはなるのだそうです
先日
テストの採点結果に納得いかない生徒が
Chat GPTに聞いた結果を持って
先生に申し入れにいったケースがありました
ところが
「それは Chat GPT の見解でしょ
先生はあきらかに間違いだと思うよ」
納得いかない生徒は他の先生へ尋ねにいくのですが
やっぱりそれは間違い
ようやく納得のいったその子は
「Chat GPT が間違うことがあるんですね」
Chat GPT は正しい文章を作るツールではなくて
耳障りのいいなめらかな文章を作るツールであることを
しっかりと生徒に認識させる必要があるなと感じました
輪島でおすすめのグルメスポットを訊いてみました
以下AIくんからのお返事です
「輪島には美味しいお食事処がたくさんあります
以下はおすすめのいくつかのお店です
1. **輪島市場** - 新鮮な海の幸が楽しめる市場内の食事処
寿司や刺身焼き魚など多彩なメニューがあります
2. **なまこや** - 地元の名物であるなまこ料理が楽しめるお店
独特の風味が楽しめるので興味があれば是非試してみてください
3. **山本屋** - 輪島の伝統的な和食が楽しめるお店
地元の食材を使用した心温まる料理が揃っています
4. **とれとれ市場** - 新鮮な魚介類を使った料理や地元の特産物も販売しているお店
ランチにぴったりのセットメニューも豊富です
5. **寿司処たかしま** - 新鮮なネタを使った寿司が楽しめるお店
カウンターで職人の技を楽しみながら食事できます
これらのお店はどれも地元の素材を活かした料理を提供しているので
訪れる際はぜひチェックしてみてください!」
残念ながらこれらのお店は輪島にはありません
(よく似た名前のお店が県内にある場合はあります)
東京大学の言語脳科学者 酒井 邦嘉 教授は
「生成AI」という呼称が誤解を生みやすいとし
「合成AI」と呼んでいらっしゃいます
AIには人間の脳のはたらきを再現することはできない
いわゆる「もどき」でしかないということです
生徒のみなさん
AIがやっていることは
新しいものを産み出すつまり「生成」ではなく
既存の文章や画像を組み合わせて
つまり「合成」して
それらしく見せているだけなんですよ
10年以上昔の話になりますが
生徒の探究活動で
「モーツァルトの音楽を再現する」
をテーマに研究したグループがありました
彼らがやったことは
モーツァルトの音楽を徹底的に解析して
たとえば「ド」の音の次に続く音のデータを数値化する
「レ」の次にはどの音に移るパターンが多いか
「ミ」の次は?
そのデータに基づいてランダムに音を並べたら
あら不思議
モーツァルトぽく聞こえたのです
驚くべき研究でした
10年前の日本の高校生が
今の「生成AI」を先駆けて
同じ事をやっていたのですね
先生方
AIを授業に使うか使わないか
二項対立ではなく
どの場面でどういうふうに使うのか考えながら使う
このことがAIにはできない人間の仕事です
ちなみに
今回参加した生徒たちに
「AIにはない人間の先生の魅力とは?」と尋ねたら
「あたたかさ!」
という答えが圧倒的に多く返ってきました