
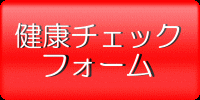

 今年の節分は2月2日です
今年の節分は2月2日です
皆さんご存じでしたか?今年の節分は2月3日ではなくて、2月2日です!理由は、地球が太陽の周りを365日ピッタリではなく、365.2422日で1周しているためです。0.2422日は約6時間弱らしいので、4年に1度うるう年(366日)の日を設けて調整していますよね。(365.2422日×4年=1460.9688日≒1461日。365日×3年+366日=1461日。)さらに、この365日ピッタリではなく毎年約6時間弱長いことで、少しずつですが地球の位置がずれて、立春もズレるらしいのです。(国立天文台が毎年2月に官報で翌年の暦を発表しています)
因みに「立春」。紀元前4世紀ごろの中国で発明された二十四節気(にじゅうしせっき:1年を四季や気候などの視点で分ける方法)の一つで、この日から春がスタートします。当然「立夏」「立秋」「立冬」があって、それぞれの季節を分ける、その前日が「節分」の日となります。ですから本来節分は年4回あるのですが、日本では1年の始まりとしての立春が特に大切にされてきたので、春の節分だけが残ったようです。
平安時代の宮中では、節分の
最近は豆をまくよりも恵方巻を食べるというお家や、「両方します!」というお家が多くなってきているのかなと思うのですが、因みに今年の恵方は西南西です。日を間違えずに、丸かぶりしたいものですね。
余談になりますが、24節気をさらに細分した「七十二候(しちじゅうにこう)」というものがあります。因みに今日までの5日間は「水沢腹堅(さわみず こおりつめる)」。極寒のピークを迎えて沢を流れる水さえも氷となり、厚く堅く張りつめる頃、という意味です。ほかにも71あるのですが、昔の人は自然のなりわいをよく見つめて大切にしていたのだなぁという思いを抱くと同時に、言葉の美しさ、面白さにふと頬が緩みます。時を経ても変わらずに大切にしたいもの…私たちの周りにまだまだ沢山ありますね。
3つの方針
令和7年度
スクール・ミッション.pdf
令和7年度
学校経営・評価計画
→ こちら
本校の校則
R7/4/4掲載
不登校児童生徒の保護者のための支援ガイド
R8/1/7
いじめ防止基本方針
R6/4/1 更新
卒業証明書、成績証明書、調査書の申請について
R6/11/19 申請解説書 改訂
→ 証明書申請
学校感染症による
出席停止願の様式が、
一種類になります
R5/5/2 更新
こちら
金沢市大場町東590番地
TEL: 076-258-2355
FAX: 076-258-3592
E-mail:
