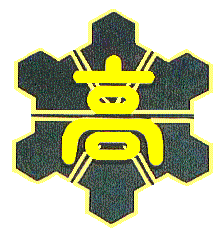 能登半島の付根に位置した「白砂青松」の地
能登半島の付根に位置した「白砂青松」の地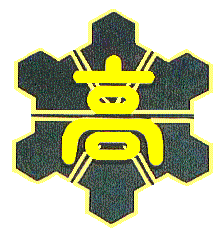 能登半島の付根に位置した「白砂青松」の地
能登半島の付根に位置した「白砂青松」の地

℡(076)281-0068 fax (076)281-0090
メールアドレス
takamatsu-es@school.city.kahoku.ishikawa.jp
第2回学校支援委員会
今回の支援委員会の内容、いただいた意見をお知らせします。このことはホームページだけでなく、来月の学校便り「砂丘」でもご報告します。
今回の議題は、前期学校評価(児童・保護者・教職員アンケート)の結果について。そして、今年度の学力調査についてご報告いたし、ご意見をいただきました。
話合われた主な内容は以下の事柄です。
・学力調査の意義や実施方法、結果によって職員や学校に対する評価になるのか質問が出ました。回答としては実施時期は、新学期早々なので担任個人への評価などとはならないが、学校全体としての教育効果として受け止め、分析改善に努めていることをお話ししました。また、本校の弱点「活用力」をいかにして伸ばしていくかの取り組みについて説明しました。ちょうど昨日付で学校便り「砂丘」特別号が各家庭に届いたいると思います。くわしくはそちらをご覧いただければと思います。学校と家庭が連携して日常生活の中で読書や本物の体験を増やしていくことが大切だと考えています。
・今年度地域と一体になった学習や取り組みが特徴的だが実績や今後の予定についても確認やご助言がありましたた。「社会形成能力の育成」聞き慣れない言葉ですが、将来にわたって地域の中でそこに住む一員として地域コミュニティで目的を持って生活できる力を育成しています。かんたんにいえばふるさと学習です。これまで校外からいろいろな方を招き、体験的な本物の学習を実施しています。来週は4年生が学校のまわりだけで無くかほく市全域にわたってグループ単位で調べ学習を行います。6年生も寒い時期でありますが金沢の検察庁へ学習に出かけます。そしてなにより大きいイベントは「知恵者桜井三郎左衛門」の児童劇公演で校区全戸にチラシが配布され、この話題についても話が盛り上がりました。これまでの経緯について説明もしました。公民館活動とのタイアップ、児童が児童にふるさとの偉人について知らせるとても良い経験です。他にも反戦川柳作家鶴彬や冒険飛行家東善作などについても積極的に学習を進めていかねばなりません。今月25日14時からの初舞台には、保護者のみならずたくさんの観客がおいでると予想しています。
・親学び、地域の教育力、家庭の教育力についても意見がたくさん出ました。
学力とともに体力も大切である。自分で歩く,目的地へ行く,歩くことをもっと推進したらよい。高校生も朝駅に送られているのを見ると「どういう大人にしたいのか,親に作文を書かせてみる」取組なども必要かもしれない。
保護者の教育も課題である。子育て教育を地域の方々と連携してやってもらいたい。11月の授業参観では講演会を行い親子で学んだ。このような取組を大切にしていってほしい。
モンスターペアレントのような学校を悩ませるようなケースはあったか。高松小ではいない。保護者の理解や良識がある。地域と連携していることで誤解も少ない。
各種アンケートは記名式かという質問もありました。アンケート後の対応もあるので記名式で行っています。今後無記名のものも意図的に行いたい。
学力向上について 詩の朗読等効果的な指導法についてもご意見をちょうだいしました。


校内生活・校外生活の決まりについて次の通り指導をしております。
一人一台タブレットの利用にあたり、次の通りルール等のお知らせをしておりますので、ご確認をお願いします。今後利用にあたってのルールの変更等がありましたら、お知らせいたします。
タブレット利用の約束
家庭で利用する場合の約束
かほく市ネットルール
R2年度版_かほく市ネットルール(リーフレット)一括版.pdf
外国語教育CAN-DOリスト
「CAN-DOリスト」とは外国語教育で扱う4技能(聞くこと・話すこと・読むこと・書くこと)ごとに「(英語を用いて)~することができる」という能力記述文によって示した学習到達目標の一覧です。外国語教育での表現の能力と理解の能力において、児童のみなさんに身に付けておいてほしい到達目標を明確にすることで、児童のみなさんが主体的に学習できるように「CAN-DOリスト」を設定しています。
CAN-DOリスト5年生.pdf CAN-DOリスト6年生.pdf
令和5年度学力・学習状況調査結果の概要
令和5年度学校評価
○石川県教育委員会:学びの支援広場 教科別一覧はこちら↓
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/manabi/kyouka/syougakkou.html
○学研:家庭学習応援プロジェクト
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/
○NHK:フライデーモーニング・スクール放送のお知らせ
【NHK資料】「フライデーモーニング・スクール」放送のお知らせ.pdf
○文部科学省:子供の学び応援サイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
○東京書籍:算数プリント「うでだめシート」
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz9263.
○石川県教育委員会:学びの支援広場
