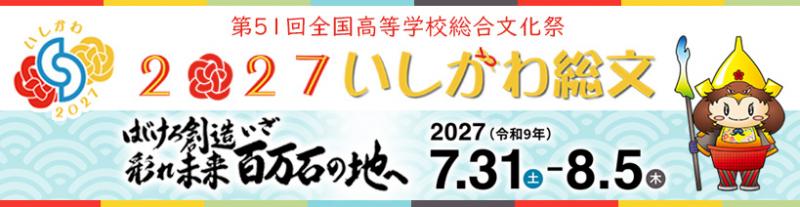日誌
サルスベリが教えてくれたこと
サルスベリが教えてくれたこと
今、伏見高校の玄関では、サルスベリ(百日紅)が青空に映え、とてもきれいに咲いています。サルスベリは中国原産で、江戸時代に日本に伝来したとされています。サルスベリという名は、木肌がツルツルして木登りが得意なサルでも滑るだろうというところからついたそうです。
一体、どのくらいツルツルしているのか、実際に木肌を触ってみました。すると、一様にツルツルではなく、色が薄くツルツルしたところと、茶色くザラザラしたところが入り混ざっていました(写真左下)。ふと、根元に目をやると、木の皮が剥がれ落ちており、一番大きいもので約60㎝の長さでした(写真右下)。まるで脱皮したかのようです。
そこで、サルスベリについて改めて調べてみました。サルスベリは成長につれ、木の皮をどんどん剥がすそうです。皮を剥がし、木肌をツルツルにすることにより、つる植物に取り付かれにくくしているとのことです。ツルツルなうえに、皮がどんどん剥がれ落ちることは、確かにつる植物から身を守ることにつながると思います。
今回、サルスベリの木肌は、どのくらいツルツルしているのか、直接、触って確かめようとしたところから、毎日、目にしているサルスベリについて、改めて調べるきっかけとなりました。
何気ない日常でも、ほんのわずかな行動が新たな発見や疑問、感動につながることを伏見のサルスベリは教えてくれました。
まだ、しばらくは、サルスベリの花を楽しめそうです。木肌もどう変化していくか、花に加えて、木肌の観察も新たな楽しみとなりました。