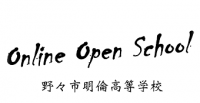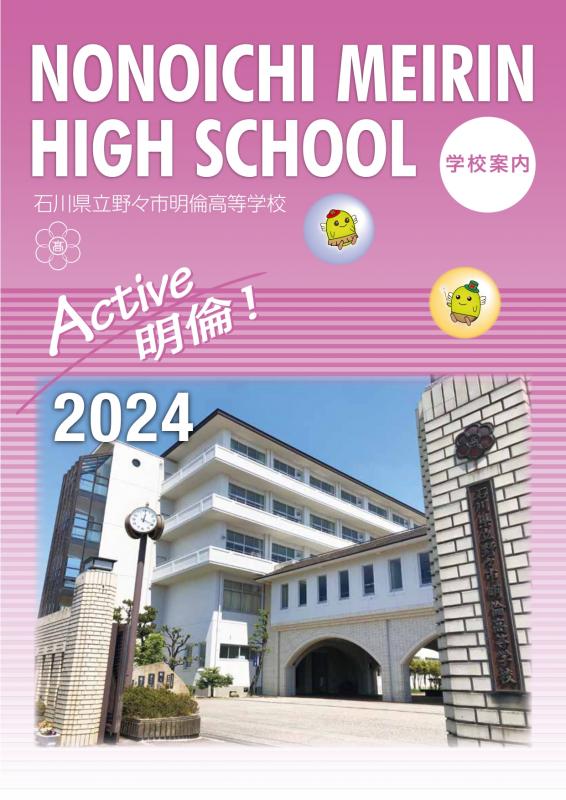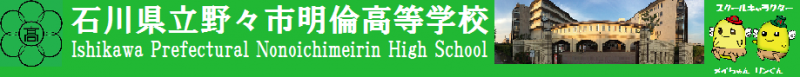 |
|
|
1年生活動記録
STEAM等の教科横断的な授業 15H編
1月30日(木)7限 総合的な探究の時間 15Hでは「数学×地歴」の教科横断型授業を行いました。
タイトルは「TM15」です。TMはタイムマシーンの略です。
日本はPISAの数学リテラシーが第5位になるほど、世界的に見ると
比較的数学が得意な国です。
ではなぜ日本は比較的数学が得意なのでしょうか?そのルーツを
探るためにタイムスリップしました。
-------------------------------------------------------------------------------------------
時は江戸 皆さんは関 孝和(せき たかかず)のことはご存じ
でしょうか?
江戸時代の数学(和算)は日本独自の数学で世界最高レベルでした。
その中で関孝和は筆算を使って円周率を小数第11位まで計算した天才
でした。
ここで数学の先生から問題です。実際に和算に挑戦してみましょう。
班で力を合わせて解くことができました。ここで新たな疑問が…
ではなぜ江戸の数学は世界最高レベルだったのでしょうか?
もっと昔にタイムスリップしてみましょう。
----------------------------------------------------------------------------------------------
時は縄文、場所は三内丸山遺跡です。有名な掘立柱建物ですね。
縄文時代の人はこの掘立柱建物を作るために縄文尺というものを使っ
ていました。下の図は上から見た図です。
「縄文時代の人々はどうやって柱と柱の間の直角を割り出して
いたのでしょう?」素朴な疑問が浮かんできます。縄文尺を利用
して直角を割り出してみよう。班でいろいろ実験してみました。
直角の鍵はどうやら、三平方の定理のようです。
この時代から日本でも3:4:5の図形が直角などの事実が知られて
いたんですね。日本の数学のルーツをたどることができる1時間でした。