
TADA Erementary School


 生き物のつながり…の授業の一環として,ミミズはウンコをするか…と言う問題を出しました。全員が,「食べているからするはず」で一致。めずらしいです。
生き物のつながり…の授業の一環として,ミミズはウンコをするか…と言う問題を出しました。全員が,「食べているからするはず」で一致。めずらしいです。 ウンコの山の近くを掘ってミミズを見つけたY君。さすがです。
ウンコの山の近くを掘ってミミズを見つけたY君。さすがです。  2学期に入って花壇を見てみると,ひまわりは枯れたように垂れ下がり,ヒャクニチソウも花が少なくなってきていました。ワタも花が終わって,まだ,ワタの姿は見えません。
2学期に入って花壇を見てみると,ひまわりは枯れたように垂れ下がり,ヒャクニチソウも花が少なくなってきていました。ワタも花が終わって,まだ,ワタの姿は見えません。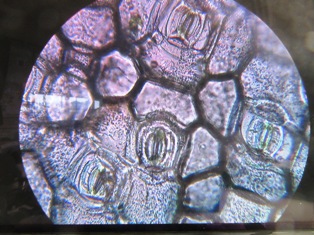 予定していた海水浴が,台風接近による強風と曇り空のためなしに…
予定していた海水浴が,台風接近による強風と曇り空のためなしに… 3年生が,里山里海自然学校の先生方お二人と一緒に生き物観察会に参加しました。
3年生が,里山里海自然学校の先生方お二人と一緒に生き物観察会に参加しました。 人体の学習のまとめに,こんなエプロンを作ってみました。
人体の学習のまとめに,こんなエプロンを作ってみました。