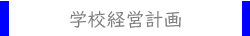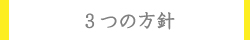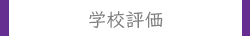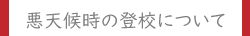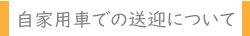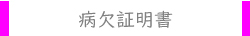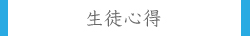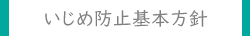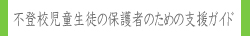1年
【1年生】レジリエンス講座
4月10日(木)1限目、本校のスクールカウンセラーの角地先生により、レジリエンス講座が行われました。
はじめにお話しがあり、その後、軽く体を動かして人間関係づくり。
「学校に早く慣れようと思わなくてよい。自然と慣れてくる」
「自分のストレスに気が付いて」
などの言葉が印象的。
生徒の緊張も、少しずつ和らいでいるようです。
【1学年】遠足
5月1日(水)
1年生が遠足で末広緑地に行ってきました。風が強く少し肌寒い気候でしたが、クラス対抗大繩大会で体を動かし盛り上がったり、お弁当を食べながら友達とゆっくり話をしたりと、それぞれが楽しい時間を過ごしていました。帰り道では少し疲れた様子も見えましたが、最後まで歩ききったという達成感が表情にあらわれていました。
1年生ミニ球技大会
12/18の5・6・7限目の授業は体育を3時間つなげて、1年生全員でミニ球技大会をしました。
生徒たちはバレーとバドミントンの好きな競技を選択し、元気にプレーしていました。
自分のクラスの応援にも熱が入り、とても賑やかな時間となりました。
国語科高大連携授業
11月16日(木)、金沢学院大学文学部文学科の寺田智美先生をお招きし、「〈色〉から読み解く日本の文学とことば」というテーマの講義を受けました。折り紙の色の名前を答えるところからスタートし、「黒」の対義語は「白」か?など、日本語学の入門分野を学習しました。日本語の奥深さに感動したり驚いたりする生徒たちの姿が見られました。今日習ったことを普段の授業にぜひ活かしていってほしいと思います。
地歴公民科高大連携授業
10月26日(木)、北陸大学経済経営学部の松本和彦先生をお招きし、「悪法も法なのかー正義について考えるー」というテーマで高大連携授業を行いました。先生と生徒が対話をする形で、「法とは?」「道徳とは?」「正義とは?」などについて考えを深めることができました。