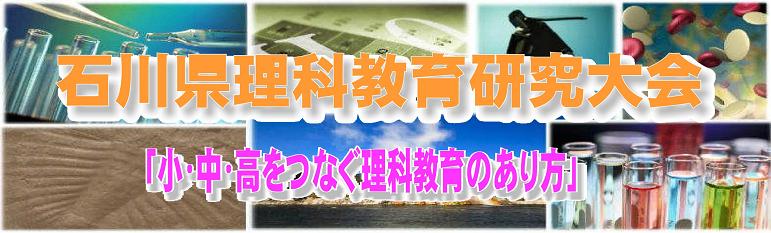第54回 石川県理科教育研究大会 金沢大会
大会主題「小・中・高をつなぐ理科教育のあり方」
副題 ~「深い学び」を追究する主体的・対話的な理科学習~
【副題設定の理由】
2016年6月9日、森田浩介氏を中心とした理化学研究所のチームが発見した113番目の新元素が、「ニホニウム」と命名された。森田氏らは10年近くの粘り強い研究の中で、原子どうしを衝突させる方法や新元素を検出する方法を工夫することにより、100兆分の1の確率であった亜鉛原子とビスマス原子の融合をより高い確率で可能にし、新元素を発見した。この発見は、今までの既成の概念が更新された出来事として世界的に大きく注目された。
さて、改訂が近づいている次期学習指導要領では、資質・能力の3つの柱である「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の育成を目指して、「何を学ぶか」だけではなく、「どのように学ぶか」が大切にされる。そして、そのためには、主体的・対話的な深い学び(「アクティブ・ラーニング」)の視点からの学習過程の改善が求められる。
理科においては、習得・活用・探究の過程で、児童・生徒が自ら理科の見方・考え方を働かせながら、知識・技能を習得したり、思考・判断・表現したりしていくものであると同時に、学習を通じて、「理科の見方・考え方」がさらに広がったり、深まったりしていく「深い学び」が必要である。このような「深い学び」を実現するためには、主体的・対話的な学びが重要である。
主体的な学びとは、見通しをもって粘り強く取り組み、次につなげる学びである。自然の事物・現象に興味や関心をもち、問題を見いだし、見通しをもって課題や仮説の設定、観察・実験の計画を立案し課題解決し、自らの問題解決の過程を振り返って次に生かしていくことが大切である。対話的な学びとは、自分の考えを他者との対話によって広げ、深める学びである。課題の設定や検証方法の立案、観察・実験結果の処理、考察・推論する場面などで、個人の考えをもとに、互いに意見を交換したり、議論したりすることを通して、実証性・再現性・客観性のある科学的なものにすることが大切である。
児童・生徒は、自然の事物・現象について、自分の見方・考え方を用いて、問題解決の過程を通して主体的・対話的に学ぶことにより、資質・能力を獲得するとともに、見方・考え方も成長する。そこで、さらに、獲得した資質・能力や成長した見方・考え方を、次の学習や日常生活などに活用することによって、「深い学び」を実感できる。本大会の副題を『「深い学び」を追究する主体的・対話的な理科学習』とし、以下の重点を設定した。
【研究の重点】
① 自然事物から、児童・生徒が自ら見いだした問題について話し合い、見通しをもって課題や仮説の設定、観察・実験の計画を検討する場面を設定する。
② 話し合いの中で、観察・実験の結果を分析・解釈し合い、仮説の妥当性を検証する場面を設定する。
③ 観察・実験などを振り返って改善策を考えたり、得られた知識や技能を基に疑問や次の課題をもったり、新たな視点で自然の事物・現象を関係付けたりするなどの観点で、学習を振り返る場面を設定する。
④ 得られた資質・能力を次の学習や日常生活に生かす場面を設定する。
公開授業と4分科会では,これらの中から何を重点目標としたかを明確にし,小・中・高の児童・生徒の学びが,発達段階に沿った連続した深まりとしてつながるようにしたい。
令和7年度 第62回 金沢大会「大会要項」をアップしました。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |