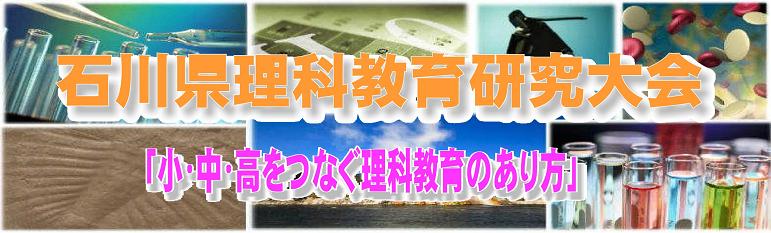第60回 石川県理科教育研究大会 加賀大会
大会主題「小・中・高をつなぐ理科教育のあり方」
副題 ~ 主体的・対話的に関わり合い、深い学びにつなげる理科学習 ~
〔副題設定の理由〕
昨年は、新型コロナウイルスの猛威とともに、地球温暖化の影響からなのか甚大な自然災害に見舞われました。また、世界の平和を揺るがすロシアのウクライナ侵攻やトルコ・シリア大地震の報道に心を痛め、平和な日常生活を取り戻せることを願うばかりです。今年で、関東大震災から100年、阪神・淡路大震災から28年、そして東日本大震災から12年が経ちます。科学者は、現地の状況調査やデータの収集・分析からのモデルに基づいたシミュレーション、ビッグデータ解析・AIによる推論など科学の力で生活の安全・安心に貢献しようと努力をしています。
また、身近なサイエンスとして最近の新聞や報道からは、盗聴防止の量子暗号の強化、新型コロナウイルスを殺菌する光触媒、電池の「リチウム越え」、デジタル通貨での企業決算、mRNAワクチン、カーボンニュートラル、ドライバーモニタリング、人工知能や完全自動運転など、科学が生み出す社会的なインパクトの飛躍的拡大により、サイエンスリテラシーはみんなに必要とされるようになりました。
教育においては、GIGAスクール構想から一人1台の端末が児童生徒に渡り、個別最適な学び、協働的な学びによる、子どもが主役、自分で学ぶ、学び合う教育への転換が進められています。新学習指導要領が2022年で小中高の全てに実施され、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力など」「学びに向かう力、人間性など」をひとり一人の子ども達に、育成していくことが求められています。学ぶ過程の中で、実社会や実生活に繋がる学びに、主体的に取り組み、他者との対話により異なる考えに触れる事で、自分の考えを広め、深める学びを実現していくことが大切となります。このような「主体的・対話的で深い学び」を実現する質の高い授業が必要であり、そのための授業改善が求められています。OECDの調査で、日本の中学生は、理数の学力は世界最高レベルであるが、「理科の勉強は楽しい」、「理科を使うことが含まれる職業につきたい」の割合が、国際的平均に比べ低い結果が出ています。児童・生徒に、自然の事物・現象をどのような視点で捉え、どのような考え方で思考すればよいのかを自覚させながら、実験・観察を進め、主体的・対話的で深い学びにより、お互いの意見を傾聴し、自分の考えを生成する学びの楽しさを実現できる授業実践を行うことが大切であると考え、上記の副題を設定しました。
『研究の重点』
①自然の事物や事象に十分に触れ合い、課題や仮説を設定し、見通しをもって解決することで
学びを深める学習
②理科の見方・考え方を働かせ、理科的な用語を使いながら根拠を明確にし、自分の考えを互いに
説明、表現することで学びを深める学習
③1人1台端末等のICTを効果的に活用し,単元ごとに振り返りなど学びの自覚化と新たな
疑問・課題へ向かう深い学びにつなげる学習
令和7年度 第62回 金沢大会「大会要項」をアップしました。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |