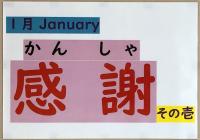学校教育目標
【力いっぱい 声をすませて 心あわせて 学ぼうよ】
〒925-0005 石川県羽咋市滝町ケ14番地2 TEL(0767)22ー7477 FAX(0767)22ー7488
E-mail;seihokudai-e@edu.city.hakui.ishikawa.jp
西北台小学校校歌:https://www.youtube.com/watch?v=85F8xoupbA8
2025年度
【一人一人が輝き出番のある学校 ~ GRIT upで ウェルビーイング ~】
『1~3月』:【学習・生活の振り返り】 凡事更深・グロース アップ をめざして!」
「★ホットなお知らせ★」
2月4日 1年生の作文が「北陸中日 すくらんぶる」に掲載
2月4日 正覚院での豆まきの記事が「北國 石川北」と「北陸中日 能登」に掲載
2月10日 4年生の作文が「北國 地鳴り」に掲載
2月11日 3年生の作文が「北陸中日 すくらんぶる」に掲載
2月19日 スクールカウンセラー来校
2月20日 感謝の集い 6年生を送る会
2月24日 オンライン英会話(1,2,5年生)
2月25日 オンライン英会話(3,4年生)
2月26日 ホクリクサンショウウオ観察会(5年生)
トキに関する講演会(4,5年生)
★3月29日(日) 登校日 閉校式(市)、 閉校記念行事(地域)
羽咋小学校校歌:v=-jYfzM_brqU
★ 貸与タブレット端末が故障・破損した場合の修繕費について R7.4.10.pdf (市教委)
☆ ガラス等破損の修理費 R7.4.10.pdf (市教委)
※ 教員の勤務時間
8:00~16:30(休憩時間:12:35~13:10 16:15~16:25)
☆休業期間中 8:00~16:30(休憩時間 12:00~12:45)