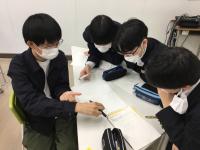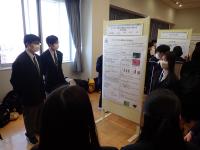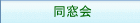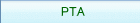理数科お知らせ
SSHだよりの第5号を掲載しました
SSHだよりの第5号を掲載しました。
CS学際科学で卒業生と合同授業を行いました
3月17日(金)の1限に、今春卒業したばかりの理数科の卒業生に来ていただき、合同授業を行いました。1年生と卒業生がコミュニケーションをとり、ともに活動することで、様々なスキルを学ぶと同時に、2年後の自分の姿をポジティブに想像することができました。また、卒業生の、課題や問題に対するアプローチの仕方を目で見て肌で感じることができ、深い考察力や学習意欲が高まりました。
Global Science Leadershipに参加しました
3月18日(土)に福井県立藤島高等学校が主催する「Global Science Leadership」が開催されました。本校から理数科2年生の5名が参加し、英語で発表を行いました。
このイベントは、国際的な研究発表の場を想定し、英語を用いてのプレゼンテーション能力や質疑応答能力を育むとともに、社会的背景の違いによる価値観の相違を理解することを目的としています。今回は、日本および海外における、研究に携わる高校生や教職員が参加し、課題研究の紹介・意見交換を行い、アドバイザーからの助言をいただきました。
本校の生徒達はフィリピンの高校生とZoomを介して交流し、アドバイザーの方からは実験手法や発表をより良いものにするための方法等についてアドバイスをいただきました。
探究の日を開催しました
3月16日(木)に「探究の日」を開催しました。今年度も、講堂での代表グループと各クラスに分かれて全ての生徒が発表する形式で実施しました。さらに、今年度は、発表の他に生徒が企画・運営する場を多く設けました。
発表した全ての皆さん、お疲れ様でした。これまでの研究の成果を十分に発表できましたか?いただいたアドバイスを次回の研究に活かしてほしいと思います。また、講堂行事では10Hの皆さんが司会・進行を、アイスブレイクでは24Hの皆さんが企画と運営をしてくれました。ありがとうございました!
午前は、予選を勝ち抜いた2年生の代表グループの発表を講堂で行いました。代表の生徒達はアンケートや実験の結果を示しながら堂々と発表し、質疑応答も時間いっぱいまで行われました。また、今年度は、卒業生が全体の講評を引き受けてくれました。ありがとうございました。
午後は1・2年生の各発表グループを、学年・クラス・文理をまぜて構成し直した班で活動しました(1班5人)。発表は5回行い、すべての生徒が1回ずつ単独で自分のグループの発表を行いました。各班、身近な問題から疑問を持った点や改善点等を発表し、各班で活発なディスカッションが行われました。
福井県合同課題研究発表会に参加しました
3月11日(土)に福井県県民ホールで開催された上記の発表会に、本校から理数科2年生AI課題研究の「蛇腹班」、「オジギソウ班」、「階段班」、「アドレナリン班」が参加し、口頭発表およびポスター発表を行いました。
このイベントは福井県立高志高等学校主催の課題研究発表会で、SSH指定校をはじめとする、福井県内の課題研究に取り組む高等学校、および研究活動を行う小学校・中学校が研究発表し、研究交流を行うものです。
本校の生徒達は、分野毎に分科会に分かれ、口頭発表を行った後、ポスター発表を行いました。数年ぶりに他県の高校生と交流することができ、意見交換をする貴重な機会となりました。
CS学際科学でフィールドワークの手法を学びました
3月3日(金)3・4限に、石川県立自然史資料館から桂 嘉志浩 先生と嶋田 敬介 先生をお招きし、フィールドワークの手法等についてお話いただきました。また、貴重な標本も持ってきてくださり、休憩時間に様々なエピソードと共に紹介してくださいました。
近畿サイエンスデイに参加しました
2月11日(土・祝)に開催された「近畿サイエンスデイ」(主催:大阪府立天王寺高校)に、本校からは理数科2年生が参加し、「学習時の温度がコオロギの学習能力に与える影響」の研究成果を発表しました。近畿サイエンスデイは、近畿圏のSSH校が課題研究の発表を行う場として、主催の大阪府立天王寺高校が毎年開催しているイベントで、今年度は、福井県立藤島高等学校、兵庫県立神戸高等学校、大阪府立北野高等学校、滋賀県立膳所高等学校、大阪府立天王寺高等学校、そして本校の6校が参加しました。今年度は現地で、他県のSSH校と研究をとおして交流することができました。
SSH公開授業を行いました
2月7日(火)6・7限目に開催された、普通科2年生の「SS課題研究Ⅰ」学年発表会の授業を県内外の教育関係者の方々に対して公開しました。1月31日(火)に開催されたクラス内発表会で決定したクラス代表班が、これまでの研究の成果を発表しました。
【発表班】
29H「音の不快感をなくすには」、27H「見やすい標識とは何か」25H「廃棄牛乳の有効利用について」25H「シャープペンシルの芯の折れにくさに関係する要素」、26H「チョークを気持チヨーク」、29H「海洋漂流ゴミの効率的な処理に関する試案」、28H「体育館で無双する方法」
CS学際科学で企業研修を行いました
1月27日(金)に中村留精密工業株式会社を訪問し、企業研修をさせていただきました。昨年度までは、感染症対策のため10名のみの訪問(30名は学校でオンライン視聴)でしたが、今年は数年ぶりに全員で伺うことができました。現地では2グループに分かれて、会社概要について説明を受け、工場見学をしました。金属加工の現場で数学が使われていることや、プログラミングで工作機械を制御する様子を見学することができ、貴重な体験をさせていただきました。
CS人間科学の特別講義を行いました
1月12日(木)に、金沢大学医薬保健研究域医学系教授の中田光俊先生をお招きし、「脳機能局在と柔軟性」というテーマの特別講義を行いました。脳には体の各部位を司る領域が存在し、その幾つもの領域がネットワーク化して働いていることなどを学ぶことができました。また、覚醒下手術の動画を使った説明もあり、実際に臨床現場でどのように運用されているのかということを知ることもできました。