 白山市立鳥越小学校
白山市立鳥越小学校電 話 076-254-2219 FAX 076-254-8001

 白山市立鳥越小学校
白山市立鳥越小学校
2月27日(月)、白山自然保護センターの平松先生と大田農場の大田さんにお越しいただき、身の回りの自然環境を大切にすることへの思いや、これからを生きる子どもたちに伝えたいことなどを語っていただきました。
これまで学習したことのまとめとして、大切なことを確かめることが
でき、これからどう生活していけばよいか、心構えができたのではないでしょうか。
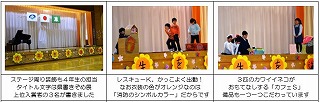


【子どもたちの主な感想】
・苦労することが多かったから、終わった時の充実感がとても大き
かった。
・つらくて「やりたくない」と思ったけど、6年生の喜ぶ顔を見て、がんばってよかった。
・自信をもらえた送る会だった。「一致団結」「協力」の大切さが、本当に分かった。
本当によくやってくれました!あきらめずにやりきった姿、大拍手を送ります!保護者の皆さま、ご参観や励ましのお声かけ、物のご準備等、本当にありがとうございました!

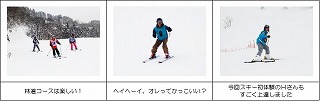
What do you want to be?(あなたの夢は何ですか?)自分の夢を英語で発表しました。ブラッド先生に表現方法を教わりながら、自分だけのスピーチをしました。
みんなの夢が叶うと良いですね。Good luck!


天気にも恵まれ、楽しみにしていたスキー教室は大盛況に終わりました。1人1人が自分の力をさらに伸ばすべく、何度も挑戦していました。
閉講式で集まったときに、楽しそうな表情がたくさん見られて、1日の充実を伺えました。


2017. 6.12 170,000件達成
2017.11.06 200,000件達成
2018. 1.04 210,000件達成
2018. 3.23 230,000件達成
2018. 7.09 250,000件達成
2018. 9.11 260,000件達成
2018.11.07 270,000件達成
2019. 1.04 280,000件達成
2019. 3.21 310,000件達成
2019. 4.02 315,000件達成
2019. 7.09 360,000件達成
2019. 8.29 380,000件達成
2019.12.04 420,000件達成
2020. 5.21 500,000件達成
2020. 7.11 550,000件達成
2020. 8.19 600,000件達成
2020. 9.30 650,000件達成
2020.11.14 700,000件達成
2020.12.22 750,000件達成
2021. 1.23 800,000件達成
2021. 3. 5 850,000件達成
2021.4.11 900,000件達成
2021.5.15 950,000件達成
2021.6. 4 1,000,000件達成
2021.7. 4 1,050,000件達成
2021.8.24 1,100,000件達成
2021.10.7 1,150,000件達成
2021.11.29 1,200,000件達成
2022.1.24 1,250,000件達成
2022.3.18 1,300,000件達成
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |