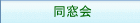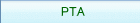|
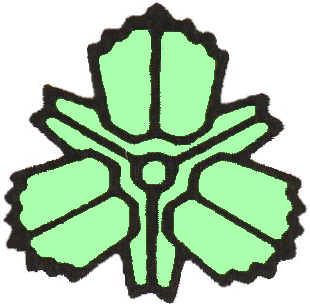 |
 |
|
 |
SGHの活動を紹介します
2年SGコースおもてなしガイド
7月15日(土)に東京外国語大学の留学生に対して、2年SGコースの有志12名がおもてなしガイドを行いました。これに先立って6月28日(水)に実施したおもてなしプロジェクトで作成したプランをもとに、兼六園→和菓子づくり→金沢21世紀美術館というコースを案内しました。留学生たちは大変喜んでくれました。
【感想】
・外国人と話して感じたことは、日本人よりも「なぜ?」「なんで?」という興味・関心が非常に高いということでした。
・自身のことや自身の学校、金沢という町について改めて考えるよい機会を得られたと思う。金沢の観光名所を案内するために自分で調べた際、今まで知らなかった知識を得られた。日本のものを分かりやすく伝えることは案外難しいと実感した。

【感想】
・外国人と話して感じたことは、日本人よりも「なぜ?」「なんで?」という興味・関心が非常に高いということでした。
・自身のことや自身の学校、金沢という町について改めて考えるよい機会を得られたと思う。金沢の観光名所を案内するために自分で調べた際、今まで知らなかった知識を得られた。日本のものを分かりやすく伝えることは案外難しいと実感した。

2年SGコース・エンパワーメントプログラム
7月14日(金)の成果発表会終了後に、2年SGコースによるエンパワーメントを行いました。現在進めている課題研究について、英語で外国人留学生と意見交換を行う機会です。生徒たちが、一生懸命研究について説明する姿、それを真剣に聞いてアドバイスしている姿が見られました。
【感想】
・自分の言いたいことが伝わらずとても悔しかった。原稿を読むだけでなく、質問やディスカッションに積極的に参加できるよう、英語力上げます!“できなかった”から“できた”に変えていきたいです。
・留学生達は私たちのプレゼンの後に、とてもたくさんの質問をしてくださった。いろんな事に疑問を持つ姿勢は学ぶべきだと感じた。

【感想】
・自分の言いたいことが伝わらずとても悔しかった。原稿を読むだけでなく、質問やディスカッションに積極的に参加できるよう、英語力上げます!“できなかった”から“できた”に変えていきたいです。
・留学生達は私たちのプレゼンの後に、とてもたくさんの質問をしてくださった。いろんな事に疑問を持つ姿勢は学ぶべきだと感じた。

3年SGコース成果発表会
7月14日(金)3年SGコースによる成果発表会が開催されました。SGコースが1年半進めてきた課題研究の集大成として、全国の教育関係者・外国人留学生に対して英語で発表を行いました。当日は立教大学の松本茂先生をはじめ、東京外国語大学・金沢大学の留学生も参加してくださいました。参加者からは、「質疑応答での物怖じしない姿勢が素晴らしかった」「各グループがSDGsに合った考察を一貫性をもって述べていた」など高い評価をいただきました。
【感想】
・1年半という長い期間、一つのプロジェクトに取り組むということが初めてのことで、様々な苦難があったが、この活動を通して他の人の力というのはすごいものだと改めて感じた。自分が絶対にできない着想や表現に触れ、自分だけではできなかった経験もすることができた。
・自分の言いたいことを相手に伝えることは母国語をもってしても難しいのに、ましてやそれを外国語でとは、どうしようと最初は困惑しましたが、発表を終えた今、伝えたいという気持ちがあれば相手に自分の考えが伝わると感じました。

【感想】
・1年半という長い期間、一つのプロジェクトに取り組むということが初めてのことで、様々な苦難があったが、この活動を通して他の人の力というのはすごいものだと改めて感じた。自分が絶対にできない着想や表現に触れ、自分だけではできなかった経験もすることができた。
・自分の言いたいことを相手に伝えることは母国語をもってしても難しいのに、ましてやそれを外国語でとは、どうしようと最初は困惑しましたが、発表を終えた今、伝えたいという気持ちがあれば相手に自分の考えが伝わると感じました。

「おもてなしプロジェクト」実施
6月28日、SGコース2年生を対象とした「おもてなしプロジェクト」を実施しました。これは、石川県教育委員会が実施し石川県内の全学校で取り組む「高等学校おもてなし講座」の一環として企画したもので、相手のことを気遣って行動するおもてなしの心への理解や、地域の人々と連携していくことの大切さを学ぶことで、他者と協働しながら社会に主体的にかかわる力の育成を目指したものです。
本校では、7月の「SGコース成果発表会」のために来校する東京外国語大学の留学生をおもてなしするため、金沢市内の観光プランを作成し、実際にSGコース生徒が案内します。
今日は日本旅行金沢支店の千田哲也氏、通訳案内士で外国人を対象として観光ガイドを行っている中井普子氏を講師に招き、北陸新幹線開業後の金沢市のインバウンド需要の状況や、観光プランを作成する上での留意点、外国人観光客をガイドする際の心構えやノウハウについてお話をいただきました。その後、グループに分かれて作成した観光プランをプレゼンし、講師の先生方からの講評やアドバイスをいただきました。
生徒は、留学生をおもてなしするため、様々なコンセプトを設定し、見学地や体験活動を計画するとともに、イラストや英語での発表など工夫を凝らしたプレゼンを行いました。今後、プランの詳細を考え、ガイド当日への準備を進めていきます。
【感想】

本校では、7月の「SGコース成果発表会」のために来校する東京外国語大学の留学生をおもてなしするため、金沢市内の観光プランを作成し、実際にSGコース生徒が案内します。
今日は日本旅行金沢支店の千田哲也氏、通訳案内士で外国人を対象として観光ガイドを行っている中井普子氏を講師に招き、北陸新幹線開業後の金沢市のインバウンド需要の状況や、観光プランを作成する上での留意点、外国人観光客をガイドする際の心構えやノウハウについてお話をいただきました。その後、グループに分かれて作成した観光プランをプレゼンし、講師の先生方からの講評やアドバイスをいただきました。
生徒は、留学生をおもてなしするため、様々なコンセプトを設定し、見学地や体験活動を計画するとともに、イラストや英語での発表など工夫を凝らしたプレゼンを行いました。今後、プランの詳細を考え、ガイド当日への準備を進めていきます。
【感想】
プランを立てるときには、相手が何を求めているのかを考えながらすることが大切であり、私たちの価値観を押し付けるようなプランでは、おもてなしとは言えないということが分かりました。限られた時間でのプランだったため難しかったですが、みんなで協力して立てることができ楽しかったです。
今日の研修を通して「おもてなしとは何か」がよく分かりました。特に日本人が思う日本らしさと、外国人が思う日本らしさが違うのだという言葉が心に残りました。プランを作るときや、おもてなしガイドとして活動するときは「楽しんでほしい」という心を大切にして、日本らしさを考えながらおもてなしを頑張りたいです。

上田高等学校 北陸新幹線サミット参加
6月17日、長野県上田高校が主催し、北陸新幹線沿線のSGH校等12校が集う「北陸新幹線サミット」に、本校生徒9名が参加しました。
はじめはJICA北陸支部長仁田知樹氏、佐久大学長堀内ふき氏からのミニレクチャーの後、分科会が行われ、各校の課題研究のプレゼンと質疑応答、ディスカッションが行われました。また、上田城址公園での昼食交流も行われ、学校の枠を超えた交流も深まりました。
参加した生徒は、他校生の発表に触れるとともに、深い議論を行うなど密度の濃い交流を行い、良い刺激となりました。今後も他県のSGH校と交流し切磋琢磨する機会を設けていきたいと思います。
【感想】

はじめはJICA北陸支部長仁田知樹氏、佐久大学長堀内ふき氏からのミニレクチャーの後、分科会が行われ、各校の課題研究のプレゼンと質疑応答、ディスカッションが行われました。また、上田城址公園での昼食交流も行われ、学校の枠を超えた交流も深まりました。
参加した生徒は、他校生の発表に触れるとともに、深い議論を行うなど密度の濃い交流を行い、良い刺激となりました。今後も他県のSGH校と交流し切磋琢磨する機会を設けていきたいと思います。
【感想】
今回の研究で最も驚いたことは、他校の生徒のプレゼンテーションスキルの高さです。ほとんどの学校が最初に聞き手への問いかけや少しくだけた話から始めて、聞き手の関心を引き寄せるなど、いい雰囲気でプレゼンを始められるようにしていました。また、しっかり聞き手とコミュニケーションをとっていました。みんなフレンドリーで頭の回転が速く、昼休憩でもディスカッションでも遠慮なく思ったことを言い合えました。私たちの発表に対しても新しい視点の新鮮な意見が聞けましたが、もっと聞きたかったです。自分の意欲が高められ、他県に顔見知りができ、とても有意義な時間になりました。私たちをサミットに参加させてくれた全ての人に感謝します。
今日話し合った他県の学生たちは、幅広い知識を持っていて、議論していてとても刺激を受けました。意外にも「平和学習」について知らない人もいたし、自分と同じ年でももう世界で活動しようとしている人がいることに驚きました。このような機会はなかなかないのではじめは緊張していたけれど、段々と緊張もとけてきて発表を聞くのもディスカッションをするのも楽しくなりました。多くの研究を聞けて、発表させてもらえてとても恵まれていると感じました。