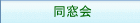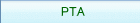|
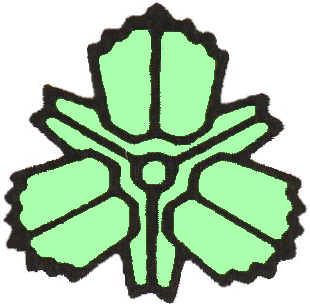 |
 |
|
 |
SGHの活動を紹介します
1年生 SG探究基礎 最終発表会
12月12日(火)の6・7限目に1年生のSG探究基礎の最終発表会を行いました。
半年間かけてグループで協力し実践してきた身近な「ごみ問題」の解決方法や実践内容を、他クラスの生徒に発表しました。
クラスを解体しての発表形式に、はじめは緊張していたようでしたが、回数を重ねるうちに質問や感想を言い合う姿が活発になっていきました。
発表会後に書いてもらった感想の多くに、他グループのアプローチの仕方や様々な解決方法に驚いたり興味を持ったりして聞くことができた。緊張したけど、発表という経験ができてよかった。と書いてくれていました。4分間の発表を堂々と話す生徒の皆さんの姿、質問を積極的に行う様子、さすがだなと感心しました。お疲れさまでした!
【生徒感想】どの班の発表も色んな視点から実施したことや調べたことをまとめていて、柔軟に考えられているのが参考になった。消費者と農家という視点でニーズを分けていたり、メリット・デメリットがよく書かれていて共感しやすかったし説得力があった。質疑応答ではみんな積極的に質問していたし、私も深い質問はできなかったけれど気になったことを聞くことができて考えを深めることができた。雰囲気も良かった。ただスライドを読むのではなく口頭でしっかり伝わるように臨機応変に発表できたと感じた。これからの探究活動でも広い視野を持って情報をわかりやすく発信したい。
【生徒感想】今日他のクラスの発表を聞いて、自分では思いつかなかったアイデアばかりでとても面白かった。オーシャンクリーンアップの影響を受けた、海洋プラスチックごみについてのテーマが多かったが、そのどれも違う切り口・違う解決法を提案していて、一つの問題でも様々なアプローチがあることを実感した。また、プラスチックごみに関係のない話題でも、独自の着眼点があって驚いた。文字が目立たせてあったり、写真やイラストを大きく使ったスライドは目を引くし、わかりやすいなと感じた。また、自信を持ってハキハキ話している発表が内容が頭に入りやすいと思った。
【お知らせ】SGコース課題研究発表会を開催します
本校では、令和元年度に文部科学省「スーパーグローバルハイスクール(SGH)」の事業指定が終了し、それ以降はSGHの取り組みと「いしかわニュースーパーハイスクール(NSH)」の取り組みとを融合し、課題研究を通したグローバル人材の育成に発展的に取り組んできました。
この度、2年SGコースの生徒たちによる「SGコース課題研究発表会」を下記の通り開催いたします。ぜひ御参加いただき、御指導、御助言を賜りますよう御案内申し上げます。
1 目的
SGコースの課題研究の成果を発表することを通して、論理的思考力や表現力を磨くとともに、質疑応答を通した対話によるコミュニケーション力を育む。また、社会に開かれた探究活動の意義や成果について、発表やアドバイザーとの対話の様子を見ていただき、教育関係者にも提示する機会とする。
2 日時
令和6年1月19日(金) 13:05~15:55 *オンデマンド配信あり
3 場所
大会議室および視聴覚室(2階)、iStudio(5階)
4 参加者
2年SGコース生8グループ40名、ゲストアドバイザー8名、企業関係者、教育関係者、生徒の保護者
5 タイムテーブル
13:05~13:15 開会の挨拶、ゲストアドバイザー紹介
13:15~13:25 移動・準備(4グループずつ2部屋に分かれる)
13:25~13:45 発表①(1グループ20分で実施:発表8分、質疑応答7分、アドバイザー講評4分、次の準備1分)
13:45~14:05 発表②
14:05~14:15 休憩(10分)
14:15~14:35 発表③
14:35~14:55 発表④
14:55~15:05 休憩(10分)※全員iStudioに移動
15:05~15:50 アフターセッション(アドバイザーと各グループの対話)@iStudio
15:50~16:00 閉会の挨拶
6 発表テーマ
A班〔食品ロスの軽減に関する研究〕 B班〔規格外野菜の有効活用に関する研究〕
C班〔県内酪農家の応援に関する研究〕 D班〔フェアトレード&TFTの促進に関する研究〕
E班〔在日外国人の教育援助に関する研究〕 F班〔高齢者との交流促進に関する研究〕
G班〔環境配慮と消費者利益に関する研究〕 H班〔ジェンダー多様性の理解促進に関する研究〕
7 オンデマンド配信について
発表の様子を録画し、後日YouTube でオンデマンド配信を行います。参加申込の際、オンデマンド配信の視聴をご希望ください。連絡用に登録いただいたメールアドレスあてに後日、視聴用URLをご案内させていただきます。
8 参加申込
参加は、「当日参観」および「後日動画視聴」を準備しています。
下記URLをクリックし、Googleフォームに必要事項を入力し、参加申込をお願いします。
参加申し込みフォーム:https://forms.gle/ixinbnjTMx8zjUzs6
申込締切:令和6年1月15日(月)
SGHだよりの第5号を掲載しました
今年度の「SGHだより」第5号を掲載しました。
10月~11月までの行事についてとなります。
下記のリンクからお読みください。
https://cms1.ishikawa-c.ed.jp/izumih/SGH%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%AE%A4/SGH%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A
未来を読むプログラム③ 本校卒業生がフェアトレードと途上国支援を語る
未来を読むプログラム「フェアトレードコーヒーでウガンダ農家を救う勝裕くんから学ぶ途上国支援」を11月17日金曜日の放課後に開催しました。講師に招いたのは勝裕遼さん(本校SGコース卒業生、神戸大学大学院生)。フェアトレードコーヒーの販売を手掛ける「ジェバレコーヒー」を立ち上げ、ウガンダの貧困問題と向き合う若き社会起業家です。勝裕さんの特別授業には、1・2年生42名が参加しました。
講演では、勝裕さんが高校時代に考えていたことや、途上国支援を始めたきっかけ、フェアトレードコーヒー販売に乗り出して気づいたこと、今後の展望などを話しました。生徒との質疑応答も盛り上がりました。
【感想】
1年女子
「今まで、アフリカの貧困や衛生環境の問題についてニュースなどで何度も見たことがあり、私も元々の勝裕さんと同じように「かわいそう」という印象を持っていたので、今回のお話で驚くことがたくさんありました。生活が苦しい・お金がないという状況の中でも日々働いて生きているウガンダの方々の姿がキラキラしていて眩しいなと感じました。ジェバレコーヒーでの農家さんのカードを見た女性のエピソードで、こんな小さな興味を持つことからも国際協力につながると気づき、はっとしました。置かれている状況からのただの連想ではなく、“その人自身”と向き合って行動されている勝裕さんのような考え方、視点を持って社会問題を見つめていきたいです。」
2年女子
「最後に探究でフェアトレードに取り組んでいるということで質問させていただいた生徒のうちの一人です。今日は素晴らしいプレゼンをありがとうございました。これまで何人かフェアトレードに関するお仕事をしている方にお話を聞いてきましたが、ビジネスとして成立させている方がほとんどだったので、国際協力の色合いが強い活動をされている方のお話を聞くのは今回が初めてでした。ダイレクトトレードというのは初めて聞いたけれど、より現地の人たちに近い取引の形なのかなと思います。フェアトレードと一口に言っても、活動の上で重要視しているものがそれぞれ違って奥が深いことを改めて実感しました。また、私自身は元々イスラム教圏やインドでの女性の人権問題に関心があって、現地に出向いて直接的に何か活動ができれば、とぼんやり思っていたので、直接発展途上国に出向いて活動しているSGの先輩のお話という意味でも有意義な時間になりました。それらの国に行くことは大きなリスクを伴うとわかってはいますが、今日のお話で現地の人と直接交流してみたいという気持ちが強まったように思います。」
※本校SGH推進室は「未来を読むプログラム」と題した特別授業を開催しています。各方面で活躍する講師の方をお招きし、それぞれの立場から、5年後、10年後、20年後の未来が、どんな世界になっているのか、どんな社会課題が生まれているのか、そのために今何を感じ、何に取り組んでいるのかを語ってもらいます。普段の授業ではなかなか考える機会のない「未来」について生徒が考え、視野を広げ、社会課題の解決を目指す志の種を手に入れてほしいと考えて、企画・実施しています。
1年「先輩に学ぶプレゼン術」、2年「社会人と語る会」を開催
11月3日(金・祝)に、本校OB・OGの社会人や大学生の方々をお招きし、恒例となっている1年「先輩に学ぶプレゼン術」および2年「社会人と語る会」を実施しました。
1年生を対象に行われた「先輩に学ぶプレゼン術」では、東京大学、京都大学、東京外国語大学、神戸大学、金沢大学で学ぶ卒業生たち13名からプレゼンテーションを通じて「大学での学びと自分の将来」について話を聴き、1年生たちは自分たちの先輩というロールモデルから大きな学びを得ました。
2年生対象の「社会人と語る会」では、様々な分野に携わる合計12名の社会人OB・OGの方から「働くとは?」というプレゼンテーションと、それに続けてグループディスカッションが行われました。グループディスカッションでは、講師のみなさんが用意した各職業に関わる「問い(仮説)」を2年生に問いかけていただきました。グローバル化する中で答えを見つけるのが容易ではない課題が今後ますます増えることが予想されますが、生徒たちは10年後、20年後の自分が何をしているか、どこにいるかを思い描きながら、熱心に語り合っていました。
さらに、放課後には第2部として座談会を行い、1、2年生の希望者が大学や高校生活について積極的に先輩に質問する様子が見られました。終了時間が過ぎても個別に質問に行く生徒もおり、盛会のうちに終わりました。
【先輩に学ぶプレゼン術:生徒感想】4人の先輩方のお話を聞いて、プレゼンでは、端的に話すところと詳しく話すところを分けて話すことが大切だと思った。パワーポイントは文字を多く入れるのではなく、写真を中心に入れて興味関心を引き、伝えたいことは目立つように入れることが大切だと学んだ。難関大には、優秀な人が多く自分自身を高められることができるとわかった。今回の話を聞いて勉強のモチベーションが高まったので、まずは基礎固め、特に古文単語や英単語などの小テストから満点をとれるように努力しようと思った。
【社会人と語る会:生徒感想】今回の講義を通して、変化に適応すること、優先度を明確化すること、なりたい自分をロールモデルすることなど働くに当たって大切なことを学ぶことができた。一つの職業に対して様々な役割の人がいて、当然その役割が自分にとってつまらない、面白いの差はあるが、自分の軸をぶれさせず、変化に対して柔軟に対応していくことが大切なのだと感じた。責任をもって一つのことをやり遂げると次の機会につながり、可能性が広がって楽しくなるという意味の「仕事の報酬は仕事」という言葉を胸にこれからも頑張ろうと思った。