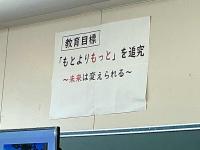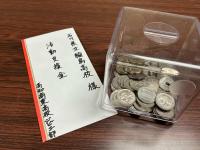校長室より「おこらいえ」
ようこそ!興譲館高校 ご一行様
地震から 668 日目
豪雨から 404 日目
山梨県立都留興譲館高等学校のみなさんが
本校を訪れてくださいました
以前に
本校生徒のアイデアを形にした『応援弁当』と
『能登復興・輪島高校復興祈願竹灯籠製作』
でお世話になった
DJ KOUSAKU さんが
連れて来てくださいました
先日万博のフィナーレで朗読した
正角 心音 さん
実は『応援弁当」にも携わっていて
玄関でKOUSAKU さんと再会を果たしました
万博閉会式の話をすると
「フィナーレ見たよ
櫻井くんと出てたね
実はうちのバンドのメンバーが
『嵐』に楽曲提供してるよ」
とのこと
何?この引き寄せ

自ら希望してきてくださった
心優しい10名の生徒さんと
ふたりの先生方です
ビジネスコース1年生と交流しました
校舎案内のあと
山上 佳織 先生による
防災に関する授業を受けました
グループワークの結果を発表する場面では
両校の生徒で絡みながら発表する
グループも見られました
岡山県立興陽高校さんと開発したバスソルトを
お土産におあげしました
輪島高校の「さかなクン」
伊奈岡克俊 先生の研究授業です
伊奈岡先生は生物が大好きで
いつも楽しそうに授業をする
と生徒から評判で
生物の楽しさを知り
自分も生物学に進みたいという
卒業生を何人も送り出しています
今日は血液型の話です
ゴリラの血液型は全員B型
よく言われますが
実はそれは正確ではなくて
確かにニシローランドゴリラは
全員B型だけど
ゴリラ全種でいうと何種類かあります
というトリビアを導入として
DNAの塩基配列とアミノ酸配列
の関係を学びました
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(18)千枚田の復興
(19)カフェと音楽で輪島を活性化させる
コーヒーは漢字で「珈琲」と書きます
考案したのは幕末の蘭学者
宇田川榕菴(うだがわようあん)です
「珈」は髪に挿す花かんざし
「琲」はかんざしの玉をつなぐ紐
をそれぞれ意味する字です
コーヒーの赤い実が
当時の女性が髪に飾っていた
「かんざし」に似ていることから
つけたそうです
「琲」の王篇を糸篇に変えると
「緋(あか)」になりますし
なんともセンスの塊です
「酸素」「水素」「細胞」なども
彼の命名によります
「酸」の素は実は水素イオンなので
「酸素」は誤訳といえば誤訳
なんですけどね
(20)運動で市民同士の絆を深めよう
被災地でもできるスポーツ
子どももお年寄りも一緒に楽しめる
そんなスポーツを考えています
例えばモルックのような
モルックは
フィンランドのカレリア地方の
伝統的なゲームであるキイッカ(kyykkä)を元に
1996年に開発されたスポーツです。
木の棒を投げてピンを倒す
ボーリングのようなスポーツです
床が傾いている本校の体育館でやると
投げた棒が
ひとりでにコロコロと戻ってくるという
オートマチックモルック場と
なるのでした
今回の発表会はその傾いた体育館で行います
紅白歌合戦を中継した時に
待合室として使用していた場所です
そんなところもぜひご覧になってください
能登で被災した高校生たちはいま
地震から 667 日目
豪雨から 403 日目
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(15)輪島をゆるキャラで盛り上げよう
今では観光地のマスコットとして
全国展開している『ゆるキャラ』
もともとは
イラストレーターのみうらじゅんさん
が考案したものです
『ゆるキャラ』には3つの条件があるそうで
① 郷土愛に満ちた強いメッセージ性があること
② 立ち居振る舞いが不安定でユニークであること
③ 愛すべき「ゆるさ」を兼ね備えていること
ちなみに「マイブーム」もみうらさんの造語
「ゆるい」+「キャラクター」=「ゆるキャラ」
「マイ(私)」+「ブーム(大衆)」=「マイブーム」
既存のものを組み合わせて
新しいものを創り出しているのですね
(16)災害に向けた電源づくり
さあ今回のエネルギー三部作の最後
昨年つまり被災1年目の『街プロ』では
子供やお年寄りの居場所づくりの
探究が目立ちました
今年はエネルギー
つまり被災経験を経て
次の世代へどう繋げるか?
をテーマにしたものが目立ちます
生徒たちの心の持ちようも
少しずつ未来に向かって
変わってきています
(17)ペットと安全に避難するには?
輪島高校では
避難所として
ペット同伴者の部屋を
ひとつこしらえました
ペット同伴避難の実現に向けての活動を
展開されている団体の方の話によると
学校を避難所として運営するときに
ペットを入れると
避難所を閉鎖した後
その部屋に生徒を入れることが
衛生上問題である
という理由でなかなか進まない
という話です
何ら問題がなかったことが
今回実証されましたけど
いかがでしょう?
朝日新聞さんから
「能登で被災した高校生たちはいま」
という動画のLINKをいただきました
https://m.youtube.com/watch?si=tqQGPmWELN0YFEyz&v=YPL9MfEWKdk&feature=youtu.be
24分ほどの動画になります
もとよりもっと
地震から 666 日目
豪雨から 402 日目
東陽中学校の高校説明会に行ってきました
素敵な教育目標を見つけました
「もとよりもっと」
短い言葉の中に
深い意味が込められた
素晴らしいメッセージですね
東陽中学校は
地震はもとより
半年後の豪雨で
甚大な被害を受けた場所です
氾濫した河川の両岸には
おびただしい数の土嚢が
痛々しいまでに積まれています
それでも少しずつ
ほんとうに少しずつですが
前に進んでいます
傾いた電柱の横に
新しい電柱が建てられていました
「もとよりもっと」
よくなりますように
途中の道路
一旦傾きが止まっていたのですが
またひどくなってきています
今日は急に寒くなって
冬の日本海を思わせる荒波です
隆起してできた新しい海岸と織りなす
コントラストは
ドラクロワの絵画のようです
先日「商い甲子園」でお世話になった
藤原美江さまから
すてきな贈り物をいただきました
流木アートでしょうか?
おしゃれなトレイです
11月1日の「MAJIでWAJI活」
街プロ発表会にお越しくださった方で
ご希望の方に差し上げます
またいっしょに活動してくださった
高知商業高等学校ジビエ部と
三重県の青山高等学校のみなさまからも
支援金をいただきました
ありがとうございました
OECD(経済協力開発機構)から
「ティーチングコンパス2025」 が
リリースされました
未来における理想の教員の姿を
描いたものです
本校もご指導いただきながら
作成に関わらせていただきました
ぜひごらんになってください
ポンチ絵も公開されています
世界各国からの参加者一覧です
Wajima High School (JAPAN)
の名前があります!
半島の最先端から
目指せ世界の最先端!!
商い甲子園
地震から 665 日目
豪雨から 401 日目
高知県は安芸市で行われている
全国商い甲子園に出店する機会を
いただきました
発災以来いろいろと
寄り添ってくださっている
藤原美江 先生に
お繋ぎいただきました
藤原先生は
「はりまや橋デザインコンテスト」
でグランプリを取られ
以来この大会の顧問を
務めていらっしゃるそうです
「土佐の高知の播磨屋橋で
坊さんかんざし買うを見た
よさこいよさこい」
江戸時代の
僧侶の「純信」と
少女「お馬」の恋物語
かんざしを買った「坊さん」は
実は「純信」ではなく
「お馬」に横恋慕する「慶全」
さらにはふたりを引き裂くために
嘘の噂まで流します
当時僧侶は妻帯が禁止されていたため
噂が広まり捕まるのを恐れ
「お馬」と「純信」は駆け落ちしますが
結局捕まりふたりは引き裂かれます
そんな悲恋物語の残る高知
そのお隣の安芸市での商い甲子園です
開会式で入場行進
四国の高校を中心に全国から集まりました
出店のみなさんをご紹介します
高知中央高等学校さん
近森産業さんとコラボしての
カツオ香る高知の揚げ餃子です
高知県立檮原高等学校さん
ワイン用のブドウで育てた高知牛
廃棄食材で作った
フードロスにも配慮したカレーです
高知県立山田高等学校さん
香美市の三谷ミートさんの
大人気の手羽先とチューリップです
高知県立安芸高等学校
「あきこう防災特別課」のみなさん
被災地のために
募金活動をしてくださっています
高知県立宿毛高等学校さん
OBである「豊ノ島」関の
ご実家のお豆腐です
愛媛県立西条高等学校さん
商業科で経営するお店「めぐみソムリエ」
たぬきまんじゅうがおすすめです
全部紹介したかったけど
時間がなくて
回りきれませんでした
私は会場の一室を借りて
能登半島地震での経験を語る
講演会をさせていただきました
会場には地震の悲惨さを物語る
パネルも展示してくださっていました
アキ市だけにアキない甲子園
かと思ったら
もっと深い理由がありました
安芸市は岩崎彌太郎氏の生誕地
世界に名だたる
現在の三菱グループの礎を築いた
幕末屈指の経済人です
彌太郎は30代で「土佐商会」に務めます
土佐特産である
樟脳や和紙そして鰹節
それらを売り
軍艦や武器を買いました
彌太郎は
坂本龍馬ら海援隊の
給料の支払いも行ったそうです
現在輪島高校は
「三菱みらい財団」さんから
採択されて資金援助を受けていますので
生徒のみなさんは胸をはりましょう
我々は
坂本龍馬が給料をもらっていた人と同じ人から
資金援助を受けています
龍馬も我々も
日本の未来をつくっちゅうぜよ
帰路につきました
目の前に太平洋が広がります

アンパンマン電車も走っています
高知駅のホームはオシャレです
なんかヨーロッパにこんな感じの
なかったですか?
福岡第一高校さんでの「パラマ祭」で
頑張っている様子を
岡本先生が知らせてくださいました
生徒たち疲れも見えますが元気です。
朝食のバイキングでプリン2泊とも3つずつ
計6個食べた生徒がいます
昨日の様子をお知らせします
パラマ祭1日目
10時からの開場を目指し
福岡第一高校さんに向かいました
今回のパラマ祭では
きゅうりのバスソルト
とまとのバスソルト
藤のバスソルト3種類を販売します
これらのバスソルトは
輪島高校の生徒が
県外の高校 大学そして企業と
コラボして作ったものです
前日福岡に到着してから
ホテルで手分けして袋詰めしたので
自分たちで準備したからか
商品に対して愛着を感じているようです。
福岡第一高校さんの生徒会メンバーの力も借りながら
販売しました
みなさんの頼もしいこと!
お客さんに声をかけてくれたり
商品の説明を丁寧にしてくださったりしました
買ってくださる方の中には
能登の状況を聞いてくださる方や
「応援しています!」と声をかけてくださる方が
たくさんいらっしゃいました
今回「ペットと災害」について探究しているチームの
パンフレットも持参しました
ペットを飼っていてもいなくても
興味深く聞いてくださり
当時の状況も聞いてくださいました
せっかくパラマ祭に参加させていただいたので
今後の輪島高校のイベントの参考にするために
校内を散策もさせていただきました
輪島高校生徒会長の北村くんは
スマッシュブラザーズ大会に参加しましたが
結果は惨敗
勝てそうな要素は全くなかったそうです
ステージではたくさんのパフォーマンスが
披露されていました
今回のパラマ祭に向けて
みなさん準備をされているらしく
盛り上がりがすごかったようです
前回夜の体育祭でお邪魔した際にも感じましたが
福岡第一高校のみなさんは
それぞれが全力で学校行事を楽しんでいる様子です
自分の「好き」をつきつめ
表現している姿がとてもきらきらしていました
輪島高校も
そんな自分の好きを形にできる学校になると
いいなと感じました
どうでもいい話ですけど
新幹線の前の座席の網に
フリーペーパー戻す時
角っこが折れ曲がって
「イーッ」てなりませんか?

パラマ祭
地震から 664 日目
豪雨から 400 日目
福岡第一高校さんの「パラマ祭」に
お招きいただきました
個性教育の一環として展開されている
「パラマ塾」の成果を発表する学校祭です
『パラマ塾』は
「個性の伸展による人生錬磨」を具体化させた
個性の育成を目的とした
ユニークな塾形式の授業です
生徒一人ひとりが持つ「個性」を
引き出し伸ばし育てることを
目的としています
都築 仁子 校長先生のご挨拶より
「Parama とは
サンスクリット語の
『Parama-alta』
即ち「第一義諦」の略です
仏教語です
校名の由来となりました
個性の意味です
本校には福岡はもとより
全国そして海外からも
毎年多くの個性を持った
高校生が集結します
それぞれが
夢や希望の実現に向かって
パラマ塾を居場所にして
常に新しい自分
本当の自分に向かって挑戦し
それぞれが目指すものを
確実に手にしてほしいです
素晴らしいパラマ塾です
今年もアクティブな成功を祈っています」
福岡第一高校さんは
能登半島地震直後の
1月から数ヶ月間
寒空の下募金活動に立ってくださり
本校へと支援してくださいました
それ以来ずっと寄り添って
くださっています
一年間の活動の集大成の場ということで
圧巻のクオリティーです
生徒会の生徒をお招きいただき
『輪島塾』として
仲間入りをさせていただきました
環太平洋大学の大池教授のご指導ものと
岡山県の興陽高校さんと共同開発した
バスソルトの販売をしてきました
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「街プロ」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(12)囲碁ボールで輪島を明るく
碁盤に見立てた人工芝マット上で
木製スティックで白黒のボールを操って
五目並べを行うニュースポーツです
兵庫県氷上郡柏原町(現在の丹波市)で
町おこしのために1992年に
考案されたものだそうです
囲碁の勝負によって領地争いを解決した
という故事が同町にあることが
考案のきっかけとなっています
(13)積雪発酵発電
積雪発電とは
太陽熱や廃熱などの熱源と
積雪による冷熱の温度差で
発電する仕組みです
発酵発電とは
発酵によって生じた
メタンガスを燃料に
発電する仕組みです
このグループは
このふたつを組み合わせることを考えた
ということでしょうか?
(14) 心も輪島も未来も明るくしよう
昨年度花火を打ち上げたグループの
流れを汲む活動です
冬の夜を彩る
イルミネーションをつくります
「まちを明るく元気にしていくこと」
「参加・交流の生まれる活動にしていくこと」
「資源循環や観光の要素も入れていくこと」
を意識して動いています
博多での販売を応援した後は
高知での販売の応援に向かいます
吉野川の美しい渓流です
大歩危小歩危の山あいを抜けます
アンパンマン号も走っています
ごめんまちこさんが迎えてくれます
明日は安芸市で開かれる
「商い甲子園」に参加してきます
奥尻島も忘れないで
地震から 663 日目
豪雨から 399 日目
佐賀で開催された
全国音楽教育研究大会
フィナーレでふたたび
全員でフェニックスを大合唱しました
全国の多くの先生方から
励ましのお声をかけていただきました
北海道からお越しの
今金中学校の 清水 桃子 先生
奥尻中学校の 塩原 祐馬 先生と
お隣になり
いっしょに歌いました
奥尻島といえば
平成5年に発生した
北海道南西沖を震源とする
マグニチュード7.8の
地震によって発生した津波が
わずか2分後に到達して
奥尻町だけで 198人もの
死者・行方不明者が出た場所です
先日も別の機会に
奥尻島ご出身の先生とお会いしましたが
「世間は阪神淡路大震災以降
東日本大震災や
熊本地震などよく取り上げるけど
阪神淡路の2年前に起こった
私たちを襲った悲劇のことも
忘れないでほしい」
とおっしゃっていたのが
心に残っています
【今日のDeep Purple】
教科を超えた授業実践を紹介し
深い教科横断型授業を作り出すコーナー
今日は国語と商業の教科横断です
授業者は
電話が鳴る前に
かかってくることを予知できる
高森まどか先生
テーマは
「メールの書き方を学ぼう!」
書き方を学ぶ前に書いたメールを
全員で見ながら
良い点と良くない点を考えました
「件名」はあったほうが良いことや
長すぎると見ずらいこと
また最初に名乗ったほうが良いことに
気づきました
そのあと
商業と国語表現の教科書を
見比べながら
ビジネスにおけるメールの
一般的なルールについて学びました
その後日程調整のメールを例に
スムーズなやり取りにするには
どうすればよいか考えました
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(9)高齢者といっしょ
〜心も身体も健康に〜
75歳以上を後期高齢者
65歳以上を前期高齢者
と呼ぶそうですが
初期高齢者の私は
後期高齢者並みの記憶力が自慢です
最も得意とするのは
用事があってある場所に来たのに
着いた途端用事を忘れてしまい
思い出そうと元の場所に戻ってみても
用事があったことすら忘れてしまうことです
これが私が心身共に健康である
元気の源となっています
周りは迷惑していると思いますが
(10)こども食堂について
子どもが一人でも安心して利用できる
無料または安価な食堂です
食事の提供だけでなく
子どもたちの「第三の居場所」として
学習支援や多世代交流の場としての
役割も担っています
(11)らくして防災
〜防災 × AI〜
防災が大切なのはわかっていても
なにを準備していいのか?
食品の消費期限が気になったり…
そんな不安や面倒を
一気に解決するアプリを開発中です
今回の発表会は
オンラインでもご覧になれます
お楽しみに
呼子の朝市
地震から 662 日目
豪雨から 398 日目
朝日新聞さんから
本校卒業生のその後を追った
ドキュメンタリー動画の
リンクを送っていただきました
デジタル版記事もあります
https://www.asahi.com/articles/ASTBM12QNTBMDIFI01FM.html
呼子(よぶこ)の朝市に行ってきました
佐賀県にある100年の歴史のある朝市です
港に隣接していて
水揚げしたての海の幸を扱います
輪島朝市も港と直結して
セリ体験などやってもいいですね
堤防も利用して釣り体験とセットにして
自分で釣った魚をその場で食べるとか
港にはズラッとイカが干してあります
輪島でこれやると
たちまちトンビにやられるかも
ここにはトンビいないのでしょうか
透き通ったイカ刺しが名物です
今朝は水揚げがなかったので
メニューの看板を見て我慢
輪島でもできそうですね
おそらくこれは水揚げしたイカを
生かしておくための生け簀
買った海産物を焼いて食べる
バーベキューコーナーもありました
アワビ250円〜
サザエ200円など
結構リーズナブル
ただし土日のみの営業なので
こちらも断念
道端でおばちゃんがサザエを焼いています
特大のもので1個 850円
これは結構なお値段ですね

こちらはイカの天ぷらを揚げたてで
8個ほど入って 500 円
観光客は「いろんなものを食べたい」
と考えているはずなので
ボリュームを落として
価格も下げるべきだと思います
昔ながらの土壁の家屋が続きます
クジラ漁の親方の屋敷を見つけました
この辺は昔はクジラ漁がさかんでした
漁の時期は12月から始まり春先まで
出漁の前に親方の家に集まり
酒を酌み交わしたのだそう

建物を活用して
中は資料館になっていました
輪島朝市にも震災を伝える
資料館があるといいですね
火災で消失する前は
輪島塗職人の伝統的な家屋が
あったんですけどね
阪神淡路大震災の時には
「しあわせ運べるように」
東日本大震災の時には
「群青」
傷ついた子供たちを励まし
未来に向かって歩き出すための
素敵な合唱曲が生まれました
私たちにも合唱曲が欲しい!
生徒や保護者の皆さんから
声が聞こえるようになりました
そんな時です
合唱作曲家の弓削田健介先生が
能登を訪れて
「被災地の子どもたちの
心の声を紡いで
合唱曲を作りたい」
とお申し出があったのは
そうして生まれたのが
合唱曲「フェニックス」です
今日は佐賀で
全日本音楽教育研究会全国大会
平たく言えば
日本中の音楽の先生方が集まる会で
弓削田先生の講演会
というよりコンサートがありました
最後にフェニックスを会場で大合唱
その時にステージの上から
指揮をさせていただきました
全国の音楽の先生の
会場を震わせる歌声に感動しました
会場では録音撮影が
禁じられていましたので
雰囲気をお伝えすることができず
残念です
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(6)能登のまいもんを広めよう
「まいもん」とは「美味しいもの」
海の幸山の幸からスイーツと
美味しいものの宝庫です
どんな「まいもん」を
紹介してくれるのでしょう
(7)タービンで輪島に灯を
被災地の子供達にとって
何日も電気が来ないことは
大きなストレスでした
ですので
今年の研究発表には
エネルギー問題についてのものが
多くあります
(8)災害による栄養状態の変化を改善したい
被災地では
お年寄りがトイレに行くのを億劫がり
飲食をしなくなるケースが多くあります
また若い世代においても
仮設住宅での調理が
困難極まることから
適当に済ますことも増えます
そんな状況に解決策を提案します
英語の研究授業を研究する
地震から 661 日目
豪雨から 397 日目
生徒と雑談しました
「7時間全部奥野先生の授業ならいいのに!」
「どうして?」
「だって奥野先生
授業のゴール示してくれるし
ゴールしたらそこで授業終わるし」
「他の先生は?」
「2分ほど余ってもいきなり
小テスト入れたりして
時間ギリギリまで引っ張る」
「最大限に学んで欲しいんじゃ?」
「でも授業の内容終わっとるし
集中力切れとるし
全く意味ないと思う」
「じゃあそれ先生に伝えてみたら?」
「ダメやと思う」
「どうしてかな?」
「俺らうるさくするから?」
自分たちでもわかっているようです
私も現役時代は
この生徒たちと同じことを考えていて
終了のチャイムが鳴っても
授業のまとめをしている先生を
「アホちゃうか
生徒が早よ終われ思てんのに
意味ないやろ」
とどんなに話が途中でも
チャイムと共にサッと終わって
生徒の貴重な休み時間を
1秒たりとも奪わない
そんな努力をしていたものです
キレイに授業をまとめたいのは
教員のサガではありますが
生徒が聞いていないのでは意味ないのです
最近では
「教師がなにを教え込んだか
ではなく
生徒が何を学んだかが大切」
という考えが主流になっています
生徒が言うように
授業の目的達したんだから
そこで授業終わればいいようなものの
「教員は給料もらって働いているのだから
授業をサッサと切り上げて
給料分働かないのは
契約違反だ」
といった問題も絡んでくると
ややこしくなってきます
こういった社会の問題について
生徒と教員とで
じっくり議論する時間も
必要なのかもしれません
しかしながら
教育と経済は
必ずしも相容れないものであって
例えばアメリカの研究で
こんなのがあります
アメリカは結構思い切った
教育に関する実証実験をするお国柄で
ある州で
教員の給料を完全出来高払いにしたそうです
進学実績に基づいて
教員の働きぶりを査定し
結果を出した教員を優遇したそうです
教員のモチベーションが上がり
優れた教育効果をもたらすと
期待されていたのですが
結果は
アメリカの教育施策上
最大の失敗のひとつとなりました
なぜか?
学校がこれまでにないほど
荒れ出したのです
教員の指示に対して
「へん!どうせ自分の成績上げたいだけだろう」
「俺たちに言うこと聞かせれば
自分の給料上がるからな」
全く従わないようになってしまいました
教育の世界に
費用対効果だとか
経済の原理だとかは
決して持ち込んではならないという
教訓とすべきです
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(3)ヤマメ大捜査線 in 輪島
環境DNAを調査して
輪島の川にヤマメがいないか
調査しています
生物は体表から剥がれた細胞や糞を
環境中に放出します
河川水中に含まれるDNAを分析することで
そこにどんな生物が住んでいるか特定できます
捕獲する必要がないので
生物や環境への負荷が少ない技術です
(4)神戸震災学習ツアー
かつての被災地神戸を視察して
30年間どのように復興してきたのか
自分の目と足で学んできました
30年経った今だからこそわかる
復興の成功と失敗
その教訓を能登の復興に活かします
(5)スポーツで健康 〜訪問型ジム〜
スポーツが大好きなのに場所がない
このグループでは
自分たちでジムを作ろうと
行政にかけあうなど
さまざまな活動を行い
多くの困難にぶつかってきました
そして今
訪問型ジムという
新しいスタイルのジムを考えました
発表会では
落成したての仮設校舎の
内見会も予定しています
内田洋行様にご支援いただいた
フリーアドレス制の職員室も
ご覧になれます
ぜひのお越しを
【今日の震災新採5】
震災の地に赴任となった
5人の新採者を紹介するコーナー
外国語科の加藤先生の
初任者研修の研究授業が行われました
授業はAll English でテンポよく
教師と生徒のトークが繰り広げられました
こんな授業ならもっと英語好きに
なっただろうなと思いました
特にいいなと思ったのは
教師から日本語の例文が提示され
即座にペアで英語に直す活動
ただ今回の授業では
教員が指名したひとりの生徒の英文しか
全員でシェアできず
その他のペアは
自分たちが作った英文について
合っているのか間違っているのかわからず
モヤモヤするのではと思います
そこで
AIを活用したこんなアプリどうでしょう
もし既にあったら教えてください
全ペアで話している例文を
マイクで拾います
現在門前高校とのオンライン授業で
使用している機器では
教室の一番後ろの席の生徒の
雑談まで拾えるので充分可能だと多います
拾った音声は全て
即座にスクリーンに投影されます
すると全てのペアで作られた英文を
全員でシェアできるのです
その際AIが
文法的な誤りなどを修正して表示します
すると間違った本人は
間違いに気づき
文法的に正確な英文を学べる上に
間違えたことは他の生徒に知られないので
間違いを恐れず話す習慣がつきます
ただ同じような文章ばかり集まっても
面白くも何ともありません
そこで教員に発問力が求められます
「彼は午後三時に駅で彼女を見かけた」
みたいな
他に訳しようのない例文ではダメです
生活に密着し
なおかつ汎用性の高い文章
例えば
「先生遅えな」
主語をどうするかだけでも
何通りも作れるし
そこに一言自分で付け加えるよう指示し
「先生遅えな 何してるんだろう?」
「先生遅えな 忙しいんかな?」
「先生遅えな 時間守れって言うとるくせに
自分が遅れるってどうなん?」
みたいに自由に生徒が作文すると
一気にボキャブラリが増えて
楽しいと思います
集まった例文はそのまま保存されて
いつでもアクセスできるようにしておけば
家庭学習にも使えます
木犀の花咲く頃に故郷へ帰りたいな
地震から 660 日目
豪雨から 396 日目
校庭の金木犀が香る頃となりました
タイトル何のフレーズかわかりますか
「日生のおばちゃん」の歌です
この秋の佳き日
体育祭が開催されました
保護者の方もお越しになり
元気いっぱいの姿を見ていただきました
とはいえグラウンドには
仮設校舎がもうじき完成
生徒席のすぐ後ろに
工事用のフェンスが
限られたスペースに
トラックを斜めに描く
というアイデアできり抜けます
不便なら不便なりに
アイデアが湧くものです
普段のことを普通通りにしようとするだけで
生徒も先生も考える力が
鍛えられる
おもしろい環境です
種目も工夫を凝らしてあります
運動が得意ではない生徒も
みんなが楽しめるような
工夫が散りばめられています
生徒会の生徒が
福岡第一高校さんの
夜の体育祭を見て刺激を受け
趣向を凝らして
種目設定をしてくれました
グラウンドの隅っこには
野球のブルペン
以前の屋根付きのに比べると
雨の日は使えませんが
できることをやるだけです
こちらもがんばりましたよ
陸上部が自分たちでこしらえた
お手製の砲丸投げ練習場です
ここで練習して
北信越大会出場を果たしたって考えると
ほんとにがんばったなって
感動します
こんなスペック
地震から 659 日目
豪雨から 395 日目
用事があって進路指導室に行きました
授業中なので先生は
国語科の高森まどか先生だけでした
私が入室するやいなや
何か用事があるかのように
高森先生はおもむろに立ち上がり
歩き出しました
するとちょうど電話の呼び出し音が鳴り
高森先生は受話器を取り上げるのでした
通話を終えると
何事もなかったように自席へと
「あれ?何か用事あったのでは?」
と問いかけると
「電話が鳴ったので出ただけです」
いやいや
電話が鳴ったのは
あなたがが立ち上がって歩き出したあとです
どうやら
電話が鳴る前に音が聞こえるという
特殊なスペックをお持ちのようです
電話が鳴ると
誰からの電話かピンとくることありませんか?
それを超えた特殊能力のようです
もうすぐハロウィンですね
英語科の矢田勇先生の
奥様とお子さんで
カボチャのランタンをつくって
高校に飾ってくれました
発災以来ずっと寄り添ってくださっている
福岡第一高等学校さん
文化祭に輪島高校も
出店させていただけることとなりました
福岡第一高校さんの文化祭は
「パラマ祭」といいます
ここには
「パラマ塾」という
部活動のようでちょっと違う
生徒が自分の意思で
好きなことを極める
そんな活動があります
氷川きよしさんは
ここの「演歌塾」で
その才能を開花させました
それぞれの塾が
その輝きを発揮する場が
「パラマ祭」です
「輪島塾」として出店します
環太平洋大学さん
岡山の興陽高校さんと
コラボして開発した
バスソルトを販売してきます
震災後にできた
いろんな絆にホント感謝です