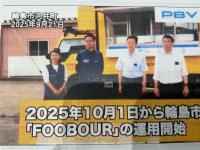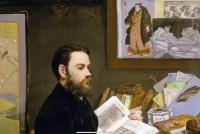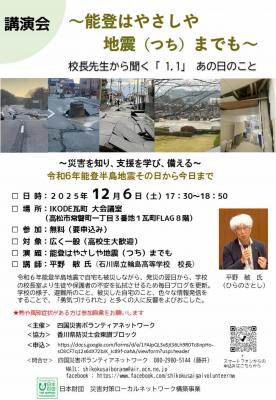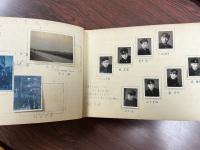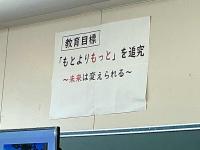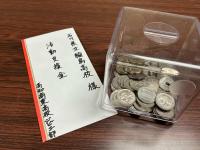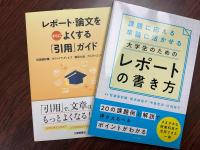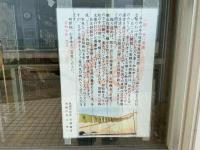校長室より「おこらいえ」
心も輪島も未来も
地震から 720 日目
東日本大震災から15年
震災の教訓を共有し
復興の知恵を次世代へつなぐため
「新しい東北」官民連携推進協議会
「東北3県石川県合同セミナー」が
地場産業センターで開催されました
本校から
小住 優太 さん
川口 はるひ さんが
パネルディスカッションに参加し
復興の途上にある能登地域の現状や課題に
東日本大震災で培った官民連携の知見を重ね
対話を通じて
今後の地域間連携のあり方を
共に考えました
東北からは
岩手 福島 宮城 の3県から
参加いただきました
発表者からのメッセージです
【岩手県】
釜石の奇跡は偶然ではなく
日ごろの訓練と教育の結果によるものだった
苛酷な避難所生活を経て
自分の身は自分で守る意識が変わった
【宮城県】
語り部活動を体験して
軽い言葉では片付けられない
命の思いを感じた
ハード面の復興だけでなく
心の復興つまりソフト面こそが重要であり
それは人々の思いによって支えられている
【福島県】
現地の経営者の方々を見て
福島は元に戻すのではなく
新しい仕事や価値を作るフェーズにあると
知りました
被災地と言う言葉の裏にある
子供の強さと前向きさに圧倒されました
自分で生きることに
誇りに思って選択している姿が印象的でした
【岩手県】
震災の記憶を持つ最後の世代として
これだけは伝えたいこととして
「他人事にしないこと」
自然にはかないません
ネットで見た気にならず
実際に現地に行って空気を感じてください
行けばわかります
【宮城県】
私たちは震災を知らない世代への
繋ぎ役とならなければなりません
過去の悲しみをただ怖がるのではなく
未来の命を守るための教訓として
私たちが語り継いでいく責任があると感じています
【福島県】
地元に戻ることも離れることも
自分の選択として尊重されるべきです
福島には挑戦する人を応援する土壌があります
地域に関わる事は特別なことではなく
自分の暮らしを大切にすることです
発災以来寄り添ってくださっている
金沢大学
能登里山里海未来創造センター長
谷内江 昭宏 先生から
「能登地域の復興の現状と課題」
についてお話がありました
先生は実はご専門は免疫学
細胞に例えて
こんなお話をしてくださいました
「健康な細胞には
表面に無数の小さな突起があります
写真左側です
この突起がなくなると
アポトーシス
つまり細胞の死を迎えます
写真右側です
今回の能登半島地震で
半島の先っぽの小さな突起のような場所に
多額の復興資金をかけることに
何の意味があるのか
と言う議論がありました
今の能登半島の姿は
将来の日本の姿です
そのことを忘れてはなりません」
輪高生のアイデアが
街に灯りをともしました
「心も輪島も未来も明るくしよう」
『イルミネーションプロジェクト』
本日点灯式が行われました
場所は錦川通りと本町通りです
みんなでカウントダウンしました
温かい飲み物などの
振る舞いも行われました
灯したランタンは
生徒がデザイン・制作したもので
被災地の瓦礫を
大成建設様のご協力を得て
成形し直したものです
たとえ倒壊した家屋であっても
そこにある瓦礫や割れた瓦一つひとつ
その家主の持ち物なので
勝手に持ち出しては犯罪です
そこで今回は
公費解体した我が家の瓦を
活用しました
焼けた朝市通りの隅っこで
街を全焼から救うべく
炎を食い止めた我が家の瓦
生徒たちの手によって
新たな命を吹き込んでもらいました
ありがとう
他のいろんな街の
豪華なクリスマスイルミネーションに比べると
ちっちゃなイルミネーションですが
生徒たちそして
寄り添ってくださっている方々の
思いが詰まった
とても大切な灯りです
朝市の焼け跡は
このイルミネーションがなければ
午後5時でこんなに真っ暗です
パリへのミッション
地震から 719 日目
昨日も『街プロ』で
さまざまなアイデア出しをしました
アイデアを出すための9項目をまとめた
オズボーンのチェックリスト
というものがあります
① 転用:他のものや別の用途で使えないかを検討します
② 応用:過去の例や他のアイデアを取り入れ応用します
③ 変更:一部を変更することで新たな価値を見出します
④ 拡大:対象の大きさや長さを拡大できないか検討します
⑤ 縮小:対象を小さくできないか検討します
⑥ 代用:別の材料に変えられないか臨機応変に考えます
⑦ 置換:レイアウトや順番を入れ替えます
⑧ 逆転:向きや順番・時間・役割をひっくり返します
⑨ 結合:別の何かを組み合わせて新しいものを生み出します
探究活動の際にぜひ実践してみてください
とある財団に
本校が申請していた新規事業が採択され
来年1月にパリに行けることとなりました
さてここで研修参加メンバーに
『フランス渡航前事前ミッション』
が課されました
「ミッション インポッシブル」ではなく
「ミッション ポッシブル!」です
研修に参加する生徒以外のみなさんも
楽しくいろいろ調べたり
発想を飛ばしたりしてください
【ミッション1】
能登の復興〜伝統産業を世界に売り込めるか?!
「日本文化をビジネスに結びつけるには?」
「世界に響く日本文化の伝え方は?」
について自分なりに考えてみてください
『輪島塗』の世界展開を目指す田谷漆器店様と
たまたまパリで逢うことにしています
『輪島塗』で世界ビジネスに勝負するには?
真剣に考えてみましょう
以下のふたつの事例から
いろんな視点で教訓があるかと思います!
事例1)西陣織で世界で勝負
〜失敗続きから、発想の転換して成功した事例〜
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00716/00001/
https://diamond.jp/articles/-/285048?page=2
他にも自分たちで調べてみましょう
メゾンエオブジェに出展した最初は
全く契約に結びつかなかった経験を経ています
「海外出展」はゴールではなく
そこから「本気の暗中模索」が始まります
事例2)子どもからお年寄りまで日本文化大人気!
〜「海外に人気の日本文化」と
「日本人として感じる日本文化」に差はあるか?〜
https://franceparisinfo.hatenablog.com/entry/paris-acclimatation-japan-lights-2025-2026
日本全体に興味ある海外人口を
能登復興に取り込めるか?
その場合どんなアプローチがあるか?
自由に「問い立て」含めて考えてみましょう
【ミッション2】
OECD本部教育スキル局アンドレアス局長
OECD日本政府代表部 佐藤 一等書記官
に会いに行って
もっともっと能登復興に巻き込もう!
「OECD本部」と「OECD日本政府代表部」の違い
調べてみましょう
そしてOECDやOECD政府代表部を訪問する
「意味/意義」を考えてみましょう
どんどん希望が拡がっていきますね
すばらしい研修旅行になりそうです
いろんな百周年
地震から 718 日目
全商簿記北信越大会に
本校より平野唯人さんが
出場することとなりました
団体枠のほかに
個人で出場できる枠があるのですが
県大会を見事勝ち抜いて
出場権を勝ち取りました
土曜日に長野県で行われます
校長室で
激励金をお渡ししました
健闘を祈ります
さて今年は実にたくさんのものが
100歳を迎えています
【日本相撲協会】
1923年の関東大震災で
両国にあった初代国技館が
甚大な被害を受けました
相撲は復興の象徴のひとつとなり
国民の心の拠り所として発展しました
被災した経験と再建の努力は
2年後の日本相撲協会誕生へと受け継がれ
復興へのエネルギーの象徴となりました
【NHK】
関東大震災は
「ラジオ放送の誕生」を決定づける
重要な出来事でもありました
通信網が寸断され
「情報が届かない」ことの
甚大な被害を目の当たりにした逓信省が
災害時の迅速な情報伝達手段として
放送の必要性を痛感し
ラジオ放送を始めました
命を救うメディア『ラジオ』は
のちのNHKとなるのです
【雪印メグミルク】
関東大震災により
多くの国民は貧しい食生活を
送らざるを得ない状況となりました
国として
「栄養価の高い乳製品を拡めよう」
という方向に舵を切り
乳製品の輸入を始めたのです
それは国内酪農家への大打撃となりました
「自分たちが牛から絞った牛乳を
自分たちで加工して販売しよう」
という目的で集まった酪農家たちにより
雪印乳業の前身である
北海道製酪販売組合が誕生したのです
【ブルボン】
関東大震災が発生した当時
お菓子工場は関東近郊にしかなく
震災で地方への供給がストップし
子供たちがおやつを食べることが
できなくなってしまいました
とある新潟県にある和菓子屋が
「地方にも菓子の量産工場が必要だ」
と設立した「北日本製菓」が
ブルボンの前身です
当初は栄養価があり保存が利くビスケット
つまり保存食の製造から始め
やがて全国展開していくのです
【トヨタ】
関東大震災の際
鉄道が壊滅的な被害を受け
輸送手段として自動車が大活躍しました
大地震による火災から
多くの人命を救出したのも自動車であり
震災の後始末から復興事業まで
トラックが全面的に使われました
贅沢品と見られていた自動車は
実用品として
その公共性・利便性が
広く理解されるようになり
自動車の輸入が激増しました
そんな時代背景の中創業した
のちに自動車部となる自動車製作部門を持つ
豊田自動織機製作所は
来年百周年を迎えます
(トヨタ自動車は自動車部の設立をもって
創立としていますので百周年はまだ先です)
【山手線】
甚大な被害を受けた鉄道整備も始まりました
その混乱と焼失を機に
現在の「環状」山手線の原型が整備されました
都市交通網の近代化が一気に進みました
今年百周年が集中しているのは
偶然ではなく
関東大震災から立ち上がる
力強い人々の証なのです
日本人はこうやって
災害のたびに何度も何度も立ち上がり
そのたびに素晴らしいものを
築きあげてきたのですね
関東大震災からちょうど100年が過ぎた
最初の元日に起こった能登半島地震
我々だって負けてられません
今日朝市のまちづくりに関する
打ち合わせを持ちました
朝市も立ち上がりますよ
今までの良さを残しつつ
新しい朝市を目指します
こども家庭庁実施事業である
「こども・若者分科会」が
わじまティーンラボさんを会場に
開催されることとなりました
またあの日が来ます
地震から 717 日目
お店にお正月用品が並び始めると
たとえ大人の私でも
2年が過ぎ去ろうとしている今でも
なんだか心がザワザワしてきます
スクールカウンセラーの板本 淳子 先生から
生徒のみなさんにメッセージです
「大 き な 出 来 事 ・ つ ら い 出 来 事 か ら 、 、 1 ヶ 月 、 1 年 な ど の 節 目 に 、 こ こ ろ や 体 が い つ も と 違 っ た 状
態 に な る こ と を 節 目 反 応 と い い ま す 。つ ら い 反 応 で す が 、 た く さ ん の 人 に 起 こ る 、 普 通 の 反 応 で す 。
多 く の 場 合 は 、 し ば ら く す る と の 心 と 体 の 状 態 に 戻 る 事 が で き ま す 。
か ら だ :な ん だ か 気 持 ち 悪 い ・ 頭 が 痛 い ・ お 腹 が 痛 い ・ く ら く ら す る ・ 息 が し に く い ・ト イ レ に 何 度 も 行 き た く な る な ど 。
気 持 ち : 何 も し た く な い ・ 食 欲 が な い ・ 眠 れ な い ・ イ ラ イ ラ す る ・ す ぐ 怒 っ て し ま う ・何 と な く 不 安 ・ い な く な り た い ・ 悲 し く な る な ど 。
行 動 : 物 を 叩 い た り 投 げ た り す る ・ ソ ワ ソ ワ す る ・ い つ も で き る 事 が で き な い な ど 。
そ の 他 :何 も し て い な い の に 涙 が で て く る ・ 車 が 通 っ た り し て 揺 れ る と 怖 い な ど 。
こ の 他 に も 、 い つ も の 自 分 と 違 う と 思 っ た ら 、 そ の こ と を 大 人 に 話 し て み て く だ さ い 。 お か し な
こ と で も 、 恥 ず か し い こ と で も あ り ま せ ん 。
心 が け て ほ し い こ と
・ い つ も 通 り の 生 活 リ ズ ム で 過 ご し ま し ょ う ( 食 事 ・ 遊 び ・ 学 習 ・ 睡 眠 )
・ 楽 し い と 思 え る こ と を し ま し ょ う
・ 大 人 と 一 緒 に 過 ご す 時 間 を 持 ち ま し ょ う
・ 気 持 ち を 話 せ る 人 は 、 大 人 に 聞 い て も ら い ま し ょ う
・ 無 理 を せ ず 、 つ ら い 時 は 「 つ ら い 」 と 言 っ て い い で す
・ 安 心 で き る 大 人 と 一 緒 に 過 ご し ま し ょ う
節 目 と は 関 係 な く 、 今 も 反 応 が あ る 人 、 こ れ か ら ず っ と 後 に な っ て 反 応 が 出 る 人 、 ま た 反 応 が 長
く 続 く 人 な ど 、 人 に よ っ て そ れ ぞ れ 反 応 は 違 い ま す 。
気 に な る 事 が あ れ ば 、 気 楽 に 、 相 談 室 に 来 て く だ さ い 。
受 験 を 控 え て い る 人 も い ま す ね 。 頑 張 っ て く だ さ い !」
今輪島市では
子どもたちが
犯罪に巻き込まれるリスクが高まっています
元々のんびりした田舎で
犯罪とは程遠い平和な場所なので
そこで育った『おぼこい』子たちは
すぐに他人の言うことを信じてしまうので
犯罪に巻き込まれたり
さらには知らず知らずのうちに
加害者になってしまう危険性もあります
『おぼこい』とはこちらの方言で
純粋で穢れを知らないと言う意味です
石川県警の
中西 裕也 様
清谷 柚子 さまが来てくださり
『防犯教室』をしてくださいました
『闇バイト』ならぬ『闇犯罪』
『SNS』に関する問題
困ったことがあれば
迷わずに相談しましょう
奉納の舞
地震から 716 日目
福岡で教室をされている
『ユカリクラシックバレエ』代表
光永 ゆかり さま
同じく福岡で活動されている
『なないろハーモニー』の
指揮者 稲永 恵子 さま
ピアニスト 黒瀬 明子 さま
コーラス 國友 むつみ さま
そして運転手兼陰のラスボス
太田 俊隆 様
が学校にお見えになりました
『なないろ』といえば
今朝美しい二重の虹が出ていましたね
ほんの一瞬でしたが
北陸の冬の始まりの朝は
しょっちゅう虹が見えます
二重の虹は
ダブルレインボーと呼ばれる
非常に珍しい現象で
見られる確率は約1%ほどと言われています
『主虹』とよばれる内側の虹は
色の並びが通常の虹と一緒
外側から 赤→橙→黄→緑→青→藍→紫
ところが『副庭』外側の虹は色の並びが逆で
外側から 紫→藍→青→緑→黄→橙→赤
二重の虹の間を見ると
ほんのり薄暗くなっています
これを見ると幸せになれるそう!
これはアレキサンダーの暗帯と呼ばれています
さてご一行さまは
先日先々日と珠州などを訪れ
本日重蔵神社へ向かわれる途中
お立ち寄りくださいました
重蔵神社では歌と舞を奉納なさいました
『ユカリ』さん『なないろ』さんとは
弓削田健介さんによる
合唱曲『フェニックス』が御縁です
合唱曲で全国を繋いだ動画で
歌ってそして踊ってくださっています
重蔵神社の禰宜さまより
能登復興祈願のステッカーをいただきました
なるほど
能登半島は龍の形をしているんですね
そして重蔵さんは
その龍眼に位置します
仮設校舎での授業が始まって1週間
さまざまな課題満載の中
教員も生徒も試行錯誤しながら
それでも一歩ずつ前へ進んでいます
調理実習もはじまりました
思えば水道の通っていない旧校舎では
水汲みからしていましたね
その時に比べると
ほんと恵まれた環境です
以下家庭科の 山上 佳織 先生からの報告です
「お皿は地震でたくさん割れてしまったので
カレー皿やお椀も使い工夫して
ローストチキン
コンソメジュリエンヌ
苺サンタクロースケーキ
を作りました
生徒たちは
「先生〜ありがとう〜美味しかったよ〜」
「うめ〜また食べたい〜」
と目をキラキラ輝かせて
調理室を去っていきました
高校での家庭科の単位数は少ないですが
記憶に残る授業になっていたらいいな
と思う今日この頃でした」
水汲み体験も含めて
きっといい思い出になって
生徒たちの心の中に
輝き続けると思いますよ
それにしても
コンソメジュリエンヌって
名前からしてオシャレやな
人生で一度も食べたことないわ
山上先生は
文部科学省より
今年度の優秀教員に選ばれました
被災地での
先進的な遠隔授業の実践も含め
その高い授業力が評価されてのものです
おめでとうございます
明日 17日 夕方
HAB 北陸朝日放送 にて
本校の卒業生のその後を追った
ドキュメンタリーが放送されます
18:15 からの番組の中
18:25 過ぎから5~7分間の放映です
ぜひご覧ください
蔦重逝く
地震から 715 日目
江戸のメディア王「蔦屋重三郎」を描いた
NHK大河ドラマ「べらぼう」が
最終回を迎えました
小芝風花さん演ずる花魁『瀬川』との別れ以来
実は私はなかなか見れなかったのですが
久々に最終回を見ることができました
わずか10ヶ月で140点以上もの作品を残し
忽然と姿を消した謎の絵師『東洲斎写楽』
番組では絵師集団として描かれていました
バンクシーみたいですね
そうだとすると
前期と後期で作風がガラリと変わることも
短期間で多くの絵を残したことも
説明がつきますね
なるほど
川に落ちて消息不明となった『唐丸(からまる)』
彼が実は『写楽』で
いつか蔦重が窮地に落ちいたった時に
助けに来るんだとばかり予想していたのですが
彼はのちの喜多川歌麿でした
東洲斎写楽の正体には諸説あり
現在最も有力とされているのは
阿波徳島藩お抱えの能役者
『斎藤十郎兵衛』説です
役者の内面をえぐるような大胆な筆致と
極端なデフォルメは
当時の役者からは不評だったようですが
そんな日本人離れした感性の持ち主は
オランダ人絵師『シャーロック』であった
というのが私の一押しの説です
これから新しい発見があったら
明らかになっていくのでしょう
これが『歴史』の醍醐味です
さあその江戸時代
なんだか色々興味が湧いてきたので
いろいろ調べてみました
まずは蔦重の本のお値段は?
新刊本は300文
今の値段にして4,950円
結構しますね
でも写真集と思えばそんなもんか
浮世絵は1枚32文
今の値段で528円
これもそんなもんですかね
江戸の宿泊代は
1泊2食で48文(4,092円)
やすっ!!
中国人が大量に押し寄せていた
少し前の日本での
1杯40,000円の海鮮丼
(築地で実際に見た!)
に比べれば驚きの安さですね
「中国人は所構わず
でっかい声で騒ぎまくる
でもそれは文化の違いである
常に他民族による
侵略の危機に晒されていた中国では
他の人に聞こえないように
ヒソヒソ話すると
クーデターを企てていると思われるから
「私たちは何も隠し事はありませんよ」
アピールのため
わざと他人に聞こえるように
大声で話すのです
中国人にしてみたら
他人に迷惑かけまいと小声で話す日本人こそ
不気味な存在に見えるのです」
ということは以前このブログにも書きましたが
最近では
大声で話す人に「シーッ!」と
互いに注意しあう中国人同士の姿を
見かけるようになりました
きっと「日本の文化ってこんなんですよ」
って紹介するガイドブックやガイドさんが
増えてきてるんだろうなって感じています
他国の文化を理解しあって
尊重し合うってとっても素敵なことですね
『世界平和』
防災講座
地震から 714 日目
仮設校舎に受験生が集って頑張っています
金沢大学で
「探究・STEAM フェスタ」が開催され
本校から3名の1年生が参加しました
金沢大学では
教科横断型の探究学習を通した
高大接続・高大連携の取り組みを
推進されています
今回は「高校生の探究心に火を灯す」
特別企画です
大学生とのリアル探究トークを通して
新たな学びを得て
将来に向けてのきっかけとなりました
私ごとですが
先日受験した防災士試験
合格することができました
晴れて防災士として初めて
防災講習に参加しました
輪島市避難所運営研修会です
ピースボート災害支援センターさんが
主催してくださいました

ピースボート災害支援センターさんは
国内外の災害支援と
防災・減災を専門にする公益法人です
まずはコーディネーターの
辛嶋 友香里 さまから
様々な知見をいただきました
まずは避難所の運営主体は
避難者自身であること
その意識を持つことの大切さ
避難所で繰り返し起こっている
3つの課題があります
① 「場」の課題
衛生環境 安全管理 情報共有など
② 「人」の課題
安否確認 要配慮者 生活再建など
③ 「運営体制」の課題
環境整備 運営者も被災者 など
これらの課題を解決するには
避難者一人ひとりが
自主的に考え行動することが大切です
次に簡易ベッドの大切さ
単に寝心地の良さかと
これまで認識していたのですが
睡眠時の頭の高さを
床から35センチ離すことに
大きな意味があるそうです
それだけ違うだけで
温度が10℃も違ったり
床から舞い上がる埃やウィルスが
激減することがその理由です
今回の能登半島地震では
186ヶ所の避難所が開設されました
これは全国的にみても
例のない多さなんだそうです
今回は
避難所で実際に暮らした方
あるいは避難所運営に携わった方
そんな方が集まって
避難所で実際にあったあるあるを
語り合うことから始めました
6つのグループに分かれて
テーマに沿って
「次はこうしたい」
経験を踏まえたアイデアを出し合いました
【洗濯】
◯ 発電機の設置
◯ 男女別の物干し場
ただしその際娘を持つシングルファーザーなど
解決すべき課題は多い
【食事】
◯ 好き嫌いがある人は自分で備えるべき
【情報】
◯ 掲示板を充実させる
◯ 電波状況を改善する
◯ 情報弱者への配慮
【入浴】
◯ 入浴情報の周知
◯ 入浴用の送迎車両
◯ 要介護者用風呂
◯ 介護シャワー用車両
【寝床】
◯ テントを張ってのプライベート確保
◯ 枕とシーツの支援
今回得た知見として
しっかりと将来へ伝えていく
責任を感じました
またピースボートさんは
平常時のひとり親家庭支援と
災害時の迅速な職の支援を両立する
フェーズフリー型キッチンカー
「FOOBOUR(フーバー)」の運用を
10月から輪島市でも始めたそうです
これは
平時には
食品・日用品を24時間取り出し可能な
無人車両として
地域のひとり親世帯の支援をします
そして災害時には
キッチンカーとして
温かい食料を提供できるものです
輪島市では発災前は
1800人に3食分の備蓄しかなかったものを
今回の地震を受けて
13000人に対して3食2日分に
増やすそうです
ふるさとプレコン最優秀賞!
地震から 713 日目
「ふるさとプレゼンコンテスト」に
参加してきました
場所は KANDA SQUARE
開始までしばらく時間がありましたので
じっとすることと
長い話がことのほか苦手な私は
例によって
会場付近をうろちょろするのでした
上野東照宮へ行ってみました
家康危篤の床に呼ばれた
藤堂高虎と天海僧正
「末永く魂鎮まるところに祀ってほしい」
との遺言に則って建てられたのが
ここ上野東照宮です
元々は藤堂高虎邸敷地だそうです
こちらは国指定重要文化財の『唐門』
日光東照宮『眠り猫』で有名な
左甚五郎(ひだりじんごろう)作による
昇り龍・降り龍の彫刻が左右にあります
偉大な人ほど頭を垂れるということから
頭が下を向いている方が
昇り龍なんだそうです
諫鼓鳥(かんこどり)の透かし彫りも見れます
これは中国の皇帝が門の前に太鼓を置き
政治に誤りがある時は人民にそれを打たせ
訴えを聞こうとしたけど
善政のため打たれることが無く
太鼓の台座は苔生し
鶏が住みつくほどであったと言う話が
基となっています
まさに家康が築いた300年に及ぶ
戦のない
泰平の世の中を象徴しています
「閑古鳥が鳴く」
の由来になったとも言われています
大きな銀杏の木があちこちに
銀杏の木は燃えにくいので
防火のために植えられたのだそうです
防災意識高いですね
国立西洋博物館では
オルセー美術館所蔵
「印象派」特別展が開催されていました
オルセー美術館は
パリ万博の際に建てられた
会場への終着駅だったんだそうです
大阪でいうと「夢洲」駅
みたいなもんですね
印象派とは
19世紀後半にフランスで生まれた芸術運動です
カメラの発明がその契機となっています
画家たちにとって死活問題だったでしょう
「カメラによって職業が奪われる」
ちょうど現代の我々が
「AIによって職業が奪われる」
と危惧しているのと似ています
AI時代を生き抜くヒントが
『印象派』の絵画にあります
こちらはドガによる『家族の肖像』

当時身を寄せていた叔父一家です
叔父の事業の失敗により家族は不仲
一堂に会することなどなかった家族
ひとりずつ個別にデッサンを重ね
一枚の絵に仕上げ
当時の家族の間に流れる不安を
見事に描き出しています
これなどは
当時のカメラにはできない
それこそヒトでないとできない
まさに芸術です
『印象派』の名称は
モネの《印象、日の出》がきっかけで
当時のカメラでは表現しきれない
光と色彩を重視したものです
これまでの絵画が担ってきた
「現実を写す」役割は
これからはカメラがやってくれる
明るい色彩や大胆な構図を取り入れ
「光と瞬間的な印象を捉える」
ことを目指した芸術活動が
近代美術の幕開けを告げたのです
『印象派』には日本の芸術も
大きな影響を与えています
こちらは『マネ』による
『エミール・ゾラ』
懇意にしていた美術評論家を描いたものです
背景には浮世絵が見えます
他国の文化を積極的に取り入れ
新しいものを生み出しているのも
『印象派』の特徴です
来年
本校からパリ研修に出かけます
ぜひオルセー美術館も
見てきて欲しいと思います
オルセー美術館は
古典芸術を集めたルーブル美術館と
現代アートの殿堂ポンピドゥー・センターを
繋ぐものといわれています
プレゼン大会はというと
全国から予選を勝ち抜いた
小学生から3組
中高校生から4組
大学生から3組の
ノミネートがありました
本校教諭 寺田 知絵 先生が
開会挨拶を務めました
電気が復旧するのに4ヶ月
水道が復旧するまで8ヶ月
かかったんですと
そのつらかった生活の話をすると
言葉につまり
会場の皆さんも目頭を押さえていました
いつも笑顔の寺田先生
こんなに辛い毎日を乗り越えていたんです
本校から
2年生の
平 愛結奈 さん
大岩 楓 さんが
「輪島が生きる」と題して発表しました
千枚田そして輪島塗に
輪島の復興をかけるみなさんのことを
紹介しました
多くの方々の感動を呼び
最優秀賞をいただくことができました
出張のたびに
これまで遠くからご支援くださった方を
順番に尋ね
直接ご挨拶を申し上げています
昨日は
発災後真っ先にご連絡くださり
地震避けのステッカーを
送ってくださった
東京で小学校にお勤めの
毛利 泉 先生を尋ねました
いただいたステッカーは
先生が師事されている
寄席文字書家「橘右之吉(たちばなうのきち)師匠」
によるもので
輪島高校避難所のあちこちに
貼らせていただいていました
なんだか遠い昔のことのようです
まだご挨拶できていないみなさん
申し訳ございません
いつの日か行きたいと思っております
プレゼンの極意
地震から 712 日目
昨日
アナウンサーの 原田 幸子 さまをお招きして
話し方講座の3回目〜発展編〜を実施しました
これまでのおさらいをプリントにして
配っていただきました
原田師匠は
昨年『紅白歌合戦』の輪島高校中継で
進行役を務めたNHK金沢放送局の高畠菜那アナ
私から見たら
有吉弘行さん
橋本環奈さん
伊藤沙莉さんと並ぶ名司会者
彼女の師匠に当たる方ですので
それはそれは相当なものです
師匠直伝のおさらいプリント
ぜひ紹介させていただきたいと
お願いしたところ
惜しみもなくご了承くださいましたので
ここにご紹介させていただきます
* * *
そもそも『プレゼン」とは何でしょう?
『プレゼン』の語源は『プレゼント』
心を込めた、相手への「贈り物」です
「伝えたいこと」つまり「想い」を贈るのです
ではどうやったら伝わるのでしょう?
それは『声の道」を意識することです
大きな声で
ゆっくりと
聴衆に目を配りながら
「伝えたい」と思いながら話すのです
「伝わるプレゼン」には
いくつかのポイントがあります
① 導入の大切さ
声と内容を意識して「第一声で心を掴む」
ことが大切です
② 着地点を意識することの大切さ
「終わりよければすべてよし」
③ 構成の適切さ
「山はどこか」
最も言いたかったことに
時間が割かれていますか
④ 身近なエピソード
「誰でも言えることではない
“あなたらしさ”」
⑤ 思いをのせる話し方
「声に表情をのせる」
⑥「間」が大切
伝えたいワードの前に
大切な話の後に
⑦ 緩急を使う
初めて出てくる言葉
核となる言葉
強調したい部分は
ゆっくりと
「自分が聞きたいプレゼンを目指しましょう!」
自分のプレゼンを撮影し
原稿を見ずに客観的に聴いて見てみましょう
その声から
表情から
姿勢から
「伝えたい気持ち」は伝わりますか?
常に
「初めて聞く人にわかってもらう」
ことを意識しましょう
プレゼンを魅力的にするには
「取材の仕方」も大切です
事前に準備していった質問に
囚われすぎないこと
相手と「会話する」
話を “広げる” “深める”
相手に “興味を持つ”
予定調和でない流れから
思いがけない話を
聞くことができます
* * *
さすがプロのアナウンサー
一つひとつが
なるほどな!
というポイントばかりです
文部科学省へ出かけ
自分たちの活動を報告してくるとともに
被災地の探究活動に対し
格段のご配慮を賜りますよう
お願いをして来ました
夕べ1時近くまでかかって
ホテルのロビーで準備した甲斐あって
素晴らしい発表ができました
生徒の感想です
宮腰花歩(1年生)
【一日目】OECDのお話を聞いて
日本の教育、国際関係、災害が起こった際などの様々な観点からの議論を聞いていてとても興味深かったです。例えば日本の教育について群馬県教育委員会の今井さんが話されていた非認知能力の育成についてですが、ただ単に勉強ができるというだけなく、主体性、創造力、コミュニケーション能力などの国際化していく社会において不可欠となっていると思っています。そのような中で私自身も学校という少し閉鎖的な空間だけではなく、今回行った東京や今度行くフランスなどの様々な地域や人との交流を通じて経験をたくさん積んでいきたい、と思いました。また、輪島のような過疎化が進んでいる地域でどうしたら都会との格差を埋めることができるかなどの課題も知ることができました。
【二日目】文科省へ行って
今日のスライド発表で自分の改善点が浮き彫りになったな、と思いました。もっと自分のスライドの原稿を突き詰めていけばよかったな、と少々後悔していることもありますが、これをバネにして今後の探究におけるスライド発表などに活かしていきたいと思います。
この2日間を通して、おそらくなかなかできない体験をさせていただいて、自分の中でとてもいい経験になったと思いますし、今の自分に足りないものを知ることができたと思います。ここで学んだことなどを、今度はフランスに行ったときに活かせることができればな、と思いました。
出る杭はつながる!
地震から 711 日目
今日のキーワードは『つながる』
被災地の子どもたちの想いを綴って
作曲家 弓削田 健介 さんがつくってくださった
合唱曲『フェニックス』
今も多くの絆を繋いでくださっています
佐賀での全日本音楽研究大会でお会いした
北海道の奥尻中学校の塩原祐馬先生より
仮校舎完成お祝いのメールをいただきました
「フェニックス」の音楽の力を
今度授業でお話されるそうです
素敵な授業になりますように
全国の教育現場を合唱でつなぐ
『フェニックス』つながるプロジェクト
に参加された
福岡市で『ユカリクラシックバレエ』
を主催されている
光永 ゆかり さまから
お手紙をいただきました
14日から16日に能登半島にお越しになり
仮設住宅でバレエを披露してくださいます
さて今日は
日本OECD共同研究
『2040年の日本の教育を
ホンキで考えるシンポジウム』
に参加するために東京に来ました
ポルトガルより
パウロ教育局課長が来日されたので
お逢いしてきました
生徒たちも
今春のポルトガル研修について発表しました
国際比較で見た
日本の教育の課題と可能性について
課題先進国の日本
そしてその課題が
さらに浮き彫りになった被災地で
未来の教育の先取り実装に
試行錯誤したがら取り組んでいる
現場の実例を紹介してきました
東京駅から会場まで歩いて移動しました
完全におのぼりさん気分です
東京駅何年ぶりでしょう
江戸時代に徳川家康に仕えた
オランダ人通訳「ヤン・ヨーステン」
彼が住まいをした場所は
彼の日本名「耶楊子(やようす)」がなまって
「八重洲(やえす)」となりました
東京駅八重洲口の反対側の丸の内口が
皇居へ向かう出口です
桜田門をくぐります
大老井伊直弼が殺害されたところですね
こちらは百人番所

江戸城の警備をするところで
各藩が担当していたそうです
現在でいうと
皇居の警備に各県警が当たっている
って感じですね
松の廊下跡です
松と千鳥が描かれた襖の長い量敗きの廊下で
赤穂演士討ち入りにつながったことで知られる
浅野内匠頭の吉良上野介への事件があった場所です
「殿中でござる!」
石室です
火災などがあった時
大奥の調度などを避難させた場所です
防災意識高いですね
そんなこんなでたどり着いた会場
今日のセッションでは
人口減少・自然災害・国際化経済・デジタル社会
という4つの切り口から
「2040年の日本にホンキで備える」
そのための具体的な一歩を考えます
パネルディスカッションに参加して
こんな感じでしゃべくりました
【セッション1】
問い:2040年よりも前に
もしも南海トラフがおきたら
なにができますか?
「昨年元日の地震で家も車も何もかも失って
それ以来退屈しない毎日を過ごしております
本来退職となる年でしたが
留年してもう一年校長を務めております
昨年1月の残業時間は300時間を超えるという
教員のWell-beingという今日のアジェンダとは
程遠い生活を送ってきましたが
その代わり通常では経験できない
多くの幸せにも出会うことができました
学校が避難所と教育機関として運営していく中
さまざまな課題に直面し
その度多くの方々に助けられてきました
中でも
DMATとの出会いは衝撃的なものでした
Disaster Medical Assistant Team
日本中の医療関係者が
被災地での医療を止めない
そんな枠組みをつくっています
教育でも同じような
国を挙げての支援の枠組みが必要である
DMATの教育版が必要であると文科省に提言し
D-est(Disaster Education Support Team)の
設立につながりました
南海トラフが起こったら
その一員として
もちろん恩送りに駆けつけます」
【セッション2】
問い:もしものために
あなた自身ができること
していきたいことは何ですか?
「自然災害は時を10年進めるといわれます
これは10年未来の世界に行ける
という夢のある話ではなくて
10 年後に起こるであろう諸課題が
前倒しして一気に襲ってくる
という意味です
現在能登半島はまさにその状況です
これから10年後
必ず日本の各地
さらには世界の各国に起こるであろう
様々な課題
少子高齢化であったり教育格差であったり
そういったものが
容赦なく襲いかかって来ている訳です
特に教員不足の問題は深刻で
今年度30人中5人が大学を卒業したての新規採用者です
これまで在籍していた教員が
生活拠点を失って転勤してしまうからです
教員の絶対数が圧倒的に不足している訳です
ただ被災地での最初の教員経験は
今後の生涯の教員人生において貴重なものとなるはずです
被災地で何もかも失った子供達が
それでも前を向いている姿を目にし
何も感じないのであれば
残念ながら教員としての資格はありません
今日もそんな震災地の学校に赴任してしまった新規採用教員
まさに震災の新採
一緒に来てもらっています
彼にとっても今日この場に同席すること
これ自体が大きな財産になるはずです
そんな中で多くの課題に対して
これ以上失うものが何もない被災地であるからこそ
思い切った教育活動を展開できています
『教育とは
魚に泳ぎ方を教えることではなく
自由に泳げる環境を与えることである 』
を体現していきたいです」
今日はいわゆる『出る杭』たちの集まりでした
「出る杭は打たれる」それは昭和の田舎の話
出た杭どうしでどんどんつながっていきましょう!
仮校舎2日目
地震から 710 日目
昨日の仮校舎初日の様子を
多くのマスコミの方が
取材に来てくださいました
ある地元誌では
私が言ってもいないことを
コメントとして掲載してありました
「環境が変わってもしっかり勉強してほしい」
と言ったのが
「十分な施設ではないけれど…」
とあたかも現状に不満があるかのような
書きぶりでした
『伝える』のって難しいです
切り取られ方によって
全く意図しないものになってしまうので
今後はマスコミへの発言を控えようと思います
『ごちゃまる出張ラボ』さんが
来てくださいました

新しい仮説校舎での
ふれあいのひとときです
スノーマンのキーホルダー作りなどで
楽しみました
日本の雪だるまは2段重ねですが
西洋のスノーマンは3段重ねです
なぜなのかチャッピーさんに訊いてみたら
(チャッピーさんはチャットgptのことです
岡本先生がそう呼んでいました)
Snow Manが6人から9人に増えた
理由を説明してくれました
ほんとうに『伝える』のって難しいです
高校化学の発展的な内容に
「ラウールの法則」ってありますが
女の子が目をキラキラさせて
聴いていたのを思い出しました
(芸能界に疎い私のような方のために
Snow Man はアイドルグループで
ラウールくんはそのメンバーです
合ってますか?)
各国の雪だるま事情を調べてみました
英語圏では「スノーマン=雪男」と呼ばれますが
イタリア・オランダでは「雪人形」
「雪男」と言うと
日本では雪男=UMA(未確認生物)
のイメージになってしまいます
『だるま』はもともとインドのお坊さん
さすがにインドに雪は降らないだろうから
中国ではどうかなと調べたら「雪人」
円錐形の胴体に丸い顔が載っています
韓国のは日本のに似ていますね
『冬のソナタ』にも出ていました
『ヌン(雪)サラム(人)』
というそうです
今日はクリスマスに計画している
朝市焼け跡のイルミネーション
の準備もしました
千枚田『あぜのきらめき』を彩っていた
『ペットボタル』を借りてきて
まずはクリーニングです
ステンドグラスのデザインもします
思い思いを形にして成形します
みんなの心を明るく照らしてください
輪島高校生の街づくりプロジェクト
『街プロ』の公認キャラクター
『わじねことふぐ郎』の
ポストイットが完成しました
1セット400円で販売しています
ご希望の方は輪島高校まで
ご連絡ください!
仮校舎での最初の日
地震から 709 日目
昨日仮校舎への引っ越しを終えて
今日は最初の授業の日でした
2年生を対象に
大学の模擬授業を実施しました
『学びウィーク』の一環でもあります
本校では中間考査を廃止して
その期間中
学びの心に火をつける
『学びウィーク』を行っています
今回は2学期末考査を終えた後
『学びウィーク』を実施
県内の多くの大学からお招きしました
講義の内容を
仮設校舎の案内も兼ねて
ご紹介します
国際(北陸大学)【調理室】
国際的なコミュニケーションを図るには
単に言葉の壁を乗り越えるだけでなく
互いの文化を理解し合うことが大切である
ということを
トランプを使ったゲームで実感しました
栄養(北陸学院大学)【物化実験室】
ようやく実験室が完成しました
これまでは水道が出なくて
実験できなかったのですが
さあお立ちあい!
保育・幼児教育(金城大学短期大学部)【音楽室】

ご覧ください
この広々とした音楽室
吹奏楽部も思う存分練習できますね
スポーツ(金沢学院大学)
女子ソフトボール
北京オリンピック金メダリストの
藤本索子 助教です
文学(金沢学院大学)
工学(金沢工業大学)【生地実験室】
標本たちも引っ越してきましたよ
理学療法(金城大学)
生物資源環境学(石川県立大学)
看護(石川県立看護大学)
今年の夏
トリアージの実習でお世話になった
木田 亮平 教授です
経営(かなざわ食マネジメント専門職大学)
日本で唯一フードサービスに特化した
経営学を学ぶことのできる
新しい大学です
こうして見ると
さすが学都金沢
人口あたりの大学数が
京都に次いで全国2位だということに
納得です
さて今回の『学びウィーク』
他にも様々な取り組みが
予定されていますよ
恒例の
原田幸子アナウンサーによる
「話し方教室」
今回は第3回『発展編』です
それから
南カリフォルニア大学
EUI-SUNG YI(イー・サン・イ)教授の講義
世界で注目される都市研究の第一人者です
最新の都市計画の実践をお聞きし
被災地の復興へのヒントとします
高校生に限らず一般の方もぜひお越しください
詳しくはこちら
学校へお電話の上お越しください
0768-22-2105
お引越し大作戦
地震から 708 日目
いよいよ仮設校舎ができました
これまで長かったような
短かったような
校舎の傾きが見つかったのは
地震直後のことでした
最初に気がついたのは
山崎先生でした
「二号棟が傾いている気がします」
最初は言われて初めて気づく程度
の傾きでした
そのうちだんだんと傾きが大きくなり
三号棟との間に大きな亀裂が走り
壁のヒビも大きくなって
中に入ると気分が悪くなるほどになりました
職員室がその中にありましたが
キャスター付きの椅子に座ると
コロコロ転がっていくようになりました
職員室を一号棟の会議室に移動しました
発災後4日目には
避難所として開設しましたが
二号棟は立ち入り禁止としました
体育館はというと
第一体育館は床がハーフパイプ状に窪み
第二体育館一階は床が山脈のように盛り上がり
どちらも体育では使えません
唯一使える第二体育館二階と廊下など
できるところで工夫をして
体育や部活動を行ってきました
春になると簡易検査が入りました
二号棟の傾きが3度少々
これはピサの斜塔とほぼ同じです
一号棟にも1度の傾きが確認されました
法律上公共施設は1度傾くと
半壊扱いになるので
それまで入居していらっしゃった
被災者の方々を体育館へと
移っていただきました
秋には精密検査が入り
一号棟の基礎の部分に損傷
が認められました
そこで学習していた
一・二年生の教室を
安全な三号棟に移しました
パソコン室を普通教室に作り替えたり
ひとつの教室を間仕切りで区切って
習熟度別授業のための小部屋を
作ったりしました
グラウンドの3分の1ほどを利用して
仮設校舎の建築が始まりました
工期およそ半年ほどで
二階建ての校舎が完成しました
先週の土日を利用して
金庫などの重量物のほか
大きな家具の移動を
業者の方にしていただいて
本日は生徒の使う机椅子などを
全員で搬入しました
仮設校舎への移動が終わり次第
本校舎のジャッキアップ作業に入ります
建て替えはしません
完成まで
一・二年生が仮設校舎を利用し
三年生は三号棟の一階を使います
校長室もガランとしました
何年後かに帰ってきます
その時は別の校長先生でしょうが
その日までさようなら
こちらは仮設校舎の校長室
どこにこんなに荷物があったんだと
まるでミミズの缶詰めを開けた状態
どこから片付けてよいのやら
怪我しないように慎重に慎重に
新しい事務室です
こちらは新しい職員室
フリーアドレス化しました
近未来型の机椅子は
『内田洋行』様より
ご寄贈いただいたものです
ほんとうにありがとうございました
「量子力学」百周年
地震から 707 日目
今週末は3件の講演会をさせていただきました
移動の新幹線で前の座席に座っていた方が
乗り換えた特急では隣の座席になりました
なんという偶然でしょう
この引き寄せに縁を感じ話しかけてみました
国際風水氣学協会の本鑑定士の方でした
普段から風水を科学と捉えている私は
興味津々でいろんなことを尋ねてみました
「目に見えるものだけが全てではない」
サン・テグジュペリの
『星の王子さま』にも登場するこの言葉
目には見えない酸素や二酸化炭素
そして電磁波が厳然として存在するように
風水は量子力学である
という言葉に妙に納得するのでした
アインシュタインは
「月は私たちが見ている時だけ存在するのか?」
と懐疑的だったこの量子力学
量子力学と私の出会いは
40年前に遡ります
大学時代の『理論化学』という講義の
シュレディンガー方程式の教科書は
これまでの私の常識を覆しました
難しい本を読むと3ページほどで
眠りに落ちてしまう特異体質の私を
わずか5行ほどで眠らせるものでした
1895年
ドイツのレントゲンは
空気を抜いて真空にしたガラス管に
電圧をかけて放電させる実験中に
管を厚い紙で覆っているにもかかわらず
近くに置いてあった物が光っているのを見て
「物を突き抜ける不思議な光が出ている」
と考え
この不思議な光をX線と名づけました
この発見の翌年 1896年
フランスのベクレルは
保存しておいた写真乾板が
光を受けていないのに
感光していることを見つけました
一緒に保存していた岩塩から
X線に似た何らかの光が出ていると
考えました
1903年
マリー・キュリーは
夫のピエール・キュリーが発明した装置を使って
ベクレルの岩塩から光を出しているのは
そこに含まれるウラン原子であることを発見し
その光を出す性質を「放射能」と名づけました
時は第二次産業革命
製鉄業がさかんとなったドイツでは
溶鉱炉の中の溶けた鉄の色で
温度を判断していました
赤黒いときは千数百度
真っ赤の時は二千度以上、
それ以上では白っぽくなる
といった具合です
物体の温度と放射される光の波長の関係を
プランクは公式で示しました
そしてこのことを説明するためには
『量子』という考えが必要であるとしました
光のエネルギーは連続的に変わるのではなく
飛び飛びの値を取るということです
そのことを突き詰めたのが
シュレディンガー方程式です
ここからいよいよ私が秒で寝る領域です
ともかく
トランジスタ
発光ダイオード
太陽電池
MRI
量子コンピュータ
我々の現在の豊かな生活は
量子力学の上に成り立っています
量子力学の世界では
「実験の測定値は測定した瞬間に決まる」
とされています
このことは『シュレディンガーの猫』
と例えられて説明されています
電子は『スピン』という磁力を持っています
『スピン』には上向きと下向き
ふたつの状態があります
ある電子の『スピン』がどちらなのかは
測定した瞬間に決まり
測定する直前はどちらでもない
いわばグレーな状態です
オセロのコマを弾いて回転させて
倒れた瞬間に白か黒か決まる感じです
さらに奇妙な
『量子もつれ』とう現象もあります
この状態のふたつの粒子は
どんなに遠く隠れても
瞬間的に影響を伝え合うのです
『量子もつれ』の状態にある
ふたつのオセロのコマを
『スピン』を逆向きに設定して
北極と南極に移動させます
そして回転させた後
同時に測定すると
その瞬間
必ず一方が白なら他方は黒
となるのです
一見何の関係もない
ふたつの現象であっても
目に見えない不思議な力で
影響を及ぼしあうということです
これはユングの提唱する
シンクロニシティの原理とも重なります
これは「意味のある偶然の一致」
あるいは「非因果性同時多発性」
ともいわれます
精神分析家ユングと
量子力学研究家パウリは
この非因果的な相関に注目し
精神と物質を統一する理論を構想するなど
シンクロニシティの原理を
科学的に探求しました
私たちの直感を超えた世界のあり方を
理解しようとする試みといえます
さて量子力学と風水に話を戻して
徳川家康が江戸のまちを築く時に
天海僧正らの助言を得て風水を取り入れています
東の隅田川を「青龍」
西の中山道などの道を「白虎」
南の江戸湾を「朱雀」
北の上野や神田山を「玄武」とする
四神相応の配置を基本としています
今日の大都市東京の繁栄の基礎がそこにあります
北に山があるとなぜ都市が繁栄するのか?
一見無関係に見えるこのことが
量子力学的に何か因果関係があるのかもしれません
実は焼けた朝市
風水的には
北に海
南に山
西に川
東に道と
四神相応の真逆なんですよね
だからこそ復興させる際には
その気を整える建物配置を
考えてみたらどうかなと思う次第です
愛媛の朝
地震から 706 日目
気持ちのいい朝を迎えています
今日は高松で
講演会を行いました
高松へ向かう前のひととき
丹原高校の合田校長先生に
地域巡見をしていただきました
地歴が専門である先生からは
地理と日本史の視点から
さまざまなことを
教えていただきました
まずは四国三十六不動霊場である
西山興隆寺
紅葉の美しい古刹です
『千と千尋の神隠し』に出てくるような
『みゆるぎ橋』を渡ると
国指定文化財の『三重塔』などがあります
愛媛県は東予・中予・南予に区分されますが
丹原高校のある東予地区には
独特の地形が見られます
まずは日本で有数の扇状地が連なります
扇状地では水が伏流水となって流れますので
川がなく
稲作には向きません
そこで果樹園として活用しています
下流に行くと伏流水は地表に現れ
川となって流れますが
多量に運んできた土砂を堆積させ
だんだん川底と堤防が高くなり
周囲より高いところを流れる
天井川となります
こちらは鉄道が
川の下のトンネルを潜るという
珍しい光景です
以前に「ゆず」のおふたりが
輪島高校に歌いに来てくださった時の模様が
NHKで放送されます
【番組名】東北ココから ゆずとつくる 未来へつなぐうた
【放送日時】12/12(金) 19:30~19:57 <東北地方のみ>
※NHK ONEで見逃し配信
【内容】来年東日本大震災から15年を迎えるにあたり、
ゆずのおふたりが
震災の経験を未来へつなぐ歌を制作するべく
東北の被災地を訪れ
地域の人たちと語り合う
旅のドキュメント
ぜひご覧ください
初冬の伊予路へ
地震から 705 日目
今年の夏休みに
韓国に視察旅行に行きました
バスの中で偶然隣合わせになったのは
愛媛県立丹原高等学校の
合田 明典 校長先生でした
防災教育に力を入れるなど
たいへんパワフルな校長先生でした
合田先生のお招きを受けて
本日同校で講演会を行います
今日は『防災デー』ということで
その一環ということになります
秋の京都駅で乗り換えです
紅葉がちょうど見ごろを迎えているようです
駅員さんお手製の案内板
『街プロ』でも
やってみるといいですね
京都では
中国人観光客が減って
日本人観光客が増えているとか
ホテル代なんかもグッと下がってお得に
予約を取り直す方も
いらっしゃるようです
丹原高校の『防災デー』
最先端の避難訓練を見せていただきました
予告なしの避難訓練です
掃除中に発災の設定です
生徒たちはすかさず
「落ちてこない倒れてこない」
場所を見つけて避難姿勢です
揺れが収まると
生徒たちは駆け足でグラウンドへ
途中通行不可能箇所を設定
みんな自分で避難路を見つけて
避難します
緊張感を持って取り組んでいます
生徒がふたり負傷した設定です
先生方が捜索に向かいます
ひとりは骨折で動けなかったようです
安全な場所までおんぶで運びました
もうひとりは心肺停止です
タンカで運んできました
ここは問題提起です
「訓練のための訓練」
になっていませんか?
心肺停止は一刻を争います
わざわざみんなのいるとこまで
連れてこないで
安全な場所で胸骨圧迫をすべきでは?
小学生も一緒に参加です
防災訓練は単独でなく
地域で行うべきものですね
勉強になりました
降下訓練も行いました
4階の高さから緩衝機を用いて
降下して避難する練習です
私も体験してみました
輪島高校でもぜひ取り入れましょう
煙避難訓練です
スモークマシンで煙を充満させた部屋を
潜って避難します
ハンカチの大切さを実感しました
SONPO さんのご協力による
『学防ッチャ(まなぼっちゃ)』
防災の知識を楽しみながら学べる
ボッチャです

防災リュックを作るワークショップ
防災バッグに必要なものを組み合わせる
パズルゲームです
私も講演会をさせていただきました
「南海トラフは必ずやってくる」
そう言われ続けて
暗い未来を刷り込まれるだけでは
高校生がかわいそうです
正しい防災知識を身につけて
地震の最初の15分間に命さえ守れば
つらいことの後には
人は大きく成長できるよ
予想もしなかった輝かしい未来が待ってるよ
そのことを
輪島高校生が頑張っている姿を紹介することで
伝えてきました
とっても素直で明るい生徒さんたちで
みんな真剣に話を聴いてくれました
藤原 禄都 さんと 桑村 桜羽 さんは
『江戸走り』を
渡部 もも花 さんと 佐々木 真央 さんは
『能登半島ポーズ』を考案して
それぞれ披露してくださいました
この中のどこかに
「能登半島ポーズ』の
ふたりがいます
金沢大学特別講義
地震から 704 日
金沢大学特別講義
「石川県の学校安全」で
お話をさせていただきました
金沢大学では
学校安全の中核を担う教員を育成するため
地理的環境・過疎化・被災など
石川県の地域特性を踏まえた
学校安全の取り組みについて
理解を深めるために
本講義を開講しています
今日明日と集中講義期間となっていて
通常講義はお休みです
キャンパスはガランとしていましたが
そんな中この講義を選択した学生さんは
熱心に講義を聴きに来てくださいました
さすが休みの日に進んで受講されるだけあって
みなさん本当に熱心に耳を傾けて
こちらからの問いかけについては
積極的に答えてくださいました
意識高く頼もしい限りでした
午前中は
発災後珠洲市の中学校で
陣頭指揮をとってこられた
現奥能登教育事務所長の
山岸 昭彦 先生の講義があり
拝聴させていただきました
珠洲市は今回の地震以前から
群発地震に見舞われていたので
防災教育そして地震への備えを
計画的に実践されていました
我々の認識の甘さを痛感しました
講義を受けられた方の中に
大切なご家族を亡くした方も
いらっしゃいました
言葉を一つひとつ選んで話したつもりです
教員採用試験に合格された方も
いらっしゃいました
被災地に赴任となる可能性もありますよ
とお伝えしました
被災地での教師としての実務経験は
今後の長い教員人生にとって
かけがえのないものを学ぶ機会になりますよとも
お伝えしました
実際震災わずか3ヶ月後
傷だらけで
住むところもない本校に
大学出たてのふたりの先生が赴任しました
そのうちひとりは
こんなとこ住めないと
金沢から毎日通い続けました
そんな厳しい環境の中
ふたりは真剣に生徒に向き合いました
どんなにつらい環境に置かれようと
それでも前を向いて歩き出そうとしている
生徒たちに
自分にももっとできることがある!
ふたりはそう思うようになってきました
今年はふたりとも学級担任をしています
明日は丸一日
「子どものための心理的応急処置」と題して
セーブ・ザ・チルドレンさんによる
実習が行われるそうです
がんばってください
高校生ガイドツアー
地震から 703 日目
石川県では
全国から修学旅行に訪れる学校向けに
高校生ガイドの取り組みをしています
本校もそのガイド校のひとつです
被災地ではありますが
今しかここしか体験できないコースもあります
今日はそのリハーサルということで
輪島市内の全中学校の生徒に来てもらい
お客さん役をしてもらう予定でした
ところが北陸特有の冬の気候となり
となると『鰤起こし』つまり
冬の雷もありうるなということで
急きょ予定を変更して
屋内で実施することとしました
せっかく来てもらうのだから
すこしでも楽しんでもらえるように
先生方は知恵を絞ります
建ったばかりの仮設の校舎に
高校生よりも一足早く入ってもらい
被災地ライフを楽しんでもらうことにしました
ところがここで問題発生
Wi-Fiがつながりません
生徒と先生は知恵を絞ります
急きょアナログの資料を準備して
紙芝居形式で何とかつなぐことにしました

ここでさらに問題発生
街を案内しながら話す原稿だったので
座ったままだと10分で終わってしまいました
先生方は知恵を絞ります
出たがり校長にに喋らせとけ
良いアイディアです
急遽音楽室に全員を集めることにしました
先生方がドタバタ準備をしている間
生徒たちが勝手に喋り始め
場を盛り上げてつないでくれていました
なんて気の利く生徒たちでしょう
想定外の出来事が次々と起こる中
生徒たちも先生方も
自分たちで最善を考え
自分たちで行動する
そんな姿が着実に身に付いています
震災がくれたプレゼントです
と言っては不謹慎でしょうか
さて、東陽中学校と門前中学校のみなさんは
道路事情が悪く
震災後輪島市街に入ることも
滅多になかったということで
バスで輪島塗会館とキリコ会館を案内しました
先生がそっちについて行ったので
残された生徒たちは
「おい!片付けやっちゃおうぜ」
自主的に使った部屋の片付けと
掃除をしてくれました
入学した頃は
やんちゃでどうなることやらと
心配した子たちではあったのですが
本当に成長しました
頼もしい限りです
県の産業について考える
地震から702 日目
「石川県産業教育振興会」
に参加しました
産業界 教育界 行政関係者が一堂に介して
県の産業教育の振興充実についての
諸課題の解決を図ることが目的です
ホクショー株式会社代表取締役社長
北村 宜大 氏による講演を
拝聴させていただきました
ホクショーさんでは
コロナ禍の際には
テレワーク手当の支給
ガソリン価格高騰の際には
通勤手当の2割増など
会社の業績アップと
従業員のWell-biing を
同時に実現されています
昭和の時代は
「電話がならない会社は危ない」
「社員が休みがちな会社は危ない」
などと言われたものですが
現在では必ずしも当てはまりません
社員のWell-being を実現しながら
業績を上げるには
① 営業の行動量を上げる
② 営業の「勝ち率」を上げる
③ 受注単価を上げる
だそうです
3つに共通することは
他者との差別化を図ることです
やってはいけないことは
価格競争に陥ること
学校現場にも応用できそうです
意見交換会がありました
企業側からの質問に対し
突然指名されたある校長先生は
「すみません もう一回言ってください」
聞き逃したようです
私が指名されても
きっと同じようになったと思います
ドキドキしました
「高校ではどのような指導されていますか?」
という質問だったのですが
その先生は
「人の話をちゃんと聞けと指導しています」
センスある回答ぶりに心で拍手を送りました
意見交換会でわかったこと
企業側が懸念していることは
現在学校教育で比重が大きくなっている探究活動
それにより基礎学力の指導が疎かになっていないか
ということのようです
どうも探究活動と基礎学力を
2項対立で捉えているという認識を変えるための
学校側の努力が必要なようです
専門用語では
企業側の捉えている基礎学力を「認知能力」
探究活動で身に付く能力を「非認知能力」といいます
ここでいう『認知』とは
『認知症』の『認知』とは意味合いが違います
『認知能力』とは
共通の尺度で点数化して評価できる能力のこと
『見える学力』ともいいます
例えば『漢字能力』のような
『非認知能力』は
それができない能力
『見えない学力』ともいいます
例えば『積極性』のような
「非認知能力が高ければそれでいいのか!」
「積極性があれば漢字書けなくていいのか!」
そんな極端な論法はやめてください
『非認知能力』or 『認知能力』
ではなく
『非認知能力』for『認知能力』
です
『非認知能力』を高めれば
『認知能力』が高まるのです
ヒトがコトに臨むうえで
必要な力を身につけるのに必要な力
それが『非認知能力』です
もっと簡単に言えば
『認知能力』とは国数英理社の力
『非認知能力』とはざっと上げると
自主性・向上心・協調性・共感性
創造性・コミュニケーション能力
などなど
おわかりになると思いますが
『非認知能力』とは全く新しい概念ではなく
これまでも日本の学校教育で重視されていたこと
すなわち「心の教育」なのです
「心の教育」の育成には
例えば部活動が大きな役割を果たしています
部活動においては
競技力を高めるために
従来は競技に特化した訓練を
スパルタ式で行っていました
しかしながら今はそんなやり方は時代遅れ
フィジカルトレーニングや
メンタルトレーニング
主体性の育成やチームビルディングなどを
科学的に体現できるチームが強いです
それを
学習にも応用しましょうというのが
探究学習の目指すところなのです
「単語練習」や「計算練習」を
意味もわからず機械的にこなしても
それで身に付く力は一時的なもので
将来的に生きていく力とは
程遠いものです
「学びに向かう力」を
高める必要があるのです
はじけろ創造彩れ未来 いざ百万石の地へ
地震から701日目
令和9年夏
高校生による芸術文化の祭典
「全国高等学校総合文化祭」が
石川県で開催されます
石川県での開催は47年ぶり2回目
ちょうど全国を一回りしてきました
今日のタイトルはそのスローガンです
演劇 合唱 吹奏楽 マーチングバンド
バトントワリング 美術 書道 放送など
22の部門の展示や発表が
石川県を舞台に繰りひろげられます
とはいえ
能登の文化的施設は壊滅的被害を受けていますので
羽咋以南での開催になるのですが
現在それに向かって
各校で分担して準備を進めています
輪島高校は『郷土芸能』を担当します
全国各地に伝わる
祭囃子や神楽 民謡 踊りなどの『伝承芸能』と
伝承曲や創作曲を含む『和太鼓』の
ふたつの部門によるコンクールです
今日は運営のご協力をお願いしに
白山市にある浅野太鼓楽器店様を
訪問しました
浅野太鼓様は
江戸時代初期の創業以来
400年以上にわたり
和太鼓づくりの技を継承なさっていて
全国の太鼓の制作を引き受けていらっしゃいます
原木の選定からクリ抜き 塗り 皮はりまで
全て自社で行われ
職人さんによる
一つひとつ丁寧な手作業での生産を
続けていらっしゃいます
こちらは6尺もある大太鼓
直径2m 以上もあるアフリカの大木を
くり抜いて作られたものです
現在ワシントン条約により
日本では入手不可能な木です
ワシントン条約には
学術目的を除き国際間の取引が一切禁止される
『附属書I』と
締約国が『留保』できる
『附属書II』があります
『附属書Ⅱ』に属するこの大木に対して
中国は『留保』の姿勢をとっているので
中国に流れて家具に変えられているそうです
日本も過去に
「ヨシキリザメ」の規制に対して
『留保』の姿勢をとりました
フカヒレとして食されるほか
コンドロイチンも豊富に含まれているからです
皮は肉牛のもの
現在
牛は若いうちに食肉に変えられるので
ここまでの大きな皮は
手に入らないのだそうです
部位で言うと
腰のあたりの皮が
最も厚くて丈夫です
それはライオンなどに襲われるときは
いつも背後からなので
その辺りの皮が厚く丈夫に進化したからです
写真後方に写っているのは
『鉦鼓』でしょうか?
神楽に使われるものかなと
詳しくはないので
よくわかりませんが
とにかく
いろんな太鼓があって興味は尽きません
ちなみに現在日本で一番大きな太鼓は
飛騨高山の『祭りの森』にある
9尺のもので
重さにして4.5t
実はこちらも『浅野太鼓』さんが
こしらえたものです
「みちのくひとり旅」その参
地震から 700 日目
震災遺構 荒浜小学校へ行ってきました
荒浜は仙台の東
太平洋に面した地区です
当時10m ほどの津波に襲われました
こちらが
生徒教員含め320名の住民が避難した
荒浜小学校
写真左側2階のベランダに
「ここまで津波が来ました」の表示が
非常階段を見ると確かに2階と4階で
明らかに被害が違います
3 月11日 14:46
1~3年生は下校途中で
4年生以上が校舎で授業中でした
地震がおさまってから
全員を4階に避難させましたが
津波の襲来に伴い
避難してきた住民とともに屋上へ
3 月11日 17:30
救助のヘリが来ました
ちっちゃい子どもとお母さん
小学生 中学生 高校生 大人の顧番で
救助してもらうことにしました
真っ暗な中で屋上から
一人ひとり吊り上げられました
高学年の児童が
低学年の児童の面倒を
しっかり見たそうです
3 月12日 5:00
中学生高校生の救助が始まりました
その後ヘリが来なくなり
籠城の準備を始めたそうです
お昼頃消防団が歩いて来たので
誘導に従い
ひざや腰まで水につかりながら
50名ほどが歩いて避難しました
ヘリではペットが避難できなかったため
ペットと一緒の人は徒歩での避難を選びました
3月12日 午後
水が引いたため
ヘリが地上に着陸できるようになり
残っていた人全員の非難が
ようやく終わりました
荒波地区には
津波から住民や街を守るための
様々な工夫がされています
全長9km におよぶ堤防を
国・県・市が分担して整備しました
想定を上回る規模の津波が来ても
堤防が破壊・倒壊するまでの時間を稼ぎ
全域に至る可能性を少しでも減らす
構造上の工夫が施されています
潮害・風害・飛砂を防ぐ海岸防災林は
津波到達時間を通らせる効果も期待できます
2014(平成26)年から植林を開始しました
震災前の海岸防災林に戻るのに
数十年かかると言われています
沿岸部を南北に走る県道102kmにおいて
約6mの嵩上げ道路にしています
震災で発生したコンクリートくずや
津波で運ばれてきた土砂を活用しました
道路に堤防の機能を持たせます
このようにさまざまな設備を
組み合わせて防御することで
津波による被害の大幅な軽減を図っています
校舎の方は
防災教育の拠点として活用されていました
音楽室がシアタールームに
映像アーカイブが流されています
児童たちの作品も展示されています
こちらは輪島高校でもしましたね
思い出の場所旗立てワークです
あの時のまま止まった時計
校庭には
二宮金次郎さんの像が倒れたまんまでした
江戸時代に農民の子として生まれた金次郎は
朝暗いうちから夜遅くまで
汗と泥にまみれて一生懸命に働きながら
わずかな時間も無駄にせず勉強をしました
荒れ地を耕して米を作り
余った米をお金に変え
お金が貯まると土地を買いました
そして一生を世の中のために捧げ
大飢饉で困っているたくさんの人々を
救ったのです
その姿を見習いましょうと
マキを背負いながら勉強している像が
日本中の小学校に建てられました
その頃日本は
尺貫法からメートル法に
切り替える時期だったので
子供たちがメートルをイメージしやすいように
像の高さを1m に統一したそうです
『尺』は長さの単位
『貫』は重さの単位です
1尺は親指と人差し指を開いて
2歩測った長さで
だいたい30cmです
それを10等分したのが1寸なので
一寸法師の身長は3cm
キティちゃんの身長が
リンゴ5個分なので
それより小さいです
このように昔の単位は
人のサイズが基準になっていることが多いです
大人が両手を伸ばした長さより
少し長いのが1間
ヒトが両手を伸ばした長さとpy
その人の身長はほぼ同じなので
1間はヒトがひとり余裕を持って
横になれる長さということになります
海外でもことは同じで
1フィートはつま先からかかとまでです
約 30cm なのでやはりヨーロッパ人は
でかいですね
3フィートで1ヤード
これは腰回りが由来であるという説があります
ところで北極から赤道までの距離を測ると
ピタリ1000万m になります
これは偶然ではなくて
もともと
子午線の距離の1000万分の1を
1m とすると決めたからなんですね
水がちょうど0℃で凍って
ちょうど100℃ で沸騰するのと同じです
この定義は
パリの科学アカデミーが1799年に
パリを通る子午線の一象限の 1000万分の1の長さ
を1m と定めたもので
最初の『国際メートル原器』
つまり1m の基準となる「ものさし」
もその時作られました
その後作製された白金-イリジウム合金製のものが
1889年の第1回国際度量衡総会で
世界的に承認され
その時作られたものが
メートル条約全加盟国に配布されて各国原器とされました
日本のものは No.22
「産業技術総合研究所計量標準総合センター」
に保管されているそうです
その後
「メートルはクリプトン 86原子の
準位 2p10 と 5d5 との間の遷移に対応する
光の真空中における波長の
165万 763.73倍に等しい長さである」
と定義が変わり
現在では
「光が真空中で
299,792,458分の1秒間に進んだ距離」
となっています
東京ドーム何個分の方がわかりやすいですね
世界中にはまだまだ面白い単位があって
古代ローマでは
牛1頭が1日に耕すことのできる面積を
1モルゲンと言います
ドイツ語勉強している方はお分かりですね
英語の Good morning に相当する
グーテン・モルゲン
朝(Morgen)の語源となっています
ちなみにドイツ語では
文頭でなくても名詞の頭は
大文字で表記します
膨大な単位に『グーゴル』があります
1グーゴルは10の100乗です
日本語で表すことができる最大の数は
9999無量大数9999不可思議9999那由多
9999阿僧祇9999恒河沙9999極
9999載9999正9999澗9999溝
9999穣9999秭9999垓9999京
9999兆9999億9999万9999
10の70乗程度なので
一体何に使う数字か?
という気がします
ちなみにGoogleは
グーゴルの綴り間違いに由来する
と言われています
話があちこちに飛びましたが
最近では
金次郎さんが歩きながら勉強する姿は
歩きスマホを助長するとか言って
座って勉強する像に作り変えられているそうです
「みちのくひとり旅 」その弐
地震から 699 日目
東日本大震災を生き延びた方が
どんな思いで復興への道を歩んできたのか
その生の声を聞きたくて
ホテルではなく民宿に泊まりました
気仙沼の民宿『天心』さんは
昔船乗りをリタイアしたご主人が
震災前に始めた喫茶店がそのルーツ
復旧工事関係者の宿泊施設がないということで
民宿に変えたそうです
サンマの刺身やマンボウの腸にツブ貝
気仙沼の新鮮な海の幸をいただきました
当時のご苦労などをお聞きし
元気をいただきました
「おかえりモネ」の舞台気仙沼
付近の町とはBRTでつながれています
BRTつまり
Bus Rapid Transit(バス高速輸送システム)
バスを基盤とした次世代公共交通システムです
渋滞に関係なく
鉄道と同じくらい時間に正確な運行ができます
様々な工夫がされています
渋滞の影響を回避するため
廃線となった鉄道軌道跡等を利用した
専用レーンを走る区間があります

一般車両は走ることができないので
1車線のみ
単線鉄道のように駅ですれ違います
交差点ではバスの通行に合わせて
遮断機が動作します
トンネルなんかも1車線
高速道路を利用する区間もあり
一般道を走る際は
バスの接近に応じて
優先的に信号が青になります
鉄道に比べて整備費用が安く
導入までの期間も短いという利点があり
東日本大震災で被災した
気仙沼線や大船渡線の
復旧までの代替手段として
採用されています
陸前高田の『奇跡の一本松』
見てきました
震災前この場所には
約7万本の松林が広がっていましたが
大津波により
ほぼ全ての松がなぎ倒されました。
その中で
唯一津波に耐えて残った一本の松が
『奇跡の一本松」と呼ばれ
希望の象徴となりました
現状は残念ながら
地盤沈下による海水の影響(塩害)で
翌年枯死が確認されました
しかし復興の象徴として後世に残すため
幹に防腐処理を施すなど保存整備が行われ
モニュメントとして元の場所に立っています
実は輪島朝市の焼け跡にも
『奇跡のタイサンボク』
がありまして
震災直後から
炊き出しで地域の食を支えてきた
ミシュラン一つ星のフランス料理店
「ラトリエ・ドゥ・ノト」のシェフ池端隼也さんが
震災後の春に
この木に芽が出てきたのを見て
新たに居酒屋を開店する際に
1 本だけ残ったこの木が芽吹いたように
輪島市の復興の芽となることを期待して
店名を『mebuki』としました
手前の建物は『陸前高田ユースホステル』
この建物が根元にあったおかげで
一本松は残ったのだと考えられます
こちらは水没した松の根株群
元々この松林は
江戸時代にたったひとりの翁が
防災のためにと私財を投げ打って
植林されたものだったそうです
翁の志を引き継ぐべく
新しい松林が植林されていました
これも震災遺構です
なんだと思いますか
復旧工事のための大量の土砂を運搬する
ベルトコンベアーの橋の橋脚です
この橋のおかげで
トラックの運搬だけだと9年かかる
と試算されていた工期が
わずか1年半に短縮されたのだそうです
工事が終了しても
住民が「残して欲しい」と
感謝を込めて残すことにしたのだそうです
震災遺構『気仙沼中学校』です
誰かが亡くなられた場所が
『震災遺構』になることは基本ありません
この中学校も死者ゼロでした
当時の写真がこれです
震災の1年前に赴任された校長先生が
実際に避難場所まで歩いてみて
これでは危険だと
避難場所を設定し直して
避難訓練を徹底したことが
生徒全員の命を守ったのです
『東日本大震災津波伝承館』を訪れました
鉄橋の切れ端です
1cm以上もある分厚い鉄板が
引きちぎられています
被災した消防車です
主査の須貝 翔 先生に
案内していただきました
高校の先生をされているのですが
教育委員会からの出向という形で
震災の伝承をされているそうです
とても良い制度です!
須貝先生から
素敵な詩を紹介していただきました
「人はみんな過去を持ち
現在があって未来がある
その時々に出会いがあり
別れがある
風の電話はそれ等の人と話す電話です
あなたは誰と話しますか
それは言葉ですか
文字ですか
それとも表情ですか
風の電話は心で話します
静かに目を閉じ
耳を溢ましてください
風の音が又は浪の音が
或いは小鳥のさえずりが聞こえたなら
あなたの想いを伝えて下さい
想いはきっとその人に届くでしょう」
伝承館のある祈念公園は
高い防波堤に守られています
防波堤に登ると献花台がありました
未来に向けて大切なことを伝えていく
その思いを新たにしました
「気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館 」です
予約を入れてガイドツアーしていただきました
ガイドは元中学校の菅原校長先生でした
ここは元々水産高校だった場所です
津波の跡そのままの部屋
3階の教室には流された車が
校舎の間には何台もの車が
当時は濁流が渦巻き
洗濯機のようだったそうです
流されてきた冷凍倉庫がぶつかった跡
つまり屋上近くまで水位が上がったのです
その日は入学試験があった翌日
生徒は全員避難したのですが
一部の先生は入試の答案を
3階4階へ運ぶために残ったそうです
その結果無事合格発表まで
こぎつけたのだそうです
それを指示された校長先生には
敬意を表します
私だったらできないと思います
命よりも大切な紙切れなんかあるか
と思うからです
どちらが正解かはわかりません
逃げ遅れた先生方は屋上に避難しました
屋上への出入り口は通常施錠されています
何という判断力でしょう!
校務員さんがこんなこともあろうかと
逃げる前に鍵を開けておいたそうです!
下は避難した屋上の写真です
津波は屋上に迫る勢いでした
「女は電柱の上に登れ!
男は手すりにしがみついて耐えろ!」
と指示されたそうです
でも女性の先生方が
電柱に登れるはずもありません
そこにもうひとつの奇跡が
一緒に屋上に避難してきた方の中に
学校の工事に来ていた方がいて
ハシゴを持って避難して来ていたのです!
先ほどの写真の左手奥の建物の上に
全員避難できたのです
引き波で水が引いたのを見計らって
全員4階のじゅうたんばりの部屋へ移動しました
教室からカーテンを引きちぎってきて
寒さをしのぎました
見ると津波で流されてきた家が
校舎に引っかかっていました
一階部分はありません
声をかけると
中に女性がふたり
真っ暗闇の中
先生方は
「明るくなったら助けに行くからね!」
「頑張って耐えて!」
夜が明けるまで交代で声をかけ続けたそうです
翌朝先述のハシゴを使って無事助け出しました
いろんなことを学ばせていただいている旅です
気仙沼でちょっといい感じの
写真が撮れました
「みちのく一人旅」その壱
地震から 698 日目
始発列車で仙台に向かいます
海に浮かぶ小さなガラス箱
日立市出身の建築家である
妹島和世氏の設計による日立駅は
美しい駅ランキングで
東京駅 京都駅 金沢駅などと並び
必ず上位にランクインします
太平洋を一望できるロケーション
「展望スペース」からは
美しい朝日を見ることができ
絶景スポットとして人気を集めていますが
何せ出発が夜明け前でしたので

こんな感じです
今度来る楽しみができました
東北大学で開催されている
「世界津波の日」
"World Tsunami Awareness Day"
高校生サミットに参加しました
国連防災事務総長特別代表兼国連防災事務所長の
カマル・キショア氏より
ビデオメッセージが送られました
前方の座席にはヒジャブを被った
イスラム女子高生が座っています
彼女らに限らず
民族衣装を纏った高校生が
それぞれの国を見舞う災害と
その対策について発表し合いました
国際色豊かな会議です
来年はぜひ着物で参加しようと思います
さて週末を利用して
東日本大震災の震災遺構や
復興の様子を見て回るつもりです
まずはNHK仙台放送局を訪ねました
当時を伝える貴重なアーカイブを
見せていただきました
どんな大地震でも放送を続けることのできる
最新鋭のスタジオにも
入らせていただきました

見よこのミーハーぶり
次に平泉へ行ってみました
内陸にある平泉自体は
被害はさほど大きくなかったようですが
世界遺産に登録された毛越寺(もうつうじ)
仏の世界を表現した「浄土庭園」の池にある
趣深い傾いた岩「立石(たていし)」が
余震のたびに傾きが増したので
布を巻き付けたうえ添え木をして
倒れないように守ったのだそう
中尊寺は一部の建物の壁が壊れるなどの
被害を受けました
表門は柱が傾くなど被害が大きく
本格的な修理のための
クラウドファンディングをしています
発災時は
避難所として被災者の受け入れも
おこなっていたそうです
世界遺産であっても
非常時はそうなるのですね
次に一関に行ってみました
『祭畤橋(まつるべばし)』の
崩落事故がありました
橋脚の地盤そのものが
11mにわたり
地すべりを起こしたことが原因でした
崩壊した橋はそのまま
「災害遺構」として保存されていて
整備された周辺の公園から
見学する事ができます
一関市街地には磐井川が流れます
太平洋から86kmあるので
さすがにここまで
津波は遡上しなかったようです
川のほとりには
N.S.P メモリアルがありました
ここから見える夕暮れの風景が
名曲「夕暮れ時はさびしそう」
の舞台だそうです!
N.S.P は一関工業高等専門学校の同級生の
フォーク・グループです
ギターを形どったベンチに
上品な女性が腰掛けていらっしゃったので
声をかけてみました
昨日は中村貴之さんの命日だったそうです
同じく既に亡くなった天野滋さんの
実家も教えていただきました
平賀和人さんはご健在で
今も草野球に夢中なんだそうです
私が初めてギターを弾けるようになったのは
N.S.P の「八十八夜」でした
仙台と茨城県でそれぞれ
地震から 697 日目
東北大学で
世界津波の日高校生サミットが
開催されています
以下現場の岡本先生より
「本校からは2名の生徒が参加しています
英語でのプレゼン発表は
緊張のためか少したどたどしかったですが
適度に笑いを取り
聴衆の方々には
輪島のことにも
興味を持っていただくことができました
生徒2人はとても頼もしく
学校に戻ってからも
今回の経験を他の生徒たちに広めてくれそうです
それぞれ「もっと英語話せるようになりたい!」
と思ったようで
これをきっかけに
たくさん練習してもらおうと思います」
さて私はといえば
茨城県県北高等学校からのお招きを受け
お話をさせていただきます
移動の新幹線
新幹線のトイレには
男性用小便器の他に
女性専用と男女兼用があります
見ると女性の長蛇の列が…
男女兼用が空いてるのに…
ひとりの女性が男女兼用に入るや否や
嫌な顔をして出てきて譲ってくださいました
入ってみると
「これか…」
立ってするもんだから
あっちこっちに溢れています
こっち使う時は座ってしましょ
自分が汚したと思われたら嫌なので
掃除して出ました
風味豊かな「笠間の栗」を贅沢に使用した
極細モンブランが人気です
注文を受けてから目の前でクリームを絞るので
栗本来の香りと食感を楽しめます
そのため「賞味期限5分」だそうです
道の駅かさまの笠間モンブラン
がおすすめというテレビ番組を見たので
お昼はそれにしようと思いましたが
時間が無くて断念で残念です
講演開始まで時間があり
野口雨情記念館を訪れました
『赤い靴』や『シャボン玉』
で知られます
『シャボン玉』は
裏付ける資料こそ残ってはいませんが
生後数ヶ月で亡くした我が子へ
歌ったものだそうです
そう思って聞くと2番の詩
悲しく心に響きます
「シャボン玉消えた
飛ばずに消えた
生まれてすぐに
飛ばずに消えた」
入口の雨情像の前に立つと
曲とともに
シャボン玉がいっぱい飛ぶ仕掛けが
さて昨日紹介した「学び舎ゆめの森」のように
個別最適な学びを重視した設計の校舎が
全国的に増えてきています
SSRが多くの小中学校で取り入れられています
SSR「スペシャルサポートルーム」は
教室に入ることが難しい児童生徒のための
「心の居場所」であり「学びの居場所」です
石川県の小中学校では半数以上の学校に
設置されています
ひとりで学習に集中できるブースや
寝転んだりトランプで遊んだりする
畳のスペースがあったりします
今思い出すと
自分の娘たちにとって
じいちゃんばあちゃんの家が
この役割を果たしていました
ところが子供が来なくなるSSRが
最近増えているそうです
ある中学校では
校長が巡回してきて
「教室で勉強しなさい」
と繰り返し言いました
不安を拭えず
ぬいぐるみを抱きしめていた女生徒には
「中学生にもなって」と…
結局その子たちは教室に戻るどころか
とうとう学校に来れなくなりました
「せっかくほっとできる場所だったのに」
支援員は肩を落としました
誰も来なくなったSSRは
ついに閉鎖されたそうです
学校の方では期末考査が行われています
インフルエンザの流行により
先週末は学年の半分ほどの欠席で
学年閉鎖及び考査の延期も
視野に入れていましたが
みなさんの蔓延防止の意識高く
予防に努めていただいた結果
欠席者は最小に収まっているようです
欠席しているみなさんは
考査を欠席したことだけを理由に
成績が不利になることはありません
その点は心配しないで
元気になることに専念してください
さて以前にもこのブログに書いた
「最後のひとつが思い出せない」問題
今日直面しているのは
「接待の5せる」です
思い出せたのは
『食わせる』
『呑ませる』
『◯◯せる』
『威張らせる』
3つめは社会通念上問題があるので
伏せ字です
冒頭にも書きましたが
茨城県県北高等学校校長会のみなさまから
本日お招きいただき
お話をさせていただきました
みなさん東日本大震災当時は
学校の中核として
生徒の安全確保
そして教育の再開に向けて
ご活躍されていた方ですので
当時のことを思い出されながら
真剣に聴いてくださいました
自己主張が限りなく下手な能登の人間は
黙って耐えていますが
とある県の知事からは
「今回の復旧が前例になってしまうと
他の地区に起こった際に
同じような扱いをするぞと
宣言されたようなものである」
と危惧なさっています
阪神淡路大震災の際には
倒壊した家屋の処理費用も自費負担でした
我々が今回当然のように受けた
「公費解体」の制度は
その時の方々が
声を上げてくださったおかげなのです
であるならば
今私に課せられた使命は
今回の地震で思い知らされた負の側面も含め
多くの方に伝えていくことであると
思っています
つい最近誰かに聞いた話ですが
「能登」って
「能く登る」って書くんですよね
今回何千年に一度という地殻変動で
4mの土地の隆起が見られましたが
地質調査の結果
能登半島は
土地の隆起の連続で形成されたものである
ということがわかっています
地名の由来を調べると
その土地の災害リスクを予測することができます
大阪の「梅田」は元々「埋め田」
田んぼを埋め立てた土地なので
地盤が弱く液状化が危惧されています
講演会の後
懇親会もご一緒させていただきました
思う存分
『食わせて』
『呑ませて』
『威張らせて』
いただきました
学び舎 ゆめの森
地震から 696 日目
しばらく連載をお休みしていた間
何をしていたかというと
まずは東北へ復興を学びに行ってきました
今日ご紹介するのは「学び舎 ゆめの森」
福島県双葉郡大熊町にあります
ここは東日本大震災震度 6 強を観測
死亡者 53 名を出す被害を受けました
さらには福島第一原発の事故により
立ち入り禁止区域に指定されました
そのうち特定復興再生拠点区域は
2022年に避難指示が解除され
通行証なしで自由に出入りできますが
宿泊はできません
一方で帰還困難区域は
依然として立ち入りが禁止されており
国の許可なしに立ち入ることはできません
そんな中で
子どもたちの学びの場を確保するための
並々ならぬ努力がありました
そして今では
認定こども園での「あそび」と
義務教育学校での「探究」をつないだ
遊びの中から多くを学び
子どもと大人が一緒になって
みんなで未来を紡ぎ出す
そんな魅力的な学校になって
全国から子どもたちが
集まってくるようになりました
玄関をくぐると目に飛び込んでくるのがこれ!
図書館です
石川県の方
どこか見覚えありませんか?
石川県立図書館「ビブリオバウム」を
参考にしたそうです
毎朝ここで全校生徒が集まって朝礼します
チャイムは鳴らないそうです
自分たちでタイムマネジメントします
実は輪島高校も昨年からチャイムを止めまして
生徒も教員も時間に厳密になり
チャイムが鳴っても廊下でザワザワという
以前のようなみっともない姿は
見られなくなりました
教室の形はいろいろです
四角い教室はありません
そしてふたつとして同じ教室もありません
こんな隠れ家のような教室や
こんな寺子屋のようなお座敷教室も
こちらは音楽室
一段高く設計されています
普段は壁で仕切られていますが
このように壁を取っ払うと
演奏会ができるステージになります
楽器庫はガラス張り
楽器がオブジェになっています
のんびり読書のできるスペース
こちらは職員室の入り口
対面型のテーブルが設置されており
子どもたちが質問できる
スペースになっています
校庭に出ると
大阪・関西万博の大屋根を思わせる
吹き抜けと回廊
校庭でお米を作っています
自分たちで育てたお米で
調理実習しています
こんな素敵な学校ですが
校舎が完成したのはごく最近
それまではずっと間借りしていました
先生方は
被災したこの地で
子どもたちにどんな力をつけるのか?
そんな姿になって欲しいのか?
そのためにどんな学校が必要か?
そのことを徹底的に議論し続けたそうです
「最初に箱物ありきでは
うまくいかなかった」
校長先生はそうおっしゃっていました
その時の議論のホワイトボードをそのまま
一室に残してありました
魔法のように突然素晴らしい学校が
できあがるわけでは決してありません
そこに至るまでは
学校と保護者そして行政が一緒になって
子供達の将来を真剣に考える
プロセスが必要なのです
「学ぶ環境が整っていない輪島にはいられない
一家転住して転校させよう」
と考えている小中学生の保護者の方は
一歩立ち止まって考えていただきたいのです
環境さえ変われば勉強するようになるのですか?
与えられる学習環境を待つだけでよいのですか?
子どもたちの将来を
親も一緒に真剣に考えざるをえないこの環境こそ
子どもたちに本物の力をつけさせるチャンスです
他所者若者馬鹿者あつまれ〜
地震から 695 日目
動摩擦係数に比べて
静止摩擦係数はかなり大きいです
平たく言えば
動いているものを動かし続けることに比べて
止まっているものを動かし始めるのは大変
ということです
「やる気が出ないのですが
どうしたらいいですか?」
という人生相談には
「やる気なんか出さなくていい
やる気がないまま始めなさい」
と答えています
脳みそは本当に単純な馬鹿タレで
動いていると簡単に騙されて
やる気がでてくるのです
さてさてしばらくお休みしていたこのブログ
講演原稿と執筆原稿の目処が立ちまして
本日より再開です
決してやる気がないわけではなく
むしろお休み中におもろいことがたくさんあって
書きたいことは山ほどあるのですが
どうも静止摩擦係数がことのほか大きく
何から書こう?
変に考えすぎてなかなか進みません
とりあえず
今日の素敵な出会いの話から
よそもの
わかもの
ばかもの
地方創生の鍵を握ると言われています
とりわけ
私はばかものが大好きで
いつもばかものを追い求めています
そんな素敵なばかものたちに
今日はいっぱい出会いました
このブログを再開するための起爆剤としては
充分すぎるパワーでした
この出会いをセッティングしてくれたのは
「日本の教育を変える!」
と息巻いて日本を飛び出した先で
能登半島地震の知らせを聞きつけ
いち早く帰国したまではいいものの
輪島に着いた途端に行き倒れ
忙しい被災民の手を煩わすという
荒技をやってのけ
以来輪島高校に籍を置きながら
被災地ガイドツアーで大人気を博している
本校きってのうつけ者
「てるてる坊主」です
能登里山空港の麓の三井町にある
『のと復耕ラボ』に
素敵なばかものたちが大集合しました
元々この地で開業していた
「里山まるごとホテル」
地域がまるごとひとつのホテルとなり
かまどのご飯や
縁側での昼寝
囲炉裏ばたでの食事など
能登の暮らしをまるごと堪能できる処
地震のため今は休業していますが
その場所を
ボランティアの方が休憩でき
交流が生まれる起点として活用している
それが『のと復耕ラボ』です
そんな素敵なみなさんをご紹介します!
まずはこの「能登若衆の会」のお頭
古矢拓夢さん
能登が大好きな熱い若者の会です
金沢のご出身ですが能登にも縁が…
実は飯田高校で校長先生を務められた
上乗秀雄先生のお孫さんです
本人曰く
Uターンならぬ『孫ターン』
上乗先生はご自身の退職金で
『ケロンの小さな村』を作られました
自然の中でひっそり暮らす
小さな生き物の観察や
米粉で作ったパンやピザが大人気の
自然体験村です
お頭は現在そこを経営なさっています
そんなお頭を慕って集まった
愉快な仲間たち
まずは加藤愛梨さん
東京から移住されました
防災コンサル Mutsubi を主宰されています
のとの復興に取り組む
若手人材育成を手がけ
Mutubeで能登の様子を配信されています
そしてその Mutsubi でのインターンシップ
山本浩毅さん
地域の事業者への
環境観光コンテンツ企画や
プロモーション代行を手掛けています
能登の魅力を YouTube『のとのと』
で配信されています
鎌倉出身の藤田ちはるさん
ゲストハウス黒島で働いていたのがきっかけです
高校生の時から仲間と一緒に
被災地支援や防災に取り組んできました
現在上智大学新聞学科で
防災教育を研究なさっています
高崎稚春さん
大分や静岡での災害ボランティアの経験を活かし
現在柳田植物公園の
指定管理者をされています
本谷悠樹さん
洪水被害の大きかった生まれた町野町へ
水害後に戻ってきました
子供の頃は大阪で過ごされ
高校は日本航空石川
現在 災害復興ラジオ「FMまちのラジオ」で
週一回木曜日にレギュラー出演されています
能登町ご出身の上野壱生さん
福井の高校を出られた後
現在牧場で肉牛のお世話をしてます
金沢大学融合学域の岡本岳人さん
合同会社SandBoxConectionsを
立ち上げられました
留学支援や
企業向けの海外への進出支援を
手掛けていらしゃいます
同じくSandBoxConectionsの花田怜大さん
七尾地域おこし協力隊として
御祓(みそぎ)地区活性化として
空き地空き家の利活用をされています
その他『マタギ』をされている方もいらっしゃいました
渋い職業ですね
石川県に若者の就労を支援するセンターがあり
そこに職業の適性を見極めるマシンがあります
質問にYes Noで答えていくと
ぴったりの職業を教えてくれます
一度生徒を連れて行ったことがありますが
出てきた職業が
『マタギ』
『キコリ』
『鷹匠』
『狂言師』
『床山』
よっぽど連れて行ったメンバーが
個性的だったのか
それともそのマシンの設定が
ぶっ飛んでいるのか
どうやってなるんだ?
って職業のオンパレードでした
その他全員の声を聞くことはできませんでしたが
とにかく素敵な仲間たちです
今後は
地元の若者たちと
どんどん繋がっていってもらいたいです
輪島高校では
毎週木曜日の午後に
街づくりプロジェクト『街プロ』をしていますので
みなさんぜひ遊びに来てください!!
休載のお知らせ
いつも読んでくださり
そして暖かい励ましのお言葉
ありがとうございます
しばらく「おこらいえ」の投稿を
お休みさせていただきます
講演と原稿執筆のご依頼が
立て込んできたことによります
中でも
OECD(経済協力開発機構)様からは
「未来の教師へのラブレター(仮)」
を書かせていただけることとなりました
震災体験を経て感じている
未来の教育への思いを綴ります
この「おこらいえ」の総集編
とも言うべきものになるのかなと思います
再会の目処は12月を考えています
生徒の活動につきましては
「輪高生の活動記録ブログ」にて
更新してまいりますので
引き続き応援・伴走
よろしくお願いいたします
ご来場ご視聴ありがとうございました
地震から 671 日目
豪雨から 407 日目
たくさんの方々に見守られて
「MAJI で WAJI 活」
行われました
ウエルカムボードは
「WAJI活公式キャラクター」であり
「輪島市未公式キャラクター」でもある
ワジねことフグたろう
これも生徒の作品です
お客様を迎えます
午前中は5つのステージ発表がありました
発表の内容はZOOMで配信し
全国のみなさまに見ていただきました
お昼にはキッチンカーが来てくださいました
「からてん」さん
なかよしのおふたりでやってます
からあげっ 揚げたこやきっ
フルーツドリンク
お品の最後にちっちゃい「っ」
が入るのがおちゃめです
金沢港クルーズターミナルに
よく出店されているそうです
「ふしぎなネッシー」さん
ドリンクとスイーツの専門店
オリジナルメニューの
「バーボー」がおすすめです
バームクーヘンを棒に刺して
だから「ばーぼー」
かわいくペイントしてあります
キャラクターのオリジナルネッシー
金沢の小さな公園でひっそり開店
なので店名が「ネッシー」
お目にかかるのがちょっと難しくて
でも見かけるとしあわせになれます
「萬屋おてる」
元気いっぱいテルさんのお店です
牛ロース串やオムそば チヂミ
定期的に被災地輪島に来てくださり
「ワイプラザ」などにも
出店してくださっています
今度は珠洲にも行かれるそう
こんなお店にも来ていただきました
四十沢木工工芸さんの作品になります
輪島塗の木地で被災地の涙を形どった
震災後に生まれた作品です
さまざまな支援で輪島に来られる方が
被災地にはお土産が売られていないので
金沢のお土産を買って帰られることに
さびしさを感じ
今できる輪島のお土産をつくりだされました
四十沢さんはその他にも
や
Sudo Masahiro Quartet Jazz Live.pdf
など
被災地元気づける
さまざまなイベントも
手がけていらしゃいます
キッチンカーも持ってきて
手作りスイーツや焙煎コーヒーを
振る舞ってくださいました
「WAJI活」でカフェを経営しているふたりも
玄関先でコーヒーを振る舞いました
お昼には供用間近の
仮設校舎内覧会も行われ
保護者をはじめ
多くの方々にご覧になっていただきました
こちらは「内田洋行」さんからのご寄付
新しい職員室に入れられた
フリーアドレス対応の
先生方の机と椅子です
新しい職員室を
先生方が働きやすい環境にしたい
とお願いしたところ
今回のご寄付につながったものです
内覧会に訪れた方からは
「どこかの I T 企業のオフィスみたい!」
と感嘆の声が聞こえました
午後からはポスターセッション
ポスターを円形に配置し
中央に設置した360°カメラから
全ての発表を配信できるようにしました
こちらの機材を今回ご提供くださったのは
音響機器の
「アバー・インフォメーション」様
今回こんな発表会にしたいと
提案させていただいたところ
こんなに素晴らしい機器を
ご準備してくださいました
全てのポスターセッションの様子が
ズームや移動も思うがままに
リアルタイムに送信できること
しかも周りのざわめきに関係なく
発表者の音声だけを
クリアに捉えることができる技術に
驚きでした
オンラインでご覧になってくださった方は
実感されたことと思います
クロージングでは
2年生の小町さんが
感動的なご挨拶をしてくださいました
最後には
「フードバンク愛知」様からの
ドーナツなどの支援物質を
岩本様が届けてくださり
会場のみなさんに配られました
防災用おにぎりの提供も
たくさんの方々にZOOM配信でも
お楽しみいただきました
以下
お寄せいただいた感想を
ご紹介させていただきます
「本日『街プロ』を視聴させて頂きました。生徒の皆さん、凄いですね。どんな取り組みをするかよく考えて取り組まれた様子がとてもよくわかりました。午後からしか見れなかったんですが、高校生の目線とは思えないくらい、課題や考察、今後の取り組みの展望など、しっかりと考えられていて、楽しく拝見させて頂きました。高齢化の進む現代に地域課題を若い世代が一緒に考えて自分達の社会を「こうしていきたい」「こんな風になったらいいな…」と考える事ができるのはとても重要ですね。私達リハビリテーションの取り組みも、「地域共生社会」の実現がキーワードになっていますので、改めて考えさせられました。」
新潟県より 言語聴覚士の堂井真理さま より
「『街プロ』発表会、リモートで拝見しましたが、生徒さんたちの表情が生き生きとして、とてもよいイベントでした。発表内容はバラエティに富んでいましたが、AIや発酵発電などには感心しました。何よりも、「街プロ」が地域に根付いた取り組みになってきていることが感じられて、喜ばしかったです。ご苦労様でした。」
RISE(ライズ)理事 岩見 一太 様 より
「千枚田の復興の子達と是非一度お話しが出来ればと思いました。直接訪問出来るタイミングとしては恐らく12月以降になってしまいそうですが、来年4月のイベント時に輪島高校ブースを設置して、クッキーの販売や活動PRをしてもらえないか?と相談出来ると幸いです。」
umbling Dice Records 大石 崇史 様 より
「これからの地域の主役である輪島高校の皆さんが、元気に、明るく積極的に活動できていることが伝わってきて、とても嬉しく思いました。輪島高校の探究活動は地域との繋がりが強く、活動性の高さを感じています。特に、自分たちで考え、試行錯誤している様子が伺え、今後につながる体験ができていると思いました。最後の生徒さんの挨拶を聞いて、輪島高校の探究活動自体が、輪島の活性化に繋がっている、役立っているのではないかと思いました。近い将来、輪島にお邪魔し、皆さんと交流できることを楽しみにしています。」
久留米大学 安永 悟 教授 より
その他紹介しきれませんが
ありがとうございました
明日は「MAJIでWAJI活」
地震から 670 日目
豪雨から 406 日目
震災直後
来れる生徒だけで集まって
傾いた体育館の冷たい床に
輪になって座って
「どうする?これから・・・」
見えない明日に向かって
たわいもない話から始めて
「上から降ってきた復興計画に
そのまま乗っかるな
僕らのまちは僕らがつくる!」
傷ついたふるさとを
元の形に戻そう
そうやって始まった
街づくりプロジェクト「街プロ」
明日はその発表会です
たくさんの方々に寄り添っていただき
励まされここまできました
明日に向かうたくさんの勇気をいただきました
その感謝の心をこめて
これまで取り組んできたことを
それぞれが発表します
明日の様子はZOOMで配信します
ミーティング 276 485 4778
パスコード 222105
で入室ください
9:50 スタートです
無料版ZOOMを利用していますので
40分経過したら接続が切断されてしまいますが
同じミーティングとパスコードで
入室しなおしてください
ご面倒をおかけしますが
よろしくお願いいたします
配信スケジュールは次のとおりです
【ステージ発表】
10:10 らくして防災 ~防災✕AI~
10:25 ヤマメ大捜査線 in 輪島
10:40 スポーツで健康 ~訪問型ジム~
10:55 猫も人間も食べられるお菓子
11:10 神戸震災学習ツアー
【ポスターセッション】
13:00 能登のまいもんを広めよう
13:10 積雪発酵発電
13:20 高齢者といっしょ~心も身体も健康に~
13:30 未来へつなぐツアー
13:50 心も輪島も未来も明るくしよう
14:00 ペットと安全に避難するには?
14:10 災害に向けた電源づくり
14:20 千枚田の復興
今回配信機器をご提供してくださったのは
アバーインフォメーション株式会社様
360°カメラで全方向のポスターを捉え
高性能マイクで
ざわつくポスターセッションの中から
ピンポイントで目的の音声のみを拾います
クリアで臨場感ある音声をお試しください
こちらは使用する機器のパンフレットになります
今回無償でご提供いただけることになりました
ありがとうございます
じゃんけんの壺
地震から 669 日目
豪雨から 405 日目
2年前の大晦日
忙しすぎて帰省できずに
そのうち帰ろうと
アパートでお正月を迎え
被災してしまい
そのまま何ヶ月も
車中泊をせざるを得なかった
山崎裕貴先生
情報科の彼がいてくれたおかげで
輪島高校のネットワークは
1月4日に全面復旧するという
奇跡を見せるわけです
その山崎先生の研究授業が行われました
楽しみながら
プログラミングの技術を身につけます
試行錯誤しながら
諦めない力や順序立てて考える力を
身につけます
山崎先生曰く
「今日の授業は数学に例えると
因数分解ができるように
なったレベル
これから様々な技術を身につけると
アプリ開発できるようになる」
とのことでした
隣のクラスでもおもしろそうな授業をしていますよ
山上 佳織 先生の家庭一般
本物の和服の10分の1
ミニチュアの着物づくりです
和装の基礎とその特徴を学びました
昨日お越しになった
山梨県立興譲館高校さん
支援金をくださるとともに
牛奥商店様からの寄付金も
お持ちくださいました
株式会社まもかーる様も
一緒に支援金を持ってきてくださいました
本当にありがとうございます
輪島実業高校の元同窓会会長の椿原様
「元」というのは
現在は「桐章会」役員だからです
「桐章会」は輪島高校の同窓会組織
震災直前に迎えた
輪島高校の創立百周年の際に
両校の同窓会組織が一緒になりました
輪島実業高校は
元々は輪島高校の商業科
戦後のベビーブームにより
独立したのですが
少子化により募集停止
輪島実業高校の商業科や
輪島塗職人を養成するインテリア科の
優れた教育実践は
現在の輪島高校普通科ビジネスコースに
脈々と引き継がれています
いわば元の鞘に収まった
という形でしょうか
一時期両校は仲が悪く
同窓会組織が一緒になることに対して
苦情やお怒りの言葉も聞きました
しかしながら
昔のしがらみを捨て
親の出身校に関係なく
これからの輪島の子どもたちを
一緒に力を合わせて育てていくことが
重要であると判断しました
話は大きくなりますが
日韓関係もそのようになればいいなと
新しい総理の手腕に期待しています
さてその椿原様が
被災した自宅から見つけた
1952年の輪島高校の卒業アルバムを
学校に寄付してくださいました
戦後わずか7年後のアルバムには
戦後復興の中心となっていく
若者の姿が凛々しく写っていました
まるで当時の映画のポスターのような
何ともおしゃれなアルバムです
みなさんにお願いです
被災した家の片付けの際に
このような昔のアルバムありませんか?
ありましたら
輪島高校に寄贈していただけないでしょうか
ある年度以降のものは揃っているのですが
貴重な資料として揃えたいと考えます
3年生「英語探究」選択の生徒たちが
「海の星幼稚園」を訪れ
園児たちとの交流を楽しみました
まずは「じゃんけん列車」
英語でじゃんけん
「Rock Paper Scissors!」
話はそれますが
フランスのじゃんけんには
石 ハサミ 葉っぱ(紙)のほかに
壺があります
グーを緩めて丸い壺を作ります
石やハサミは沈むので壺に負けますが
葉っぱは浮かぶので壺の負けです
ちょっとややこしいのですが
色々駆け引きがあって面白そうです
次はクイズ
そして絵本読み聞かせ
「きんぎょがにげた」
「はらぺこあおむし」
「Good Morning Mr. Moon」
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
今日が最終回
(21)未来へつなぐツアー
さあどんな未来が待っているのでしょう
ご覧になってのお楽しみです
当日はお昼にキッチンカーも来てくださいます
できたばかりの仮設校舎のお披露目会もあります
内田洋行さんからご支援いただいた
フリーアドレス制の職員室も
ご覧になれます
ぜひお越しください
また
360°カメラで発表会の様子を
同時配信します
お越しになれない方は
どうぞご覧ください
被災地の生徒たちが思い描く
未来のふるさとを
ぜひご覧いただきたく思います
ようこそ!興譲館高校 ご一行様
地震から 668 日目
豪雨から 404 日目
山梨県立都留興譲館高等学校のみなさんが
本校を訪れてくださいました
以前に
本校生徒のアイデアを形にした『応援弁当』と
『能登復興・輪島高校復興祈願竹灯籠製作』
でお世話になった
DJ KOUSAKU さんが
連れて来てくださいました
先日万博のフィナーレで朗読した
正角 心音 さん
実は『応援弁当」にも携わっていて
玄関でKOUSAKU さんと再会を果たしました
万博閉会式の話をすると
「フィナーレ見たよ
櫻井くんと出てたね
実はうちのバンドのメンバーが
『嵐』に楽曲提供してるよ」
とのこと
何?この引き寄せ

自ら希望してきてくださった
心優しい10名の生徒さんと
ふたりの先生方です
ビジネスコース1年生と交流しました
校舎案内のあと
山上 佳織 先生による
防災に関する授業を受けました
グループワークの結果を発表する場面では
両校の生徒で絡みながら発表する
グループも見られました
岡山県立興陽高校さんと開発したバスソルトを
お土産におあげしました
輪島高校の「さかなクン」
伊奈岡克俊 先生の研究授業です
伊奈岡先生は生物が大好きで
いつも楽しそうに授業をする
と生徒から評判で
生物の楽しさを知り
自分も生物学に進みたいという
卒業生を何人も送り出しています
今日は血液型の話です
ゴリラの血液型は全員B型
よく言われますが
実はそれは正確ではなくて
確かにニシローランドゴリラは
全員B型だけど
ゴリラ全種でいうと何種類かあります
というトリビアを導入として
DNAの塩基配列とアミノ酸配列
の関係を学びました
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(18)千枚田の復興
(19)カフェと音楽で輪島を活性化させる
コーヒーは漢字で「珈琲」と書きます
考案したのは幕末の蘭学者
宇田川榕菴(うだがわようあん)です
「珈」は髪に挿す花かんざし
「琲」はかんざしの玉をつなぐ紐
をそれぞれ意味する字です
コーヒーの赤い実が
当時の女性が髪に飾っていた
「かんざし」に似ていることから
つけたそうです
「琲」の王篇を糸篇に変えると
「緋(あか)」になりますし
なんともセンスの塊です
「酸素」「水素」「細胞」なども
彼の命名によります
「酸」の素は実は水素イオンなので
「酸素」は誤訳といえば誤訳
なんですけどね
(20)運動で市民同士の絆を深めよう
被災地でもできるスポーツ
子どももお年寄りも一緒に楽しめる
そんなスポーツを考えています
例えばモルックのような
モルックは
フィンランドのカレリア地方の
伝統的なゲームであるキイッカ(kyykkä)を元に
1996年に開発されたスポーツです。
木の棒を投げてピンを倒す
ボーリングのようなスポーツです
床が傾いている本校の体育館でやると
投げた棒が
ひとりでにコロコロと戻ってくるという
オートマチックモルック場と
なるのでした
今回の発表会はその傾いた体育館で行います
紅白歌合戦を中継した時に
待合室として使用していた場所です
そんなところもぜひご覧になってください
能登で被災した高校生たちはいま
地震から 667 日目
豪雨から 403 日目
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(15)輪島をゆるキャラで盛り上げよう
今では観光地のマスコットとして
全国展開している『ゆるキャラ』
もともとは
イラストレーターのみうらじゅんさん
が考案したものです
『ゆるキャラ』には3つの条件があるそうで
① 郷土愛に満ちた強いメッセージ性があること
② 立ち居振る舞いが不安定でユニークであること
③ 愛すべき「ゆるさ」を兼ね備えていること
ちなみに「マイブーム」もみうらさんの造語
「ゆるい」+「キャラクター」=「ゆるキャラ」
「マイ(私)」+「ブーム(大衆)」=「マイブーム」
既存のものを組み合わせて
新しいものを創り出しているのですね
(16)災害に向けた電源づくり
さあ今回のエネルギー三部作の最後
昨年つまり被災1年目の『街プロ』では
子供やお年寄りの居場所づくりの
探究が目立ちました
今年はエネルギー
つまり被災経験を経て
次の世代へどう繋げるか?
をテーマにしたものが目立ちます
生徒たちの心の持ちようも
少しずつ未来に向かって
変わってきています
(17)ペットと安全に避難するには?
輪島高校では
避難所として
ペット同伴者の部屋を
ひとつこしらえました
ペット同伴避難の実現に向けての活動を
展開されている団体の方の話によると
学校を避難所として運営するときに
ペットを入れると
避難所を閉鎖した後
その部屋に生徒を入れることが
衛生上問題である
という理由でなかなか進まない
という話です
何ら問題がなかったことが
今回実証されましたけど
いかがでしょう?
朝日新聞さんから
「能登で被災した高校生たちはいま」
という動画のLINKをいただきました
https://m.youtube.com/watch?si=tqQGPmWELN0YFEyz&v=YPL9MfEWKdk&feature=youtu.be
24分ほどの動画になります
もとよりもっと
地震から 666 日目
豪雨から 402 日目
東陽中学校の高校説明会に行ってきました
素敵な教育目標を見つけました
「もとよりもっと」
短い言葉の中に
深い意味が込められた
素晴らしいメッセージですね
東陽中学校は
地震はもとより
半年後の豪雨で
甚大な被害を受けた場所です
氾濫した河川の両岸には
おびただしい数の土嚢が
痛々しいまでに積まれています
それでも少しずつ
ほんとうに少しずつですが
前に進んでいます
傾いた電柱の横に
新しい電柱が建てられていました
「もとよりもっと」
よくなりますように
途中の道路
一旦傾きが止まっていたのですが
またひどくなってきています
今日は急に寒くなって
冬の日本海を思わせる荒波です
隆起してできた新しい海岸と織りなす
コントラストは
ドラクロワの絵画のようです
先日「商い甲子園」でお世話になった
藤原美江さまから
すてきな贈り物をいただきました
流木アートでしょうか?
おしゃれなトレイです
11月1日の「MAJIでWAJI活」
街プロ発表会にお越しくださった方で
ご希望の方に差し上げます
またいっしょに活動してくださった
高知商業高等学校ジビエ部と
三重県の青山高等学校のみなさまからも
支援金をいただきました
ありがとうございました
OECD(経済協力開発機構)から
「ティーチングコンパス2025」 が
リリースされました
未来における理想の教員の姿を
描いたものです
本校もご指導いただきながら
作成に関わらせていただきました
ぜひごらんになってください
ポンチ絵も公開されています
世界各国からの参加者一覧です
Wajima High School (JAPAN)
の名前があります!
半島の最先端から
目指せ世界の最先端!!
商い甲子園
地震から 665 日目
豪雨から 401 日目
高知県は安芸市で行われている
全国商い甲子園に出店する機会を
いただきました
発災以来いろいろと
寄り添ってくださっている
藤原美江 先生に
お繋ぎいただきました
藤原先生は
「はりまや橋デザインコンテスト」
でグランプリを取られ
以来この大会の顧問を
務めていらっしゃるそうです
「土佐の高知の播磨屋橋で
坊さんかんざし買うを見た
よさこいよさこい」
江戸時代の
僧侶の「純信」と
少女「お馬」の恋物語
かんざしを買った「坊さん」は
実は「純信」ではなく
「お馬」に横恋慕する「慶全」
さらにはふたりを引き裂くために
嘘の噂まで流します
当時僧侶は妻帯が禁止されていたため
噂が広まり捕まるのを恐れ
「お馬」と「純信」は駆け落ちしますが
結局捕まりふたりは引き裂かれます
そんな悲恋物語の残る高知
そのお隣の安芸市での商い甲子園です
開会式で入場行進
四国の高校を中心に全国から集まりました
出店のみなさんをご紹介します
高知中央高等学校さん
近森産業さんとコラボしての
カツオ香る高知の揚げ餃子です
高知県立檮原高等学校さん
ワイン用のブドウで育てた高知牛
廃棄食材で作った
フードロスにも配慮したカレーです
高知県立山田高等学校さん
香美市の三谷ミートさんの
大人気の手羽先とチューリップです
高知県立安芸高等学校
「あきこう防災特別課」のみなさん
被災地のために
募金活動をしてくださっています
高知県立宿毛高等学校さん
OBである「豊ノ島」関の
ご実家のお豆腐です
愛媛県立西条高等学校さん
商業科で経営するお店「めぐみソムリエ」
たぬきまんじゅうがおすすめです
全部紹介したかったけど
時間がなくて
回りきれませんでした
私は会場の一室を借りて
能登半島地震での経験を語る
講演会をさせていただきました
会場には地震の悲惨さを物語る
パネルも展示してくださっていました
アキ市だけにアキない甲子園
かと思ったら
もっと深い理由がありました
安芸市は岩崎彌太郎氏の生誕地
世界に名だたる
現在の三菱グループの礎を築いた
幕末屈指の経済人です
彌太郎は30代で「土佐商会」に務めます
土佐特産である
樟脳や和紙そして鰹節
それらを売り
軍艦や武器を買いました
彌太郎は
坂本龍馬ら海援隊の
給料の支払いも行ったそうです
現在輪島高校は
「三菱みらい財団」さんから
採択されて資金援助を受けていますので
生徒のみなさんは胸をはりましょう
我々は
坂本龍馬が給料をもらっていた人と同じ人から
資金援助を受けています
龍馬も我々も
日本の未来をつくっちゅうぜよ
帰路につきました
目の前に太平洋が広がります

アンパンマン電車も走っています
高知駅のホームはオシャレです
なんかヨーロッパにこんな感じの
なかったですか?
福岡第一高校さんでの「パラマ祭」で
頑張っている様子を
岡本先生が知らせてくださいました
生徒たち疲れも見えますが元気です。
朝食のバイキングでプリン2泊とも3つずつ
計6個食べた生徒がいます
昨日の様子をお知らせします
パラマ祭1日目
10時からの開場を目指し
福岡第一高校さんに向かいました
今回のパラマ祭では
きゅうりのバスソルト
とまとのバスソルト
藤のバスソルト3種類を販売します
これらのバスソルトは
輪島高校の生徒が
県外の高校 大学そして企業と
コラボして作ったものです
前日福岡に到着してから
ホテルで手分けして袋詰めしたので
自分たちで準備したからか
商品に対して愛着を感じているようです。
福岡第一高校さんの生徒会メンバーの力も借りながら
販売しました
みなさんの頼もしいこと!
お客さんに声をかけてくれたり
商品の説明を丁寧にしてくださったりしました
買ってくださる方の中には
能登の状況を聞いてくださる方や
「応援しています!」と声をかけてくださる方が
たくさんいらっしゃいました
今回「ペットと災害」について探究しているチームの
パンフレットも持参しました
ペットを飼っていてもいなくても
興味深く聞いてくださり
当時の状況も聞いてくださいました
せっかくパラマ祭に参加させていただいたので
今後の輪島高校のイベントの参考にするために
校内を散策もさせていただきました
輪島高校生徒会長の北村くんは
スマッシュブラザーズ大会に参加しましたが
結果は惨敗
勝てそうな要素は全くなかったそうです
ステージではたくさんのパフォーマンスが
披露されていました
今回のパラマ祭に向けて
みなさん準備をされているらしく
盛り上がりがすごかったようです
前回夜の体育祭でお邪魔した際にも感じましたが
福岡第一高校のみなさんは
それぞれが全力で学校行事を楽しんでいる様子です
自分の「好き」をつきつめ
表現している姿がとてもきらきらしていました
輪島高校も
そんな自分の好きを形にできる学校になると
いいなと感じました
どうでもいい話ですけど
新幹線の前の座席の網に
フリーペーパー戻す時
角っこが折れ曲がって
「イーッ」てなりませんか?

パラマ祭
地震から 664 日目
豪雨から 400 日目
福岡第一高校さんの「パラマ祭」に
お招きいただきました
個性教育の一環として展開されている
「パラマ塾」の成果を発表する学校祭です
『パラマ塾』は
「個性の伸展による人生錬磨」を具体化させた
個性の育成を目的とした
ユニークな塾形式の授業です
生徒一人ひとりが持つ「個性」を
引き出し伸ばし育てることを
目的としています
都築 仁子 校長先生のご挨拶より
「Parama とは
サンスクリット語の
『Parama-alta』
即ち「第一義諦」の略です
仏教語です
校名の由来となりました
個性の意味です
本校には福岡はもとより
全国そして海外からも
毎年多くの個性を持った
高校生が集結します
それぞれが
夢や希望の実現に向かって
パラマ塾を居場所にして
常に新しい自分
本当の自分に向かって挑戦し
それぞれが目指すものを
確実に手にしてほしいです
素晴らしいパラマ塾です
今年もアクティブな成功を祈っています」
福岡第一高校さんは
能登半島地震直後の
1月から数ヶ月間
寒空の下募金活動に立ってくださり
本校へと支援してくださいました
それ以来ずっと寄り添って
くださっています
一年間の活動の集大成の場ということで
圧巻のクオリティーです
生徒会の生徒をお招きいただき
『輪島塾』として
仲間入りをさせていただきました
環太平洋大学の大池教授のご指導ものと
岡山県の興陽高校さんと共同開発した
バスソルトの販売をしてきました
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「街プロ」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(12)囲碁ボールで輪島を明るく
碁盤に見立てた人工芝マット上で
木製スティックで白黒のボールを操って
五目並べを行うニュースポーツです
兵庫県氷上郡柏原町(現在の丹波市)で
町おこしのために1992年に
考案されたものだそうです
囲碁の勝負によって領地争いを解決した
という故事が同町にあることが
考案のきっかけとなっています
(13)積雪発酵発電
積雪発電とは
太陽熱や廃熱などの熱源と
積雪による冷熱の温度差で
発電する仕組みです
発酵発電とは
発酵によって生じた
メタンガスを燃料に
発電する仕組みです
このグループは
このふたつを組み合わせることを考えた
ということでしょうか?
(14) 心も輪島も未来も明るくしよう
昨年度花火を打ち上げたグループの
流れを汲む活動です
冬の夜を彩る
イルミネーションをつくります
「まちを明るく元気にしていくこと」
「参加・交流の生まれる活動にしていくこと」
「資源循環や観光の要素も入れていくこと」
を意識して動いています
博多での販売を応援した後は
高知での販売の応援に向かいます
吉野川の美しい渓流です
大歩危小歩危の山あいを抜けます
アンパンマン号も走っています
ごめんまちこさんが迎えてくれます
明日は安芸市で開かれる
「商い甲子園」に参加してきます
奥尻島も忘れないで
地震から 663 日目
豪雨から 399 日目
佐賀で開催された
全国音楽教育研究大会
フィナーレでふたたび
全員でフェニックスを大合唱しました
全国の多くの先生方から
励ましのお声をかけていただきました
北海道からお越しの
今金中学校の 清水 桃子 先生
奥尻中学校の 塩原 祐馬 先生と
お隣になり
いっしょに歌いました
奥尻島といえば
平成5年に発生した
北海道南西沖を震源とする
マグニチュード7.8の
地震によって発生した津波が
わずか2分後に到達して
奥尻町だけで 198人もの
死者・行方不明者が出た場所です
先日も別の機会に
奥尻島ご出身の先生とお会いしましたが
「世間は阪神淡路大震災以降
東日本大震災や
熊本地震などよく取り上げるけど
阪神淡路の2年前に起こった
私たちを襲った悲劇のことも
忘れないでほしい」
とおっしゃっていたのが
心に残っています
【今日のDeep Purple】
教科を超えた授業実践を紹介し
深い教科横断型授業を作り出すコーナー
今日は国語と商業の教科横断です
授業者は
電話が鳴る前に
かかってくることを予知できる
高森まどか先生
テーマは
「メールの書き方を学ぼう!」
書き方を学ぶ前に書いたメールを
全員で見ながら
良い点と良くない点を考えました
「件名」はあったほうが良いことや
長すぎると見ずらいこと
また最初に名乗ったほうが良いことに
気づきました
そのあと
商業と国語表現の教科書を
見比べながら
ビジネスにおけるメールの
一般的なルールについて学びました
その後日程調整のメールを例に
スムーズなやり取りにするには
どうすればよいか考えました
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(9)高齢者といっしょ
〜心も身体も健康に〜
75歳以上を後期高齢者
65歳以上を前期高齢者
と呼ぶそうですが
初期高齢者の私は
後期高齢者並みの記憶力が自慢です
最も得意とするのは
用事があってある場所に来たのに
着いた途端用事を忘れてしまい
思い出そうと元の場所に戻ってみても
用事があったことすら忘れてしまうことです
これが私が心身共に健康である
元気の源となっています
周りは迷惑していると思いますが
(10)こども食堂について
子どもが一人でも安心して利用できる
無料または安価な食堂です
食事の提供だけでなく
子どもたちの「第三の居場所」として
学習支援や多世代交流の場としての
役割も担っています
(11)らくして防災
〜防災 × AI〜
防災が大切なのはわかっていても
なにを準備していいのか?
食品の消費期限が気になったり…
そんな不安や面倒を
一気に解決するアプリを開発中です
今回の発表会は
オンラインでもご覧になれます
お楽しみに
呼子の朝市
地震から 662 日目
豪雨から 398 日目
朝日新聞さんから
本校卒業生のその後を追った
ドキュメンタリー動画の
リンクを送っていただきました
デジタル版記事もあります
https://www.asahi.com/articles/ASTBM12QNTBMDIFI01FM.html
呼子(よぶこ)の朝市に行ってきました
佐賀県にある100年の歴史のある朝市です
港に隣接していて
水揚げしたての海の幸を扱います
輪島朝市も港と直結して
セリ体験などやってもいいですね
堤防も利用して釣り体験とセットにして
自分で釣った魚をその場で食べるとか
港にはズラッとイカが干してあります
輪島でこれやると
たちまちトンビにやられるかも
ここにはトンビいないのでしょうか
透き通ったイカ刺しが名物です
今朝は水揚げがなかったので
メニューの看板を見て我慢
輪島でもできそうですね
おそらくこれは水揚げしたイカを
生かしておくための生け簀
買った海産物を焼いて食べる
バーベキューコーナーもありました
アワビ250円〜
サザエ200円など
結構リーズナブル
ただし土日のみの営業なので
こちらも断念
道端でおばちゃんがサザエを焼いています
特大のもので1個 850円
これは結構なお値段ですね

こちらはイカの天ぷらを揚げたてで
8個ほど入って 500 円
観光客は「いろんなものを食べたい」
と考えているはずなので
ボリュームを落として
価格も下げるべきだと思います
昔ながらの土壁の家屋が続きます
クジラ漁の親方の屋敷を見つけました
この辺は昔はクジラ漁がさかんでした
漁の時期は12月から始まり春先まで
出漁の前に親方の家に集まり
酒を酌み交わしたのだそう

建物を活用して
中は資料館になっていました
輪島朝市にも震災を伝える
資料館があるといいですね
火災で消失する前は
輪島塗職人の伝統的な家屋が
あったんですけどね
阪神淡路大震災の時には
「しあわせ運べるように」
東日本大震災の時には
「群青」
傷ついた子供たちを励まし
未来に向かって歩き出すための
素敵な合唱曲が生まれました
私たちにも合唱曲が欲しい!
生徒や保護者の皆さんから
声が聞こえるようになりました
そんな時です
合唱作曲家の弓削田健介先生が
能登を訪れて
「被災地の子どもたちの
心の声を紡いで
合唱曲を作りたい」
とお申し出があったのは
そうして生まれたのが
合唱曲「フェニックス」です
今日は佐賀で
全日本音楽教育研究会全国大会
平たく言えば
日本中の音楽の先生方が集まる会で
弓削田先生の講演会
というよりコンサートがありました
最後にフェニックスを会場で大合唱
その時にステージの上から
指揮をさせていただきました
全国の音楽の先生の
会場を震わせる歌声に感動しました
会場では録音撮影が
禁じられていましたので
雰囲気をお伝えすることができず
残念です
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(6)能登のまいもんを広めよう
「まいもん」とは「美味しいもの」
海の幸山の幸からスイーツと
美味しいものの宝庫です
どんな「まいもん」を
紹介してくれるのでしょう
(7)タービンで輪島に灯を
被災地の子供達にとって
何日も電気が来ないことは
大きなストレスでした
ですので
今年の研究発表には
エネルギー問題についてのものが
多くあります
(8)災害による栄養状態の変化を改善したい
被災地では
お年寄りがトイレに行くのを億劫がり
飲食をしなくなるケースが多くあります
また若い世代においても
仮設住宅での調理が
困難極まることから
適当に済ますことも増えます
そんな状況に解決策を提案します
英語の研究授業を研究する
地震から 661 日目
豪雨から 397 日目
生徒と雑談しました
「7時間全部奥野先生の授業ならいいのに!」
「どうして?」
「だって奥野先生
授業のゴール示してくれるし
ゴールしたらそこで授業終わるし」
「他の先生は?」
「2分ほど余ってもいきなり
小テスト入れたりして
時間ギリギリまで引っ張る」
「最大限に学んで欲しいんじゃ?」
「でも授業の内容終わっとるし
集中力切れとるし
全く意味ないと思う」
「じゃあそれ先生に伝えてみたら?」
「ダメやと思う」
「どうしてかな?」
「俺らうるさくするから?」
自分たちでもわかっているようです
私も現役時代は
この生徒たちと同じことを考えていて
終了のチャイムが鳴っても
授業のまとめをしている先生を
「アホちゃうか
生徒が早よ終われ思てんのに
意味ないやろ」
とどんなに話が途中でも
チャイムと共にサッと終わって
生徒の貴重な休み時間を
1秒たりとも奪わない
そんな努力をしていたものです
キレイに授業をまとめたいのは
教員のサガではありますが
生徒が聞いていないのでは意味ないのです
最近では
「教師がなにを教え込んだか
ではなく
生徒が何を学んだかが大切」
という考えが主流になっています
生徒が言うように
授業の目的達したんだから
そこで授業終わればいいようなものの
「教員は給料もらって働いているのだから
授業をサッサと切り上げて
給料分働かないのは
契約違反だ」
といった問題も絡んでくると
ややこしくなってきます
こういった社会の問題について
生徒と教員とで
じっくり議論する時間も
必要なのかもしれません
しかしながら
教育と経済は
必ずしも相容れないものであって
例えばアメリカの研究で
こんなのがあります
アメリカは結構思い切った
教育に関する実証実験をするお国柄で
ある州で
教員の給料を完全出来高払いにしたそうです
進学実績に基づいて
教員の働きぶりを査定し
結果を出した教員を優遇したそうです
教員のモチベーションが上がり
優れた教育効果をもたらすと
期待されていたのですが
結果は
アメリカの教育施策上
最大の失敗のひとつとなりました
なぜか?
学校がこれまでにないほど
荒れ出したのです
教員の指示に対して
「へん!どうせ自分の成績上げたいだけだろう」
「俺たちに言うこと聞かせれば
自分の給料上がるからな」
全く従わないようになってしまいました
教育の世界に
費用対効果だとか
経済の原理だとかは
決して持ち込んではならないという
教訓とすべきです
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(3)ヤマメ大捜査線 in 輪島
環境DNAを調査して
輪島の川にヤマメがいないか
調査しています
生物は体表から剥がれた細胞や糞を
環境中に放出します
河川水中に含まれるDNAを分析することで
そこにどんな生物が住んでいるか特定できます
捕獲する必要がないので
生物や環境への負荷が少ない技術です
(4)神戸震災学習ツアー
かつての被災地神戸を視察して
30年間どのように復興してきたのか
自分の目と足で学んできました
30年経った今だからこそわかる
復興の成功と失敗
その教訓を能登の復興に活かします
(5)スポーツで健康 〜訪問型ジム〜
スポーツが大好きなのに場所がない
このグループでは
自分たちでジムを作ろうと
行政にかけあうなど
さまざまな活動を行い
多くの困難にぶつかってきました
そして今
訪問型ジムという
新しいスタイルのジムを考えました
発表会では
落成したての仮設校舎の
内見会も予定しています
内田洋行様にご支援いただいた
フリーアドレス制の職員室も
ご覧になれます
ぜひのお越しを
【今日の震災新採5】
震災の地に赴任となった
5人の新採者を紹介するコーナー
外国語科の加藤先生の
初任者研修の研究授業が行われました
授業はAll English でテンポよく
教師と生徒のトークが繰り広げられました
こんな授業ならもっと英語好きに
なっただろうなと思いました
特にいいなと思ったのは
教師から日本語の例文が提示され
即座にペアで英語に直す活動
ただ今回の授業では
教員が指名したひとりの生徒の英文しか
全員でシェアできず
その他のペアは
自分たちが作った英文について
合っているのか間違っているのかわからず
モヤモヤするのではと思います
そこで
AIを活用したこんなアプリどうでしょう
もし既にあったら教えてください
全ペアで話している例文を
マイクで拾います
現在門前高校とのオンライン授業で
使用している機器では
教室の一番後ろの席の生徒の
雑談まで拾えるので充分可能だと多います
拾った音声は全て
即座にスクリーンに投影されます
すると全てのペアで作られた英文を
全員でシェアできるのです
その際AIが
文法的な誤りなどを修正して表示します
すると間違った本人は
間違いに気づき
文法的に正確な英文を学べる上に
間違えたことは他の生徒に知られないので
間違いを恐れず話す習慣がつきます
ただ同じような文章ばかり集まっても
面白くも何ともありません
そこで教員に発問力が求められます
「彼は午後三時に駅で彼女を見かけた」
みたいな
他に訳しようのない例文ではダメです
生活に密着し
なおかつ汎用性の高い文章
例えば
「先生遅えな」
主語をどうするかだけでも
何通りも作れるし
そこに一言自分で付け加えるよう指示し
「先生遅えな 何してるんだろう?」
「先生遅えな 忙しいんかな?」
「先生遅えな 時間守れって言うとるくせに
自分が遅れるってどうなん?」
みたいに自由に生徒が作文すると
一気にボキャブラリが増えて
楽しいと思います
集まった例文はそのまま保存されて
いつでもアクセスできるようにしておけば
家庭学習にも使えます
木犀の花咲く頃に故郷へ帰りたいな
地震から 660 日目
豪雨から 396 日目
校庭の金木犀が香る頃となりました
タイトル何のフレーズかわかりますか
「日生のおばちゃん」の歌です
この秋の佳き日
体育祭が開催されました
保護者の方もお越しになり
元気いっぱいの姿を見ていただきました
とはいえグラウンドには
仮設校舎がもうじき完成
生徒席のすぐ後ろに
工事用のフェンスが
限られたスペースに
トラックを斜めに描く
というアイデアできり抜けます
不便なら不便なりに
アイデアが湧くものです
普段のことを普通通りにしようとするだけで
生徒も先生も考える力が
鍛えられる
おもしろい環境です
種目も工夫を凝らしてあります
運動が得意ではない生徒も
みんなが楽しめるような
工夫が散りばめられています
生徒会の生徒が
福岡第一高校さんの
夜の体育祭を見て刺激を受け
趣向を凝らして
種目設定をしてくれました
グラウンドの隅っこには
野球のブルペン
以前の屋根付きのに比べると
雨の日は使えませんが
できることをやるだけです
こちらもがんばりましたよ
陸上部が自分たちでこしらえた
お手製の砲丸投げ練習場です
ここで練習して
北信越大会出場を果たしたって考えると
ほんとにがんばったなって
感動します
こんなスペック
地震から 659 日目
豪雨から 395 日目
用事があって進路指導室に行きました
授業中なので先生は
国語科の高森まどか先生だけでした
私が入室するやいなや
何か用事があるかのように
高森先生はおもむろに立ち上がり
歩き出しました
するとちょうど電話の呼び出し音が鳴り
高森先生は受話器を取り上げるのでした
通話を終えると
何事もなかったように自席へと
「あれ?何か用事あったのでは?」
と問いかけると
「電話が鳴ったので出ただけです」
いやいや
電話が鳴ったのは
あなたがが立ち上がって歩き出したあとです
どうやら
電話が鳴る前に音が聞こえるという
特殊なスペックをお持ちのようです
電話が鳴ると
誰からの電話かピンとくることありませんか?
それを超えた特殊能力のようです
もうすぐハロウィンですね
英語科の矢田勇先生の
奥様とお子さんで
カボチャのランタンをつくって
高校に飾ってくれました
発災以来ずっと寄り添ってくださっている
福岡第一高等学校さん
文化祭に輪島高校も
出店させていただけることとなりました
福岡第一高校さんの文化祭は
「パラマ祭」といいます
ここには
「パラマ塾」という
部活動のようでちょっと違う
生徒が自分の意思で
好きなことを極める
そんな活動があります
氷川きよしさんは
ここの「演歌塾」で
その才能を開花させました
それぞれの塾が
その輝きを発揮する場が
「パラマ祭」です
「輪島塾」として出店します
環太平洋大学さん
岡山の興陽高校さんと
コラボして開発した
バスソルトを販売してきます
震災後にできた
いろんな絆にホント感謝です
投げやりにならずやり投げについて考える
地震から 658 日目
豪雨から 394 日目
つい先日までの暑さが
嘘のように肌寒い
西部緑地公園陸上競技場
陸上部の生徒が
北信越大会で頑張っています
大久保侑選手 砲丸投げ
11m21で11位
干場泰志選手 800m
1分59秒92で予選3位
池端龍太郎選手 5000m競歩
27分36秒52で14位 自己ベスト
林祐馬選手 3000m障害
10分04秒77 11位 自己ベスト
山崎煌季選手 やり投げ
震災のハンデを乗り越え
ひしめく強豪の中見せる
堂々としたパフォーマンスには
ただただ感激です
やり投げについて
いろいろ気になったので
訊いてみました
競技としての起源は
古代ギリシャやローマ
紀元前4世紀頃のことです
もともとは狩猟時代の投槍
獲物めがけて
エイヤっと投げつけていたものです
18世紀頃から北欧諸国で
さかんに行われるようになりましたが
他の種目が競技として
取り入れられていく中
やり投げだけはあまり一般的にはならず
20世紀に入ってから
ようやくオリンピック競技となります
やりの規格は
男子が 800 g 以上
女子が 600 g 以上
バスケットボールが約 600 g なので
結構重いですね
材質には金属製とファイバー製があります
ファイバー製はよくしなるそうだので
今日観ていて
シューっと飛んで行くのと
フワフワと飛んでいくのがあったのは
その違いでしょうか
世界記録は 100 m 近くだそうで
今日出場していた高校生たちは
およそ 40 〜50 m ほどの勝負だったので
とてつもない距離ですね
バスケットボールより重いもんを
100m 近く投げるんかい!?
って感じです
おもしろいのは
シューズが左右で違うこと
トップスピードに持ってきた助走を
投げる瞬間ピタッと止める必要があるので
右投げの場合
右足はつま先が厚いカバー仕立て
左足は捻挫防止のためハイカットです
やりは個人持ちですが
他の選手のを
その場で借りてもいいそうです
フェアなルールでいいですね
ところで
「なげやりになる」は
「投げ槍」ではなく
「投げ遣り」だそうです
競技の名誉のために
「餌を遣る」
「酒を遣る」
「片っ端から遣る」
「ひとおもいに遣る」
結構やんちゃな言葉ですね
Future そして Futures
地震から 657 日目
豪雨から 393 日目
いしかわ高校科学グランプリが
開催されています
本校からも6名の生徒が参加し
頑張っています
中は撮影禁止なので
詳細を伝えることはできませんが
日頃の数学理科の勉強の成果を
発揮していました
先日行われた大阪・関西万博の閉会式
そのフィナーレで
本校の 正角 心音 さんが
朗読をしました
その模様がこちら
https://drive.google.com/file/d/14Ti8auky31fViBxWodnG_yvIPWkBszf2/view?usp=drive_link
どうぞご覧ください
こんぴらさんが守ってくれる!?
地震から 656 日目
豪雨から 392 日目
新米の季節ですね
例年ですと晴れ女の実家で
稲刈りをしている頃ですが
地震と豪雨で
両親が避難していて
田んぼをつくってないものですから
ちょっぴりさみしい秋を迎えています
そんな折
数学の 宮下 琢磨 先生から
新米をいただきました
金沢のご実家でとれたお米だそうです
宮下先生は
昨年地震の3ヶ月後に
被災地の学校に赴任が決まり
はじめてご実家を離れて
本校を目にした時
さぞ驚かれたことと思います
赴任以来
金沢から毎日自家用車で通いました
当時は『のと里山海道』も使えず
片道3時間ほど
かかっていたのではないかと思います
被災地での仮設官舎暮らしより
長時間通勤を選ぶほど
それほど過酷な環境ではありました
さていただいた新米
今年の概算金
つまりJAが生産者に支払う価格は
前年比6〜7割増しだそうです
過去最高を記録した生産地も
我々の口に入る頃には
5kg で 5,000 円弱ってところでしょうか
米1合は約 150 g
1合でおにぎりが3つできるとして
おにぎりひとつに 50 g
5kg だと 100 個できる計算になります
米原価だけでいうと
おにぎり1個 50 円です
それに具や海苔
光熱費や人件費 輸送費などを計上し
コンビニおにぎり
だいたい 200 〜 300 円で
設定されています
高いと捉えるか安いと捉えるか?
パリの空港で売っていた
1個 1,800 円のに比べると
さすがに安いですね
【今日のDeep Purple】
教科を超えた授業実践を紹介し
深い教科横断型授業を作り出すコーナー
今日は国語と商業の教科横断です
テーマは
「図書委員会のポスターの掲示内容を検討する」
です
話し言葉と書き言葉の特徴や役割
そして表現の特色を踏まえた上で
正確さ
分かりやすさ
適切さ 敬意と親しさ
などに配慮した
表現や言葉遣いについて理解し
使う力の育成が目的です
『図書館利用のしおり』
を改善するための会議に用いる
議案書を作成する実習です
商業科の山元 真吾先生より
議案書に適した文章上の言葉遣いや表現方法を学び
その後実際に作成しました
ビジネス文書検定3級の内容が
基となっています
山元教諭(商業科)
「それぞれの教科の視点から
議案書を捉えることができてよかった
文章を考える部分は国語科
文章を作る際の技術的な部分は商業科
の範囲であることを認識できた」
濵田教諭(国語科)
「実学主義的な側面の強い教科と連携することで
人文主義的な側面が強い国語科の活動に
日常生活に即した目的を与えることができた
それを学んで何に使えるのかという点は
生徒の学ぶ意欲に直結すると感じた」
先日
初年次教育学会でお世話にあった
佐渡島 沙織 さまより
書籍を贈っていただきました
夏休みにアメリカへ
災害医療を学びに行っていた生徒が
その報告をした学会の時に
お世話になった方です
その時の発表そしてインタビューを
今後の教育に反映してくださるそうです
いただいた書籍は
今後の生徒の発表のスキルアップに
大いに活用させていただきます
どうもありがとうございました
今日は四国は高松に来ています
眼下には煌びやかな瀬戸内海
中国からの観光客が驚いています
「日本也有这么大的河流!」
(日本にもこんなに大きな川があるんだね)
違います
これ海です
さすが中国人はスケールが違います
時間があったので
金比羅さまに行ってみました

以前高松で防災備災関係の
講演をさせていただいた時に
主催者からこう依頼されました
「香川県民は本当に防災意識低いんですよ
『こんぴら様が守ってくださる』
と本気で思っているんです
なんとか言ってやってください」
確かに何がおこっても守ってくださる
霊験あらたかな氣がします
震災地の新採ファイブ
地震から 655 日目
豪雨から 391 日目
本校の教員は約30名
そのうち5名
まさに6人にひとりが新規採用
大学出たての
フレッシュな面々です
うち4名が
教委が準備してくださった
教員向け仮設住居に住まいし
毎朝1時間近くかけて通勤しています
6畳ほどの部屋ひとつに
シンクとトイレと風呂
我々住まいを失った者にしてみれば
それでも涙が出るほど
ありがたいのですが
人生で初めて一人暮らし
それもいきなり被災地への勤務
さぞ心細く不安も不満も
あると思いますが
それでも被災地の生徒のため
身を粉にして
がんばってくれています
そのうちのひとり
地歴公民科の 竹田 悠月 先生の
初任者研修研究授業が行われました
テーマは
「日清戦争の勝利によって
日本は『列強』の一員になれたのか」
さまざまな資料を活用して
各人で調べながら
ディスカッションを通じて
思考を深めていく
素晴らしい授業でした
新採とは思えない
しっかりとした準備の上に立ち
新採の強みを活かして
生徒の発言を最大限に引き出す
そんな授業でした
輪島の中学生の保護者のみなさん
どうぞ安心して地元の高校に
通わせてください
授業後の研究協議会では
まずは私の方から
「日清戦争の頃
アレニウスという科学者が
世界で初めて
二酸化炭素の温室効果に関する
論文を発表している
そうした科学の発展を
当時の政策に絡めると
新たな気づきがあるかもしれない」
と提案しました
そして指導主事の 大田 新 先生から
投げ込まれた新たな問いは
「日清戦争で得た賠償金は
どのように受け取って
どのように使ったのか?」
まず賠償金は
8回の分割払いにしたそうです
なぜか?
膨大な利子が発生するからです
結果
当時の国家予算の
4倍ほどの賠償金を受け取っています
そしてポンドで受け取っています
なぜか?
そのお金でイギリスの国債を
大量に購入したのです
イギリスは当時アフリカへの投資で
資金繰りに苦しんでいたのです
イギリスに恩を売ることで
その後の日英同盟に
つながったそうです
こうして歴史を
前後のつながりで見てみると
ダイナミックなうねりが見えて
本当に興味深いです
さすが長年の指導主事経験
深い教材理解です
教師が深く教材を理解することで
生徒に活き活きと語ることができる
そんなことふと思いました
高松で普通科高校校長会に参加しています
記念講演の講師は
なんと昨日訪れた
環太平洋大学の 中山 芳人 特任教授
TBS日曜劇場『御上先生』の
教育監修もなさっています
「非認知能力の育て方」
について学びました
共通の尺度で評価測定できる能力を
「認知能力」
共通の尺度で評価測定できない能力を
「非認知能力」
といいます
ただし個別の尺度で主観的になら
「非認知能力」であっても
評価ができます
例えば
「あなたの根性は10段階でいくつ?」
簡単に言い換えると
「見える学力」
「見えない学力」
とも言えます
「非認知能力」の具体的として
自立心 向上心 自制心 好奇心 冒険心
積極性 創造性 協調性 自主性 社交性
などなど
決して新しい概念ではなく
実は日本の教育には
ずっと昔から取り入れられていたものです
ひとことで表すと
「心」
「認知能力」or「非認知能力」
といった二項対立ではなく
「非認知能力」for「認知能力」
といった捉え方が適切です
勉強によって「学力」を高めるために
従前の
識字・読字訓練
書出表出訓練
計算訓練
といった勉学に特化した訓練
すなわち詰め込み学習から脱却し
意欲
向上心
協働性
といった学びに向かう力
すなわち「非認知能力」を
高める必要があるのです
本校では
「街プロ」がそのための
有効な取り組みとなっています
未来の教室
地震から 654 日目
豪雨から 390 日目
被災した奥能登公立高校5校
今後どうしていくのかは
大きな課題となっています
県は今のところ5校全てを
存続させる方針を打ち出していますが
今後の生徒減を鑑みると
このままの形では
様々な問題があり
何らかの新たな枠組みは必要です
魅力ある高校にしないと
人口の流出に拍車をかけてしまいます
先日も県主導で
そのための会合が持たれました
今日は
魅力ある学校づくりのヒントを求め
岡山県にある
ふたつの施設を訪ねました
まずは Benesse 本社
岡山市を一望できる
ロケーションにあります
全国的な企業なので
東京に本社があるのかと
思っていました
創業者は元々小学校の先生
生徒手帳の制作を手がける
福武書店がそのルーツです
やがて通信添削講座を始め
進研ゼミから現在に至ります
社員の創造性を引き出す
オフィスシステムのあり方
次世代の教育が向かう方向
芸術を中心に据えて展開されています
私自身もAI時代の
授業の中心は
芸術・家庭・体育になっていくと
考えています
次に訪れたのが環太平洋大学
『非認知能力』の育成をコンセプトにした
キャンパスとなっています
キャンパスのデザインは
瀬戸内海の絶景と一体となった
「地中美術館」
都市に光が差し込む
「こども本の森 中之島」
など世界中から高い評価を得ている
安藤忠雄氏
こちらは『Coaching Lab.』
教室をぐるっと囲むように
ガラス越しの参観席があり
模擬授業・研究授業を行い
本物の教員を育成します
『Learning.Lab』
最新機材を揃えたグループワーク室で
「考え抜く・伝える力」
を育成します
『Presentation Lab.』
語る力
人の心を動かす力の養成空間で
自分の考えをわかりやすく
大勢に伝える力を育成します
『Discussion Lab.』
英国議会をモチーフに
「白熱した議論をする力」
を育成します
『Debate Lab.』
国連安保理をモチーフに
「徹底的に討論する力」
を育成します
『IPU Studio』
テレビ局スタジオをモチーフに
「世界に発信する力」
を育成します
これらの施設を参考に
半島の最先端から
世界の最先端を目指せる
魅力ある高校を
能登の地に
つくりたいと妄想しています
左右の思いやり
地震から 653 日目
豪雨から 389 日目
最近知った豆知識
何を今さらという方が
ほとんどかもしれませんが
車のメーターのガソリンマーク
横にチョコっとついている三角
給油口がどっちにあるか
示しているそうですね
今まで自分の車でない時は
いつもドアを開けてどっちかなと
確認していたのですが…
どうして給油口が
右にあったり左にあったりするのか
気になったので考えてみました
ガソリンスタンドで混雑しないため?
仮説を立ててみました
調べてみると
歩行者に対する優しい配慮がありました
マフラー(排気口)との位置関係によって
給油口の位置が決められているのだそう
道路運送車両法第18条7項
「給油口とマフラーの配管は
300mm以上離す」
マフラーの位置は
歩行者に配慮して
歩道から離れた位置
日本車の場合は多くは右側なので
給油口が左側にある車が多いそうです
逆に車が右側通行の国では
給油口が右側にあります
マフラーが2本左右にある一部のアメ車は
給油口が後方中央
ナンバープレートの裏にあるそうです
フォレスターの排気口は2本あります
給油口は右側です
SUBARU の車は
給油口は運転席側にあった方が便利
という思いやりから
全ての車の給油口は右側にあるそうです
ところでガソリンスタンドで
自分の給油口側が混雑していたので
反対側に突っ込んで
車の屋根越しにエイヤっと
ホースを伸ばして給油したら
「やめてください」と
店員に叱られたことがありますが
実際どうなんでしょう?
ダメな理由がわかりません
機械の構造上負担がかかるからか?
曲がったことが嫌いな店員だったのか?
北信越大会へ出場する陸上部の生徒が
昨日校長室へ表敬訪問してくださいました
参加選手は以下の通り
1年 干場 泰志 800m
2年 池端 龍太郎 5000m競歩
2年 林 佑馬 3000mSC
2年 大久保 侑 砲丸投
2年 山崎 煌季 やり投
17名の部員のうち5人
つまり3割の選手が
県予選を勝ち抜いたことになります
これってすごくないですか?
まともなグラウンドがない中で
傾いた校舎の廊下や
隆起した町の歩道で
できることを積み重ねてきた結果です
「恵まれた環境がないと練習できない」
などといった寝ぼけた妄想を
打ち砕いてくれました
とこんなことを書くと
「そうでしょう
銭金の問題じゃないんですよ」
と理解のない一部の行政の人に
言われるんだろうな
今日出会った素敵な言葉
「比べるな
隣の芝は
合成芝」
11月1日(土)
探究活動『街プロ』発表会
「MAJI で WAJI活」
が本校を会場に開催されます
どんな発表があるか
少しずつご紹介します
(1)「らくして防災 〜防災 × AI〜」
明石の青楓館高等学院さんとの共創
AIを使った防災アプリを開発しました
災害への備えって
大切だとはわかっていても
何から始めていいのかわからなかったり
ついつい億劫になりがちですよね
あなたのライフスタイルを
AIが分析して
手間をかけずに
最適な備えを提供する
そんなアプリを
実際の被災経験を踏まえて
開発しています
(2)「猫も人間も食べられるお菓子」
先輩の探究を引き継ぎました
本校が避難所として運営されていた頃
一部屋をペットと同居ができる部屋
としていました
しかし全国的に見ると
動物も一緒に入れる避難所への
理解は進んでいません
そんな中
例えばネコは
小麦粉を食べることができません
避難所にパンしかなく
ペットフードがなかった頃
ペットたちがお腹を空かせていたのです
それをなんとかしたいというのが
このグループの
テーマ設定のきっかけです
水の記憶
地震から 652 日目
豪雨から 388 日目
大阪・関西万博
フィナーレを迎えました
本校2年生 正角心音さんが
櫻井翔さん
河瀬直美監督
有働由美子アナウンサーとともに
未来へのメッセージを語りました
被災地からの復興を誓い
世界中に感動を届けました
櫻井翔さんが
気さくに話しかけてくださいました
今回お繋ぎくださったのは
能登半島の太鼓から始まる
オープニングの演出も手がけていた
芸術家 大志さんです
素敵なプレゼントありがとうございました
一酸化二水素
様々な物質を溶かす性質を持ち
金属すら腐食させてしまう
毎年多くの方が
これにより命を奪われている
この恐るべき物質
一酸化二水素
すなわち H2O にまつわる話です
この物質により
昨年9月に甚大な被害を受けた
珠洲市大谷地区へ行って来ました
こちらは地域の避難所となっていた
馬緤(まつなぎ)地区の公民館
大切なお神輿もこちらに避難
壁には所狭しと
当時の写真が貼られています
そして当時入所者へ
連絡事項を伝えていた張り紙が
時系列順に並べられていて
当時の極限状態が
臨場感を持って迫ってきます
さながら建物まるごと
被災を伝える一級資料となっています
こちらはボランティアさんが
寝泊まりしていた段ボールベッド
兵どもが夢の痕
「一期一会に感謝
令和6年の能登半島地震に際しまして
温かい励ましのお言葉や
お心遣いをいただき
厚く御礼申し上げます
1月2日に開設した
馬緤自主避難所は
住民の支え合いのみならず
多くの方々による
様々なご支援を受けながら
運営を続けて参りましたが
地区内での仮設住宅の整備や
生活インフラの復旧に伴い
その役割を終え
12月をもって閉所いたしました
振り返れば
炊き出しや物資支援
土砂撤去
災害ゴミの搬出作業等
様々な形で助けていただきました
こいのぼりの下での餅つき
黄色いハンカチプロジェクト
砂取節祭りや秋のキリコ祭りなど
様々な行事ができたのも
皆様からのご支援のおかげと
感謝申し上げます」
(ご挨拶の看板文章より)
命を脅かす恐怖の物質 H2O
一方で全ての命の源H2O
これにまつわる感動の話が
ここにはありました
待てど暮らせど水道が出ない中
ここの住民がいかにして
大切な水を手に入れて
命を繋いできたのか
一冊の報告書に
まとめ上げられています
「地震で全てを失った小さな集落
そこには
名もなき男と女たちの
水を手に入れるための
壮絶なドラマがあった」
「風の中のすばる〜
砂の中の銀河〜」
被災者が集まった避難所
しかしそこは断水したまま
復旧の目処すらありません
「うちのライナープレートに水あるぞ!」
ひとりの避難民のアイデアから
物語は始まりました
ライナープレートとは
縦井戸の形をした集水井
地滑りの原因となる地下水を抜き
地盤を安定させる装置です
その地下水を水道水に利用すべく
協力が始まりました!
平時であれば
井戸内に溜まった地下水は
ボーリングを通して
外に捨てられるのですが
それを利用しようと考え
住民自らの力で
簡易水道をこしらえたのでした
なんという生命力でしょう
繋いだパイプからは
とめどなく水が滴り
それを受けるタライは
満々と水を湛えるのでした
その後も定期的に
水質検査を繰り返し
飲料としても充分な水質であることが
確認されています
被災地における水源確保の技術として
先進的いや昔へ遡っての
素晴らしい事例であると思います
未来と過去
その捉え方に関する
面白い話があります
昔の人は
「サキの戦は苦しいものであった」
この『サキ』は
『サ』にアクセントがありますが
過去のことを指しています
現代人は
「そんなサキのことはわからない」
この『サキ』は
『キ』にアクセントがあり
未来のことを指しています
同じ『サキ』なのに
時代によって使い方が異なるのは
時間の流れに対する
捉え方に違いがあるからなのだそうです
現代人は未来に向かって
前向きに進んでいる時間感覚を持ち
なので視線のサキにあるのが『未来」
一方昔の人は
未来は見えないが過去は見える
過去を見つめながら
後ろ向きに進んでいる時間感覚を持つので
視線のサキにあるのが『過去』
なんだそうです
後ろ向きに吸い込まれていく
ジェットコースターに乗っているような
イメージなんでしょうね
明日でいよいよ
地震から 651 日目
豪雨から 387 日目
小松市でどんどん祭りが
開催されています
本校生徒と
岡山の興陽高校さんを結んで
商品開発してくださった
環太平洋大学のみなさんがお越しになり
バスソルトとジェラートを
販売しました
さあさあ予想を遥かに超える
盛り上がりを見せ
「なんで年間パスポート買うたのに
入れへんねんな」
という大阪マダムたちの
怒りのボルテージも最高潮の
大阪・関西万博
輪島塗の地球儀も
多くの方にご覧いただいたり
被災地から生まれた商品の
販売をさせていただいたり
我々被災者としても
たくさんの元気をいただいた万博
いよいよ明日閉会式が行われます
14時〜15時10分
NHK総合テレビで全国生放送されます
また
大阪・関西万博の
公式YouTubeチャンネルにて
ライブ配信されます
https://www.youtube.com/@Expo2025Japan
ぜひご覧ください
今はまだ言えませんが
素敵な演出があります
未来の図書館
地震から 650 日目
豪雨から 386 日目
3年生の普通コース理系の生徒を対象に
国語科の松本昭子先生による
「論理国語」と外国語科及び理科との
教科横断的な授業を実施しました
テーマは
「まちづくりの拠点として
輪島に公立図書館を作るとしたら
どのような図書館が良いか」
です

これまでに
「人とともにある図書館の未来は明るい」や
「図書館と『ものがたり』」を学び
前回の授業で
発表用のスライドを作成し
さらに新聞記事を活用しながら
多様な角度から図書館に関する話題に
触れてきました
本時は
スライドを用いて
グループ内で発表を行いました
そして次の時間は
グループ代表を決めて
代表全体発表を行う予定です
生徒たちは
「説得力とは何か」
という問いを意識しながら
質問やコメントを通して
互いの意見を深め合っていました

以下に生徒の発表内容と
聞き手のコメント質問の一部を示します
生徒Aは
これからの図書館のあり方について
発表しました
図書館が必要である理由として
「憩いの場があれば
住みやすくなるのではないか」
と述べ
これからの図書館として
「全ての人に
知識や情報へのアクセスを
提供することが大切であり
飲食スペースや
話し合いに使える会議室も必要」
と提案しました
聞き手であった生徒Bは
「輪島にある図書館の課題が
書かれていてよかった」
とコメントしました
生徒Cは
誰もが利用しやすく
魅力的な図書館作りについて
発表を行いました
「キッズスペースや
飲食可能なスペースを
設けるとよい」
「日本語の本だけでなく
他国の本を置くことで
外国や言語への関心を高められる」
「誰もが気軽に立ち寄れる
場所にしたい」
と提案しました
聞き手であった生徒Dは
「図書館の大きさは
どれくらいを想定しているのか」
「フリースペースを設けたほうが
よいのでは」
とコメントしました
生徒Eは
幅広い年代が利用できる図書館のあり方
特に中高生も利用しやすい
図書館づくりについて発表しました
データを活用し
高齢者が利用が多い割に
中高生の利用が少ないことを指摘し
その要因として
「高齢者は余暇がある」
「中高生はスマホを使う」
などを挙げました
その上で
「中高生も通用しやすい環境にするには
本を借りるだけでなく
雑談や飲食
参考書利用
カフェなどの機能を併設するとよい」
と提案しました
構造としては
「1階に児童コーナーやカフェ
2階に自習スペースを設けた二階建て」
を構想しました
生徒Fは
理想の図書館の具体例として
武雄市図書館を紹介しました
図書館とTSUTAYA書店が併設され
気に入った本を
その場で購入できる点や
親子で楽しめる絵本コーナー
スターバックスが併設されている点など挙げ
寄り道がてら立ち寄りやすい図書館
として紹介しました
また輪島で建設する場合を想定し
敷地面積や延床面積
建設費や運営費についても
具体的に提示しました
そのほか
教科書から文章を引用して
考えを補強する生徒
データを元に考察を行う生徒
輪島の現状を踏まえて
図書館は必要ないと主張する生徒
聞き手を引きつける「つかみ」について
工夫する生徒
図書館の存在意義を考えながら
高齢者や子供など
多様な立場から
図書館のあり方を考える生徒などなど
それぞれが主体的に
意見を表現していました
全体発表が終わると
生徒たちは自らの
発表原稿やスライドを見直し
より説得力のある
プレゼンをするための方法について
意欲的に意見交換していました
今日のレポートは
新採の櫻庭先生が
まとめてくださいました
めんそ〜れ沖縄最終日
地震から 649 日目
豪雨から 385 日目
楽しかった修学旅行も最後の日
食事の後は
ホテルの方が片付けやすいようにと
自分たちで食器をまとめるグループ
ご家庭でのしつけでしょうか
それとも避難生活で身についた
助け合いの心でしょうか
いずれにしても
美しい日本の心を見ました
最後の見学地
首里城に行きました
昨年来たときよりも
はるかに復興が進んでいます
輪島塗の職人さんも
復興作業に関わっています
今年の夏には
本校和太鼓部が
演奏させていただきました
そんなゆかりのある場所です
復興をお祈りしております
最後にガイドさんから
教えていただいた
素敵なことば
「誠(まくと)そ〜ち〜ね〜
なんくるないさ〜」
(誠実に一生懸命生きていれば
必ず道は開かれる)
いろんな思いを抱き沖縄を後に
ただいま
送り出してくださったご
ご家族のみなさま
おかげさまで
たくさんのことを学んで
つらい環境の中でも
明るく強く
未来を夢見て生き抜く力を
さらに強くして帰ってきました
ありがとうございました