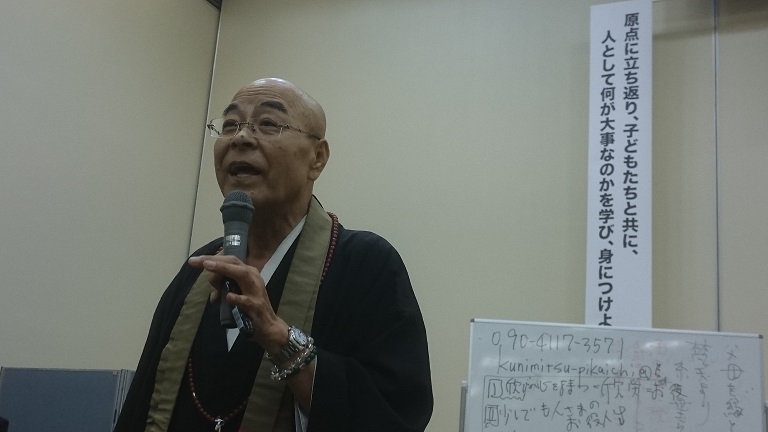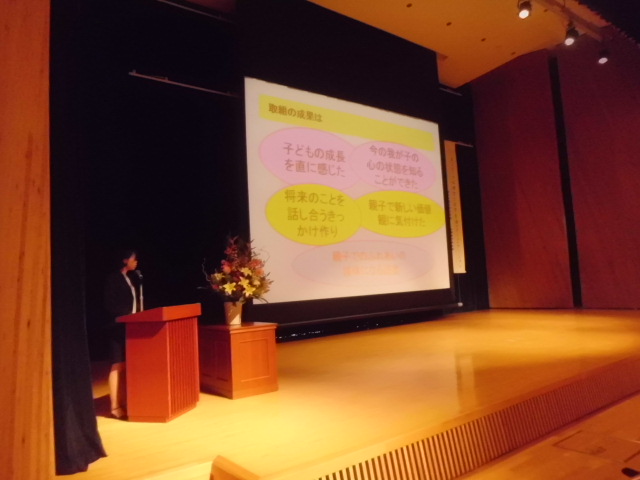PTA東海北陸ブロック研究大会 二日目は全体会ということで、
昨日分散していた参加者が、小松ドームに集結しました。
全体会の内容は、オープニングアトラクション、表彰式、記念講演、閉会式となります。

小松ドーム。
間近で見ると中々の迫力。

歌舞伎のまちでもある小松らしい開会の挨拶。

小松市立御幸中学校の生徒による、こまつ勧進帳連中のオープニング。
まだ2ヶ月ほどしか練習できていないというものの、中々の完成度。
小さいころから芸に親しんでいるからできるのだろう。
オープニングが終了し、功労者の皆様が表彰されました。
そして、今日のメインイベント記念講演が始まりました。
演題【宇宙、人、夢をつなぐ 未来を担う子供たちのために】
講師:元宇宙飛行士 山崎直子さん
宇宙飛行士になるきっかけの話や、子供の疑問を親と共に共有する話等を聞きました。
幼少の頃過ごした北海道の夜空が綺麗で星に興味を持ち、プラネタリウムにもよく通ったそうです。
子供の頃に興味を持った事は、大人になっても忘れないんですね。
私自身もそうですが・・・。
子供の興味や好奇心を、大人目線でブレーキをかけたりせず、温かく見守る事が大切なんですね。
もし、プラネタリウムに通うのが面倒で親が通わせなかったら、
そして本人もプラネタリウムに通うという行動をとらなかったら、
宇宙飛行士山崎直子は居なかったのでは?と思います。
ニュースでも取り上げられた、
「宇宙で膨らませたシャボン玉は色がつくのか?」
という、自分の子供の疑問に一緒になって考えた事。
入浴剤入りの色の付いたお風呂の水でシャボン玉を作ったのに、
色が付かなかったので不思議に思った子供。
色は重力の影響で下に下がってしまうので、
無重力の宇宙なら色が付くのでは?と思ったお母さん。
宇宙で実験というスケールの大きな実験でしたが、
何気ない私生活の中で湧き上がる子供の興味や疑問を、親がしっかりと受け止め
子供と一緒になって考える。行動する。
子供の興味、好奇心を伸ばすためには、
親も子供と同じ温度で一緒に行動する、考える事が大切なのだと思いました。
そうすることによって自分というものが出来上がる。確立する。
自分軸が出来上がる。自信が付く。という事に繋がっていくのだと思います。
国際宇宙ステーションでは、様々な国の人との仕事になります。
コミュニケーションも大事だけど、
「自国の文化を知る。という事も大切です。」
と仰っていたのが印象に残っています。
一日目で出た「地元愛」そして講演で出た「自国の文化を知る」
やっぱり地元は大切にしないといけませんね。
山崎さんは就寝前に必ず「産まれてきてくれてありがとう」と言っているそうです。
その言葉を子供が聞くと、優しく微笑んでくれるそうです。
毎日子供に感謝の言葉を唱えると、より優しく子供に接する事が出来るのではないでしょうか?
私も試しに唱えてみました。
すると、子供から
「急にどうしたん?」
と、不思議がられてしまいました。日頃の行いですね(笑)
質疑応答の時間では、質問者に直接マイクを渡しに行き、
質問に答えた後に質問者と握手をしていました。
私も握手をしたいがために、「手を上げよう」と心の中で思っただけでいたので、
握手はできませんでした。行動した者のみが得られるのです(笑)
そして山崎さんは終始笑顔で素晴らしいお人柄だと感じました。
見習いたいものです。
色々と考えさせられた二日間でした。
一分一秒でも長く、この思いを続けられるよう、
また、志を少しでも高く持つように過ごせて行けたら。と。
 かほく市立外日角小学校
かほく市立外日角小学校 


 かほく市立外日角小学校
かほく市立外日角小学校