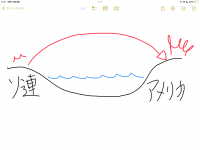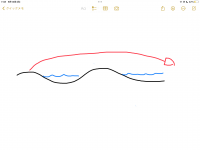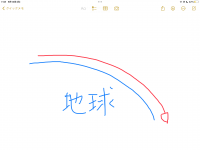校長室より「おこらいえ」
後生畏るべし
地震から 631 日目
豪雨から 367 日目
タイトルの言葉は
『論語』に出てくる孔子の言葉で
「自分より若い世代は
将来どのような人物になるか計り知れないので
決して侮らず畏敬の念を持って接するべきだ」
という意味の言葉です
若者が持つ無限の可能性を称えるものです
最近は昔の教え子に会うごとに
この言葉の意味をかみしめています
懐かしいお客様
二本松市立東和中学校の 鈴木 直樹 先生です
私の町野高校赴任時代の教え子で
町野高校が第1回の21世紀枠
最終選考全国9校にまで残ったときのエースです
廃校直前たった11人の部員でそこまで残って
絶対選ばれると勝手にワクワクして
甲子園球場に行くときは
大型バスじゃなくてワゴンで充分ですね
ワゴンで甲子園横付けする出場校なんて
これまでないでしょ
なんて妄想ふくらましていました
大学卒業後は福島県で教員をしながら
好きな野球の研究をずっとされていて
多くの論文も残されています
「野球における投手の投球に関する運動技術史的研究」
ーオーバースローにおける「胴体の動き」を中心にしてー
ーオーバースローにおける「バックスイング」を中心にしてー
ーオーバースローにおける「フォワードスイング」を中心にしてー
ーオーバースローにおける「下肢の動き」を中心にしてー
「野球における投手のオーバースローの運動技術史」
ー競技規則との関係からー
「日本におけるアンダースローの運動技術史」
「野球の投手におけるコントロールのコツに関する一考察」
ー技術の定立に向けてー
「野球における投手のオーバースローの構造体系化」
いずれも「スポーツ教育学研究」や
「スポーツ運動学研究」などに掲載されたものです
彼自身高校時代に
オーバースローからサイドスローに転向し
その中で探究の芽が育まれていったのですね
好きなことをとことん突き詰める
これからの時代に大切な力です
生徒にぜひ身につけさせたい力です
【GIS不自由研究】第5回
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に分析する手法を学ぶこのコーナー
今回は「知を作る!」
重ねるレイヤーを自分で検索して探します
「浸水深想定」「浸水推定」「標高」
などをキーワードに洪水災害について
「土砂災害」「警戒区域」
をキーワードに土砂災害について
それぞれ活用可能なデータを作ります
【夏を詠む】夢眠の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
夏の昼寝は至福のひととき
今日は夢見の句を集めてみました
「昼寝して 夢の中まで 夏休み」
夢占いで検索してみました
夏休みの夢を見るということは
自由になる時間を求めているそうです
退屈な日々からの逃避願望の可能性も
日頃から勤勉な人であれば
働き過ぎの赤信号が点滅しています
怠けがちな人であれば
手つかずに放置している課題を片付けるように
と夢が警告しています
「夏休み 呼ばれてもなお 夢のなか」
起きたいのになかなか起きれない夢は
人間関係の変化を暗示しているそうです
嫌々付き合っている人がいるケースが多いとか
何かに対して不満を持っている
ということを暗示している夢でもあるそうです
「気にしない」或いは「知らんふりでやり過ごす」
そうすることで運気が上昇することもあります
「夏の夜 布団に沈み 秒で寝る」
部活動の練習で疲れてバタンキューでしょうか
昼間に思いっきり汗をかくと
暑い夜でもぐっすり眠れていいですね
ところで若い人はバタンキューって
わかりませんよね
「死語の世界は存在する」
モロこの句のような状態を表します
モロも死語か?
気になって調べてみたら
名古屋の方言なのだそうです
未だに「写メ」って言ってる人いませんか?
若い人に「なにそれ?」って言われますよ
芸術の秋スポーツの秋
地震から 630 日目
豪雨から ちょうど1年目
【芸術の秋】
中部航空音楽隊のみなさんが
はるばる静岡からお越しくださり
復興応援演奏会を開いてくださいました
「心の中の一番綺麗な風景と
大切な人のことを思いながら聞いてください」
とアンコールで演奏してくださった
Danny Boy には
込み上げる思いでいっぱいになりました
アイルランド民謡に詩をつけた Danny Boy は
第一次世界大戦中
「生まれ育ったこの場所へ
きっといつか帰っておいで」
出征する我が子への思いを綴った曲です
発災以来
傾いた体育館にずっと寝泊まりして
救助に当たってくださっていた
隊員のみなさんのこと思い出しました
それからその頃にもらった
東日本大震災を経験したお母さんからの
こんなメッセージ
「東日本大震災に襲われたとき
当時2歳だった娘には
その時の記憶がありません
ただひとつ覚えているのが
『真っ暗なお風呂の中に
黄色いアヒルちゃんが浮かんでた』
自衛隊のみなさんが準備してくださった
お風呂の思い出です
壊れた建物
慌てふためく大人たち
そんなものじゃなくて
暖かい思い出を
娘の心に残してくださった
自衛隊のお姉さんたち
本当にありがとうございました」
今日の演奏会も
きっとみなさんの心の中に
残っていくものと思います
【スポーツの秋】
バレーボール部が体験入部を行いました
輪島市内の中学校から
6名の3年生が参加してくれました
輪島中学校には
女子バレー部はありますが男子バレー部がありません
輪島高校には
男子バレー部がありますが女子バレー部はありません
ですので男子は全員初心者からのスタート
女子は続けたくてもできません
そんな中ひとりの女子部員が
マネージャーとして3年間
頑張ってくれました
きっとプレイしたかったろうと思います
でも影でみんなを支えてくれました
本当にけなげで立派な姿でした
とってもセンスあるので
男子に混じっても
決してひけを取らなかった
というより下手すると
一番うまかったかもしれません
40年ほど前
リベロの制度がない時代
全日本女子で広瀬選手っていう
小さな選手がいました
アメリカのハイマンやクロケット
中国の郎平らが放つ強烈スパイクを
とにかく拾いまくっていました
確か男子の中に混じって
レシーブの練習をして
技を磨いたと聞いています
今日は女子バレー部のない東陽中学校から
女の子がひとり参加してくれたので
そのマネージャーの子も
受験勉強の合間を縫って
お手伝いに来てくれました
少子高齢化が進み
部活動の存続が危うくなってくるこれからは
吹奏楽に大編成と小編成があるように
男女混合大会もひとつの選択肢かもしれません
この模様の秘密は明日書きます
キーワードはイグノーベル賞
【GIS不自由研究】第4回
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に分析する手法を学ぶこのコーナー
今回は「データ」
ArcGISのアプリ「Survey123」を用い
重ねたレイヤー上のさまざまな地点において
どんな情報が欲しいかリクエストする
「調査票」をつくります
「調査票」によって集められたデータは
一覧表となって管理されます
【夏を詠む】香味の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
いっぱい食べて元気な夏を
今日は美味しい句を集めてみました
「種飛ばす 黙して笑う 夏の午後」
スイカの種の飛ばしっこですね
スイカを切る時は
皮の縞模様の濃いところに沿って
包丁を入れるといいですよ
種はその線に並んでいるので
切り口に一列に並んで取りやすくなります
「かき氷 食べて後悔 また一口」
ダイエットしてるのかな?
冷たいと甘みを感じにくくなっているので
摂取過多になりやすく
注意が必要ですね
「夏の午後 残る胃の奥 祭味」
お祭りに行って
屋台のおいしいもの
いっぱい食べたんですね
創造的復興サミット in 神戸
地震から 629 日目
豪雨から 365 日目
「創造的復興」
この言葉が生まれた神戸のまちで
今日はサミットが開催されています
会場はポートピアホテル
Portopia, the city of light and waves
ゴダイゴが歌っていましたね
3本の国旗からわかるように
本日はトルコとウクライナからも
発表にいらっしゃいます
朝一番からリハーサル
司会は武庫川女子大付属高校3年生
竹内 舞桜さん
どこかで聞き覚えのある
お名前ではないですか?
夏の甲子園の開会式の司会を務めた方です
素敵な響きの声でした
齋藤 元彦 兵庫県知事からのご挨拶です
「創造的復興」
という言葉を生んだこのまちでは
震災から30年が過ぎ
その記憶を風化させないため
今年から「つなぐ」という
キーワードを追加したそうです
兵庫県立舞子高校のみなさんです
各学年で1週間に8時間ほど
防災に関する授業を行っています
宮城県多賀城高校の災害科学科さん
防災に特化した独特なカリキュラムで
計問的に防災について学んでいます
神戸学院大学のおふたり
阪神・淡路大震災の震源地に
最も近い大学なんだそうです
兵庫県立大学学生災害支援団体LAN のおふたり
先日の新潟での「ぼうさいこくたい」で
ご挨拶させていただきました
東北学院大学 地域総合学部のおふたり
本校からは中村輝人さん
自ら取り組む居場所づくりと
ガイド活動について発表しました
そのあとは発表者全員で
パネルディスカッションを行いました
午後からはサミットです
神戸市立御影北小学校のみなさんによる
『しあわせ運べるように』の合唱で幕を開けます
「傷ついた神戸を もとの姿にもどそう
支えあう心と 明日への 希望を胸に
響きわたれ ぼくたちの歌
生まれ変わる 神戸のまちに
届けたい わたしたちの歌
しあわせ 運べるように」
涙がとめどなく流れてきます
学生からの行動宣言が行われました
防災教育とは
単に学ぶことではなくて
行動に起こすこと
力強い宣言が行われました
石川県から馳浩知事も参加されました
発災時
当時の岸田総理から
「金の心配はするな!
できることは全てやれ!」
との指示を受け取り組んでこられたことを
お話されました
【GIS不自由研究】
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に分析する手法を学ぶこのコーナー
第3回は「ラベル」と「シンボル」
地図上に重ねたレイヤーに
文字を表記させるのが「ラベル」です
例えば「耕作地」レイヤーの
「ラベル」をオンにすると
『田』や『畑』といった
耕作地の活用状況が表示されます
そしてレイヤーの色味や透過度を
調整するのが「シンボル」です
「ラベル」と「シンボル」を
うまく調整して
一目でわかるデータに仕上げるのです
【夏を詠む】空蝉の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
空蝉とは蝉の抜け殻のこと
今日は虫を詠んだ句を集めてみました
「蝉の声 追いかけるよう 泣く子かな」
小さい弟さん妹さんがいるのかな?
それにしても今年はあまりセミが鳴かないなと
勝手に感じていましたが
どうも全国的な傾向であったようですね
急激に暑くなったことと
空梅雨で地面が乾燥し固まって
羽化しにくかったことが原因と
考えられています
「蝉の羽 数えて落ちる 風の中」
過去の文献にも蝉の鳴かない年が見られます
1923年夏は神奈川県橘樹郡登戸村で
1707年は伊勢国萩原で
蝉がまったく鳴かなかった
という記録が残されています
1923年は関東大震災の年で
1707年は宝永地震の年
「蝉が鳴かない年には大地震が起こる」
などと短絡的に考えずに
しっかりデータを集めて
科学的に分析する必要がありそうです
GISの出番ですね
「夜もふけて 蚊に囲まれて 香にまみれ」
これはお見事!というほかありません
なんてテンポのいいリズムでしょう
香(か)とは蚊取り線香の香ですね
蚊取り線香の有効成分はピレトリン
除虫菊(シロバナムシヨケギク)
の花から抽出されます
昆虫の神経系に作用しますが
人に対する毒性は低いです
ただ魚や猫には高い毒性を示すため
飼い主は注意が必要です
震災前の輪島朝市の魚売りも
独特な虫除けの香を焚いていました
その匂いも含めて
懐かしい思い出です
越後を後に山を越え
地震から 628 日目
豪雨から 364 日目
今日は新潟での「商業研究大会」を終え
明日の「創造的復興サミット」のため
山を越え神戸へと来ました
サミットは明日ですが
今日は
「人と防災未来センター」を訪ねました
来週生徒たちが復興研修で訪れることになっていて
その事前研修をオンラインで行いました
副センター長様からご講義をいただいたのですが
生徒の「なんで校長がそこにいるんだ?」感が
おかしかったです
お話の中で心に残ったのは
「災害が起こると時間が10年進む」
今能登半島で起こっている出来事は
もし地震がなかったとしても
10年後には起こっていたこと
という意味です
人工流出や地価下落
10年後の日本の姿を映し出しているのが
今の能登半島です
今
目の前のことに一生懸命取り組んでいる
能登半島の高校生たちは
きっと10年後には
このノウハウを活かして
日本中で活躍しているはずなのです
それを目指してさまざまなことに
挑戦しています
学校では昨日より
地理情報システムGISを用いての
不自由研究が始まっています
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に分析する手法を学びます
イントロダクションに続く第2回は
『マップ』
地図上にさまざまな情報(レイヤー)を
重ね合わせる手法を学びました
重ねる基礎となるベースマップには
「地形図」
「衛星画像」
「起伏図」
「キャンバス」
などがあります
「マップ」アプリでお馴染みですね
さてそこに重ねるレイヤーとして
農林水産省による「耕作地」
基盤地図による「建物」や「標高10m」
国土数値情報による
「河川」やその「流域界」
「学校」やその「校区」
「バス停」や「バスルート」
さまざまなものがあります
地図に情報を重ねるだけで
いろんなことが見えてきて楽しいです
【夏を詠む】灼炎の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
補習も終わりいよいよ夏真っ盛り
今日はそんな頃を謳った句を集めてみました
「夏の風 肌にまとわる 熱の息」
今年の夏も暑かったですね
多くのお嬢さんが持っていた
ハンディ式の扇風機
あれすら熱風が当たるだけから危険
とまで言われていました
「炎天を 食べて笑って 越えにけり」
夏になると無性に食べたくなるものって
ありますよね
子供の頃の夏休みの思い出と
リンクしているものが多いです
みなさんの夏の思い出の食べ物は何ですか?
私は『しただめ』です
「かき氷 勝負のあとに 歯がうなる」
歯に染みるし頭もキーン
この頭キーンは
顔の感覚を司る三叉神経が
冷たさを痛みと勘違いするからです
三叉神経はよく勘違いする神経で
お酒を飲むと
赤くなる人と青くなる人
頭が痛くなる人とそうでない人がいますが
これも三叉神経の勘違いに関係しているといいます
アルコールは体内でアルデヒドに変わります
アルデヒドには血管を拡張させる作用があります
血管が拡張すると顔が赤くなると同時に
三叉神経を刺激します
三叉神経はそれを氷キーン同様痛みと勘違いします
アルデヒドを分解する酵素を持つ人には
それが起こりません
そのかわり次の作用がより大きく現れます
アルコールが脳下垂体後葉に作用すると
バソプレシンというホルモンの分泌が抑制されます
バソプレシンには
血圧を上げる作用があります
分泌が抑制されると血圧が下がり
顔が青ざめることになります
またバソプレシンは抗利尿ホルモンとも呼ばれ
腎臓での水の再吸収を促進して
尿量を減らす作用があります
お酒を飲むとトイレが近くなるのは
これができなくなることによります
ところでかき氷の頭キーン
天然氷よりも人工氷の方が
起こりやすいんだそうです
人工氷は一気に冷やして作るのに対して
天然氷はゆっくり冷やされてできます
すると不純物が入りにくいのです
不純物が混じると凝固点降下という現象が起こり
0℃より低くても溶け始めます
つまり人工氷は
温度が低いまま一気に削らないと
すぐに溶けてしまうのです
このため人工氷から作ったかき氷は
天然氷から作ったものに比べて
温度が低いのです
俳句から
生物や化学への教科横断に繋がりましたね
夏を詠む
地震から 627 日目
豪雨から 363 日目
夏休み俳句コンテスト開催中
生徒玄関に作品を展示してあります
一人ひとりにいろんな夏があったようです
毎日少しずつ紹介します
夏のはじまりに胸躍る
今日はそんな句を紹介します
「夏の海 きらめく先に 七ツ島」
七ツ島は輪島の沖合の小島です
輪島市名舟町に属します
北の島群(大島 狩又島 竜島)と
南の島群(荒三子島 烏帽子島 赤島 御厨島)
からなります
もともとは能登半島と陸続きでしたが
1万4千年前に別れたと考えられています
7つの峰を有し南西部に噴火口のある
大きなひとつの火山であったようです
「天高く馬肥ゆる秋」
夏の湿った太平洋高気圧とは異なり
秋の移動性高気圧は大陸から来る乾いた空気なので
雲のできる高さが高くなります
夏は雲底が2000m程度の積乱雲が中心ですが
秋は5000m付近でようやく高積雲
8000mを超えて巻雲ができるなど
実際に雲の高さが違うのです
それを昔の人は「天高く」と表現したのですね
さらには空気中の水蒸気が少ないと
青い光が散乱されず地表に届くので
空自体の青が深く澄んで見えます
ところでこの
「天高く馬肥ゆる秋」
美味しいもの食べて馬も太るよ
などと呑気な諺ではなく
本来は古代中国で
「北方騎馬民族が肥えた馬に乗って
秋に侵攻してくる」という
敵襲への警戒を促す意味合いで
使われていた物騒なものです
講談社の近藤大介氏は
著書『ほんとうの中国』の中で
多くの国に囲まれ
常に周辺異民族との侵略に晒されていた中国人と
周りを海に囲まれ
侵略から守られてきた日本人では
考え方がまるで違うと指摘なさっています
「常に周りに気を遣って同調しなければならない」
日本社会と
「周りはいつ敵になってもおかしくない」
中国人は
どうも相性が悪いような気がしますが
日本にやってくる多くの中国人は
社会保障制度やセーフティネットが脆弱で
政府や周囲の人間を信用できない
カネだけが唯一の拠り所である
そんな社会に疲弊しているそうです
【科学と歴史】vol.4
20世紀のマッドサイエンティストを紹介し
科学の発展と人類の幸せを考えるコーナー
実は日本にもマッドサイエンティストが存在します
名前は伏せます
先日とあるテレビ番組で
ある歴史上の人物を批判的に描いたところ
その子孫の方から名誉を貶められたと
局が訴えられていたからです
第二次世界大戦中
生物兵器の研究に携わっていた
陸軍731部隊の初代隊長が
捕虜に対して細菌を注射する
生きたまま解剖して感染細胞を取り出す
手足を切断するなどの
人体実験を繰り返したという
記録が残っています
このことは
中国で本日封切りとなる映画
「421」にも描かれているそうです
中国では政権が不安定になってくると
反日感情を煽って国民の目を逸らすのが
常套手段ではありますが
中国が「抗日戦争勝利80年」を謳う今年は
記念式典や軍事パレードが大々的に行われるなど
これまでとは違って穏やかではなさそうです
そんな中
南京での日本兵の残虐を描いた映画「南京大虐殺」
が7月25日に公開されるや空前のヒットとなり
8月15日にはアメリカとカナダでも上映され
中国国民のみならず
全世界に拡がりを見せているそうです
さらには8月8日公開の「東獄島」に続き
本日封切りの「421」
反日三部作ともいうべき作品が揃います
本来7月に封切りされる予定でしたが
中国共産党の意向で
本日に延期されています
9月18日は満州事変の発端となる
柳条湖事件が起こった日で
中国はこの日を「国恥日」としています
「421」のキーワードは
『馬路大』
「マールーター」と読みます
人体実験の実験台にする中国人を
「木材のような扱い」ということで
隠語で「丸太」と呼んでいたそうです
その中国語読みが『馬路大」です
戦争が落とした傷跡は大きいです
80年経っても癒えません
それでも世界中の人が
お互いを認め合って暮らせる社会の実現に向けて
歩みを止めてはいけません
北信越地区商業教育研究大会のため
先々週に引き続き
新潟の朱鷺メッセに来ています
イベント告知
地震から 626 日目
豪雨から 362 日目
本校男子バレー部が体験入部を行います
輪島市の小中学校には男子バレーのチームがないので
全員が初心者です
それでも
Aきらめない
Aいさつできる
Aいされる
みっつのAをモットーに
県ベスト8以上を目指して
頑張っています
9月21日(日)13:00~16:00
本校体育館で行います
希望者は
チラシのQRコード
あるいはこちらのリンクから
お申し込みください
お申し込みのデータをもとに
こちらで傷害保険に加入します
もひとつ耳寄りな情報です
私の尊敬する『口田 圭』氏による
トークライブ「なんやかんやで」
が開催されることとなりました
10月26日(日)15:00 より
金沢市湯涌温泉はCafé Lente において
かつて「ナンチャッテ教師」として
高校で英語の教鞭をとられ
今や
「口だけおじさん」として名を馳せる
口田 圭(くちだ けい)氏による
笑いながらなぜか元気になる
渾身の30分授業が繰り広げられます
ワンドリンクオーダー制ですが
「『おこらいえ』見てきたよ!」
と言っていただけると
店員さんの「怪訝な顔」のサービスがつきます
竹久夢二が生きていたら
きっと最愛の人と訪れたであろうトークショー
秋の湯涌温泉へぜひどうぞ
【科学と歴史】vol.3
20世紀のマッドサイエンティストを紹介し
科学の発展と人類の幸せを考えるコーナー
ハンガリー系アメリカ人数学者
『ノイマン』
ナチス時代にドイツからアメリカに渡りました
現代のコンピュータにつながる
多くの業績を残しましたが
彼が発見した
「爆弾による被害は
地上に落ちる前に
爆発したときの方が大きくなる」
という理論は
広島と長崎に落とされた原子爆弾にも応用されました
また投下の目標地点を選定する際には
「日本国民にとって最も大きな痛手を与えるために
深い文化的意義をもっている場所に落とすべき」と
京都への投下を進言しました
このような側面を持つ彼は
スタンリー・キューブリックによる映画
『博士の異常な愛情』の
主人公のモデルとされています
本当に京都に落とされていたら
今頃の日本はどんな世界だったでしょう
三谷産業さまのお力添えで
本校を会場に
卓球イベントを開催していただけることとなりました
企画運営は
石川県のプロ卓球チーム『金沢ポート』様
本日挨拶に来てくださったのは
執行委員で経営企画部長の 堀 祐巳 様
なんと私の七尾高校時代の教え子でした
久しぶりの再会に驚きです
慶応義塾で化学を学ぶ彼が
教育実習で来たときに
慶応の実験書見せてくれと頼んで
それを参考に
ハイレベル実験書を作ったのを
思い出しました
陸上部が新人戦に向けて出発しました
世界陸上に負けない熱戦を
繰り広げてくれるでしょう
明日から3日間
西部緑地公園陸上競技場で繰り広げられます
ぜひ応援にお越しください
学校では明日〜明後日と
GISを用いての探究学習が行われます
全15回の『不自由研究』の第2〜5回です
GIS(地理情報システム)とは
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に表示・分析するシステムです
地図上に複数の情報を重ね合わせることで
これまで見えなかったデータ間の関係性や傾向を把握し
効率的な情報管理や業務の最適化を可能にします
商圏分析やインフラ管理など
幅広い分野での応用が可能です
いよいよ明日から実践編です
高校生と一緒に学んでみたい方は
ぜひお越しください
18日(木)は14:00から2時間
19日(金)は 9:30から2時間行います
受講料は無料です
お気軽にお越しください
レモン彗星の日
地震から 625 日目
豪雨から 361 日目
朝日新聞の記事から
AI開発や活用で世界に遅れをとっていることは
政府も認めるところです
総務省の調査によると
個人的に生成AIを使ったことのある人の割合は
日本では27%なのに対し
中国では81%にのぼります
またスタンフォード大の調査では
2024年のAI分野への投資額は
米国が1091億ドルなのに対して
日本は9億ドルと
100分の1にも届きません
経済産業省の推計では
このままでは
海外のデジタルサービスに伴う日本の赤字が
30年後に原油の輸入額を超えるとしています
しかしながら
AIに対する認識が
「AIを使いこなす」から
「AIをパートナーとしてみなす」
に変わってきているところから
日本のAI技術が世界のモデルになる時代が
これからやってくるように思います
さて本日
和歌山大学から
くわ 将倫 客員准教授
此松 昌彦 教授
太田 和良 アドバイザー
のお三方が学校を訪れてくださいました
和歌山大学災害科学・レジリエンス共創センターでは
孤立集落における情報発信システムについて
研究なさっています
和歌山県は半島に位置する
少子高齢化が進む地域として
能登と同じ条件下にあることに加え
近い将来発生が懸念される
南海トラフ地震により
孤立集落が多く発生する危険性があります
今回我々が得た知見をお伝えさせていただきました
また和歌山大学さんでは
内閣府の主導のもと
「Q-ANPI」
の活用にも携わってこられました
これは衛星安否確認システムです
阪神淡路大震災の頃は
ちょうど携帯電話が
東日本大震災の頃は
電子メールが
熊本地震の頃は
インスタなどのサービスが
それぞれ普及し始めた時でした
いずれもその活用が期待されたのですが
電波がなければただの箱
結局最後は避難所を回って安否確認したといいます
今回の能登半島地震も同じ
最も有効な手段は
紙とマジックそしてガムテープでした
「ANPI 」のような安否確認システムの
普及が待たれます
ところでレモン彗星がやってきていますね
今年1月3日に
アメリカ・アリゾナ州の
マウントレモン天文台で発見されました
緑色をした彗星で
10月後半に向けて接近しています
北斗七星のひしゃくの柄を伸ばしていくと
アークトゥルスという
オレンジ色に輝く全天で4番目に明るい星に
ぶつかりますが
その近くに現れます
4等星ぐらいに輝くそうですが
その頃は新月と重なり
観測には最適なようです
さらには流星群とも重なり
1時間に数十個の流れ星も見られるそうなので
天文ファンでなくても
ワクワクなイベントになりそうです
マウントレモンは植物学者のレモンさんが
初めてその山に登頂したことにちなんでいるそうです
なんとも可愛い
そしてちょっとお間抜けなネーミングです
可愛くお間抜けといえば
最近全国的に
可愛くお間抜けな名前の幼稚園が
増えているようです
これは幼稚園の風紀を乱すような子の親は
えてしてそんな名前の幼稚園にやりたがらず
結果として落ち着いて活動できる雰囲気を
保つことができるからだそうです
空気からパンをつくる
地震から 624 日目
豪雨から 360 日目
【科学と歴史】vol.2
20世紀のマッドサイエンティストを紹介し
科学の発展と人類の幸せを考えるコーナー
前回は第二次世界大戦中に活躍した
原子力開発に関わる3人の科学者を紹介しました
今日はもう少し遡って
第一次世界大戦の頃の話をします
ドイツの物理化学者
『ハーバー』
人口増加に伴う食糧危機が叫ばれていた
19世紀末期のヨーロッパでは
アンモニア合成が喫緊の課題でした
カリウム・リンと並んで
植物の成長に欠かせない3元素のひとつ
窒素を含む肥料が不足したからです
特にドイツにおいてそれは深刻でした
それまで窒素肥料は硝石から作っていたのですが
硝石の輸入国チリとの関係が悪化し
手に入らなくなっていたからでした
1902年に同じくドイツのオストワルトが
アンモニアからの硝酸の合成に成功しました
その時用いた白金(プラチナ)の
触媒としての有用性も確認できました
硝酸さえできてしまえば
そこから窒素肥料を作るのは簡単です
あとはアンモニアをどうするか?
アンモニアは窒素と水素の化合物
窒素は空気中にたくさんあります
そこに水素をくっつける方法を
ハーバーは探ります
オストワルトに倣い
白金を触媒として鉄製の装置を用いて
その合成に成功します
しかしその実験には再現性がありませんでした
つまり他の科学者が同じように
白金触媒で実験してもうまくいかないのです
しかしその後ハーバーは
国家予算を受けて数千にも及ぶ触媒を試し
ついにその触媒を探し当てるのです
その触媒とは…
鉄
つまり最初に成功した実験に用いられた
実験装置そのものが触媒だったのです
鉄を触媒にして高温高圧にすると
空気中の窒素から
アンモニアを作ることができるのです
ところがその実験結果に
ネルンストが「測定値がおかしい」と酷評します
ハーバーが行った条件では合成できない
成功させるにはさらに高温高圧条件が必要である
そうすると費用対効果が低く
とてもじゃないが実用化はできない
ちょうどその頃
東京大学を卒業してハーバー研究所に入った
日本人研究者がいました
田丸節郎です
「死ぬほどはたらく人」
とハーバーに言わしめた田丸は
アンモニアの生成熱と反応ガスの比熱を正確に測定し
ハーバーの正しさを証明しました
田丸はハーバー研究所に入る前は
ネルンストの研究所にいましたので
恩師の反論を見事論破したことになります
こんなところにも日本人の繊細で根気強い
研究の成果が生かされているのですね
かくして空気中の窒素をアンモニアに変えて
それを硝酸そして肥料に
つまり空気からパンを作ることに成功したのでした
そのはずでした
ところが硝酸は肥料の原料となると同時に
爆薬の原料ともなるのです
ハーバーの理論が実用化され
実際に硝酸の大量生産が開始されたのが1913年
その翌年1914年にドイツが
フランスやロシアに宣戦布告しているところを見ると
ドイツ国家は国民の飢えへの対策ではなく
軍事への応用を
最初から狙ってのものだったのでしょう
ハーバーがその後
塩素ガスを用いた大量虐殺の研究に手を染めていることを見ても
そのことは明らかです
科学の発展は人々を豊かにします
しかしそれを用いる者が
「命」を蔑ろにした瞬間
それは破滅の道を転げ落ちることを意味します
科学と歴史
地震から 623 日目
豪雨から 359 日目
小松末広球場で高校野球秋の大会です
春の選抜につながる大会です
先発は森 晃大 くん
先制を許しますが…
3回の表23塁のピンチを
渾身のストレートで
4番打者を三振です
その裏
田屋くんのタイムリーで同点に追いつくと
坂本くんのライトオーバーの長打で
さらに2点追加です
スタンドでは
小さな応援団長が大活躍
1年生冨水選手の弟さんたちです
輪島高校にとって
給水タイムの後の6回表は
どうも鬼門のようで
夏の大会に続いての失点で
追いつかれてしまいますが
その裏すかさず
水口くんのタイムリーで突き放します
その後リードを許し
9回にはライトの坂本くんがマウンドに
4番の山田くんに特大ホームランを浴びます
3塁を回るところで
サードの水口くんが
「ナイスバッティング!」
拍手で見送りました
敵味方関係なく
素晴らしいプレイは讃える!
部活動の本来の姿です
あとになって相手の浅井監督から
伺った話です
私はスタンドから
目にすることができなかったのですが
その時冨水監督も
ベンチから拍手を送っていたのだそう
勝利至上主義に走り
生徒を傷つける言葉を浴びせる指導者が
最近問題になっていますが
ぜひ見てもらいたいものです
龍谷 100 002 211 7
輪島 003 001 001 5
グラウンドの修繕は終わりましたが
防球ネットがまだ立たず
打撃練習が全くできていません
それでもできることを
ひとつずつやってきて
私立の強豪相手にここまで戦えました
守備は鍛え上げられていて無失策
素晴らしいプレイが
そこかしこに見られました
未来の授業をつくる力をつけるため
教科横断型の授業を
全員ひとり1回は実施してください
と先生方にお願いしています
科学と歴史は特に親和性が高く
というより
科学の発展そのものが人類の歴史です
今日はそんな科学の歴史の中でも
20世紀が産んだモンスター
マッドサイエンティストについて
まずはユダヤ系アメリカ人物理学者
『オッペンハイマー』
「原爆の父」と呼ばれます
広島長崎に投下する直前の実験では
その成功に満足気だったと伝えられています
戦後に態度を一変させて
核兵器廃絶を熱心に唱える
ようになったところをみると
自らの研究が人殺しに利用されることを
もしかしたら知らされていなかったのかも
しれません
ユダヤ系ハンガリー人物理学者
『テラー』
ナチス時代に
ドイツからアメリカに亡命しています
「アメリカ水爆の父」と呼ばれます
水素爆発を5回起こして掘削し
巨大港湾を建設する
「チャリオット作戦」を計画しましたが
実現には至りませんでした
ソ連のロケット開発指導者
『コロリョフ』
1957年に世界初の
大陸間弾道ミサイル「R-7」を開発し
アメリカを直接攻撃できるようにしました
この技術を現在北朝鮮が利用しています
InterContinental Ballistic Missile(ICBM)です
また彼はこんなことも考えます
「もっと速度を上げれば
もっと遠くに届くはず
もっともっと遠くに飛ばして
ミサイルが落下する時に描く弧が
地球の球面に沿うくらいになれば
永遠に地球の周りを墜ち続けるはず」
世界初の人工衛星「スプートニク1号」
の開発に繋がりました
人工衛星は飛び続けているのではなくて
地球の重力によって
実は墜ち続けているのですね
【科学と歴史】
しばらくシリーズ化して連載します
桃毛
地震から 622 日目
豪雨から 358 日目
チコちゃんが
チョー難しい早口言葉を募集しています
うちの晴れ女が
「今あるので充分難しいわ
生グミ 生ゴミ 生桃毛」
とスラスラとのたまっていました
一個も合っていません
さすが
「親に向かって歯応えするな!」
の豊かな言葉の使い手です