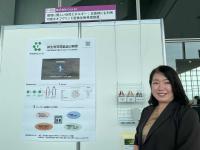校長室より「おこらいえ」
さよなら いろは橋
地震から 620 日目
豪雨から 356 日目
燃えた朝市通りと
夕市の立つお宮さんを結んでいた
『いろは橋』
昔は緑色の鉄骨の橋でしたが
あるとき
輪島塗りの黒と朱に塗り替えられました
以来多くの観光客が渡り
NHK連続テレビ小説「まれ」では
土屋太鳳さんが自転車で駆け抜けた
市民に親しまれているこの橋
架け替えられることが
先日の市議会で明らかになりました
橋のたもとには
『まれ』記念館がありましたが
火事で焼失してしまいました
奇跡的にスイーツのモニュメントが
残っています
スイーツといえば
大阪万博において
本校生徒が企画した
スイーツの販売が始まりました
ご協力くださったのは
(株)日本旅行様とまねき食品様
私立神戸野田高等学校様と
コラボしました
商品化してくださったのは
神戸を代表する洋菓子店の
(有)菓子工房ボックサン様
期間限定で出品したものが
好評によりレギュラー販売となったものです
現在販売されているものは
輪島高校が作った
「まいもんブルーベリー大福」
野田高校が作った
「淡路レモンの輝きカップスイーツ」
のセット商品です
24日からはメニューが一新され
輪島高校の
「栗とチョコのまいもん大福」
野田高校の
「マスカットの煌めきカップスイーツ」
セットです
輪島高校の商品には
「うま味の塩 能登 わじまの海塩」
野田高校の商品には
「淡路島の藻塩」
がそれぞれ使用されています
それぞれの地方の海の香りの違いを
感じてみてはいかがでしょう
こうして生徒たちはそれぞれ
未来に向けての歩みを
けなげに着実に始めています
ところが・・・
先日発売された『女性自身』に
ショッキングな記事を見つけました
被災地にいると自分の生活で精一杯で
意外と被災地のことを知ることができずにいて
自分自身も初めて耳にしたのですが
石川県の医療費の免除が
6月末で突如打ち切りになっていた
というものです
能登半島地震から1年半
いまだ仮設住宅に住み
生活困窮や病気にあえぐ高齢者に
非情な仕打ち
発災以降
自宅が半壊以上の被害を受けた人には
医療費の窓口負担などが免除される
特別措置がとられていました
国は9月末までの財政支援の継続を決めていますが
免除の継続については
保険組合が決定することになっています
富山県や福井県では
いまも免除が続いているようですが
石川県は財政が逼迫して
継続が困難だと判断したようです
患者アンケートでは
「受診せず我慢する」と28%の方が答え
「がん治療をあきらめる」といった声もあるそうです
東日本大震災の際には
いったん打ち切られた医療費免除が
住民の強い要望を受けて
再開された事例もあるそうです
【ぼうさいこくたいでのであいそのよん】
「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティアのみなさんを
紹介するコーナー
北九州市にある明治学園高等学校
防災減災班のみなさん
"Disaster Prevention Of Meijigakuen”
『DPOMs』さんは
地域の防災意識の向上を目指し活動しています
特にこどもたちに防災意識啓発活動を行っています
輪島高校の『街プロ』グループと
何かいっしょにできるといいね
きゅうきゅうきゅう命
地震から 619 日目
豪雨から 355 日目
多くの方に助けていただいて
今を生かせていただいている
そのことを一日たりとも忘れたことのない日々ですが
今度どこかで何かがあったら
自分に何ができるのか?
問い続けています
まずは防災士の資格を取ろうと考えています
そのためには救急救命講習の受講証明書が必要
私のそれは期限切れになっているということで
講習を受け直してきました
(1)安全を確認します
〇 傷病者の救助の前に自らの安全の確保が第一です
車が通って来ないか
煙が立ちこめていないか
(2)反応を確認します
〇 肩をやさしく叩きながら大きな声で
「大丈夫ですか?」「わかりますか?」
(3)119番通報してAEDを手配します
〇「誰か来て下さい!人が倒れています!」
大きな声で応援を求めます
〇 協力者が駆けつけたら
「あなたは119番へ通報してください」
「あなたはAEDを持ってきて下さい」
と具体的に指示します
〇 119番に電話したら
① 消防か救急か?
② 場所はどこか?
その2点をまず伝えます
傷病者の容態などはあとでいいです
その2点さえ伝えればその時点で
出動できるからです
場所がわからないときは
電柱に町名の表示があります
あるいは自動販売機にも貼ってあります
〇 次に携帯電話をスピーカーモードに切り替えます
両手をフリーにすることで
電話の指示を聞きながら次の処置ができるからです
(4)呼吸を確認します
〇 胸と腹を見て「普段どおりの呼吸」をしているか
10秒以内に判断します
〇 よくわからない場合は心停止と判断します
〇 しゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸は
「死戦期呼吸」といって「普段どおりの呼吸」ではありません
(5)胸骨圧迫をします
〇 心停止ではない傷病者に胸骨圧迫をしても
重大な障害が生じることはありません
〇 胸骨圧迫がうまくいかなくて助からなくても
罪に問われることはありません
ですので勇気を持ってしましょう
とはいえ私自身経験がないので自信はありませんが
〇 1分間に100回~120回の速さで30回
両手を重ね両胸の真ん中を
5cmくらい沈むように強く圧迫します
「そうだ おそれないで みんなのために
あいと ゆうきだけが ともだちさ
あ あ アンパンマン やさしいきみは
いけ みんなのゆめ まもるため」
これを歌いながらすると
ちょうどのテンポで32回になります
〇 人工呼吸の技術と意思があれば1秒ずつ2回
これもさっきのアンパンマンのマーチに合わせ
「ちゃーらっ ちゃーらっ ちゃらちゃかちゃんちゃん
ちゃっちゃかちゃんちゃん ちゃっちゃかちゃらちゃん」
間奏部分にぴったりはまります
(6)AEDが届いたら使います
〇 スイッチをオンにさえすれば
あとは機械の指示に従います
ひとりでやるとパニックになりそうですが
何人かで協力しながら行えば
誰にでもできそうです
今回受講した研修は
前もってオンラインで講義部分を受講し
その修了書を持って
実技に臨みます
まさにこれからの教育のヒントになりそうです
知識の伝達はオンラインで充分できますし
いやむしろ
その方が自分のペースで学べて
一時停止や繰り返し再生も自由なので
一斉講義よりも効果がありそうです
学校は
個々がそうやって知識を学んで集まって
それらを融合させて新しいものを産み出すための
場所となっていきそうです
【ぼうさいこくたいでのであいそのさん】
「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティアのみなさんを
紹介するコーナー
株式会社 JX通信社の 井戸 健介 様
市民参加型ニュースアプリ
地域密着型ニュース速報アプリ
AIリスク情報配信サービス
AIビッグデータリスクセンサ
などを開発され
多くの自治体で活用されています
本校の「街プロ」でも取り組んでいる
アプリ開発グループにご助言などいただけると
うれしいです
ことりのさえずりなぜピーチクパーチク?
地震から 618 日目
豪雨から 354 日目
被災地では
住むところをなくし
引っ越さざるを得ない教員が多くいて
全国的に教員の成り手が不足している中
一層教員不足が進んでいます
そんな状況を遠隔授業で解決すべく
県教委では機材を導入してくださいました
家庭科の山上佳織先生が
門前高校と繋いで
輪島高校から授業の配信です
今日は
「命を守るためには
どんな住まいがいいのだろうか」
家の模型を造り
揺れを確認したあと
地震に強い家について
グループでアイデアを出し合いました
門前高校の教室の様子を
モニターで確認でき
高性能のマイクで
教室の後ろの方の生徒のつぶやきも
しっかり配信側まで聞こえてきます
半島の最先端の小さな取り組みが
今後全世界で起こってくる
教員不足の問題への解決策の
糸口となります
まさに世界の最先端
そして未来を見据えています
今日は2回目の授業でしたが
1回目の問題点を踏まえ
格段に良くなっていることを実感できます
私は配信側で視聴していましたが
生徒のつぶやきが英語に聞こえました
マイクの機能または設定に
課題がありそうです
もしかして英語の特性に特化した
設定になっているのでは?
英語は「cap」「cat」「desk」など
子音で終わる単語が多いのですが
日本語で発音すると
「キャッpu」「キャッto」「デスku 」
のように必ず最後に母音がつきます
このことにより
はじめて英語を聞いた江戸っ子たちは
「p」「t」「k」の子音が
やたらと耳についたそうです
「なんでぇ!なんでぇ!毛唐め!
ptkptk
訳のわかんねぇことさえずりやがって」
『さえずる』という言葉は
現在は小鳥の鳴き声に特化して使われますが
当時は訳の分からない言葉を話す
人間に対して使われる言葉でした
ところが江戸っ子は
慣れない子音だけの発音がうまくできず
どうしても母音をつけて発音してしまうのでした
本人はptkptkと
英語っぽく発音しているつもりでも
ピーチクパーチク
と発音してしまいます
これが
小鳥のさえずりを
ピーチクパーチクと表現する
語源となりました
今回使用した機材はアメリカ製です
つまり子音を中心に聞き取り
子音を強調して再生する
おそらくそのように
開発されたのではないかと思います
母音が多くアクセントの少ない平坦な
日本語に特化したシステムが
開発されるといいなと思います
【ぼうさいこくたいでのであいそのに】
「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティアのみなさんを
紹介するコーナー
難民を助ける会 ARR Japan の
山形 真紀 さま
注目すべきは外国人被災者支援です
実は輪島高校避難所にもひとりいました
日本語も英語もできないベトナム人青年
さぞ心細かったことと思います
ポツンとひとり避難所の隅っこに
うずくまっていました
ときおり私も
翻訳機を持って行き
ベトナム語でお話したのですが
そんなに時間を割けるわけもなく・・・
どうなったんだろう?
ずっと気になっています
本校卒業生で早稲田大学名誉教授の 木棚 照一 様
奥様のまり子さまより
書籍の寄贈をいただきました
「80日間世界一周 80万円」
という新聞広告から始まった
世界一周クルーズ
ご自身の船旅の生活を
正確かつ詳細に記録したもので
今後の人生を考えさせてくれる一冊です
照一先生は高校時代
修学旅行をキャンセルして
大学入試の参考書を買われ
自己研鑽に励まれたそうです
後輩たちへの
「能登の復興と勉強に邁進せよ」
というエールとともに
贈っていただきました
図書室や学級文庫そして移動図書館にも
置かせていただきます
またご希望の方には差し上げますので
学校までご連絡ください
芸術の秋 落語の秋
地震から 617 日目
豪雨から 353 日目
ちゃかちゃんりんちゃんりんでんでん
てなわけで
今日は
チャリティー落語の会を催しました
桂 空治 師匠が来てくださいました
落語は想像の芸だそうです
演者が手にするのは扇子と手拭い
それだけで脇差と大太刀を演じ分けたります
それを補うのが観客の想像力
演者と観客が一体となって創り出す
日本の伝統芸能なんですね
もともと落語はお寺の講話だそうです
説法だけだと退屈して
しまいに誰も聞かなくなってしまうところを
あそこんちの熊さんがこんな面白いことしたよ
はっつぁんもこんな間抜けなことを言ってたよ
どんどん膨らんで面白くなったのだそう
教会でみんなが楽しめるゴスペルが生まれたのと
よく似ていますね
本当は月亭方正師匠も
いらっしゃる予定だったのですが
大雨警報のため急遽お越しになれませんでした
お詫びの方正師匠の手拭い
大争奪ジャンケン大会で幕を開けました
まず演じられたのはご存知
「寿限無寿限無五劫の擦り切れ
海砂利水魚の水行末雲来末風来末
食う寝るところに住むところ
やぶら小路のぶら小路
パイポパイポパイポのシューリンガン
シューリンガンのグーリンダイ
グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの
長久命の長助」
私自身フルバージョンで聞いたのははじめて
かと思いきや
実は被災地用にアレンジしてあったのだそうです
子どもを名付ける「お七夜」を「初七日」と間違えるくだりや
長い名前を「お経みたいだねチーン」とやるくだり
古典落語には本来ブラックな笑いがつきものなのですが
そういったものを一切排除して演じてくださいました
細やかな心遣いに感謝です
先日の「ぼうさいこくたい」でお逢いした
林 信太郎 先生から
興味深い情報を教えていただきました
「秋田城址という遺跡がありまして
そこからは平安時代の古文書が発掘されます
漆にゴミが入らないように
入れ物に反古で蓋をした紙は漆付きの紙になります
それが発掘されて
赤外線を当てると字が読めるのだそうです
漆のたいへんな保存性がわかります」
【ぼうさいこくたいでのであいそのいち】
昨日の「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティア団体の皆さま
一日で紹介しきれなかったので
今日からシリーズで紹介します
兵庫県立大学学生復興支援団体
LANのみなさま
2011年に東日本大震災を機に発足しました
今回の能登半島地震にも
のべ50名以上の学生さんたちが
支援に入ってくださいました
国際商経学部
社会情報学部
理学部
工学部
環境人間学部
看護学部
それぞれの学生さんたちが
それぞれの専門性を活かして
総合的な支援をしてくださっています
また大学院には
減災復興政策研究科が設置されており
誰ひとり取り残さない
社会を作る人の育成を目指し
災害に強い社会づくりに貢献されています
ぼうさいこくたい2025
地震から 616 日目
豪雨から 352 日目
地震 津波 豪雨 台風 噴火 豪雪 竜巻
様々な自然災害の影響を受けやすい環境にある日本
近年の自然災害は激甚化・頻発化しており
南海トラフ地震の発生も懸念されています
これまでに災害が発生するたびに
課題を洗い出し
経験と教訓を踏まえて
災害対応を進化させてきました
行政による「公助」
自分の身は自分で守る「自助」
地域で助け合う「共助」
能登半島地震においても
様々な支援の手を差し伸べていただきました
地域コミュニティやボランティアなど
人的物的両面での事前の備えや連携が重要であることを
身をもって知ることができました
そんな過去の教訓を未来へ伝えるべく
新潟において「ぼうさいこくたい」が開催されています
これまで日本各地で展開されてきたこの大会は
今回で10 回目を迎えます
多くの能登地区支援に入っておられた方々にお逢いして
お礼を申し上げてきました
災害支援団 Gorilla 代表理事の 茅野 匠 様と
環境防災総合政策究機構の 松本 健一 様
行政に止められても突破して支援に入ってくださった
力強い民間のボランティアの方です
https://npohoujin-gorilla.com/
日本ラクテーション・コンサルタント協会の
近藤 望 さま
被災地における
母乳で赤ちゃんを育てる必要のある
ママさんの支援をしていらっしゃいます
日本災害リハビリテーション支援協会の
堂井 真理 さま
高齢者や体に不自由がある方への
災害のフェーズに合わせた
リハビリ支援をしてくださっています
株式会社 Cell-En の代表取締役 COO
山口 直美 さま
環境に優しい自然エネルギー
「微生物発電」を開発なさっています
ぜひ『街プロ』のエネルギーグループに
伴走していただけるとうれしいです
日本地球惑星科学連合の
林 信太郎 様
自然現象 地殻変動 環境変動を研究対象とされており
防災教育小委員会を立ち上げていらっしゃいます
秋田大学の名誉教授でもいらっしゃる林先生は
「世界一おいしい火山の本」を書かれています
https://www.kodomo.go.jp/guide/kids/read/book/book_2012_03.html
昨年度の東北復興研修旅行以来
交流を深めている多賀城高校さん
今回も発表に参加です
生徒さんはテスト期間中ということで
津守先生と石山先生が
来ていらっしゃいました
関西大学 KANDAI DPE の
松井 芳樹 様
次世代を担うこどもたちへの
双方向型でワクワクできる
防災教育を実現しています
本校の「みつばちプロジェクト」に
教えていただけることがありそうです
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/about/pr/topics/2024/10/post_80323.html
災害時に子供を守る最低基準 様
まさかこんなところでお会いするとは!
「ごちゃまるクリニック」の
小浦詩先生と一緒に活躍してくださったみなさんです
https://sites.google.com/view/cpmsnetwork-japan-com/
続きはまたあした
愛子さまが手を振ってくださいました