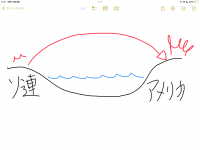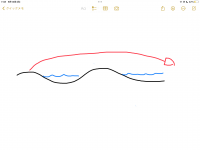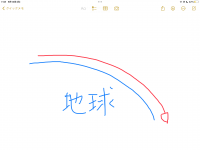校長室より「おこらいえ」
科学と歴史
地震から 623 日目
豪雨から 359 日目
小松末広球場で高校野球秋の大会です
春の選抜につながる大会です
先発は森 晃大 くん
先制を許しますが…
3回の表23塁のピンチを
渾身のストレートで
4番打者を三振です
その裏
田屋くんのタイムリーで同点に追いつくと
坂本くんのライトオーバーの長打で
さらに2点追加です
スタンドでは
小さな応援団長が大活躍
1年生冨水選手の弟さんたちです
輪島高校にとって
給水タイムの後の6回表は
どうも鬼門のようで
夏の大会に続いての失点で
追いつかれてしまいますが
その裏すかさず
水口くんのタイムリーで突き放します
その後リードを許し
9回にはライトの坂本くんがマウンドに
4番の山田くんに特大ホームランを浴びます
3塁を回るところで
サードの水口くんが
「ナイスバッティング!」
拍手で見送りました
敵味方関係なく
素晴らしいプレイは讃える!
部活動の本来の姿です
あとになって相手の浅井監督から
伺った話です
私はスタンドから
目にすることができなかったのですが
その時冨水監督も
ベンチから拍手を送っていたのだそう
勝利至上主義に走り
生徒を傷つける言葉を浴びせる指導者が
最近問題になっていますが
ぜひ見てもらいたいものです
龍谷 100 002 211 7
輪島 003 001 001 5
グラウンドの修繕は終わりましたが
防球ネットがまだ立たず
打撃練習が全くできていません
それでもできることを
ひとつずつやってきて
私立の強豪相手にここまで戦えました
守備は鍛え上げられていて無失策
素晴らしいプレイが
そこかしこに見られました
未来の授業をつくる力をつけるため
教科横断型の授業を
全員ひとり1回は実施してください
と先生方にお願いしています
科学と歴史は特に親和性が高く
というより
科学の発展そのものが人類の歴史です
今日はそんな科学の歴史の中でも
20世紀が産んだモンスター
マッドサイエンティストについて
まずはユダヤ系アメリカ人物理学者
『オッペンハイマー』
「原爆の父」と呼ばれます
広島長崎に投下する直前の実験では
その成功に満足気だったと伝えられています
戦後に態度を一変させて
核兵器廃絶を熱心に唱える
ようになったところをみると
自らの研究が人殺しに利用されることを
もしかしたら知らされていなかったのかも
しれません
ユダヤ系ハンガリー人物理学者
『テラー』
ナチス時代に
ドイツからアメリカに亡命しています
「アメリカ水爆の父」と呼ばれます
水素爆発を5回起こして掘削し
巨大港湾を建設する
「チャリオット作戦」を計画しましたが
実現には至りませんでした
ソ連のロケット開発指導者
『コロリョフ』
1957年に世界初の
大陸間弾道ミサイル「R-7」を開発し
アメリカを直接攻撃できるようにしました
この技術を現在北朝鮮が利用しています
InterContinental Ballistic Missile(ICBM)です
また彼はこんなことも考えます
「もっと速度を上げれば
もっと遠くに届くはず
もっともっと遠くに飛ばして
ミサイルが落下する時に描く弧が
地球の球面に沿うくらいになれば
永遠に地球の周りを墜ち続けるはず」
世界初の人工衛星「スプートニク1号」
の開発に繋がりました
人工衛星は飛び続けているのではなくて
地球の重力によって
実は墜ち続けているのですね
【科学と歴史】
しばらくシリーズ化して連載します
桃毛
地震から 622 日目
豪雨から 358 日目
チコちゃんが
チョー難しい早口言葉を募集しています
うちの晴れ女が
「今あるので充分難しいわ
生グミ 生ゴミ 生桃毛」
とスラスラとのたまっていました
一個も合っていません
さすが
「親に向かって歯応えするな!」
の豊かな言葉の使い手です
がんばれAI!
地震から 621 日目
豪雨から 357 日目
新しいプロジェクトの名前を
AIに考えてもらいました
さすがAI
瞬時に素敵なネーミングを
いくつも考えてくれました
出してくれたアイデア全てがスマートなのですが
と同時に全てが頭に残りません
ここがAIの限界ですね
どこかで聞いたことのあるような
耳障りのいいフレーズばかりで
新しいものがないのです
やはり時間をかけて自分の頭で考えないと
新しいものは生まれないのだなと思いました
三菱商事などの企業連合が
採算悪化を理由に
国内3海域からの
『洋上風力発電』撤退を表明しています
実は輪島沖にも震災前から設置計画を進めています
半島の先っぽにおいて
海上から安定した電気供給を受けれることは
大変魅力的です
本校では「電検三種」の資格取得を目指して
講座を設けています
このあと設置計画がどうなるかわかりませんが
勉強したことはきっと役に立つはずなので
がんばりましょうね!
NPO法人 RISE様のご協力により
GISシステムを学ぶ講座が
1年生全員を対象に実施されています
全15回のこの講座
今日はその第1回です
復興で終わることなく
世界をリードしよう
ご指導くださる京都大学の林春男先生から
オンラインで力強いエールをいただきました
GISによるデータ共有と相互作用によって
問題解決能力の向上を図る
「総合的な探究の時間」と
「地理総合」の教科横断型の学びです
1年生主任の山本宏行先生より
名人芸のガイダンスです
「GISとは
Geographic Information System
概念そのものは決して新しいものではないのですが
従来の単独目的利用モデルから
相互利用モデルへの転換が図られています
例えば昔の事例
Case1:パソコン素人の店主はじめ社員2名
個人経営のたこ焼き屋 2003年の事例
①たこ焼きができる間に来店客に郵便番号を書いてもらう
②データを委託会社に渡す
③結果から来客の地域を割り出す
Case2:三重県のある温泉旅館
①アンケートは取っていたが集計していなかった
②高評価を市町村別に集計して色分けして地図で見ると
はっきりと地域的傾向が見えた。
③ターゲットエリアを決定し集中して広告を打った
Case3:北海道のある自動車ディーラー
①新型が発表された際には
同じ車種の旧型に乗っている顧客を
GISで検索する
②同車種に乗っている顧客の多いエリアに
集中的に営業をかける
③営業マンが集めてきたお客様の反応を
再度GISにフィードバックする
現在ではマップの上に
お店の情報として
価格やメニューなどのほか混んでる時間帯など
さまざまなデータが重ねられ
あまりにも日常的になりすぎて
どこにその技術が使われているのか
わからないほどです
大谷選手の部屋に張ってあった
武田信玄の言葉です
『真剣だと知恵が出る
中途半端だと愚痴が出る
いい加減だと言い訳ばかり
本気でするからたいていの事はできる
本気でするから何でも面白い
本気でしているから誰かが助けてくれる』
なんでもおもしろがって本気でやろう!」
さよなら いろは橋
地震から 620 日目
豪雨から 356 日目
燃えた朝市通りと
夕市の立つお宮さんを結んでいた
『いろは橋』
昔は緑色の鉄骨の橋でしたが
あるとき
輪島塗りの黒と朱に塗り替えられました
以来多くの観光客が渡り
NHK連続テレビ小説「まれ」では
土屋太鳳さんが自転車で駆け抜けた
市民に親しまれているこの橋
架け替えられることが
先日の市議会で明らかになりました
橋のたもとには
『まれ』記念館がありましたが
火事で焼失してしまいました
奇跡的にスイーツのモニュメントが
残っています
スイーツといえば
大阪万博において
本校生徒が企画した
スイーツの販売が始まりました
ご協力くださったのは
(株)日本旅行様とまねき食品様
私立神戸野田高等学校様と
コラボしました
商品化してくださったのは
神戸を代表する洋菓子店の
(有)菓子工房ボックサン様
期間限定で出品したものが
好評によりレギュラー販売となったものです
現在販売されているものは
輪島高校が作った
「まいもんブルーベリー大福」
野田高校が作った
「淡路レモンの輝きカップスイーツ」
のセット商品です
24日からはメニューが一新され
輪島高校の
「栗とチョコのまいもん大福」
野田高校の
「マスカットの煌めきカップスイーツ」
セットです
輪島高校の商品には
「うま味の塩 能登 わじまの海塩」
野田高校の商品には
「淡路島の藻塩」
がそれぞれ使用されています
それぞれの地方の海の香りの違いを
感じてみてはいかがでしょう
こうして生徒たちはそれぞれ
未来に向けての歩みを
けなげに着実に始めています
ところが・・・
先日発売された『女性自身』に
ショッキングな記事を見つけました
被災地にいると自分の生活で精一杯で
意外と被災地のことを知ることができずにいて
自分自身も初めて耳にしたのですが
石川県の医療費の免除が
6月末で突如打ち切りになっていた
というものです
能登半島地震から1年半
いまだ仮設住宅に住み
生活困窮や病気にあえぐ高齢者に
非情な仕打ち
発災以降
自宅が半壊以上の被害を受けた人には
医療費の窓口負担などが免除される
特別措置がとられていました
国は9月末までの財政支援の継続を決めていますが
免除の継続については
保険組合が決定することになっています
富山県や福井県では
いまも免除が続いているようですが
石川県は財政が逼迫して
継続が困難だと判断したようです
患者アンケートでは
「受診せず我慢する」と28%の方が答え
「がん治療をあきらめる」といった声もあるそうです
東日本大震災の際には
いったん打ち切られた医療費免除が
住民の強い要望を受けて
再開された事例もあるそうです
【ぼうさいこくたいでのであいそのよん】
「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティアのみなさんを
紹介するコーナー
北九州市にある明治学園高等学校
防災減災班のみなさん
"Disaster Prevention Of Meijigakuen”
『DPOMs』さんは
地域の防災意識の向上を目指し活動しています
特にこどもたちに防災意識啓発活動を行っています
輪島高校の『街プロ』グループと
何かいっしょにできるといいね
きゅうきゅうきゅう命
地震から 619 日目
豪雨から 355 日目
多くの方に助けていただいて
今を生かせていただいている
そのことを一日たりとも忘れたことのない日々ですが
今度どこかで何かがあったら
自分に何ができるのか?
問い続けています
まずは防災士の資格を取ろうと考えています
そのためには救急救命講習の受講証明書が必要
私のそれは期限切れになっているということで
講習を受け直してきました
(1)安全を確認します
〇 傷病者の救助の前に自らの安全の確保が第一です
車が通って来ないか
煙が立ちこめていないか
(2)反応を確認します
〇 肩をやさしく叩きながら大きな声で
「大丈夫ですか?」「わかりますか?」
(3)119番通報してAEDを手配します
〇「誰か来て下さい!人が倒れています!」
大きな声で応援を求めます
〇 協力者が駆けつけたら
「あなたは119番へ通報してください」
「あなたはAEDを持ってきて下さい」
と具体的に指示します
〇 119番に電話したら
① 消防か救急か?
② 場所はどこか?
その2点をまず伝えます
傷病者の容態などはあとでいいです
その2点さえ伝えればその時点で
出動できるからです
場所がわからないときは
電柱に町名の表示があります
あるいは自動販売機にも貼ってあります
〇 次に携帯電話をスピーカーモードに切り替えます
両手をフリーにすることで
電話の指示を聞きながら次の処置ができるからです
(4)呼吸を確認します
〇 胸と腹を見て「普段どおりの呼吸」をしているか
10秒以内に判断します
〇 よくわからない場合は心停止と判断します
〇 しゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸は
「死戦期呼吸」といって「普段どおりの呼吸」ではありません
(5)胸骨圧迫をします
〇 心停止ではない傷病者に胸骨圧迫をしても
重大な障害が生じることはありません
〇 胸骨圧迫がうまくいかなくて助からなくても
罪に問われることはありません
ですので勇気を持ってしましょう
とはいえ私自身経験がないので自信はありませんが
〇 1分間に100回~120回の速さで30回
両手を重ね両胸の真ん中を
5cmくらい沈むように強く圧迫します
「そうだ おそれないで みんなのために
あいと ゆうきだけが ともだちさ
あ あ アンパンマン やさしいきみは
いけ みんなのゆめ まもるため」
これを歌いながらすると
ちょうどのテンポで32回になります
〇 人工呼吸の技術と意思があれば1秒ずつ2回
これもさっきのアンパンマンのマーチに合わせ
「ちゃーらっ ちゃーらっ ちゃらちゃかちゃんちゃん
ちゃっちゃかちゃんちゃん ちゃっちゃかちゃらちゃん」
間奏部分にぴったりはまります
(6)AEDが届いたら使います
〇 スイッチをオンにさえすれば
あとは機械の指示に従います
ひとりでやるとパニックになりそうですが
何人かで協力しながら行えば
誰にでもできそうです
今回受講した研修は
前もってオンラインで講義部分を受講し
その修了書を持って
実技に臨みます
まさにこれからの教育のヒントになりそうです
知識の伝達はオンラインで充分できますし
いやむしろ
その方が自分のペースで学べて
一時停止や繰り返し再生も自由なので
一斉講義よりも効果がありそうです
学校は
個々がそうやって知識を学んで集まって
それらを融合させて新しいものを産み出すための
場所となっていきそうです
【ぼうさいこくたいでのであいそのさん】
「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティアのみなさんを
紹介するコーナー
株式会社 JX通信社の 井戸 健介 様
市民参加型ニュースアプリ
地域密着型ニュース速報アプリ
AIリスク情報配信サービス
AIビッグデータリスクセンサ
などを開発され
多くの自治体で活用されています
本校の「街プロ」でも取り組んでいる
アプリ開発グループにご助言などいただけると
うれしいです