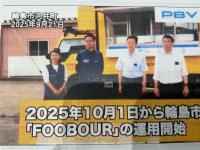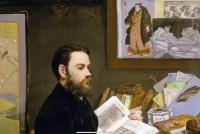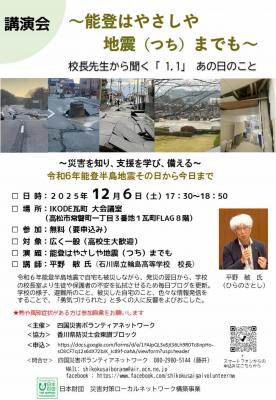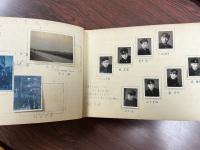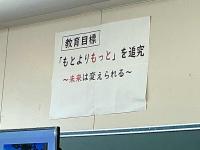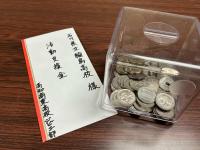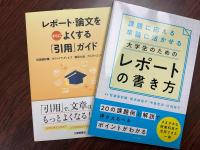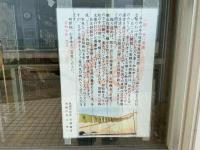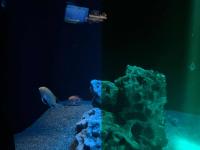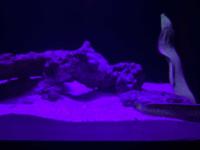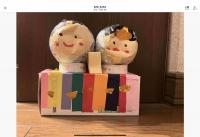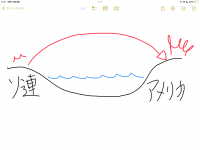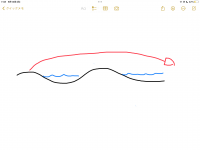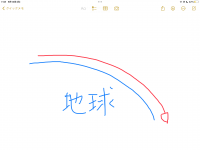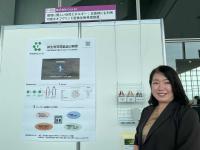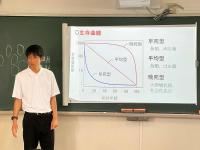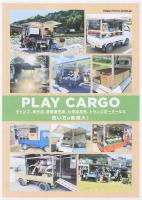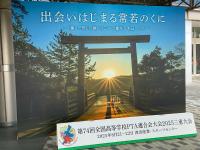校長室より「おこらいえ」
いろんな百周年
地震から 718 日目
全商簿記北信越大会に
本校より平野唯人さんが
出場することとなりました
団体枠のほかに
個人で出場できる枠があるのですが
県大会を見事勝ち抜いて
出場権を勝ち取りました
土曜日に長野県で行われます
校長室で
激励金をお渡ししました
健闘を祈ります
さて今年は実にたくさんのものが
100歳を迎えています
【日本相撲協会】
1923年の関東大震災で
両国にあった初代国技館が
甚大な被害を受けました
相撲は復興の象徴のひとつとなり
国民の心の拠り所として発展しました
被災した経験と再建の努力は
2年後の日本相撲協会誕生へと受け継がれ
復興へのエネルギーの象徴となりました
【NHK】
関東大震災は
「ラジオ放送の誕生」を決定づける
重要な出来事でもありました
通信網が寸断され
「情報が届かない」ことの
甚大な被害を目の当たりにした逓信省が
災害時の迅速な情報伝達手段として
放送の必要性を痛感し
ラジオ放送を始めました
命を救うメディア『ラジオ』は
のちのNHKとなるのです
【雪印メグミルク】
関東大震災により
多くの国民は貧しい食生活を
送らざるを得ない状況となりました
国として
「栄養価の高い乳製品を拡めよう」
という方向に舵を切り
乳製品の輸入を始めたのです
それは国内酪農家への大打撃となりました
「自分たちが牛から絞った牛乳を
自分たちで加工して販売しよう」
という目的で集まった酪農家たちにより
雪印乳業の前身である
北海道製酪販売組合が誕生したのです
【ブルボン】
関東大震災が発生した当時
お菓子工場は関東近郊にしかなく
震災で地方への供給がストップし
子供たちがおやつを食べることが
できなくなってしまいました
とある新潟県にある和菓子屋が
「地方にも菓子の量産工場が必要だ」
と設立した「北日本製菓」が
ブルボンの前身です
当初は栄養価があり保存が利くビスケット
つまり保存食の製造から始め
やがて全国展開していくのです
【トヨタ】
関東大震災の際
鉄道が壊滅的な被害を受け
輸送手段として自動車が大活躍しました
大地震による火災から
多くの人命を救出したのも自動車であり
震災の後始末から復興事業まで
トラックが全面的に使われました
贅沢品と見られていた自動車は
実用品として
その公共性・利便性が
広く理解されるようになり
自動車の輸入が激増しました
そんな時代背景の中創業した
のちに自動車部となる自動車製作部門を持つ
豊田自動織機製作所は
来年百周年を迎えます
(トヨタ自動車は自動車部の設立をもって
創立としていますので百周年はまだ先です)
【山手線】
甚大な被害を受けた鉄道整備も始まりました
その混乱と焼失を機に
現在の「環状」山手線の原型が整備されました
都市交通網の近代化が一気に進みました
今年百周年が集中しているのは
偶然ではなく
関東大震災から立ち上がる
力強い人々の証なのです
日本人はこうやって
災害のたびに何度も何度も立ち上がり
そのたびに素晴らしいものを
築きあげてきたのですね
関東大震災からちょうど100年が過ぎた
最初の元日に起こった能登半島地震
我々だって負けてられません
今日朝市のまちづくりに関する
打ち合わせを持ちました
朝市も立ち上がりますよ
今までの良さを残しつつ
新しい朝市を目指します
こども家庭庁実施事業である
「こども・若者分科会」が
わじまティーンラボさんを会場に
開催されることとなりました
またあの日が来ます
地震から 717 日目
お店にお正月用品が並び始めると
たとえ大人の私でも
2年が過ぎ去ろうとしている今でも
なんだか心がザワザワしてきます
スクールカウンセラーの板本 淳子 先生から
生徒のみなさんにメッセージです
「大 き な 出 来 事 ・ つ ら い 出 来 事 か ら 、 、 1 ヶ 月 、 1 年 な ど の 節 目 に 、 こ こ ろ や 体 が い つ も と 違 っ た 状
態 に な る こ と を 節 目 反 応 と い い ま す 。つ ら い 反 応 で す が 、 た く さ ん の 人 に 起 こ る 、 普 通 の 反 応 で す 。
多 く の 場 合 は 、 し ば ら く す る と の 心 と 体 の 状 態 に 戻 る 事 が で き ま す 。
か ら だ :な ん だ か 気 持 ち 悪 い ・ 頭 が 痛 い ・ お 腹 が 痛 い ・ く ら く ら す る ・ 息 が し に く い ・ト イ レ に 何 度 も 行 き た く な る な ど 。
気 持 ち : 何 も し た く な い ・ 食 欲 が な い ・ 眠 れ な い ・ イ ラ イ ラ す る ・ す ぐ 怒 っ て し ま う ・何 と な く 不 安 ・ い な く な り た い ・ 悲 し く な る な ど 。
行 動 : 物 を 叩 い た り 投 げ た り す る ・ ソ ワ ソ ワ す る ・ い つ も で き る 事 が で き な い な ど 。
そ の 他 :何 も し て い な い の に 涙 が で て く る ・ 車 が 通 っ た り し て 揺 れ る と 怖 い な ど 。
こ の 他 に も 、 い つ も の 自 分 と 違 う と 思 っ た ら 、 そ の こ と を 大 人 に 話 し て み て く だ さ い 。 お か し な
こ と で も 、 恥 ず か し い こ と で も あ り ま せ ん 。
心 が け て ほ し い こ と
・ い つ も 通 り の 生 活 リ ズ ム で 過 ご し ま し ょ う ( 食 事 ・ 遊 び ・ 学 習 ・ 睡 眠 )
・ 楽 し い と 思 え る こ と を し ま し ょ う
・ 大 人 と 一 緒 に 過 ご す 時 間 を 持 ち ま し ょ う
・ 気 持 ち を 話 せ る 人 は 、 大 人 に 聞 い て も ら い ま し ょ う
・ 無 理 を せ ず 、 つ ら い 時 は 「 つ ら い 」 と 言 っ て い い で す
・ 安 心 で き る 大 人 と 一 緒 に 過 ご し ま し ょ う
節 目 と は 関 係 な く 、 今 も 反 応 が あ る 人 、 こ れ か ら ず っ と 後 に な っ て 反 応 が 出 る 人 、 ま た 反 応 が 長
く 続 く 人 な ど 、 人 に よ っ て そ れ ぞ れ 反 応 は 違 い ま す 。
気 に な る 事 が あ れ ば 、 気 楽 に 、 相 談 室 に 来 て く だ さ い 。
受 験 を 控 え て い る 人 も い ま す ね 。 頑 張 っ て く だ さ い !」
今輪島市では
子どもたちが
犯罪に巻き込まれるリスクが高まっています
元々のんびりした田舎で
犯罪とは程遠い平和な場所なので
そこで育った『おぼこい』子たちは
すぐに他人の言うことを信じてしまうので
犯罪に巻き込まれたり
さらには知らず知らずのうちに
加害者になってしまう危険性もあります
『おぼこい』とはこちらの方言で
純粋で穢れを知らないと言う意味です
石川県警の
中西 裕也 様
清谷 柚子 さまが来てくださり
『防犯教室』をしてくださいました
『闇バイト』ならぬ『闇犯罪』
『SNS』に関する問題
困ったことがあれば
迷わずに相談しましょう
奉納の舞
地震から 716 日目
福岡で教室をされている
『ユカリクラシックバレエ』代表
光永 ゆかり さま
同じく福岡で活動されている
『なないろハーモニー』の
指揮者 稲永 恵子 さま
ピアニスト 黒瀬 明子 さま
コーラス 國友 むつみ さま
そして運転手兼陰のラスボス
太田 俊隆 様
が学校にお見えになりました
『なないろ』といえば
今朝美しい二重の虹が出ていましたね
ほんの一瞬でしたが
北陸の冬の始まりの朝は
しょっちゅう虹が見えます
二重の虹は
ダブルレインボーと呼ばれる
非常に珍しい現象で
見られる確率は約1%ほどと言われています
『主虹』とよばれる内側の虹は
色の並びが通常の虹と一緒
外側から 赤→橙→黄→緑→青→藍→紫
ところが『副庭』外側の虹は色の並びが逆で
外側から 紫→藍→青→緑→黄→橙→赤
二重の虹の間を見ると
ほんのり薄暗くなっています
これを見ると幸せになれるそう!
これはアレキサンダーの暗帯と呼ばれています
さてご一行さまは
先日先々日と珠州などを訪れ
本日重蔵神社へ向かわれる途中
お立ち寄りくださいました
重蔵神社では歌と舞を奉納なさいました
『ユカリ』さん『なないろ』さんとは
弓削田健介さんによる
合唱曲『フェニックス』が御縁です
合唱曲で全国を繋いだ動画で
歌ってそして踊ってくださっています
重蔵神社の禰宜さまより
能登復興祈願のステッカーをいただきました
なるほど
能登半島は龍の形をしているんですね
そして重蔵さんは
その龍眼に位置します
仮設校舎での授業が始まって1週間
さまざまな課題満載の中
教員も生徒も試行錯誤しながら
それでも一歩ずつ前へ進んでいます
調理実習もはじまりました
思えば水道の通っていない旧校舎では
水汲みからしていましたね
その時に比べると
ほんと恵まれた環境です
以下家庭科の 山上 佳織 先生からの報告です
「お皿は地震でたくさん割れてしまったので
カレー皿やお椀も使い工夫して
ローストチキン
コンソメジュリエンヌ
苺サンタクロースケーキ
を作りました
生徒たちは
「先生〜ありがとう〜美味しかったよ〜」
「うめ〜また食べたい〜」
と目をキラキラ輝かせて
調理室を去っていきました
高校での家庭科の単位数は少ないですが
記憶に残る授業になっていたらいいな
と思う今日この頃でした」
水汲み体験も含めて
きっといい思い出になって
生徒たちの心の中に
輝き続けると思いますよ
それにしても
コンソメジュリエンヌって
名前からしてオシャレやな
人生で一度も食べたことないわ
山上先生は
文部科学省より
今年度の優秀教員に選ばれました
被災地での
先進的な遠隔授業の実践も含め
その高い授業力が評価されてのものです
おめでとうございます
明日 17日 夕方
HAB 北陸朝日放送 にて
本校の卒業生のその後を追った
ドキュメンタリーが放送されます
18:15 からの番組の中
18:25 過ぎから5~7分間の放映です
ぜひご覧ください
蔦重逝く
地震から 715 日目
江戸のメディア王「蔦屋重三郎」を描いた
NHK大河ドラマ「べらぼう」が
最終回を迎えました
小芝風花さん演ずる花魁『瀬川』との別れ以来
実は私はなかなか見れなかったのですが
久々に最終回を見ることができました
わずか10ヶ月で140点以上もの作品を残し
忽然と姿を消した謎の絵師『東洲斎写楽』
番組では絵師集団として描かれていました
バンクシーみたいですね
そうだとすると
前期と後期で作風がガラリと変わることも
短期間で多くの絵を残したことも
説明がつきますね
なるほど
川に落ちて消息不明となった『唐丸(からまる)』
彼が実は『写楽』で
いつか蔦重が窮地に落ちいたった時に
助けに来るんだとばかり予想していたのですが
彼はのちの喜多川歌麿でした
東洲斎写楽の正体には諸説あり
現在最も有力とされているのは
阿波徳島藩お抱えの能役者
『斎藤十郎兵衛』説です
役者の内面をえぐるような大胆な筆致と
極端なデフォルメは
当時の役者からは不評だったようですが
そんな日本人離れした感性の持ち主は
オランダ人絵師『シャーロック』であった
というのが私の一押しの説です
これから新しい発見があったら
明らかになっていくのでしょう
これが『歴史』の醍醐味です
さあその江戸時代
なんだか色々興味が湧いてきたので
いろいろ調べてみました
まずは蔦重の本のお値段は?
新刊本は300文
今の値段にして4,950円
結構しますね
でも写真集と思えばそんなもんか
浮世絵は1枚32文
今の値段で528円
これもそんなもんですかね
江戸の宿泊代は
1泊2食で48文(4,092円)
やすっ!!
中国人が大量に押し寄せていた
少し前の日本での
1杯40,000円の海鮮丼
(築地で実際に見た!)
に比べれば驚きの安さですね
「中国人は所構わず
でっかい声で騒ぎまくる
でもそれは文化の違いである
常に他民族による
侵略の危機に晒されていた中国では
他の人に聞こえないように
ヒソヒソ話すると
クーデターを企てていると思われるから
「私たちは何も隠し事はありませんよ」
アピールのため
わざと他人に聞こえるように
大声で話すのです
中国人にしてみたら
他人に迷惑かけまいと小声で話す日本人こそ
不気味な存在に見えるのです」
ということは以前このブログにも書きましたが
最近では
大声で話す人に「シーッ!」と
互いに注意しあう中国人同士の姿を
見かけるようになりました
きっと「日本の文化ってこんなんですよ」
って紹介するガイドブックやガイドさんが
増えてきてるんだろうなって感じています
他国の文化を理解しあって
尊重し合うってとっても素敵なことですね
『世界平和』
防災講座
地震から 714 日目
仮設校舎に受験生が集って頑張っています
金沢大学で
「探究・STEAM フェスタ」が開催され
本校から3名の1年生が参加しました
金沢大学では
教科横断型の探究学習を通した
高大接続・高大連携の取り組みを
推進されています
今回は「高校生の探究心に火を灯す」
特別企画です
大学生とのリアル探究トークを通して
新たな学びを得て
将来に向けてのきっかけとなりました
私ごとですが
先日受験した防災士試験
合格することができました
晴れて防災士として初めて
防災講習に参加しました
輪島市避難所運営研修会です
ピースボート災害支援センターさんが
主催してくださいました

ピースボート災害支援センターさんは
国内外の災害支援と
防災・減災を専門にする公益法人です
まずはコーディネーターの
辛嶋 友香里 さまから
様々な知見をいただきました
まずは避難所の運営主体は
避難者自身であること
その意識を持つことの大切さ
避難所で繰り返し起こっている
3つの課題があります
① 「場」の課題
衛生環境 安全管理 情報共有など
② 「人」の課題
安否確認 要配慮者 生活再建など
③ 「運営体制」の課題
環境整備 運営者も被災者 など
これらの課題を解決するには
避難者一人ひとりが
自主的に考え行動することが大切です
次に簡易ベッドの大切さ
単に寝心地の良さかと
これまで認識していたのですが
睡眠時の頭の高さを
床から35センチ離すことに
大きな意味があるそうです
それだけ違うだけで
温度が10℃も違ったり
床から舞い上がる埃やウィルスが
激減することがその理由です
今回の能登半島地震では
186ヶ所の避難所が開設されました
これは全国的にみても
例のない多さなんだそうです
今回は
避難所で実際に暮らした方
あるいは避難所運営に携わった方
そんな方が集まって
避難所で実際にあったあるあるを
語り合うことから始めました
6つのグループに分かれて
テーマに沿って
「次はこうしたい」
経験を踏まえたアイデアを出し合いました
【洗濯】
◯ 発電機の設置
◯ 男女別の物干し場
ただしその際娘を持つシングルファーザーなど
解決すべき課題は多い
【食事】
◯ 好き嫌いがある人は自分で備えるべき
【情報】
◯ 掲示板を充実させる
◯ 電波状況を改善する
◯ 情報弱者への配慮
【入浴】
◯ 入浴情報の周知
◯ 入浴用の送迎車両
◯ 要介護者用風呂
◯ 介護シャワー用車両
【寝床】
◯ テントを張ってのプライベート確保
◯ 枕とシーツの支援
今回得た知見として
しっかりと将来へ伝えていく
責任を感じました
またピースボートさんは
平常時のひとり親家庭支援と
災害時の迅速な職の支援を両立する
フェーズフリー型キッチンカー
「FOOBOUR(フーバー)」の運用を
10月から輪島市でも始めたそうです
これは
平時には
食品・日用品を24時間取り出し可能な
無人車両として
地域のひとり親世帯の支援をします
そして災害時には
キッチンカーとして
温かい食料を提供できるものです
輪島市では発災前は
1800人に3食分の備蓄しかなかったものを
今回の地震を受けて
13000人に対して3食2日分に
増やすそうです
ふるさとプレコン最優秀賞!
地震から 713 日目
「ふるさとプレゼンコンテスト」に
参加してきました
場所は KANDA SQUARE
開始までしばらく時間がありましたので
じっとすることと
長い話がことのほか苦手な私は
例によって
会場付近をうろちょろするのでした
上野東照宮へ行ってみました
家康危篤の床に呼ばれた
藤堂高虎と天海僧正
「末永く魂鎮まるところに祀ってほしい」
との遺言に則って建てられたのが
ここ上野東照宮です
元々は藤堂高虎邸敷地だそうです
こちらは国指定重要文化財の『唐門』
日光東照宮『眠り猫』で有名な
左甚五郎(ひだりじんごろう)作による
昇り龍・降り龍の彫刻が左右にあります
偉大な人ほど頭を垂れるということから
頭が下を向いている方が
昇り龍なんだそうです
諫鼓鳥(かんこどり)の透かし彫りも見れます
これは中国の皇帝が門の前に太鼓を置き
政治に誤りがある時は人民にそれを打たせ
訴えを聞こうとしたけど
善政のため打たれることが無く
太鼓の台座は苔生し
鶏が住みつくほどであったと言う話が
基となっています
まさに家康が築いた300年に及ぶ
戦のない
泰平の世の中を象徴しています
「閑古鳥が鳴く」
の由来になったとも言われています
大きな銀杏の木があちこちに
銀杏の木は燃えにくいので
防火のために植えられたのだそうです
防災意識高いですね
国立西洋博物館では
オルセー美術館所蔵
「印象派」特別展が開催されていました
オルセー美術館は
パリ万博の際に建てられた
会場への終着駅だったんだそうです
大阪でいうと「夢洲」駅
みたいなもんですね
印象派とは
19世紀後半にフランスで生まれた芸術運動です
カメラの発明がその契機となっています
画家たちにとって死活問題だったでしょう
「カメラによって職業が奪われる」
ちょうど現代の我々が
「AIによって職業が奪われる」
と危惧しているのと似ています
AI時代を生き抜くヒントが
『印象派』の絵画にあります
こちらはドガによる『家族の肖像』

当時身を寄せていた叔父一家です
叔父の事業の失敗により家族は不仲
一堂に会することなどなかった家族
ひとりずつ個別にデッサンを重ね
一枚の絵に仕上げ
当時の家族の間に流れる不安を
見事に描き出しています
これなどは
当時のカメラにはできない
それこそヒトでないとできない
まさに芸術です
『印象派』の名称は
モネの《印象、日の出》がきっかけで
当時のカメラでは表現しきれない
光と色彩を重視したものです
これまでの絵画が担ってきた
「現実を写す」役割は
これからはカメラがやってくれる
明るい色彩や大胆な構図を取り入れ
「光と瞬間的な印象を捉える」
ことを目指した芸術活動が
近代美術の幕開けを告げたのです
『印象派』には日本の芸術も
大きな影響を与えています
こちらは『マネ』による
『エミール・ゾラ』
懇意にしていた美術評論家を描いたものです
背景には浮世絵が見えます
他国の文化を積極的に取り入れ
新しいものを生み出しているのも
『印象派』の特徴です
来年
本校からパリ研修に出かけます
ぜひオルセー美術館も
見てきて欲しいと思います
オルセー美術館は
古典芸術を集めたルーブル美術館と
現代アートの殿堂ポンピドゥー・センターを
繋ぐものといわれています
プレゼン大会はというと
全国から予選を勝ち抜いた
小学生から3組
中高校生から4組
大学生から3組の
ノミネートがありました
本校教諭 寺田 知絵 先生が
開会挨拶を務めました
電気が復旧するのに4ヶ月
水道が復旧するまで8ヶ月
かかったんですと
そのつらかった生活の話をすると
言葉につまり
会場の皆さんも目頭を押さえていました
いつも笑顔の寺田先生
こんなに辛い毎日を乗り越えていたんです
本校から
2年生の
平 愛結奈 さん
大岩 楓 さんが
「輪島が生きる」と題して発表しました
千枚田そして輪島塗に
輪島の復興をかけるみなさんのことを
紹介しました
多くの方々の感動を呼び
最優秀賞をいただくことができました
出張のたびに
これまで遠くからご支援くださった方を
順番に尋ね
直接ご挨拶を申し上げています
昨日は
発災後真っ先にご連絡くださり
地震避けのステッカーを
送ってくださった
東京で小学校にお勤めの
毛利 泉 先生を尋ねました
いただいたステッカーは
先生が師事されている
寄席文字書家「橘右之吉(たちばなうのきち)師匠」
によるもので
輪島高校避難所のあちこちに
貼らせていただいていました
なんだか遠い昔のことのようです
まだご挨拶できていないみなさん
申し訳ございません
いつの日か行きたいと思っております
プレゼンの極意
地震から 712 日目
昨日
アナウンサーの 原田 幸子 さまをお招きして
話し方講座の3回目〜発展編〜を実施しました
これまでのおさらいをプリントにして
配っていただきました
原田師匠は
昨年『紅白歌合戦』の輪島高校中継で
進行役を務めたNHK金沢放送局の高畠菜那アナ
私から見たら
有吉弘行さん
橋本環奈さん
伊藤沙莉さんと並ぶ名司会者
彼女の師匠に当たる方ですので
それはそれは相当なものです
師匠直伝のおさらいプリント
ぜひ紹介させていただきたいと
お願いしたところ
惜しみもなくご了承くださいましたので
ここにご紹介させていただきます
* * *
そもそも『プレゼン」とは何でしょう?
『プレゼン』の語源は『プレゼント』
心を込めた、相手への「贈り物」です
「伝えたいこと」つまり「想い」を贈るのです
ではどうやったら伝わるのでしょう?
それは『声の道」を意識することです
大きな声で
ゆっくりと
聴衆に目を配りながら
「伝えたい」と思いながら話すのです
「伝わるプレゼン」には
いくつかのポイントがあります
① 導入の大切さ
声と内容を意識して「第一声で心を掴む」
ことが大切です
② 着地点を意識することの大切さ
「終わりよければすべてよし」
③ 構成の適切さ
「山はどこか」
最も言いたかったことに
時間が割かれていますか
④ 身近なエピソード
「誰でも言えることではない
“あなたらしさ”」
⑤ 思いをのせる話し方
「声に表情をのせる」
⑥「間」が大切
伝えたいワードの前に
大切な話の後に
⑦ 緩急を使う
初めて出てくる言葉
核となる言葉
強調したい部分は
ゆっくりと
「自分が聞きたいプレゼンを目指しましょう!」
自分のプレゼンを撮影し
原稿を見ずに客観的に聴いて見てみましょう
その声から
表情から
姿勢から
「伝えたい気持ち」は伝わりますか?
常に
「初めて聞く人にわかってもらう」
ことを意識しましょう
プレゼンを魅力的にするには
「取材の仕方」も大切です
事前に準備していった質問に
囚われすぎないこと
相手と「会話する」
話を “広げる” “深める”
相手に “興味を持つ”
予定調和でない流れから
思いがけない話を
聞くことができます
* * *
さすがプロのアナウンサー
一つひとつが
なるほどな!
というポイントばかりです
文部科学省へ出かけ
自分たちの活動を報告してくるとともに
被災地の探究活動に対し
格段のご配慮を賜りますよう
お願いをして来ました
夕べ1時近くまでかかって
ホテルのロビーで準備した甲斐あって
素晴らしい発表ができました
生徒の感想です
宮腰花歩(1年生)
【一日目】OECDのお話を聞いて
日本の教育、国際関係、災害が起こった際などの様々な観点からの議論を聞いていてとても興味深かったです。例えば日本の教育について群馬県教育委員会の今井さんが話されていた非認知能力の育成についてですが、ただ単に勉強ができるというだけなく、主体性、創造力、コミュニケーション能力などの国際化していく社会において不可欠となっていると思っています。そのような中で私自身も学校という少し閉鎖的な空間だけではなく、今回行った東京や今度行くフランスなどの様々な地域や人との交流を通じて経験をたくさん積んでいきたい、と思いました。また、輪島のような過疎化が進んでいる地域でどうしたら都会との格差を埋めることができるかなどの課題も知ることができました。
【二日目】文科省へ行って
今日のスライド発表で自分の改善点が浮き彫りになったな、と思いました。もっと自分のスライドの原稿を突き詰めていけばよかったな、と少々後悔していることもありますが、これをバネにして今後の探究におけるスライド発表などに活かしていきたいと思います。
この2日間を通して、おそらくなかなかできない体験をさせていただいて、自分の中でとてもいい経験になったと思いますし、今の自分に足りないものを知ることができたと思います。ここで学んだことなどを、今度はフランスに行ったときに活かせることができればな、と思いました。
出る杭はつながる!
地震から 711 日目
今日のキーワードは『つながる』
被災地の子どもたちの想いを綴って
作曲家 弓削田 健介 さんがつくってくださった
合唱曲『フェニックス』
今も多くの絆を繋いでくださっています
佐賀での全日本音楽研究大会でお会いした
北海道の奥尻中学校の塩原祐馬先生より
仮校舎完成お祝いのメールをいただきました
「フェニックス」の音楽の力を
今度授業でお話されるそうです
素敵な授業になりますように
全国の教育現場を合唱でつなぐ
『フェニックス』つながるプロジェクト
に参加された
福岡市で『ユカリクラシックバレエ』
を主催されている
光永 ゆかり さまから
お手紙をいただきました
14日から16日に能登半島にお越しになり
仮設住宅でバレエを披露してくださいます
さて今日は
日本OECD共同研究
『2040年の日本の教育を
ホンキで考えるシンポジウム』
に参加するために東京に来ました
ポルトガルより
パウロ教育局課長が来日されたので
お逢いしてきました
生徒たちも
今春のポルトガル研修について発表しました
国際比較で見た
日本の教育の課題と可能性について
課題先進国の日本
そしてその課題が
さらに浮き彫りになった被災地で
未来の教育の先取り実装に
試行錯誤したがら取り組んでいる
現場の実例を紹介してきました
東京駅から会場まで歩いて移動しました
完全におのぼりさん気分です
東京駅何年ぶりでしょう
江戸時代に徳川家康に仕えた
オランダ人通訳「ヤン・ヨーステン」
彼が住まいをした場所は
彼の日本名「耶楊子(やようす)」がなまって
「八重洲(やえす)」となりました
東京駅八重洲口の反対側の丸の内口が
皇居へ向かう出口です
桜田門をくぐります
大老井伊直弼が殺害されたところですね
こちらは百人番所

江戸城の警備をするところで
各藩が担当していたそうです
現在でいうと
皇居の警備に各県警が当たっている
って感じですね
松の廊下跡です
松と千鳥が描かれた襖の長い量敗きの廊下で
赤穂演士討ち入りにつながったことで知られる
浅野内匠頭の吉良上野介への事件があった場所です
「殿中でござる!」
石室です
火災などがあった時
大奥の調度などを避難させた場所です
防災意識高いですね
そんなこんなでたどり着いた会場
今日のセッションでは
人口減少・自然災害・国際化経済・デジタル社会
という4つの切り口から
「2040年の日本にホンキで備える」
そのための具体的な一歩を考えます
パネルディスカッションに参加して
こんな感じでしゃべくりました
【セッション1】
問い:2040年よりも前に
もしも南海トラフがおきたら
なにができますか?
「昨年元日の地震で家も車も何もかも失って
それ以来退屈しない毎日を過ごしております
本来退職となる年でしたが
留年してもう一年校長を務めております
昨年1月の残業時間は300時間を超えるという
教員のWell-beingという今日のアジェンダとは
程遠い生活を送ってきましたが
その代わり通常では経験できない
多くの幸せにも出会うことができました
学校が避難所と教育機関として運営していく中
さまざまな課題に直面し
その度多くの方々に助けられてきました
中でも
DMATとの出会いは衝撃的なものでした
Disaster Medical Assistant Team
日本中の医療関係者が
被災地での医療を止めない
そんな枠組みをつくっています
教育でも同じような
国を挙げての支援の枠組みが必要である
DMATの教育版が必要であると文科省に提言し
D-est(Disaster Education Support Team)の
設立につながりました
南海トラフが起こったら
その一員として
もちろん恩送りに駆けつけます」
【セッション2】
問い:もしものために
あなた自身ができること
していきたいことは何ですか?
「自然災害は時を10年進めるといわれます
これは10年未来の世界に行ける
という夢のある話ではなくて
10 年後に起こるであろう諸課題が
前倒しして一気に襲ってくる
という意味です
現在能登半島はまさにその状況です
これから10年後
必ず日本の各地
さらには世界の各国に起こるであろう
様々な課題
少子高齢化であったり教育格差であったり
そういったものが
容赦なく襲いかかって来ている訳です
特に教員不足の問題は深刻で
今年度30人中5人が大学を卒業したての新規採用者です
これまで在籍していた教員が
生活拠点を失って転勤してしまうからです
教員の絶対数が圧倒的に不足している訳です
ただ被災地での最初の教員経験は
今後の生涯の教員人生において貴重なものとなるはずです
被災地で何もかも失った子供達が
それでも前を向いている姿を目にし
何も感じないのであれば
残念ながら教員としての資格はありません
今日もそんな震災地の学校に赴任してしまった新規採用教員
まさに震災の新採
一緒に来てもらっています
彼にとっても今日この場に同席すること
これ自体が大きな財産になるはずです
そんな中で多くの課題に対して
これ以上失うものが何もない被災地であるからこそ
思い切った教育活動を展開できています
『教育とは
魚に泳ぎ方を教えることではなく
自由に泳げる環境を与えることである 』
を体現していきたいです」
今日はいわゆる『出る杭』たちの集まりでした
「出る杭は打たれる」それは昭和の田舎の話
出た杭どうしでどんどんつながっていきましょう!
仮校舎2日目
地震から 710 日目
昨日の仮校舎初日の様子を
多くのマスコミの方が
取材に来てくださいました
ある地元誌では
私が言ってもいないことを
コメントとして掲載してありました
「環境が変わってもしっかり勉強してほしい」
と言ったのが
「十分な施設ではないけれど…」
とあたかも現状に不満があるかのような
書きぶりでした
『伝える』のって難しいです
切り取られ方によって
全く意図しないものになってしまうので
今後はマスコミへの発言を控えようと思います
『ごちゃまる出張ラボ』さんが
来てくださいました

新しい仮説校舎での
ふれあいのひとときです
スノーマンのキーホルダー作りなどで
楽しみました
日本の雪だるまは2段重ねですが
西洋のスノーマンは3段重ねです
なぜなのかチャッピーさんに訊いてみたら
(チャッピーさんはチャットgptのことです
岡本先生がそう呼んでいました)
Snow Manが6人から9人に増えた
理由を説明してくれました
ほんとうに『伝える』のって難しいです
高校化学の発展的な内容に
「ラウールの法則」ってありますが
女の子が目をキラキラさせて
聴いていたのを思い出しました
(芸能界に疎い私のような方のために
Snow Man はアイドルグループで
ラウールくんはそのメンバーです
合ってますか?)
各国の雪だるま事情を調べてみました
英語圏では「スノーマン=雪男」と呼ばれますが
イタリア・オランダでは「雪人形」
「雪男」と言うと
日本では雪男=UMA(未確認生物)
のイメージになってしまいます
『だるま』はもともとインドのお坊さん
さすがにインドに雪は降らないだろうから
中国ではどうかなと調べたら「雪人」
円錐形の胴体に丸い顔が載っています
韓国のは日本のに似ていますね
『冬のソナタ』にも出ていました
『ヌン(雪)サラム(人)』
というそうです
今日はクリスマスに計画している
朝市焼け跡のイルミネーション
の準備もしました
千枚田『あぜのきらめき』を彩っていた
『ペットボタル』を借りてきて
まずはクリーニングです
ステンドグラスのデザインもします
思い思いを形にして成形します
みんなの心を明るく照らしてください
輪島高校生の街づくりプロジェクト
『街プロ』の公認キャラクター
『わじねことふぐ郎』の
ポストイットが完成しました
1セット400円で販売しています
ご希望の方は輪島高校まで
ご連絡ください!
仮校舎での最初の日
地震から 709 日目
昨日仮校舎への引っ越しを終えて
今日は最初の授業の日でした
2年生を対象に
大学の模擬授業を実施しました
『学びウィーク』の一環でもあります
本校では中間考査を廃止して
その期間中
学びの心に火をつける
『学びウィーク』を行っています
今回は2学期末考査を終えた後
『学びウィーク』を実施
県内の多くの大学からお招きしました
講義の内容を
仮設校舎の案内も兼ねて
ご紹介します
国際(北陸大学)【調理室】
国際的なコミュニケーションを図るには
単に言葉の壁を乗り越えるだけでなく
互いの文化を理解し合うことが大切である
ということを
トランプを使ったゲームで実感しました
栄養(北陸学院大学)【物化実験室】
ようやく実験室が完成しました
これまでは水道が出なくて
実験できなかったのですが
さあお立ちあい!
保育・幼児教育(金城大学短期大学部)【音楽室】

ご覧ください
この広々とした音楽室
吹奏楽部も思う存分練習できますね
スポーツ(金沢学院大学)
女子ソフトボール
北京オリンピック金メダリストの
藤本索子 助教です
文学(金沢学院大学)
工学(金沢工業大学)【生地実験室】
標本たちも引っ越してきましたよ
理学療法(金城大学)
生物資源環境学(石川県立大学)
看護(石川県立看護大学)
今年の夏
トリアージの実習でお世話になった
木田 亮平 教授です
経営(かなざわ食マネジメント専門職大学)
日本で唯一フードサービスに特化した
経営学を学ぶことのできる
新しい大学です
こうして見ると
さすが学都金沢
人口あたりの大学数が
京都に次いで全国2位だということに
納得です
さて今回の『学びウィーク』
他にも様々な取り組みが
予定されていますよ
恒例の
原田幸子アナウンサーによる
「話し方教室」
今回は第3回『発展編』です
それから
南カリフォルニア大学
EUI-SUNG YI(イー・サン・イ)教授の講義
世界で注目される都市研究の第一人者です
最新の都市計画の実践をお聞きし
被災地の復興へのヒントとします
高校生に限らず一般の方もぜひお越しください
詳しくはこちら
学校へお電話の上お越しください
0768-22-2105
お引越し大作戦
地震から 708 日目
いよいよ仮設校舎ができました
これまで長かったような
短かったような
校舎の傾きが見つかったのは
地震直後のことでした
最初に気がついたのは
山崎先生でした
「二号棟が傾いている気がします」
最初は言われて初めて気づく程度
の傾きでした
そのうちだんだんと傾きが大きくなり
三号棟との間に大きな亀裂が走り
壁のヒビも大きくなって
中に入ると気分が悪くなるほどになりました
職員室がその中にありましたが
キャスター付きの椅子に座ると
コロコロ転がっていくようになりました
職員室を一号棟の会議室に移動しました
発災後4日目には
避難所として開設しましたが
二号棟は立ち入り禁止としました
体育館はというと
第一体育館は床がハーフパイプ状に窪み
第二体育館一階は床が山脈のように盛り上がり
どちらも体育では使えません
唯一使える第二体育館二階と廊下など
できるところで工夫をして
体育や部活動を行ってきました
春になると簡易検査が入りました
二号棟の傾きが3度少々
これはピサの斜塔とほぼ同じです
一号棟にも1度の傾きが確認されました
法律上公共施設は1度傾くと
半壊扱いになるので
それまで入居していらっしゃった
被災者の方々を体育館へと
移っていただきました
秋には精密検査が入り
一号棟の基礎の部分に損傷
が認められました
そこで学習していた
一・二年生の教室を
安全な三号棟に移しました
パソコン室を普通教室に作り替えたり
ひとつの教室を間仕切りで区切って
習熟度別授業のための小部屋を
作ったりしました
グラウンドの3分の1ほどを利用して
仮設校舎の建築が始まりました
工期およそ半年ほどで
二階建ての校舎が完成しました
先週の土日を利用して
金庫などの重量物のほか
大きな家具の移動を
業者の方にしていただいて
本日は生徒の使う机椅子などを
全員で搬入しました
仮設校舎への移動が終わり次第
本校舎のジャッキアップ作業に入ります
建て替えはしません
完成まで
一・二年生が仮設校舎を利用し
三年生は三号棟の一階を使います
校長室もガランとしました
何年後かに帰ってきます
その時は別の校長先生でしょうが
その日までさようなら
こちらは仮設校舎の校長室
どこにこんなに荷物があったんだと
まるでミミズの缶詰めを開けた状態
どこから片付けてよいのやら
怪我しないように慎重に慎重に
新しい事務室です
こちらは新しい職員室
フリーアドレス化しました
近未来型の机椅子は
『内田洋行』様より
ご寄贈いただいたものです
ほんとうにありがとうございました
「量子力学」百周年
地震から 707 日目
今週末は3件の講演会をさせていただきました
移動の新幹線で前の座席に座っていた方が
乗り換えた特急では隣の座席になりました
なんという偶然でしょう
この引き寄せに縁を感じ話しかけてみました
国際風水氣学協会の本鑑定士の方でした
普段から風水を科学と捉えている私は
興味津々でいろんなことを尋ねてみました
「目に見えるものだけが全てではない」
サン・テグジュペリの
『星の王子さま』にも登場するこの言葉
目には見えない酸素や二酸化炭素
そして電磁波が厳然として存在するように
風水は量子力学である
という言葉に妙に納得するのでした
アインシュタインは
「月は私たちが見ている時だけ存在するのか?」
と懐疑的だったこの量子力学
量子力学と私の出会いは
40年前に遡ります
大学時代の『理論化学』という講義の
シュレディンガー方程式の教科書は
これまでの私の常識を覆しました
難しい本を読むと3ページほどで
眠りに落ちてしまう特異体質の私を
わずか5行ほどで眠らせるものでした
1895年
ドイツのレントゲンは
空気を抜いて真空にしたガラス管に
電圧をかけて放電させる実験中に
管を厚い紙で覆っているにもかかわらず
近くに置いてあった物が光っているのを見て
「物を突き抜ける不思議な光が出ている」
と考え
この不思議な光をX線と名づけました
この発見の翌年 1896年
フランスのベクレルは
保存しておいた写真乾板が
光を受けていないのに
感光していることを見つけました
一緒に保存していた岩塩から
X線に似た何らかの光が出ていると
考えました
1903年
マリー・キュリーは
夫のピエール・キュリーが発明した装置を使って
ベクレルの岩塩から光を出しているのは
そこに含まれるウラン原子であることを発見し
その光を出す性質を「放射能」と名づけました
時は第二次産業革命
製鉄業がさかんとなったドイツでは
溶鉱炉の中の溶けた鉄の色で
温度を判断していました
赤黒いときは千数百度
真っ赤の時は二千度以上、
それ以上では白っぽくなる
といった具合です
物体の温度と放射される光の波長の関係を
プランクは公式で示しました
そしてこのことを説明するためには
『量子』という考えが必要であるとしました
光のエネルギーは連続的に変わるのではなく
飛び飛びの値を取るということです
そのことを突き詰めたのが
シュレディンガー方程式です
ここからいよいよ私が秒で寝る領域です
ともかく
トランジスタ
発光ダイオード
太陽電池
MRI
量子コンピュータ
我々の現在の豊かな生活は
量子力学の上に成り立っています
量子力学の世界では
「実験の測定値は測定した瞬間に決まる」
とされています
このことは『シュレディンガーの猫』
と例えられて説明されています
電子は『スピン』という磁力を持っています
『スピン』には上向きと下向き
ふたつの状態があります
ある電子の『スピン』がどちらなのかは
測定した瞬間に決まり
測定する直前はどちらでもない
いわばグレーな状態です
オセロのコマを弾いて回転させて
倒れた瞬間に白か黒か決まる感じです
さらに奇妙な
『量子もつれ』とう現象もあります
この状態のふたつの粒子は
どんなに遠く隠れても
瞬間的に影響を伝え合うのです
『量子もつれ』の状態にある
ふたつのオセロのコマを
『スピン』を逆向きに設定して
北極と南極に移動させます
そして回転させた後
同時に測定すると
その瞬間
必ず一方が白なら他方は黒
となるのです
一見何の関係もない
ふたつの現象であっても
目に見えない不思議な力で
影響を及ぼしあうということです
これはユングの提唱する
シンクロニシティの原理とも重なります
これは「意味のある偶然の一致」
あるいは「非因果性同時多発性」
ともいわれます
精神分析家ユングと
量子力学研究家パウリは
この非因果的な相関に注目し
精神と物質を統一する理論を構想するなど
シンクロニシティの原理を
科学的に探求しました
私たちの直感を超えた世界のあり方を
理解しようとする試みといえます
さて量子力学と風水に話を戻して
徳川家康が江戸のまちを築く時に
天海僧正らの助言を得て風水を取り入れています
東の隅田川を「青龍」
西の中山道などの道を「白虎」
南の江戸湾を「朱雀」
北の上野や神田山を「玄武」とする
四神相応の配置を基本としています
今日の大都市東京の繁栄の基礎がそこにあります
北に山があるとなぜ都市が繁栄するのか?
一見無関係に見えるこのことが
量子力学的に何か因果関係があるのかもしれません
実は焼けた朝市
風水的には
北に海
南に山
西に川
東に道と
四神相応の真逆なんですよね
だからこそ復興させる際には
その気を整える建物配置を
考えてみたらどうかなと思う次第です
愛媛の朝
地震から 706 日目
気持ちのいい朝を迎えています
今日は高松で
講演会を行いました
高松へ向かう前のひととき
丹原高校の合田校長先生に
地域巡見をしていただきました
地歴が専門である先生からは
地理と日本史の視点から
さまざまなことを
教えていただきました
まずは四国三十六不動霊場である
西山興隆寺
紅葉の美しい古刹です
『千と千尋の神隠し』に出てくるような
『みゆるぎ橋』を渡ると
国指定文化財の『三重塔』などがあります
愛媛県は東予・中予・南予に区分されますが
丹原高校のある東予地区には
独特の地形が見られます
まずは日本で有数の扇状地が連なります
扇状地では水が伏流水となって流れますので
川がなく
稲作には向きません
そこで果樹園として活用しています
下流に行くと伏流水は地表に現れ
川となって流れますが
多量に運んできた土砂を堆積させ
だんだん川底と堤防が高くなり
周囲より高いところを流れる
天井川となります
こちらは鉄道が
川の下のトンネルを潜るという
珍しい光景です
以前に「ゆず」のおふたりが
輪島高校に歌いに来てくださった時の模様が
NHKで放送されます
【番組名】東北ココから ゆずとつくる 未来へつなぐうた
【放送日時】12/12(金) 19:30~19:57 <東北地方のみ>
※NHK ONEで見逃し配信
【内容】来年東日本大震災から15年を迎えるにあたり、
ゆずのおふたりが
震災の経験を未来へつなぐ歌を制作するべく
東北の被災地を訪れ
地域の人たちと語り合う
旅のドキュメント
ぜひご覧ください
初冬の伊予路へ
地震から 705 日目
今年の夏休みに
韓国に視察旅行に行きました
バスの中で偶然隣合わせになったのは
愛媛県立丹原高等学校の
合田 明典 校長先生でした
防災教育に力を入れるなど
たいへんパワフルな校長先生でした
合田先生のお招きを受けて
本日同校で講演会を行います
今日は『防災デー』ということで
その一環ということになります
秋の京都駅で乗り換えです
紅葉がちょうど見ごろを迎えているようです
駅員さんお手製の案内板
『街プロ』でも
やってみるといいですね
京都では
中国人観光客が減って
日本人観光客が増えているとか
ホテル代なんかもグッと下がってお得に
予約を取り直す方も
いらっしゃるようです
丹原高校の『防災デー』
最先端の避難訓練を見せていただきました
予告なしの避難訓練です
掃除中に発災の設定です
生徒たちはすかさず
「落ちてこない倒れてこない」
場所を見つけて避難姿勢です
揺れが収まると
生徒たちは駆け足でグラウンドへ
途中通行不可能箇所を設定
みんな自分で避難路を見つけて
避難します
緊張感を持って取り組んでいます
生徒がふたり負傷した設定です
先生方が捜索に向かいます
ひとりは骨折で動けなかったようです
安全な場所までおんぶで運びました
もうひとりは心肺停止です
タンカで運んできました
ここは問題提起です
「訓練のための訓練」
になっていませんか?
心肺停止は一刻を争います
わざわざみんなのいるとこまで
連れてこないで
安全な場所で胸骨圧迫をすべきでは?
小学生も一緒に参加です
防災訓練は単独でなく
地域で行うべきものですね
勉強になりました
降下訓練も行いました
4階の高さから緩衝機を用いて
降下して避難する練習です
私も体験してみました
輪島高校でもぜひ取り入れましょう
煙避難訓練です
スモークマシンで煙を充満させた部屋を
潜って避難します
ハンカチの大切さを実感しました
SONPO さんのご協力による
『学防ッチャ(まなぼっちゃ)』
防災の知識を楽しみながら学べる
ボッチャです

防災リュックを作るワークショップ
防災バッグに必要なものを組み合わせる
パズルゲームです
私も講演会をさせていただきました
「南海トラフは必ずやってくる」
そう言われ続けて
暗い未来を刷り込まれるだけでは
高校生がかわいそうです
正しい防災知識を身につけて
地震の最初の15分間に命さえ守れば
つらいことの後には
人は大きく成長できるよ
予想もしなかった輝かしい未来が待ってるよ
そのことを
輪島高校生が頑張っている姿を紹介することで
伝えてきました
とっても素直で明るい生徒さんたちで
みんな真剣に話を聴いてくれました
藤原 禄都 さんと 桑村 桜羽 さんは
『江戸走り』を
渡部 もも花 さんと 佐々木 真央 さんは
『能登半島ポーズ』を考案して
それぞれ披露してくださいました
この中のどこかに
「能登半島ポーズ』の
ふたりがいます
金沢大学特別講義
地震から 704 日
金沢大学特別講義
「石川県の学校安全」で
お話をさせていただきました
金沢大学では
学校安全の中核を担う教員を育成するため
地理的環境・過疎化・被災など
石川県の地域特性を踏まえた
学校安全の取り組みについて
理解を深めるために
本講義を開講しています
今日明日と集中講義期間となっていて
通常講義はお休みです
キャンパスはガランとしていましたが
そんな中この講義を選択した学生さんは
熱心に講義を聴きに来てくださいました
さすが休みの日に進んで受講されるだけあって
みなさん本当に熱心に耳を傾けて
こちらからの問いかけについては
積極的に答えてくださいました
意識高く頼もしい限りでした
午前中は
発災後珠洲市の中学校で
陣頭指揮をとってこられた
現奥能登教育事務所長の
山岸 昭彦 先生の講義があり
拝聴させていただきました
珠洲市は今回の地震以前から
群発地震に見舞われていたので
防災教育そして地震への備えを
計画的に実践されていました
我々の認識の甘さを痛感しました
講義を受けられた方の中に
大切なご家族を亡くした方も
いらっしゃいました
言葉を一つひとつ選んで話したつもりです
教員採用試験に合格された方も
いらっしゃいました
被災地に赴任となる可能性もありますよ
とお伝えしました
被災地での教師としての実務経験は
今後の長い教員人生にとって
かけがえのないものを学ぶ機会になりますよとも
お伝えしました
実際震災わずか3ヶ月後
傷だらけで
住むところもない本校に
大学出たてのふたりの先生が赴任しました
そのうちひとりは
こんなとこ住めないと
金沢から毎日通い続けました
そんな厳しい環境の中
ふたりは真剣に生徒に向き合いました
どんなにつらい環境に置かれようと
それでも前を向いて歩き出そうとしている
生徒たちに
自分にももっとできることがある!
ふたりはそう思うようになってきました
今年はふたりとも学級担任をしています
明日は丸一日
「子どものための心理的応急処置」と題して
セーブ・ザ・チルドレンさんによる
実習が行われるそうです
がんばってください
高校生ガイドツアー
地震から 703 日目
石川県では
全国から修学旅行に訪れる学校向けに
高校生ガイドの取り組みをしています
本校もそのガイド校のひとつです
被災地ではありますが
今しかここしか体験できないコースもあります
今日はそのリハーサルということで
輪島市内の全中学校の生徒に来てもらい
お客さん役をしてもらう予定でした
ところが北陸特有の冬の気候となり
となると『鰤起こし』つまり
冬の雷もありうるなということで
急きょ予定を変更して
屋内で実施することとしました
せっかく来てもらうのだから
すこしでも楽しんでもらえるように
先生方は知恵を絞ります
建ったばかりの仮設の校舎に
高校生よりも一足早く入ってもらい
被災地ライフを楽しんでもらうことにしました
ところがここで問題発生
Wi-Fiがつながりません
生徒と先生は知恵を絞ります
急きょアナログの資料を準備して
紙芝居形式で何とかつなぐことにしました

ここでさらに問題発生
街を案内しながら話す原稿だったので
座ったままだと10分で終わってしまいました
先生方は知恵を絞ります
出たがり校長にに喋らせとけ
良いアイディアです
急遽音楽室に全員を集めることにしました
先生方がドタバタ準備をしている間
生徒たちが勝手に喋り始め
場を盛り上げてつないでくれていました
なんて気の利く生徒たちでしょう
想定外の出来事が次々と起こる中
生徒たちも先生方も
自分たちで最善を考え
自分たちで行動する
そんな姿が着実に身に付いています
震災がくれたプレゼントです
と言っては不謹慎でしょうか
さて、東陽中学校と門前中学校のみなさんは
道路事情が悪く
震災後輪島市街に入ることも
滅多になかったということで
バスで輪島塗会館とキリコ会館を案内しました
先生がそっちについて行ったので
残された生徒たちは
「おい!片付けやっちゃおうぜ」
自主的に使った部屋の片付けと
掃除をしてくれました
入学した頃は
やんちゃでどうなることやらと
心配した子たちではあったのですが
本当に成長しました
頼もしい限りです
県の産業について考える
地震から702 日目
「石川県産業教育振興会」
に参加しました
産業界 教育界 行政関係者が一堂に介して
県の産業教育の振興充実についての
諸課題の解決を図ることが目的です
ホクショー株式会社代表取締役社長
北村 宜大 氏による講演を
拝聴させていただきました
ホクショーさんでは
コロナ禍の際には
テレワーク手当の支給
ガソリン価格高騰の際には
通勤手当の2割増など
会社の業績アップと
従業員のWell-biing を
同時に実現されています
昭和の時代は
「電話がならない会社は危ない」
「社員が休みがちな会社は危ない」
などと言われたものですが
現在では必ずしも当てはまりません
社員のWell-being を実現しながら
業績を上げるには
① 営業の行動量を上げる
② 営業の「勝ち率」を上げる
③ 受注単価を上げる
だそうです
3つに共通することは
他者との差別化を図ることです
やってはいけないことは
価格競争に陥ること
学校現場にも応用できそうです
意見交換会がありました
企業側からの質問に対し
突然指名されたある校長先生は
「すみません もう一回言ってください」
聞き逃したようです
私が指名されても
きっと同じようになったと思います
ドキドキしました
「高校ではどのような指導されていますか?」
という質問だったのですが
その先生は
「人の話をちゃんと聞けと指導しています」
センスある回答ぶりに心で拍手を送りました
意見交換会でわかったこと
企業側が懸念していることは
現在学校教育で比重が大きくなっている探究活動
それにより基礎学力の指導が疎かになっていないか
ということのようです
どうも探究活動と基礎学力を
2項対立で捉えているという認識を変えるための
学校側の努力が必要なようです
専門用語では
企業側の捉えている基礎学力を「認知能力」
探究活動で身に付く能力を「非認知能力」といいます
ここでいう『認知』とは
『認知症』の『認知』とは意味合いが違います
『認知能力』とは
共通の尺度で点数化して評価できる能力のこと
『見える学力』ともいいます
例えば『漢字能力』のような
『非認知能力』は
それができない能力
『見えない学力』ともいいます
例えば『積極性』のような
「非認知能力が高ければそれでいいのか!」
「積極性があれば漢字書けなくていいのか!」
そんな極端な論法はやめてください
『非認知能力』or 『認知能力』
ではなく
『非認知能力』for『認知能力』
です
『非認知能力』を高めれば
『認知能力』が高まるのです
ヒトがコトに臨むうえで
必要な力を身につけるのに必要な力
それが『非認知能力』です
もっと簡単に言えば
『認知能力』とは国数英理社の力
『非認知能力』とはざっと上げると
自主性・向上心・協調性・共感性
創造性・コミュニケーション能力
などなど
おわかりになると思いますが
『非認知能力』とは全く新しい概念ではなく
これまでも日本の学校教育で重視されていたこと
すなわち「心の教育」なのです
「心の教育」の育成には
例えば部活動が大きな役割を果たしています
部活動においては
競技力を高めるために
従来は競技に特化した訓練を
スパルタ式で行っていました
しかしながら今はそんなやり方は時代遅れ
フィジカルトレーニングや
メンタルトレーニング
主体性の育成やチームビルディングなどを
科学的に体現できるチームが強いです
それを
学習にも応用しましょうというのが
探究学習の目指すところなのです
「単語練習」や「計算練習」を
意味もわからず機械的にこなしても
それで身に付く力は一時的なもので
将来的に生きていく力とは
程遠いものです
「学びに向かう力」を
高める必要があるのです
はじけろ創造彩れ未来 いざ百万石の地へ
地震から701日目
令和9年夏
高校生による芸術文化の祭典
「全国高等学校総合文化祭」が
石川県で開催されます
石川県での開催は47年ぶり2回目
ちょうど全国を一回りしてきました
今日のタイトルはそのスローガンです
演劇 合唱 吹奏楽 マーチングバンド
バトントワリング 美術 書道 放送など
22の部門の展示や発表が
石川県を舞台に繰りひろげられます
とはいえ
能登の文化的施設は壊滅的被害を受けていますので
羽咋以南での開催になるのですが
現在それに向かって
各校で分担して準備を進めています
輪島高校は『郷土芸能』を担当します
全国各地に伝わる
祭囃子や神楽 民謡 踊りなどの『伝承芸能』と
伝承曲や創作曲を含む『和太鼓』の
ふたつの部門によるコンクールです
今日は運営のご協力をお願いしに
白山市にある浅野太鼓楽器店様を
訪問しました
浅野太鼓様は
江戸時代初期の創業以来
400年以上にわたり
和太鼓づくりの技を継承なさっていて
全国の太鼓の制作を引き受けていらっしゃいます
原木の選定からクリ抜き 塗り 皮はりまで
全て自社で行われ
職人さんによる
一つひとつ丁寧な手作業での生産を
続けていらっしゃいます
こちらは6尺もある大太鼓
直径2m 以上もあるアフリカの大木を
くり抜いて作られたものです
現在ワシントン条約により
日本では入手不可能な木です
ワシントン条約には
学術目的を除き国際間の取引が一切禁止される
『附属書I』と
締約国が『留保』できる
『附属書II』があります
『附属書Ⅱ』に属するこの大木に対して
中国は『留保』の姿勢をとっているので
中国に流れて家具に変えられているそうです
日本も過去に
「ヨシキリザメ」の規制に対して
『留保』の姿勢をとりました
フカヒレとして食されるほか
コンドロイチンも豊富に含まれているからです
皮は肉牛のもの
現在
牛は若いうちに食肉に変えられるので
ここまでの大きな皮は
手に入らないのだそうです
部位で言うと
腰のあたりの皮が
最も厚くて丈夫です
それはライオンなどに襲われるときは
いつも背後からなので
その辺りの皮が厚く丈夫に進化したからです
写真後方に写っているのは
『鉦鼓』でしょうか?
神楽に使われるものかなと
詳しくはないので
よくわかりませんが
とにかく
いろんな太鼓があって興味は尽きません
ちなみに現在日本で一番大きな太鼓は
飛騨高山の『祭りの森』にある
9尺のもので
重さにして4.5t
実はこちらも『浅野太鼓』さんが
こしらえたものです
「みちのくひとり旅」その参
地震から 700 日目
震災遺構 荒浜小学校へ行ってきました
荒浜は仙台の東
太平洋に面した地区です
当時10m ほどの津波に襲われました
こちらが
生徒教員含め320名の住民が避難した
荒浜小学校
写真左側2階のベランダに
「ここまで津波が来ました」の表示が
非常階段を見ると確かに2階と4階で
明らかに被害が違います
3 月11日 14:46
1~3年生は下校途中で
4年生以上が校舎で授業中でした
地震がおさまってから
全員を4階に避難させましたが
津波の襲来に伴い
避難してきた住民とともに屋上へ
3 月11日 17:30
救助のヘリが来ました
ちっちゃい子どもとお母さん
小学生 中学生 高校生 大人の顧番で
救助してもらうことにしました
真っ暗な中で屋上から
一人ひとり吊り上げられました
高学年の児童が
低学年の児童の面倒を
しっかり見たそうです
3 月12日 5:00
中学生高校生の救助が始まりました
その後ヘリが来なくなり
籠城の準備を始めたそうです
お昼頃消防団が歩いて来たので
誘導に従い
ひざや腰まで水につかりながら
50名ほどが歩いて避難しました
ヘリではペットが避難できなかったため
ペットと一緒の人は徒歩での避難を選びました
3月12日 午後
水が引いたため
ヘリが地上に着陸できるようになり
残っていた人全員の非難が
ようやく終わりました
荒波地区には
津波から住民や街を守るための
様々な工夫がされています
全長9km におよぶ堤防を
国・県・市が分担して整備しました
想定を上回る規模の津波が来ても
堤防が破壊・倒壊するまでの時間を稼ぎ
全域に至る可能性を少しでも減らす
構造上の工夫が施されています
潮害・風害・飛砂を防ぐ海岸防災林は
津波到達時間を通らせる効果も期待できます
2014(平成26)年から植林を開始しました
震災前の海岸防災林に戻るのに
数十年かかると言われています
沿岸部を南北に走る県道102kmにおいて
約6mの嵩上げ道路にしています
震災で発生したコンクリートくずや
津波で運ばれてきた土砂を活用しました
道路に堤防の機能を持たせます
このようにさまざまな設備を
組み合わせて防御することで
津波による被害の大幅な軽減を図っています
校舎の方は
防災教育の拠点として活用されていました
音楽室がシアタールームに
映像アーカイブが流されています
児童たちの作品も展示されています
こちらは輪島高校でもしましたね
思い出の場所旗立てワークです
あの時のまま止まった時計
校庭には
二宮金次郎さんの像が倒れたまんまでした
江戸時代に農民の子として生まれた金次郎は
朝暗いうちから夜遅くまで
汗と泥にまみれて一生懸命に働きながら
わずかな時間も無駄にせず勉強をしました
荒れ地を耕して米を作り
余った米をお金に変え
お金が貯まると土地を買いました
そして一生を世の中のために捧げ
大飢饉で困っているたくさんの人々を
救ったのです
その姿を見習いましょうと
マキを背負いながら勉強している像が
日本中の小学校に建てられました
その頃日本は
尺貫法からメートル法に
切り替える時期だったので
子供たちがメートルをイメージしやすいように
像の高さを1m に統一したそうです
『尺』は長さの単位
『貫』は重さの単位です
1尺は親指と人差し指を開いて
2歩測った長さで
だいたい30cmです
それを10等分したのが1寸なので
一寸法師の身長は3cm
キティちゃんの身長が
リンゴ5個分なので
それより小さいです
このように昔の単位は
人のサイズが基準になっていることが多いです
大人が両手を伸ばした長さより
少し長いのが1間
ヒトが両手を伸ばした長さとpy
その人の身長はほぼ同じなので
1間はヒトがひとり余裕を持って
横になれる長さということになります
海外でもことは同じで
1フィートはつま先からかかとまでです
約 30cm なのでやはりヨーロッパ人は
でかいですね
3フィートで1ヤード
これは腰回りが由来であるという説があります
ところで北極から赤道までの距離を測ると
ピタリ1000万m になります
これは偶然ではなくて
もともと
子午線の距離の1000万分の1を
1m とすると決めたからなんですね
水がちょうど0℃で凍って
ちょうど100℃ で沸騰するのと同じです
この定義は
パリの科学アカデミーが1799年に
パリを通る子午線の一象限の 1000万分の1の長さ
を1m と定めたもので
最初の『国際メートル原器』
つまり1m の基準となる「ものさし」
もその時作られました
その後作製された白金-イリジウム合金製のものが
1889年の第1回国際度量衡総会で
世界的に承認され
その時作られたものが
メートル条約全加盟国に配布されて各国原器とされました
日本のものは No.22
「産業技術総合研究所計量標準総合センター」
に保管されているそうです
その後
「メートルはクリプトン 86原子の
準位 2p10 と 5d5 との間の遷移に対応する
光の真空中における波長の
165万 763.73倍に等しい長さである」
と定義が変わり
現在では
「光が真空中で
299,792,458分の1秒間に進んだ距離」
となっています
東京ドーム何個分の方がわかりやすいですね
世界中にはまだまだ面白い単位があって
古代ローマでは
牛1頭が1日に耕すことのできる面積を
1モルゲンと言います
ドイツ語勉強している方はお分かりですね
英語の Good morning に相当する
グーテン・モルゲン
朝(Morgen)の語源となっています
ちなみにドイツ語では
文頭でなくても名詞の頭は
大文字で表記します
膨大な単位に『グーゴル』があります
1グーゴルは10の100乗です
日本語で表すことができる最大の数は
9999無量大数9999不可思議9999那由多
9999阿僧祇9999恒河沙9999極
9999載9999正9999澗9999溝
9999穣9999秭9999垓9999京
9999兆9999億9999万9999
10の70乗程度なので
一体何に使う数字か?
という気がします
ちなみにGoogleは
グーゴルの綴り間違いに由来する
と言われています
話があちこちに飛びましたが
最近では
金次郎さんが歩きながら勉強する姿は
歩きスマホを助長するとか言って
座って勉強する像に作り変えられているそうです
「みちのくひとり旅 」その弐
地震から 699 日目
東日本大震災を生き延びた方が
どんな思いで復興への道を歩んできたのか
その生の声を聞きたくて
ホテルではなく民宿に泊まりました
気仙沼の民宿『天心』さんは
昔船乗りをリタイアしたご主人が
震災前に始めた喫茶店がそのルーツ
復旧工事関係者の宿泊施設がないということで
民宿に変えたそうです
サンマの刺身やマンボウの腸にツブ貝
気仙沼の新鮮な海の幸をいただきました
当時のご苦労などをお聞きし
元気をいただきました
「おかえりモネ」の舞台気仙沼
付近の町とはBRTでつながれています
BRTつまり
Bus Rapid Transit(バス高速輸送システム)
バスを基盤とした次世代公共交通システムです
渋滞に関係なく
鉄道と同じくらい時間に正確な運行ができます
様々な工夫がされています
渋滞の影響を回避するため
廃線となった鉄道軌道跡等を利用した
専用レーンを走る区間があります

一般車両は走ることができないので
1車線のみ
単線鉄道のように駅ですれ違います
交差点ではバスの通行に合わせて
遮断機が動作します
トンネルなんかも1車線
高速道路を利用する区間もあり
一般道を走る際は
バスの接近に応じて
優先的に信号が青になります
鉄道に比べて整備費用が安く
導入までの期間も短いという利点があり
東日本大震災で被災した
気仙沼線や大船渡線の
復旧までの代替手段として
採用されています
陸前高田の『奇跡の一本松』
見てきました
震災前この場所には
約7万本の松林が広がっていましたが
大津波により
ほぼ全ての松がなぎ倒されました。
その中で
唯一津波に耐えて残った一本の松が
『奇跡の一本松」と呼ばれ
希望の象徴となりました
現状は残念ながら
地盤沈下による海水の影響(塩害)で
翌年枯死が確認されました
しかし復興の象徴として後世に残すため
幹に防腐処理を施すなど保存整備が行われ
モニュメントとして元の場所に立っています
実は輪島朝市の焼け跡にも
『奇跡のタイサンボク』
がありまして
震災直後から
炊き出しで地域の食を支えてきた
ミシュラン一つ星のフランス料理店
「ラトリエ・ドゥ・ノト」のシェフ池端隼也さんが
震災後の春に
この木に芽が出てきたのを見て
新たに居酒屋を開店する際に
1 本だけ残ったこの木が芽吹いたように
輪島市の復興の芽となることを期待して
店名を『mebuki』としました
手前の建物は『陸前高田ユースホステル』
この建物が根元にあったおかげで
一本松は残ったのだと考えられます
こちらは水没した松の根株群
元々この松林は
江戸時代にたったひとりの翁が
防災のためにと私財を投げ打って
植林されたものだったそうです
翁の志を引き継ぐべく
新しい松林が植林されていました
これも震災遺構です
なんだと思いますか
復旧工事のための大量の土砂を運搬する
ベルトコンベアーの橋の橋脚です
この橋のおかげで
トラックの運搬だけだと9年かかる
と試算されていた工期が
わずか1年半に短縮されたのだそうです
工事が終了しても
住民が「残して欲しい」と
感謝を込めて残すことにしたのだそうです
震災遺構『気仙沼中学校』です
誰かが亡くなられた場所が
『震災遺構』になることは基本ありません
この中学校も死者ゼロでした
当時の写真がこれです
震災の1年前に赴任された校長先生が
実際に避難場所まで歩いてみて
これでは危険だと
避難場所を設定し直して
避難訓練を徹底したことが
生徒全員の命を守ったのです
『東日本大震災津波伝承館』を訪れました
鉄橋の切れ端です
1cm以上もある分厚い鉄板が
引きちぎられています
被災した消防車です
主査の須貝 翔 先生に
案内していただきました
高校の先生をされているのですが
教育委員会からの出向という形で
震災の伝承をされているそうです
とても良い制度です!
須貝先生から
素敵な詩を紹介していただきました
「人はみんな過去を持ち
現在があって未来がある
その時々に出会いがあり
別れがある
風の電話はそれ等の人と話す電話です
あなたは誰と話しますか
それは言葉ですか
文字ですか
それとも表情ですか
風の電話は心で話します
静かに目を閉じ
耳を溢ましてください
風の音が又は浪の音が
或いは小鳥のさえずりが聞こえたなら
あなたの想いを伝えて下さい
想いはきっとその人に届くでしょう」
伝承館のある祈念公園は
高い防波堤に守られています
防波堤に登ると献花台がありました
未来に向けて大切なことを伝えていく
その思いを新たにしました
「気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館 」です
予約を入れてガイドツアーしていただきました
ガイドは元中学校の菅原校長先生でした
ここは元々水産高校だった場所です
津波の跡そのままの部屋
3階の教室には流された車が
校舎の間には何台もの車が
当時は濁流が渦巻き
洗濯機のようだったそうです
流されてきた冷凍倉庫がぶつかった跡
つまり屋上近くまで水位が上がったのです
その日は入学試験があった翌日
生徒は全員避難したのですが
一部の先生は入試の答案を
3階4階へ運ぶために残ったそうです
その結果無事合格発表まで
こぎつけたのだそうです
それを指示された校長先生には
敬意を表します
私だったらできないと思います
命よりも大切な紙切れなんかあるか
と思うからです
どちらが正解かはわかりません
逃げ遅れた先生方は屋上に避難しました
屋上への出入り口は通常施錠されています
何という判断力でしょう!
校務員さんがこんなこともあろうかと
逃げる前に鍵を開けておいたそうです!
下は避難した屋上の写真です
津波は屋上に迫る勢いでした
「女は電柱の上に登れ!
男は手すりにしがみついて耐えろ!」
と指示されたそうです
でも女性の先生方が
電柱に登れるはずもありません
そこにもうひとつの奇跡が
一緒に屋上に避難してきた方の中に
学校の工事に来ていた方がいて
ハシゴを持って避難して来ていたのです!
先ほどの写真の左手奥の建物の上に
全員避難できたのです
引き波で水が引いたのを見計らって
全員4階のじゅうたんばりの部屋へ移動しました
教室からカーテンを引きちぎってきて
寒さをしのぎました
見ると津波で流されてきた家が
校舎に引っかかっていました
一階部分はありません
声をかけると
中に女性がふたり
真っ暗闇の中
先生方は
「明るくなったら助けに行くからね!」
「頑張って耐えて!」
夜が明けるまで交代で声をかけ続けたそうです
翌朝先述のハシゴを使って無事助け出しました
いろんなことを学ばせていただいている旅です
気仙沼でちょっといい感じの
写真が撮れました
「みちのく一人旅」その壱
地震から 698 日目
始発列車で仙台に向かいます
海に浮かぶ小さなガラス箱
日立市出身の建築家である
妹島和世氏の設計による日立駅は
美しい駅ランキングで
東京駅 京都駅 金沢駅などと並び
必ず上位にランクインします
太平洋を一望できるロケーション
「展望スペース」からは
美しい朝日を見ることができ
絶景スポットとして人気を集めていますが
何せ出発が夜明け前でしたので

こんな感じです
今度来る楽しみができました
東北大学で開催されている
「世界津波の日」
"World Tsunami Awareness Day"
高校生サミットに参加しました
国連防災事務総長特別代表兼国連防災事務所長の
カマル・キショア氏より
ビデオメッセージが送られました
前方の座席にはヒジャブを被った
イスラム女子高生が座っています
彼女らに限らず
民族衣装を纏った高校生が
それぞれの国を見舞う災害と
その対策について発表し合いました
国際色豊かな会議です
来年はぜひ着物で参加しようと思います
さて週末を利用して
東日本大震災の震災遺構や
復興の様子を見て回るつもりです
まずはNHK仙台放送局を訪ねました
当時を伝える貴重なアーカイブを
見せていただきました
どんな大地震でも放送を続けることのできる
最新鋭のスタジオにも
入らせていただきました

見よこのミーハーぶり
次に平泉へ行ってみました
内陸にある平泉自体は
被害はさほど大きくなかったようですが
世界遺産に登録された毛越寺(もうつうじ)
仏の世界を表現した「浄土庭園」の池にある
趣深い傾いた岩「立石(たていし)」が
余震のたびに傾きが増したので
布を巻き付けたうえ添え木をして
倒れないように守ったのだそう
中尊寺は一部の建物の壁が壊れるなどの
被害を受けました
表門は柱が傾くなど被害が大きく
本格的な修理のための
クラウドファンディングをしています
発災時は
避難所として被災者の受け入れも
おこなっていたそうです
世界遺産であっても
非常時はそうなるのですね
次に一関に行ってみました
『祭畤橋(まつるべばし)』の
崩落事故がありました
橋脚の地盤そのものが
11mにわたり
地すべりを起こしたことが原因でした
崩壊した橋はそのまま
「災害遺構」として保存されていて
整備された周辺の公園から
見学する事ができます
一関市街地には磐井川が流れます
太平洋から86kmあるので
さすがにここまで
津波は遡上しなかったようです
川のほとりには
N.S.P メモリアルがありました
ここから見える夕暮れの風景が
名曲「夕暮れ時はさびしそう」
の舞台だそうです!
N.S.P は一関工業高等専門学校の同級生の
フォーク・グループです
ギターを形どったベンチに
上品な女性が腰掛けていらっしゃったので
声をかけてみました
昨日は中村貴之さんの命日だったそうです
同じく既に亡くなった天野滋さんの
実家も教えていただきました
平賀和人さんはご健在で
今も草野球に夢中なんだそうです
私が初めてギターを弾けるようになったのは
N.S.P の「八十八夜」でした
仙台と茨城県でそれぞれ
地震から 697 日目
東北大学で
世界津波の日高校生サミットが
開催されています
以下現場の岡本先生より
「本校からは2名の生徒が参加しています
英語でのプレゼン発表は
緊張のためか少したどたどしかったですが
適度に笑いを取り
聴衆の方々には
輪島のことにも
興味を持っていただくことができました
生徒2人はとても頼もしく
学校に戻ってからも
今回の経験を他の生徒たちに広めてくれそうです
それぞれ「もっと英語話せるようになりたい!」
と思ったようで
これをきっかけに
たくさん練習してもらおうと思います」
さて私はといえば
茨城県県北高等学校からのお招きを受け
お話をさせていただきます
移動の新幹線
新幹線のトイレには
男性用小便器の他に
女性専用と男女兼用があります
見ると女性の長蛇の列が…
男女兼用が空いてるのに…
ひとりの女性が男女兼用に入るや否や
嫌な顔をして出てきて譲ってくださいました
入ってみると
「これか…」
立ってするもんだから
あっちこっちに溢れています
こっち使う時は座ってしましょ
自分が汚したと思われたら嫌なので
掃除して出ました
風味豊かな「笠間の栗」を贅沢に使用した
極細モンブランが人気です
注文を受けてから目の前でクリームを絞るので
栗本来の香りと食感を楽しめます
そのため「賞味期限5分」だそうです
道の駅かさまの笠間モンブラン
がおすすめというテレビ番組を見たので
お昼はそれにしようと思いましたが
時間が無くて断念で残念です
講演開始まで時間があり
野口雨情記念館を訪れました
『赤い靴』や『シャボン玉』
で知られます
『シャボン玉』は
裏付ける資料こそ残ってはいませんが
生後数ヶ月で亡くした我が子へ
歌ったものだそうです
そう思って聞くと2番の詩
悲しく心に響きます
「シャボン玉消えた
飛ばずに消えた
生まれてすぐに
飛ばずに消えた」
入口の雨情像の前に立つと
曲とともに
シャボン玉がいっぱい飛ぶ仕掛けが
さて昨日紹介した「学び舎ゆめの森」のように
個別最適な学びを重視した設計の校舎が
全国的に増えてきています
SSRが多くの小中学校で取り入れられています
SSR「スペシャルサポートルーム」は
教室に入ることが難しい児童生徒のための
「心の居場所」であり「学びの居場所」です
石川県の小中学校では半数以上の学校に
設置されています
ひとりで学習に集中できるブースや
寝転んだりトランプで遊んだりする
畳のスペースがあったりします
今思い出すと
自分の娘たちにとって
じいちゃんばあちゃんの家が
この役割を果たしていました
ところが子供が来なくなるSSRが
最近増えているそうです
ある中学校では
校長が巡回してきて
「教室で勉強しなさい」
と繰り返し言いました
不安を拭えず
ぬいぐるみを抱きしめていた女生徒には
「中学生にもなって」と…
結局その子たちは教室に戻るどころか
とうとう学校に来れなくなりました
「せっかくほっとできる場所だったのに」
支援員は肩を落としました
誰も来なくなったSSRは
ついに閉鎖されたそうです
学校の方では期末考査が行われています
インフルエンザの流行により
先週末は学年の半分ほどの欠席で
学年閉鎖及び考査の延期も
視野に入れていましたが
みなさんの蔓延防止の意識高く
予防に努めていただいた結果
欠席者は最小に収まっているようです
欠席しているみなさんは
考査を欠席したことだけを理由に
成績が不利になることはありません
その点は心配しないで
元気になることに専念してください
さて以前にもこのブログに書いた
「最後のひとつが思い出せない」問題
今日直面しているのは
「接待の5せる」です
思い出せたのは
『食わせる』
『呑ませる』
『◯◯せる』
『威張らせる』
3つめは社会通念上問題があるので
伏せ字です
冒頭にも書きましたが
茨城県県北高等学校校長会のみなさまから
本日お招きいただき
お話をさせていただきました
みなさん東日本大震災当時は
学校の中核として
生徒の安全確保
そして教育の再開に向けて
ご活躍されていた方ですので
当時のことを思い出されながら
真剣に聴いてくださいました
自己主張が限りなく下手な能登の人間は
黙って耐えていますが
とある県の知事からは
「今回の復旧が前例になってしまうと
他の地区に起こった際に
同じような扱いをするぞと
宣言されたようなものである」
と危惧なさっています
阪神淡路大震災の際には
倒壊した家屋の処理費用も自費負担でした
我々が今回当然のように受けた
「公費解体」の制度は
その時の方々が
声を上げてくださったおかげなのです
であるならば
今私に課せられた使命は
今回の地震で思い知らされた負の側面も含め
多くの方に伝えていくことであると
思っています
つい最近誰かに聞いた話ですが
「能登」って
「能く登る」って書くんですよね
今回何千年に一度という地殻変動で
4mの土地の隆起が見られましたが
地質調査の結果
能登半島は
土地の隆起の連続で形成されたものである
ということがわかっています
地名の由来を調べると
その土地の災害リスクを予測することができます
大阪の「梅田」は元々「埋め田」
田んぼを埋め立てた土地なので
地盤が弱く液状化が危惧されています
講演会の後
懇親会もご一緒させていただきました
思う存分
『食わせて』
『呑ませて』
『威張らせて』
いただきました
学び舎 ゆめの森
地震から 696 日目
しばらく連載をお休みしていた間
何をしていたかというと
まずは東北へ復興を学びに行ってきました
今日ご紹介するのは「学び舎 ゆめの森」
福島県双葉郡大熊町にあります
ここは東日本大震災震度 6 強を観測
死亡者 53 名を出す被害を受けました
さらには福島第一原発の事故により
立ち入り禁止区域に指定されました
そのうち特定復興再生拠点区域は
2022年に避難指示が解除され
通行証なしで自由に出入りできますが
宿泊はできません
一方で帰還困難区域は
依然として立ち入りが禁止されており
国の許可なしに立ち入ることはできません
そんな中で
子どもたちの学びの場を確保するための
並々ならぬ努力がありました
そして今では
認定こども園での「あそび」と
義務教育学校での「探究」をつないだ
遊びの中から多くを学び
子どもと大人が一緒になって
みんなで未来を紡ぎ出す
そんな魅力的な学校になって
全国から子どもたちが
集まってくるようになりました
玄関をくぐると目に飛び込んでくるのがこれ!
図書館です
石川県の方
どこか見覚えありませんか?
石川県立図書館「ビブリオバウム」を
参考にしたそうです
毎朝ここで全校生徒が集まって朝礼します
チャイムは鳴らないそうです
自分たちでタイムマネジメントします
実は輪島高校も昨年からチャイムを止めまして
生徒も教員も時間に厳密になり
チャイムが鳴っても廊下でザワザワという
以前のようなみっともない姿は
見られなくなりました
教室の形はいろいろです
四角い教室はありません
そしてふたつとして同じ教室もありません
こんな隠れ家のような教室や
こんな寺子屋のようなお座敷教室も
こちらは音楽室
一段高く設計されています
普段は壁で仕切られていますが
このように壁を取っ払うと
演奏会ができるステージになります
楽器庫はガラス張り
楽器がオブジェになっています
のんびり読書のできるスペース
こちらは職員室の入り口
対面型のテーブルが設置されており
子どもたちが質問できる
スペースになっています
校庭に出ると
大阪・関西万博の大屋根を思わせる
吹き抜けと回廊
校庭でお米を作っています
自分たちで育てたお米で
調理実習しています
こんな素敵な学校ですが
校舎が完成したのはごく最近
それまではずっと間借りしていました
先生方は
被災したこの地で
子どもたちにどんな力をつけるのか?
そんな姿になって欲しいのか?
そのためにどんな学校が必要か?
そのことを徹底的に議論し続けたそうです
「最初に箱物ありきでは
うまくいかなかった」
校長先生はそうおっしゃっていました
その時の議論のホワイトボードをそのまま
一室に残してありました
魔法のように突然素晴らしい学校が
できあがるわけでは決してありません
そこに至るまでは
学校と保護者そして行政が一緒になって
子供達の将来を真剣に考える
プロセスが必要なのです
「学ぶ環境が整っていない輪島にはいられない
一家転住して転校させよう」
と考えている小中学生の保護者の方は
一歩立ち止まって考えていただきたいのです
環境さえ変われば勉強するようになるのですか?
与えられる学習環境を待つだけでよいのですか?
子どもたちの将来を
親も一緒に真剣に考えざるをえないこの環境こそ
子どもたちに本物の力をつけさせるチャンスです
他所者若者馬鹿者あつまれ〜
地震から 695 日目
動摩擦係数に比べて
静止摩擦係数はかなり大きいです
平たく言えば
動いているものを動かし続けることに比べて
止まっているものを動かし始めるのは大変
ということです
「やる気が出ないのですが
どうしたらいいですか?」
という人生相談には
「やる気なんか出さなくていい
やる気がないまま始めなさい」
と答えています
脳みそは本当に単純な馬鹿タレで
動いていると簡単に騙されて
やる気がでてくるのです
さてさてしばらくお休みしていたこのブログ
講演原稿と執筆原稿の目処が立ちまして
本日より再開です
決してやる気がないわけではなく
むしろお休み中におもろいことがたくさんあって
書きたいことは山ほどあるのですが
どうも静止摩擦係数がことのほか大きく
何から書こう?
変に考えすぎてなかなか進みません
とりあえず
今日の素敵な出会いの話から
よそもの
わかもの
ばかもの
地方創生の鍵を握ると言われています
とりわけ
私はばかものが大好きで
いつもばかものを追い求めています
そんな素敵なばかものたちに
今日はいっぱい出会いました
このブログを再開するための起爆剤としては
充分すぎるパワーでした
この出会いをセッティングしてくれたのは
「日本の教育を変える!」
と息巻いて日本を飛び出した先で
能登半島地震の知らせを聞きつけ
いち早く帰国したまではいいものの
輪島に着いた途端に行き倒れ
忙しい被災民の手を煩わすという
荒技をやってのけ
以来輪島高校に籍を置きながら
被災地ガイドツアーで大人気を博している
本校きってのうつけ者
「てるてる坊主」です
能登里山空港の麓の三井町にある
『のと復耕ラボ』に
素敵なばかものたちが大集合しました
元々この地で開業していた
「里山まるごとホテル」
地域がまるごとひとつのホテルとなり
かまどのご飯や
縁側での昼寝
囲炉裏ばたでの食事など
能登の暮らしをまるごと堪能できる処
地震のため今は休業していますが
その場所を
ボランティアの方が休憩でき
交流が生まれる起点として活用している
それが『のと復耕ラボ』です
そんな素敵なみなさんをご紹介します!
まずはこの「能登若衆の会」のお頭
古矢拓夢さん
能登が大好きな熱い若者の会です
金沢のご出身ですが能登にも縁が…
実は飯田高校で校長先生を務められた
上乗秀雄先生のお孫さんです
本人曰く
Uターンならぬ『孫ターン』
上乗先生はご自身の退職金で
『ケロンの小さな村』を作られました
自然の中でひっそり暮らす
小さな生き物の観察や
米粉で作ったパンやピザが大人気の
自然体験村です
お頭は現在そこを経営なさっています
そんなお頭を慕って集まった
愉快な仲間たち
まずは加藤愛梨さん
東京から移住されました
防災コンサル Mutsubi を主宰されています
のとの復興に取り組む
若手人材育成を手がけ
Mutubeで能登の様子を配信されています
そしてその Mutsubi でのインターンシップ
山本浩毅さん
地域の事業者への
環境観光コンテンツ企画や
プロモーション代行を手掛けています
能登の魅力を YouTube『のとのと』
で配信されています
鎌倉出身の藤田ちはるさん
ゲストハウス黒島で働いていたのがきっかけです
高校生の時から仲間と一緒に
被災地支援や防災に取り組んできました
現在上智大学新聞学科で
防災教育を研究なさっています
高崎稚春さん
大分や静岡での災害ボランティアの経験を活かし
現在柳田植物公園の
指定管理者をされています
本谷悠樹さん
洪水被害の大きかった生まれた町野町へ
水害後に戻ってきました
子供の頃は大阪で過ごされ
高校は日本航空石川
現在 災害復興ラジオ「FMまちのラジオ」で
週一回木曜日にレギュラー出演されています
能登町ご出身の上野壱生さん
福井の高校を出られた後
現在牧場で肉牛のお世話をしてます
金沢大学融合学域の岡本岳人さん
合同会社SandBoxConectionsを
立ち上げられました
留学支援や
企業向けの海外への進出支援を
手掛けていらしゃいます
同じくSandBoxConectionsの花田怜大さん
七尾地域おこし協力隊として
御祓(みそぎ)地区活性化として
空き地空き家の利活用をされています
その他『マタギ』をされている方もいらっしゃいました
渋い職業ですね
石川県に若者の就労を支援するセンターがあり
そこに職業の適性を見極めるマシンがあります
質問にYes Noで答えていくと
ぴったりの職業を教えてくれます
一度生徒を連れて行ったことがありますが
出てきた職業が
『マタギ』
『キコリ』
『鷹匠』
『狂言師』
『床山』
よっぽど連れて行ったメンバーが
個性的だったのか
それともそのマシンの設定が
ぶっ飛んでいるのか
どうやってなるんだ?
って職業のオンパレードでした
その他全員の声を聞くことはできませんでしたが
とにかく素敵な仲間たちです
今後は
地元の若者たちと
どんどん繋がっていってもらいたいです
輪島高校では
毎週木曜日の午後に
街づくりプロジェクト『街プロ』をしていますので
みなさんぜひ遊びに来てください!!
休載のお知らせ
いつも読んでくださり
そして暖かい励ましのお言葉
ありがとうございます
しばらく「おこらいえ」の投稿を
お休みさせていただきます
講演と原稿執筆のご依頼が
立て込んできたことによります
中でも
OECD(経済協力開発機構)様からは
「未来の教師へのラブレター(仮)」
を書かせていただけることとなりました
震災体験を経て感じている
未来の教育への思いを綴ります
この「おこらいえ」の総集編
とも言うべきものになるのかなと思います
再会の目処は12月を考えています
生徒の活動につきましては
「輪高生の活動記録ブログ」にて
更新してまいりますので
引き続き応援・伴走
よろしくお願いいたします
ご来場ご視聴ありがとうございました
地震から 671 日目
豪雨から 407 日目
たくさんの方々に見守られて
「MAJI で WAJI 活」
行われました
ウエルカムボードは
「WAJI活公式キャラクター」であり
「輪島市未公式キャラクター」でもある
ワジねことフグたろう
これも生徒の作品です
お客様を迎えます
午前中は5つのステージ発表がありました
発表の内容はZOOMで配信し
全国のみなさまに見ていただきました
お昼にはキッチンカーが来てくださいました
「からてん」さん
なかよしのおふたりでやってます
からあげっ 揚げたこやきっ
フルーツドリンク
お品の最後にちっちゃい「っ」
が入るのがおちゃめです
金沢港クルーズターミナルに
よく出店されているそうです
「ふしぎなネッシー」さん
ドリンクとスイーツの専門店
オリジナルメニューの
「バーボー」がおすすめです
バームクーヘンを棒に刺して
だから「ばーぼー」
かわいくペイントしてあります
キャラクターのオリジナルネッシー
金沢の小さな公園でひっそり開店
なので店名が「ネッシー」
お目にかかるのがちょっと難しくて
でも見かけるとしあわせになれます
「萬屋おてる」
元気いっぱいテルさんのお店です
牛ロース串やオムそば チヂミ
定期的に被災地輪島に来てくださり
「ワイプラザ」などにも
出店してくださっています
今度は珠洲にも行かれるそう
こんなお店にも来ていただきました
四十沢木工工芸さんの作品になります
輪島塗の木地で被災地の涙を形どった
震災後に生まれた作品です
さまざまな支援で輪島に来られる方が
被災地にはお土産が売られていないので
金沢のお土産を買って帰られることに
さびしさを感じ
今できる輪島のお土産をつくりだされました
四十沢さんはその他にも
や
Sudo Masahiro Quartet Jazz Live.pdf
など
被災地元気づける
さまざまなイベントも
手がけていらしゃいます
キッチンカーも持ってきて
手作りスイーツや焙煎コーヒーを
振る舞ってくださいました
「WAJI活」でカフェを経営しているふたりも
玄関先でコーヒーを振る舞いました
お昼には供用間近の
仮設校舎内覧会も行われ
保護者をはじめ
多くの方々にご覧になっていただきました
こちらは「内田洋行」さんからのご寄付
新しい職員室に入れられた
フリーアドレス対応の
先生方の机と椅子です
新しい職員室を
先生方が働きやすい環境にしたい
とお願いしたところ
今回のご寄付につながったものです
内覧会に訪れた方からは
「どこかの I T 企業のオフィスみたい!」
と感嘆の声が聞こえました
午後からはポスターセッション
ポスターを円形に配置し
中央に設置した360°カメラから
全ての発表を配信できるようにしました
こちらの機材を今回ご提供くださったのは
音響機器の
「アバー・インフォメーション」様
今回こんな発表会にしたいと
提案させていただいたところ
こんなに素晴らしい機器を
ご準備してくださいました
全てのポスターセッションの様子が
ズームや移動も思うがままに
リアルタイムに送信できること
しかも周りのざわめきに関係なく
発表者の音声だけを
クリアに捉えることができる技術に
驚きでした
オンラインでご覧になってくださった方は
実感されたことと思います
クロージングでは
2年生の小町さんが
感動的なご挨拶をしてくださいました
最後には
「フードバンク愛知」様からの
ドーナツなどの支援物質を
岩本様が届けてくださり
会場のみなさんに配られました
防災用おにぎりの提供も
たくさんの方々にZOOM配信でも
お楽しみいただきました
以下
お寄せいただいた感想を
ご紹介させていただきます
「本日『街プロ』を視聴させて頂きました。生徒の皆さん、凄いですね。どんな取り組みをするかよく考えて取り組まれた様子がとてもよくわかりました。午後からしか見れなかったんですが、高校生の目線とは思えないくらい、課題や考察、今後の取り組みの展望など、しっかりと考えられていて、楽しく拝見させて頂きました。高齢化の進む現代に地域課題を若い世代が一緒に考えて自分達の社会を「こうしていきたい」「こんな風になったらいいな…」と考える事ができるのはとても重要ですね。私達リハビリテーションの取り組みも、「地域共生社会」の実現がキーワードになっていますので、改めて考えさせられました。」
新潟県より 言語聴覚士の堂井真理さま より
「『街プロ』発表会、リモートで拝見しましたが、生徒さんたちの表情が生き生きとして、とてもよいイベントでした。発表内容はバラエティに富んでいましたが、AIや発酵発電などには感心しました。何よりも、「街プロ」が地域に根付いた取り組みになってきていることが感じられて、喜ばしかったです。ご苦労様でした。」
RISE(ライズ)理事 岩見 一太 様 より
「千枚田の復興の子達と是非一度お話しが出来ればと思いました。直接訪問出来るタイミングとしては恐らく12月以降になってしまいそうですが、来年4月のイベント時に輪島高校ブースを設置して、クッキーの販売や活動PRをしてもらえないか?と相談出来ると幸いです。」
umbling Dice Records 大石 崇史 様 より
「これからの地域の主役である輪島高校の皆さんが、元気に、明るく積極的に活動できていることが伝わってきて、とても嬉しく思いました。輪島高校の探究活動は地域との繋がりが強く、活動性の高さを感じています。特に、自分たちで考え、試行錯誤している様子が伺え、今後につながる体験ができていると思いました。最後の生徒さんの挨拶を聞いて、輪島高校の探究活動自体が、輪島の活性化に繋がっている、役立っているのではないかと思いました。近い将来、輪島にお邪魔し、皆さんと交流できることを楽しみにしています。」
久留米大学 安永 悟 教授 より
その他紹介しきれませんが
ありがとうございました
明日は「MAJIでWAJI活」
地震から 670 日目
豪雨から 406 日目
震災直後
来れる生徒だけで集まって
傾いた体育館の冷たい床に
輪になって座って
「どうする?これから・・・」
見えない明日に向かって
たわいもない話から始めて
「上から降ってきた復興計画に
そのまま乗っかるな
僕らのまちは僕らがつくる!」
傷ついたふるさとを
元の形に戻そう
そうやって始まった
街づくりプロジェクト「街プロ」
明日はその発表会です
たくさんの方々に寄り添っていただき
励まされここまできました
明日に向かうたくさんの勇気をいただきました
その感謝の心をこめて
これまで取り組んできたことを
それぞれが発表します
明日の様子はZOOMで配信します
ミーティング 276 485 4778
パスコード 222105
で入室ください
9:50 スタートです
無料版ZOOMを利用していますので
40分経過したら接続が切断されてしまいますが
同じミーティングとパスコードで
入室しなおしてください
ご面倒をおかけしますが
よろしくお願いいたします
配信スケジュールは次のとおりです
【ステージ発表】
10:10 らくして防災 ~防災✕AI~
10:25 ヤマメ大捜査線 in 輪島
10:40 スポーツで健康 ~訪問型ジム~
10:55 猫も人間も食べられるお菓子
11:10 神戸震災学習ツアー
【ポスターセッション】
13:00 能登のまいもんを広めよう
13:10 積雪発酵発電
13:20 高齢者といっしょ~心も身体も健康に~
13:30 未来へつなぐツアー
13:50 心も輪島も未来も明るくしよう
14:00 ペットと安全に避難するには?
14:10 災害に向けた電源づくり
14:20 千枚田の復興
今回配信機器をご提供してくださったのは
アバーインフォメーション株式会社様
360°カメラで全方向のポスターを捉え
高性能マイクで
ざわつくポスターセッションの中から
ピンポイントで目的の音声のみを拾います
クリアで臨場感ある音声をお試しください
こちらは使用する機器のパンフレットになります
今回無償でご提供いただけることになりました
ありがとうございます
じゃんけんの壺
地震から 669 日目
豪雨から 405 日目
2年前の大晦日
忙しすぎて帰省できずに
そのうち帰ろうと
アパートでお正月を迎え
被災してしまい
そのまま何ヶ月も
車中泊をせざるを得なかった
山崎裕貴先生
情報科の彼がいてくれたおかげで
輪島高校のネットワークは
1月4日に全面復旧するという
奇跡を見せるわけです
その山崎先生の研究授業が行われました
楽しみながら
プログラミングの技術を身につけます
試行錯誤しながら
諦めない力や順序立てて考える力を
身につけます
山崎先生曰く
「今日の授業は数学に例えると
因数分解ができるように
なったレベル
これから様々な技術を身につけると
アプリ開発できるようになる」
とのことでした
隣のクラスでもおもしろそうな授業をしていますよ
山上 佳織 先生の家庭一般
本物の和服の10分の1
ミニチュアの着物づくりです
和装の基礎とその特徴を学びました
昨日お越しになった
山梨県立興譲館高校さん
支援金をくださるとともに
牛奥商店様からの寄付金も
お持ちくださいました
株式会社まもかーる様も
一緒に支援金を持ってきてくださいました
本当にありがとうございます
輪島実業高校の元同窓会会長の椿原様
「元」というのは
現在は「桐章会」役員だからです
「桐章会」は輪島高校の同窓会組織
震災直前に迎えた
輪島高校の創立百周年の際に
両校の同窓会組織が一緒になりました
輪島実業高校は
元々は輪島高校の商業科
戦後のベビーブームにより
独立したのですが
少子化により募集停止
輪島実業高校の商業科や
輪島塗職人を養成するインテリア科の
優れた教育実践は
現在の輪島高校普通科ビジネスコースに
脈々と引き継がれています
いわば元の鞘に収まった
という形でしょうか
一時期両校は仲が悪く
同窓会組織が一緒になることに対して
苦情やお怒りの言葉も聞きました
しかしながら
昔のしがらみを捨て
親の出身校に関係なく
これからの輪島の子どもたちを
一緒に力を合わせて育てていくことが
重要であると判断しました
話は大きくなりますが
日韓関係もそのようになればいいなと
新しい総理の手腕に期待しています
さてその椿原様が
被災した自宅から見つけた
1952年の輪島高校の卒業アルバムを
学校に寄付してくださいました
戦後わずか7年後のアルバムには
戦後復興の中心となっていく
若者の姿が凛々しく写っていました
まるで当時の映画のポスターのような
何ともおしゃれなアルバムです
みなさんにお願いです
被災した家の片付けの際に
このような昔のアルバムありませんか?
ありましたら
輪島高校に寄贈していただけないでしょうか
ある年度以降のものは揃っているのですが
貴重な資料として揃えたいと考えます
3年生「英語探究」選択の生徒たちが
「海の星幼稚園」を訪れ
園児たちとの交流を楽しみました
まずは「じゃんけん列車」
英語でじゃんけん
「Rock Paper Scissors!」
話はそれますが
フランスのじゃんけんには
石 ハサミ 葉っぱ(紙)のほかに
壺があります
グーを緩めて丸い壺を作ります
石やハサミは沈むので壺に負けますが
葉っぱは浮かぶので壺の負けです
ちょっとややこしいのですが
色々駆け引きがあって面白そうです
次はクイズ
そして絵本読み聞かせ
「きんぎょがにげた」
「はらぺこあおむし」
「Good Morning Mr. Moon」
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
今日が最終回
(21)未来へつなぐツアー
さあどんな未来が待っているのでしょう
ご覧になってのお楽しみです
当日はお昼にキッチンカーも来てくださいます
できたばかりの仮設校舎のお披露目会もあります
内田洋行さんからご支援いただいた
フリーアドレス制の職員室も
ご覧になれます
ぜひお越しください
また
360°カメラで発表会の様子を
同時配信します
お越しになれない方は
どうぞご覧ください
被災地の生徒たちが思い描く
未来のふるさとを
ぜひご覧いただきたく思います
ようこそ!興譲館高校 ご一行様
地震から 668 日目
豪雨から 404 日目
山梨県立都留興譲館高等学校のみなさんが
本校を訪れてくださいました
以前に
本校生徒のアイデアを形にした『応援弁当』と
『能登復興・輪島高校復興祈願竹灯籠製作』
でお世話になった
DJ KOUSAKU さんが
連れて来てくださいました
先日万博のフィナーレで朗読した
正角 心音 さん
実は『応援弁当」にも携わっていて
玄関でKOUSAKU さんと再会を果たしました
万博閉会式の話をすると
「フィナーレ見たよ
櫻井くんと出てたね
実はうちのバンドのメンバーが
『嵐』に楽曲提供してるよ」
とのこと
何?この引き寄せ

自ら希望してきてくださった
心優しい10名の生徒さんと
ふたりの先生方です
ビジネスコース1年生と交流しました
校舎案内のあと
山上 佳織 先生による
防災に関する授業を受けました
グループワークの結果を発表する場面では
両校の生徒で絡みながら発表する
グループも見られました
岡山県立興陽高校さんと開発したバスソルトを
お土産におあげしました
輪島高校の「さかなクン」
伊奈岡克俊 先生の研究授業です
伊奈岡先生は生物が大好きで
いつも楽しそうに授業をする
と生徒から評判で
生物の楽しさを知り
自分も生物学に進みたいという
卒業生を何人も送り出しています
今日は血液型の話です
ゴリラの血液型は全員B型
よく言われますが
実はそれは正確ではなくて
確かにニシローランドゴリラは
全員B型だけど
ゴリラ全種でいうと何種類かあります
というトリビアを導入として
DNAの塩基配列とアミノ酸配列
の関係を学びました
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(18)千枚田の復興
(19)カフェと音楽で輪島を活性化させる
コーヒーは漢字で「珈琲」と書きます
考案したのは幕末の蘭学者
宇田川榕菴(うだがわようあん)です
「珈」は髪に挿す花かんざし
「琲」はかんざしの玉をつなぐ紐
をそれぞれ意味する字です
コーヒーの赤い実が
当時の女性が髪に飾っていた
「かんざし」に似ていることから
つけたそうです
「琲」の王篇を糸篇に変えると
「緋(あか)」になりますし
なんともセンスの塊です
「酸素」「水素」「細胞」なども
彼の命名によります
「酸」の素は実は水素イオンなので
「酸素」は誤訳といえば誤訳
なんですけどね
(20)運動で市民同士の絆を深めよう
被災地でもできるスポーツ
子どももお年寄りも一緒に楽しめる
そんなスポーツを考えています
例えばモルックのような
モルックは
フィンランドのカレリア地方の
伝統的なゲームであるキイッカ(kyykkä)を元に
1996年に開発されたスポーツです。
木の棒を投げてピンを倒す
ボーリングのようなスポーツです
床が傾いている本校の体育館でやると
投げた棒が
ひとりでにコロコロと戻ってくるという
オートマチックモルック場と
なるのでした
今回の発表会はその傾いた体育館で行います
紅白歌合戦を中継した時に
待合室として使用していた場所です
そんなところもぜひご覧になってください
能登で被災した高校生たちはいま
地震から 667 日目
豪雨から 403 日目
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(15)輪島をゆるキャラで盛り上げよう
今では観光地のマスコットとして
全国展開している『ゆるキャラ』
もともとは
イラストレーターのみうらじゅんさん
が考案したものです
『ゆるキャラ』には3つの条件があるそうで
① 郷土愛に満ちた強いメッセージ性があること
② 立ち居振る舞いが不安定でユニークであること
③ 愛すべき「ゆるさ」を兼ね備えていること
ちなみに「マイブーム」もみうらさんの造語
「ゆるい」+「キャラクター」=「ゆるキャラ」
「マイ(私)」+「ブーム(大衆)」=「マイブーム」
既存のものを組み合わせて
新しいものを創り出しているのですね
(16)災害に向けた電源づくり
さあ今回のエネルギー三部作の最後
昨年つまり被災1年目の『街プロ』では
子供やお年寄りの居場所づくりの
探究が目立ちました
今年はエネルギー
つまり被災経験を経て
次の世代へどう繋げるか?
をテーマにしたものが目立ちます
生徒たちの心の持ちようも
少しずつ未来に向かって
変わってきています
(17)ペットと安全に避難するには?
輪島高校では
避難所として
ペット同伴者の部屋を
ひとつこしらえました
ペット同伴避難の実現に向けての活動を
展開されている団体の方の話によると
学校を避難所として運営するときに
ペットを入れると
避難所を閉鎖した後
その部屋に生徒を入れることが
衛生上問題である
という理由でなかなか進まない
という話です
何ら問題がなかったことが
今回実証されましたけど
いかがでしょう?
朝日新聞さんから
「能登で被災した高校生たちはいま」
という動画のLINKをいただきました
https://m.youtube.com/watch?si=tqQGPmWELN0YFEyz&v=YPL9MfEWKdk&feature=youtu.be
24分ほどの動画になります
もとよりもっと
地震から 666 日目
豪雨から 402 日目
東陽中学校の高校説明会に行ってきました
素敵な教育目標を見つけました
「もとよりもっと」
短い言葉の中に
深い意味が込められた
素晴らしいメッセージですね
東陽中学校は
地震はもとより
半年後の豪雨で
甚大な被害を受けた場所です
氾濫した河川の両岸には
おびただしい数の土嚢が
痛々しいまでに積まれています
それでも少しずつ
ほんとうに少しずつですが
前に進んでいます
傾いた電柱の横に
新しい電柱が建てられていました
「もとよりもっと」
よくなりますように
途中の道路
一旦傾きが止まっていたのですが
またひどくなってきています
今日は急に寒くなって
冬の日本海を思わせる荒波です
隆起してできた新しい海岸と織りなす
コントラストは
ドラクロワの絵画のようです
先日「商い甲子園」でお世話になった
藤原美江さまから
すてきな贈り物をいただきました
流木アートでしょうか?
おしゃれなトレイです
11月1日の「MAJIでWAJI活」
街プロ発表会にお越しくださった方で
ご希望の方に差し上げます
またいっしょに活動してくださった
高知商業高等学校ジビエ部と
三重県の青山高等学校のみなさまからも
支援金をいただきました
ありがとうございました
OECD(経済協力開発機構)から
「ティーチングコンパス2025」 が
リリースされました
未来における理想の教員の姿を
描いたものです
本校もご指導いただきながら
作成に関わらせていただきました
ぜひごらんになってください
ポンチ絵も公開されています
世界各国からの参加者一覧です
Wajima High School (JAPAN)
の名前があります!
半島の最先端から
目指せ世界の最先端!!
商い甲子園
地震から 665 日目
豪雨から 401 日目
高知県は安芸市で行われている
全国商い甲子園に出店する機会を
いただきました
発災以来いろいろと
寄り添ってくださっている
藤原美江 先生に
お繋ぎいただきました
藤原先生は
「はりまや橋デザインコンテスト」
でグランプリを取られ
以来この大会の顧問を
務めていらっしゃるそうです
「土佐の高知の播磨屋橋で
坊さんかんざし買うを見た
よさこいよさこい」
江戸時代の
僧侶の「純信」と
少女「お馬」の恋物語
かんざしを買った「坊さん」は
実は「純信」ではなく
「お馬」に横恋慕する「慶全」
さらにはふたりを引き裂くために
嘘の噂まで流します
当時僧侶は妻帯が禁止されていたため
噂が広まり捕まるのを恐れ
「お馬」と「純信」は駆け落ちしますが
結局捕まりふたりは引き裂かれます
そんな悲恋物語の残る高知
そのお隣の安芸市での商い甲子園です
開会式で入場行進
四国の高校を中心に全国から集まりました
出店のみなさんをご紹介します
高知中央高等学校さん
近森産業さんとコラボしての
カツオ香る高知の揚げ餃子です
高知県立檮原高等学校さん
ワイン用のブドウで育てた高知牛
廃棄食材で作った
フードロスにも配慮したカレーです
高知県立山田高等学校さん
香美市の三谷ミートさんの
大人気の手羽先とチューリップです
高知県立安芸高等学校
「あきこう防災特別課」のみなさん
被災地のために
募金活動をしてくださっています
高知県立宿毛高等学校さん
OBである「豊ノ島」関の
ご実家のお豆腐です
愛媛県立西条高等学校さん
商業科で経営するお店「めぐみソムリエ」
たぬきまんじゅうがおすすめです
全部紹介したかったけど
時間がなくて
回りきれませんでした
私は会場の一室を借りて
能登半島地震での経験を語る
講演会をさせていただきました
会場には地震の悲惨さを物語る
パネルも展示してくださっていました
アキ市だけにアキない甲子園
かと思ったら
もっと深い理由がありました
安芸市は岩崎彌太郎氏の生誕地
世界に名だたる
現在の三菱グループの礎を築いた
幕末屈指の経済人です
彌太郎は30代で「土佐商会」に務めます
土佐特産である
樟脳や和紙そして鰹節
それらを売り
軍艦や武器を買いました
彌太郎は
坂本龍馬ら海援隊の
給料の支払いも行ったそうです
現在輪島高校は
「三菱みらい財団」さんから
採択されて資金援助を受けていますので
生徒のみなさんは胸をはりましょう
我々は
坂本龍馬が給料をもらっていた人と同じ人から
資金援助を受けています
龍馬も我々も
日本の未来をつくっちゅうぜよ
帰路につきました
目の前に太平洋が広がります

アンパンマン電車も走っています
高知駅のホームはオシャレです
なんかヨーロッパにこんな感じの
なかったですか?
福岡第一高校さんでの「パラマ祭」で
頑張っている様子を
岡本先生が知らせてくださいました
生徒たち疲れも見えますが元気です。
朝食のバイキングでプリン2泊とも3つずつ
計6個食べた生徒がいます
昨日の様子をお知らせします
パラマ祭1日目
10時からの開場を目指し
福岡第一高校さんに向かいました
今回のパラマ祭では
きゅうりのバスソルト
とまとのバスソルト
藤のバスソルト3種類を販売します
これらのバスソルトは
輪島高校の生徒が
県外の高校 大学そして企業と
コラボして作ったものです
前日福岡に到着してから
ホテルで手分けして袋詰めしたので
自分たちで準備したからか
商品に対して愛着を感じているようです。
福岡第一高校さんの生徒会メンバーの力も借りながら
販売しました
みなさんの頼もしいこと!
お客さんに声をかけてくれたり
商品の説明を丁寧にしてくださったりしました
買ってくださる方の中には
能登の状況を聞いてくださる方や
「応援しています!」と声をかけてくださる方が
たくさんいらっしゃいました
今回「ペットと災害」について探究しているチームの
パンフレットも持参しました
ペットを飼っていてもいなくても
興味深く聞いてくださり
当時の状況も聞いてくださいました
せっかくパラマ祭に参加させていただいたので
今後の輪島高校のイベントの参考にするために
校内を散策もさせていただきました
輪島高校生徒会長の北村くんは
スマッシュブラザーズ大会に参加しましたが
結果は惨敗
勝てそうな要素は全くなかったそうです
ステージではたくさんのパフォーマンスが
披露されていました
今回のパラマ祭に向けて
みなさん準備をされているらしく
盛り上がりがすごかったようです
前回夜の体育祭でお邪魔した際にも感じましたが
福岡第一高校のみなさんは
それぞれが全力で学校行事を楽しんでいる様子です
自分の「好き」をつきつめ
表現している姿がとてもきらきらしていました
輪島高校も
そんな自分の好きを形にできる学校になると
いいなと感じました
どうでもいい話ですけど
新幹線の前の座席の網に
フリーペーパー戻す時
角っこが折れ曲がって
「イーッ」てなりませんか?

パラマ祭
地震から 664 日目
豪雨から 400 日目
福岡第一高校さんの「パラマ祭」に
お招きいただきました
個性教育の一環として展開されている
「パラマ塾」の成果を発表する学校祭です
『パラマ塾』は
「個性の伸展による人生錬磨」を具体化させた
個性の育成を目的とした
ユニークな塾形式の授業です
生徒一人ひとりが持つ「個性」を
引き出し伸ばし育てることを
目的としています
都築 仁子 校長先生のご挨拶より
「Parama とは
サンスクリット語の
『Parama-alta』
即ち「第一義諦」の略です
仏教語です
校名の由来となりました
個性の意味です
本校には福岡はもとより
全国そして海外からも
毎年多くの個性を持った
高校生が集結します
それぞれが
夢や希望の実現に向かって
パラマ塾を居場所にして
常に新しい自分
本当の自分に向かって挑戦し
それぞれが目指すものを
確実に手にしてほしいです
素晴らしいパラマ塾です
今年もアクティブな成功を祈っています」
福岡第一高校さんは
能登半島地震直後の
1月から数ヶ月間
寒空の下募金活動に立ってくださり
本校へと支援してくださいました
それ以来ずっと寄り添って
くださっています
一年間の活動の集大成の場ということで
圧巻のクオリティーです
生徒会の生徒をお招きいただき
『輪島塾』として
仲間入りをさせていただきました
環太平洋大学の大池教授のご指導ものと
岡山県の興陽高校さんと共同開発した
バスソルトの販売をしてきました
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「街プロ」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(12)囲碁ボールで輪島を明るく
碁盤に見立てた人工芝マット上で
木製スティックで白黒のボールを操って
五目並べを行うニュースポーツです
兵庫県氷上郡柏原町(現在の丹波市)で
町おこしのために1992年に
考案されたものだそうです
囲碁の勝負によって領地争いを解決した
という故事が同町にあることが
考案のきっかけとなっています
(13)積雪発酵発電
積雪発電とは
太陽熱や廃熱などの熱源と
積雪による冷熱の温度差で
発電する仕組みです
発酵発電とは
発酵によって生じた
メタンガスを燃料に
発電する仕組みです
このグループは
このふたつを組み合わせることを考えた
ということでしょうか?
(14) 心も輪島も未来も明るくしよう
昨年度花火を打ち上げたグループの
流れを汲む活動です
冬の夜を彩る
イルミネーションをつくります
「まちを明るく元気にしていくこと」
「参加・交流の生まれる活動にしていくこと」
「資源循環や観光の要素も入れていくこと」
を意識して動いています
博多での販売を応援した後は
高知での販売の応援に向かいます
吉野川の美しい渓流です
大歩危小歩危の山あいを抜けます
アンパンマン号も走っています
ごめんまちこさんが迎えてくれます
明日は安芸市で開かれる
「商い甲子園」に参加してきます
奥尻島も忘れないで
地震から 663 日目
豪雨から 399 日目
佐賀で開催された
全国音楽教育研究大会
フィナーレでふたたび
全員でフェニックスを大合唱しました
全国の多くの先生方から
励ましのお声をかけていただきました
北海道からお越しの
今金中学校の 清水 桃子 先生
奥尻中学校の 塩原 祐馬 先生と
お隣になり
いっしょに歌いました
奥尻島といえば
平成5年に発生した
北海道南西沖を震源とする
マグニチュード7.8の
地震によって発生した津波が
わずか2分後に到達して
奥尻町だけで 198人もの
死者・行方不明者が出た場所です
先日も別の機会に
奥尻島ご出身の先生とお会いしましたが
「世間は阪神淡路大震災以降
東日本大震災や
熊本地震などよく取り上げるけど
阪神淡路の2年前に起こった
私たちを襲った悲劇のことも
忘れないでほしい」
とおっしゃっていたのが
心に残っています
【今日のDeep Purple】
教科を超えた授業実践を紹介し
深い教科横断型授業を作り出すコーナー
今日は国語と商業の教科横断です
授業者は
電話が鳴る前に
かかってくることを予知できる
高森まどか先生
テーマは
「メールの書き方を学ぼう!」
書き方を学ぶ前に書いたメールを
全員で見ながら
良い点と良くない点を考えました
「件名」はあったほうが良いことや
長すぎると見ずらいこと
また最初に名乗ったほうが良いことに
気づきました
そのあと
商業と国語表現の教科書を
見比べながら
ビジネスにおけるメールの
一般的なルールについて学びました
その後日程調整のメールを例に
スムーズなやり取りにするには
どうすればよいか考えました
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(9)高齢者といっしょ
〜心も身体も健康に〜
75歳以上を後期高齢者
65歳以上を前期高齢者
と呼ぶそうですが
初期高齢者の私は
後期高齢者並みの記憶力が自慢です
最も得意とするのは
用事があってある場所に来たのに
着いた途端用事を忘れてしまい
思い出そうと元の場所に戻ってみても
用事があったことすら忘れてしまうことです
これが私が心身共に健康である
元気の源となっています
周りは迷惑していると思いますが
(10)こども食堂について
子どもが一人でも安心して利用できる
無料または安価な食堂です
食事の提供だけでなく
子どもたちの「第三の居場所」として
学習支援や多世代交流の場としての
役割も担っています
(11)らくして防災
〜防災 × AI〜
防災が大切なのはわかっていても
なにを準備していいのか?
食品の消費期限が気になったり…
そんな不安や面倒を
一気に解決するアプリを開発中です
今回の発表会は
オンラインでもご覧になれます
お楽しみに
呼子の朝市
地震から 662 日目
豪雨から 398 日目
朝日新聞さんから
本校卒業生のその後を追った
ドキュメンタリー動画の
リンクを送っていただきました
デジタル版記事もあります
https://www.asahi.com/articles/ASTBM12QNTBMDIFI01FM.html
呼子(よぶこ)の朝市に行ってきました
佐賀県にある100年の歴史のある朝市です
港に隣接していて
水揚げしたての海の幸を扱います
輪島朝市も港と直結して
セリ体験などやってもいいですね
堤防も利用して釣り体験とセットにして
自分で釣った魚をその場で食べるとか
港にはズラッとイカが干してあります
輪島でこれやると
たちまちトンビにやられるかも
ここにはトンビいないのでしょうか
透き通ったイカ刺しが名物です
今朝は水揚げがなかったので
メニューの看板を見て我慢
輪島でもできそうですね
おそらくこれは水揚げしたイカを
生かしておくための生け簀
買った海産物を焼いて食べる
バーベキューコーナーもありました
アワビ250円〜
サザエ200円など
結構リーズナブル
ただし土日のみの営業なので
こちらも断念
道端でおばちゃんがサザエを焼いています
特大のもので1個 850円
これは結構なお値段ですね

こちらはイカの天ぷらを揚げたてで
8個ほど入って 500 円
観光客は「いろんなものを食べたい」
と考えているはずなので
ボリュームを落として
価格も下げるべきだと思います
昔ながらの土壁の家屋が続きます
クジラ漁の親方の屋敷を見つけました
この辺は昔はクジラ漁がさかんでした
漁の時期は12月から始まり春先まで
出漁の前に親方の家に集まり
酒を酌み交わしたのだそう

建物を活用して
中は資料館になっていました
輪島朝市にも震災を伝える
資料館があるといいですね
火災で消失する前は
輪島塗職人の伝統的な家屋が
あったんですけどね
阪神淡路大震災の時には
「しあわせ運べるように」
東日本大震災の時には
「群青」
傷ついた子供たちを励まし
未来に向かって歩き出すための
素敵な合唱曲が生まれました
私たちにも合唱曲が欲しい!
生徒や保護者の皆さんから
声が聞こえるようになりました
そんな時です
合唱作曲家の弓削田健介先生が
能登を訪れて
「被災地の子どもたちの
心の声を紡いで
合唱曲を作りたい」
とお申し出があったのは
そうして生まれたのが
合唱曲「フェニックス」です
今日は佐賀で
全日本音楽教育研究会全国大会
平たく言えば
日本中の音楽の先生方が集まる会で
弓削田先生の講演会
というよりコンサートがありました
最後にフェニックスを会場で大合唱
その時にステージの上から
指揮をさせていただきました
全国の音楽の先生の
会場を震わせる歌声に感動しました
会場では録音撮影が
禁じられていましたので
雰囲気をお伝えすることができず
残念です
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(6)能登のまいもんを広めよう
「まいもん」とは「美味しいもの」
海の幸山の幸からスイーツと
美味しいものの宝庫です
どんな「まいもん」を
紹介してくれるのでしょう
(7)タービンで輪島に灯を
被災地の子供達にとって
何日も電気が来ないことは
大きなストレスでした
ですので
今年の研究発表には
エネルギー問題についてのものが
多くあります
(8)災害による栄養状態の変化を改善したい
被災地では
お年寄りがトイレに行くのを億劫がり
飲食をしなくなるケースが多くあります
また若い世代においても
仮設住宅での調理が
困難極まることから
適当に済ますことも増えます
そんな状況に解決策を提案します
英語の研究授業を研究する
地震から 661 日目
豪雨から 397 日目
生徒と雑談しました
「7時間全部奥野先生の授業ならいいのに!」
「どうして?」
「だって奥野先生
授業のゴール示してくれるし
ゴールしたらそこで授業終わるし」
「他の先生は?」
「2分ほど余ってもいきなり
小テスト入れたりして
時間ギリギリまで引っ張る」
「最大限に学んで欲しいんじゃ?」
「でも授業の内容終わっとるし
集中力切れとるし
全く意味ないと思う」
「じゃあそれ先生に伝えてみたら?」
「ダメやと思う」
「どうしてかな?」
「俺らうるさくするから?」
自分たちでもわかっているようです
私も現役時代は
この生徒たちと同じことを考えていて
終了のチャイムが鳴っても
授業のまとめをしている先生を
「アホちゃうか
生徒が早よ終われ思てんのに
意味ないやろ」
とどんなに話が途中でも
チャイムと共にサッと終わって
生徒の貴重な休み時間を
1秒たりとも奪わない
そんな努力をしていたものです
キレイに授業をまとめたいのは
教員のサガではありますが
生徒が聞いていないのでは意味ないのです
最近では
「教師がなにを教え込んだか
ではなく
生徒が何を学んだかが大切」
という考えが主流になっています
生徒が言うように
授業の目的達したんだから
そこで授業終わればいいようなものの
「教員は給料もらって働いているのだから
授業をサッサと切り上げて
給料分働かないのは
契約違反だ」
といった問題も絡んでくると
ややこしくなってきます
こういった社会の問題について
生徒と教員とで
じっくり議論する時間も
必要なのかもしれません
しかしながら
教育と経済は
必ずしも相容れないものであって
例えばアメリカの研究で
こんなのがあります
アメリカは結構思い切った
教育に関する実証実験をするお国柄で
ある州で
教員の給料を完全出来高払いにしたそうです
進学実績に基づいて
教員の働きぶりを査定し
結果を出した教員を優遇したそうです
教員のモチベーションが上がり
優れた教育効果をもたらすと
期待されていたのですが
結果は
アメリカの教育施策上
最大の失敗のひとつとなりました
なぜか?
学校がこれまでにないほど
荒れ出したのです
教員の指示に対して
「へん!どうせ自分の成績上げたいだけだろう」
「俺たちに言うこと聞かせれば
自分の給料上がるからな」
全く従わないようになってしまいました
教育の世界に
費用対効果だとか
経済の原理だとかは
決して持ち込んではならないという
教訓とすべきです
【今日のMAJIでWAJI活】
11月1日に開催される
探究学習「WAJI活」発表会
その内容を告知し
繋がってくださる方を見つけるコーナー
(3)ヤマメ大捜査線 in 輪島
環境DNAを調査して
輪島の川にヤマメがいないか
調査しています
生物は体表から剥がれた細胞や糞を
環境中に放出します
河川水中に含まれるDNAを分析することで
そこにどんな生物が住んでいるか特定できます
捕獲する必要がないので
生物や環境への負荷が少ない技術です
(4)神戸震災学習ツアー
かつての被災地神戸を視察して
30年間どのように復興してきたのか
自分の目と足で学んできました
30年経った今だからこそわかる
復興の成功と失敗
その教訓を能登の復興に活かします
(5)スポーツで健康 〜訪問型ジム〜
スポーツが大好きなのに場所がない
このグループでは
自分たちでジムを作ろうと
行政にかけあうなど
さまざまな活動を行い
多くの困難にぶつかってきました
そして今
訪問型ジムという
新しいスタイルのジムを考えました
発表会では
落成したての仮設校舎の
内見会も予定しています
内田洋行様にご支援いただいた
フリーアドレス制の職員室も
ご覧になれます
ぜひのお越しを
【今日の震災新採5】
震災の地に赴任となった
5人の新採者を紹介するコーナー
外国語科の加藤先生の
初任者研修の研究授業が行われました
授業はAll English でテンポよく
教師と生徒のトークが繰り広げられました
こんな授業ならもっと英語好きに
なっただろうなと思いました
特にいいなと思ったのは
教師から日本語の例文が提示され
即座にペアで英語に直す活動
ただ今回の授業では
教員が指名したひとりの生徒の英文しか
全員でシェアできず
その他のペアは
自分たちが作った英文について
合っているのか間違っているのかわからず
モヤモヤするのではと思います
そこで
AIを活用したこんなアプリどうでしょう
もし既にあったら教えてください
全ペアで話している例文を
マイクで拾います
現在門前高校とのオンライン授業で
使用している機器では
教室の一番後ろの席の生徒の
雑談まで拾えるので充分可能だと多います
拾った音声は全て
即座にスクリーンに投影されます
すると全てのペアで作られた英文を
全員でシェアできるのです
その際AIが
文法的な誤りなどを修正して表示します
すると間違った本人は
間違いに気づき
文法的に正確な英文を学べる上に
間違えたことは他の生徒に知られないので
間違いを恐れず話す習慣がつきます
ただ同じような文章ばかり集まっても
面白くも何ともありません
そこで教員に発問力が求められます
「彼は午後三時に駅で彼女を見かけた」
みたいな
他に訳しようのない例文ではダメです
生活に密着し
なおかつ汎用性の高い文章
例えば
「先生遅えな」
主語をどうするかだけでも
何通りも作れるし
そこに一言自分で付け加えるよう指示し
「先生遅えな 何してるんだろう?」
「先生遅えな 忙しいんかな?」
「先生遅えな 時間守れって言うとるくせに
自分が遅れるってどうなん?」
みたいに自由に生徒が作文すると
一気にボキャブラリが増えて
楽しいと思います
集まった例文はそのまま保存されて
いつでもアクセスできるようにしておけば
家庭学習にも使えます
木犀の花咲く頃に故郷へ帰りたいな
地震から 660 日目
豪雨から 396 日目
校庭の金木犀が香る頃となりました
タイトル何のフレーズかわかりますか
「日生のおばちゃん」の歌です
この秋の佳き日
体育祭が開催されました
保護者の方もお越しになり
元気いっぱいの姿を見ていただきました
とはいえグラウンドには
仮設校舎がもうじき完成
生徒席のすぐ後ろに
工事用のフェンスが
限られたスペースに
トラックを斜めに描く
というアイデアできり抜けます
不便なら不便なりに
アイデアが湧くものです
普段のことを普通通りにしようとするだけで
生徒も先生も考える力が
鍛えられる
おもしろい環境です
種目も工夫を凝らしてあります
運動が得意ではない生徒も
みんなが楽しめるような
工夫が散りばめられています
生徒会の生徒が
福岡第一高校さんの
夜の体育祭を見て刺激を受け
趣向を凝らして
種目設定をしてくれました
グラウンドの隅っこには
野球のブルペン
以前の屋根付きのに比べると
雨の日は使えませんが
できることをやるだけです
こちらもがんばりましたよ
陸上部が自分たちでこしらえた
お手製の砲丸投げ練習場です
ここで練習して
北信越大会出場を果たしたって考えると
ほんとにがんばったなって
感動します
こんなスペック
地震から 659 日目
豪雨から 395 日目
用事があって進路指導室に行きました
授業中なので先生は
国語科の高森まどか先生だけでした
私が入室するやいなや
何か用事があるかのように
高森先生はおもむろに立ち上がり
歩き出しました
するとちょうど電話の呼び出し音が鳴り
高森先生は受話器を取り上げるのでした
通話を終えると
何事もなかったように自席へと
「あれ?何か用事あったのでは?」
と問いかけると
「電話が鳴ったので出ただけです」
いやいや
電話が鳴ったのは
あなたがが立ち上がって歩き出したあとです
どうやら
電話が鳴る前に音が聞こえるという
特殊なスペックをお持ちのようです
電話が鳴ると
誰からの電話かピンとくることありませんか?
それを超えた特殊能力のようです
もうすぐハロウィンですね
英語科の矢田勇先生の
奥様とお子さんで
カボチャのランタンをつくって
高校に飾ってくれました
発災以来ずっと寄り添ってくださっている
福岡第一高等学校さん
文化祭に輪島高校も
出店させていただけることとなりました
福岡第一高校さんの文化祭は
「パラマ祭」といいます
ここには
「パラマ塾」という
部活動のようでちょっと違う
生徒が自分の意思で
好きなことを極める
そんな活動があります
氷川きよしさんは
ここの「演歌塾」で
その才能を開花させました
それぞれの塾が
その輝きを発揮する場が
「パラマ祭」です
「輪島塾」として出店します
環太平洋大学さん
岡山の興陽高校さんと
コラボして開発した
バスソルトを販売してきます
震災後にできた
いろんな絆にホント感謝です
投げやりにならずやり投げについて考える
地震から 658 日目
豪雨から 394 日目
つい先日までの暑さが
嘘のように肌寒い
西部緑地公園陸上競技場
陸上部の生徒が
北信越大会で頑張っています
大久保侑選手 砲丸投げ
11m21で11位
干場泰志選手 800m
1分59秒92で予選3位
池端龍太郎選手 5000m競歩
27分36秒52で14位 自己ベスト
林祐馬選手 3000m障害
10分04秒77 11位 自己ベスト
山崎煌季選手 やり投げ
震災のハンデを乗り越え
ひしめく強豪の中見せる
堂々としたパフォーマンスには
ただただ感激です
やり投げについて
いろいろ気になったので
訊いてみました
競技としての起源は
古代ギリシャやローマ
紀元前4世紀頃のことです
もともとは狩猟時代の投槍
獲物めがけて
エイヤっと投げつけていたものです
18世紀頃から北欧諸国で
さかんに行われるようになりましたが
他の種目が競技として
取り入れられていく中
やり投げだけはあまり一般的にはならず
20世紀に入ってから
ようやくオリンピック競技となります
やりの規格は
男子が 800 g 以上
女子が 600 g 以上
バスケットボールが約 600 g なので
結構重いですね
材質には金属製とファイバー製があります
ファイバー製はよくしなるそうだので
今日観ていて
シューっと飛んで行くのと
フワフワと飛んでいくのがあったのは
その違いでしょうか
世界記録は 100 m 近くだそうで
今日出場していた高校生たちは
およそ 40 〜50 m ほどの勝負だったので
とてつもない距離ですね
バスケットボールより重いもんを
100m 近く投げるんかい!?
って感じです
おもしろいのは
シューズが左右で違うこと
トップスピードに持ってきた助走を
投げる瞬間ピタッと止める必要があるので
右投げの場合
右足はつま先が厚いカバー仕立て
左足は捻挫防止のためハイカットです
やりは個人持ちですが
他の選手のを
その場で借りてもいいそうです
フェアなルールでいいですね
ところで
「なげやりになる」は
「投げ槍」ではなく
「投げ遣り」だそうです
競技の名誉のために
「餌を遣る」
「酒を遣る」
「片っ端から遣る」
「ひとおもいに遣る」
結構やんちゃな言葉ですね
Future そして Futures
地震から 657 日目
豪雨から 393 日目
いしかわ高校科学グランプリが
開催されています
本校からも6名の生徒が参加し
頑張っています
中は撮影禁止なので
詳細を伝えることはできませんが
日頃の数学理科の勉強の成果を
発揮していました
先日行われた大阪・関西万博の閉会式
そのフィナーレで
本校の 正角 心音 さんが
朗読をしました
その模様がこちら
https://drive.google.com/file/d/14Ti8auky31fViBxWodnG_yvIPWkBszf2/view?usp=drive_link
どうぞご覧ください
こんぴらさんが守ってくれる!?
地震から 656 日目
豪雨から 392 日目
新米の季節ですね
例年ですと晴れ女の実家で
稲刈りをしている頃ですが
地震と豪雨で
両親が避難していて
田んぼをつくってないものですから
ちょっぴりさみしい秋を迎えています
そんな折
数学の 宮下 琢磨 先生から
新米をいただきました
金沢のご実家でとれたお米だそうです
宮下先生は
昨年地震の3ヶ月後に
被災地の学校に赴任が決まり
はじめてご実家を離れて
本校を目にした時
さぞ驚かれたことと思います
赴任以来
金沢から毎日自家用車で通いました
当時は『のと里山海道』も使えず
片道3時間ほど
かかっていたのではないかと思います
被災地での仮設官舎暮らしより
長時間通勤を選ぶほど
それほど過酷な環境ではありました
さていただいた新米
今年の概算金
つまりJAが生産者に支払う価格は
前年比6〜7割増しだそうです
過去最高を記録した生産地も
我々の口に入る頃には
5kg で 5,000 円弱ってところでしょうか
米1合は約 150 g
1合でおにぎりが3つできるとして
おにぎりひとつに 50 g
5kg だと 100 個できる計算になります
米原価だけでいうと
おにぎり1個 50 円です
それに具や海苔
光熱費や人件費 輸送費などを計上し
コンビニおにぎり
だいたい 200 〜 300 円で
設定されています
高いと捉えるか安いと捉えるか?
パリの空港で売っていた
1個 1,800 円のに比べると
さすがに安いですね
【今日のDeep Purple】
教科を超えた授業実践を紹介し
深い教科横断型授業を作り出すコーナー
今日は国語と商業の教科横断です
テーマは
「図書委員会のポスターの掲示内容を検討する」
です
話し言葉と書き言葉の特徴や役割
そして表現の特色を踏まえた上で
正確さ
分かりやすさ
適切さ 敬意と親しさ
などに配慮した
表現や言葉遣いについて理解し
使う力の育成が目的です
『図書館利用のしおり』
を改善するための会議に用いる
議案書を作成する実習です
商業科の山元 真吾先生より
議案書に適した文章上の言葉遣いや表現方法を学び
その後実際に作成しました
ビジネス文書検定3級の内容が
基となっています
山元教諭(商業科)
「それぞれの教科の視点から
議案書を捉えることができてよかった
文章を考える部分は国語科
文章を作る際の技術的な部分は商業科
の範囲であることを認識できた」
濵田教諭(国語科)
「実学主義的な側面の強い教科と連携することで
人文主義的な側面が強い国語科の活動に
日常生活に即した目的を与えることができた
それを学んで何に使えるのかという点は
生徒の学ぶ意欲に直結すると感じた」
先日
初年次教育学会でお世話にあった
佐渡島 沙織 さまより
書籍を贈っていただきました
夏休みにアメリカへ
災害医療を学びに行っていた生徒が
その報告をした学会の時に
お世話になった方です
その時の発表そしてインタビューを
今後の教育に反映してくださるそうです
いただいた書籍は
今後の生徒の発表のスキルアップに
大いに活用させていただきます
どうもありがとうございました
今日は四国は高松に来ています
眼下には煌びやかな瀬戸内海
中国からの観光客が驚いています
「日本也有这么大的河流!」
(日本にもこんなに大きな川があるんだね)
違います
これ海です
さすが中国人はスケールが違います
時間があったので
金比羅さまに行ってみました

以前高松で防災備災関係の
講演をさせていただいた時に
主催者からこう依頼されました
「香川県民は本当に防災意識低いんですよ
『こんぴら様が守ってくださる』
と本気で思っているんです
なんとか言ってやってください」
確かに何がおこっても守ってくださる
霊験あらたかな氣がします
震災地の新採ファイブ
地震から 655 日目
豪雨から 391 日目
本校の教員は約30名
そのうち5名
まさに6人にひとりが新規採用
大学出たての
フレッシュな面々です
うち4名が
教委が準備してくださった
教員向け仮設住居に住まいし
毎朝1時間近くかけて通勤しています
6畳ほどの部屋ひとつに
シンクとトイレと風呂
我々住まいを失った者にしてみれば
それでも涙が出るほど
ありがたいのですが
人生で初めて一人暮らし
それもいきなり被災地への勤務
さぞ心細く不安も不満も
あると思いますが
それでも被災地の生徒のため
身を粉にして
がんばってくれています
そのうちのひとり
地歴公民科の 竹田 悠月 先生の
初任者研修研究授業が行われました
テーマは
「日清戦争の勝利によって
日本は『列強』の一員になれたのか」
さまざまな資料を活用して
各人で調べながら
ディスカッションを通じて
思考を深めていく
素晴らしい授業でした
新採とは思えない
しっかりとした準備の上に立ち
新採の強みを活かして
生徒の発言を最大限に引き出す
そんな授業でした
輪島の中学生の保護者のみなさん
どうぞ安心して地元の高校に
通わせてください
授業後の研究協議会では
まずは私の方から
「日清戦争の頃
アレニウスという科学者が
世界で初めて
二酸化炭素の温室効果に関する
論文を発表している
そうした科学の発展を
当時の政策に絡めると
新たな気づきがあるかもしれない」
と提案しました
そして指導主事の 大田 新 先生から
投げ込まれた新たな問いは
「日清戦争で得た賠償金は
どのように受け取って
どのように使ったのか?」
まず賠償金は
8回の分割払いにしたそうです
なぜか?
膨大な利子が発生するからです
結果
当時の国家予算の
4倍ほどの賠償金を受け取っています
そしてポンドで受け取っています
なぜか?
そのお金でイギリスの国債を
大量に購入したのです
イギリスは当時アフリカへの投資で
資金繰りに苦しんでいたのです
イギリスに恩を売ることで
その後の日英同盟に
つながったそうです
こうして歴史を
前後のつながりで見てみると
ダイナミックなうねりが見えて
本当に興味深いです
さすが長年の指導主事経験
深い教材理解です
教師が深く教材を理解することで
生徒に活き活きと語ることができる
そんなことふと思いました
高松で普通科高校校長会に参加しています
記念講演の講師は
なんと昨日訪れた
環太平洋大学の 中山 芳人 特任教授
TBS日曜劇場『御上先生』の
教育監修もなさっています
「非認知能力の育て方」
について学びました
共通の尺度で評価測定できる能力を
「認知能力」
共通の尺度で評価測定できない能力を
「非認知能力」
といいます
ただし個別の尺度で主観的になら
「非認知能力」であっても
評価ができます
例えば
「あなたの根性は10段階でいくつ?」
簡単に言い換えると
「見える学力」
「見えない学力」
とも言えます
「非認知能力」の具体的として
自立心 向上心 自制心 好奇心 冒険心
積極性 創造性 協調性 自主性 社交性
などなど
決して新しい概念ではなく
実は日本の教育には
ずっと昔から取り入れられていたものです
ひとことで表すと
「心」
「認知能力」or「非認知能力」
といった二項対立ではなく
「非認知能力」for「認知能力」
といった捉え方が適切です
勉強によって「学力」を高めるために
従前の
識字・読字訓練
書出表出訓練
計算訓練
といった勉学に特化した訓練
すなわち詰め込み学習から脱却し
意欲
向上心
協働性
といった学びに向かう力
すなわち「非認知能力」を
高める必要があるのです
本校では
「街プロ」がそのための
有効な取り組みとなっています
未来の教室
地震から 654 日目
豪雨から 390 日目
被災した奥能登公立高校5校
今後どうしていくのかは
大きな課題となっています
県は今のところ5校全てを
存続させる方針を打ち出していますが
今後の生徒減を鑑みると
このままの形では
様々な問題があり
何らかの新たな枠組みは必要です
魅力ある高校にしないと
人口の流出に拍車をかけてしまいます
先日も県主導で
そのための会合が持たれました
今日は
魅力ある学校づくりのヒントを求め
岡山県にある
ふたつの施設を訪ねました
まずは Benesse 本社
岡山市を一望できる
ロケーションにあります
全国的な企業なので
東京に本社があるのかと
思っていました
創業者は元々小学校の先生
生徒手帳の制作を手がける
福武書店がそのルーツです
やがて通信添削講座を始め
進研ゼミから現在に至ります
社員の創造性を引き出す
オフィスシステムのあり方
次世代の教育が向かう方向
芸術を中心に据えて展開されています
私自身もAI時代の
授業の中心は
芸術・家庭・体育になっていくと
考えています
次に訪れたのが環太平洋大学
『非認知能力』の育成をコンセプトにした
キャンパスとなっています
キャンパスのデザインは
瀬戸内海の絶景と一体となった
「地中美術館」
都市に光が差し込む
「こども本の森 中之島」
など世界中から高い評価を得ている
安藤忠雄氏
こちらは『Coaching Lab.』
教室をぐるっと囲むように
ガラス越しの参観席があり
模擬授業・研究授業を行い
本物の教員を育成します
『Learning.Lab』
最新機材を揃えたグループワーク室で
「考え抜く・伝える力」
を育成します
『Presentation Lab.』
語る力
人の心を動かす力の養成空間で
自分の考えをわかりやすく
大勢に伝える力を育成します
『Discussion Lab.』
英国議会をモチーフに
「白熱した議論をする力」
を育成します
『Debate Lab.』
国連安保理をモチーフに
「徹底的に討論する力」
を育成します
『IPU Studio』
テレビ局スタジオをモチーフに
「世界に発信する力」
を育成します
これらの施設を参考に
半島の最先端から
世界の最先端を目指せる
魅力ある高校を
能登の地に
つくりたいと妄想しています
左右の思いやり
地震から 653 日目
豪雨から 389 日目
最近知った豆知識
何を今さらという方が
ほとんどかもしれませんが
車のメーターのガソリンマーク
横にチョコっとついている三角
給油口がどっちにあるか
示しているそうですね
今まで自分の車でない時は
いつもドアを開けてどっちかなと
確認していたのですが…
どうして給油口が
右にあったり左にあったりするのか
気になったので考えてみました
ガソリンスタンドで混雑しないため?
仮説を立ててみました
調べてみると
歩行者に対する優しい配慮がありました
マフラー(排気口)との位置関係によって
給油口の位置が決められているのだそう
道路運送車両法第18条7項
「給油口とマフラーの配管は
300mm以上離す」
マフラーの位置は
歩行者に配慮して
歩道から離れた位置
日本車の場合は多くは右側なので
給油口が左側にある車が多いそうです
逆に車が右側通行の国では
給油口が右側にあります
マフラーが2本左右にある一部のアメ車は
給油口が後方中央
ナンバープレートの裏にあるそうです
フォレスターの排気口は2本あります
給油口は右側です
SUBARU の車は
給油口は運転席側にあった方が便利
という思いやりから
全ての車の給油口は右側にあるそうです
ところでガソリンスタンドで
自分の給油口側が混雑していたので
反対側に突っ込んで
車の屋根越しにエイヤっと
ホースを伸ばして給油したら
「やめてください」と
店員に叱られたことがありますが
実際どうなんでしょう?
ダメな理由がわかりません
機械の構造上負担がかかるからか?
曲がったことが嫌いな店員だったのか?
北信越大会へ出場する陸上部の生徒が
昨日校長室へ表敬訪問してくださいました
参加選手は以下の通り
1年 干場 泰志 800m
2年 池端 龍太郎 5000m競歩
2年 林 佑馬 3000mSC
2年 大久保 侑 砲丸投
2年 山崎 煌季 やり投
17名の部員のうち5人
つまり3割の選手が
県予選を勝ち抜いたことになります
これってすごくないですか?
まともなグラウンドがない中で
傾いた校舎の廊下や
隆起した町の歩道で
できることを積み重ねてきた結果です
「恵まれた環境がないと練習できない」
などといった寝ぼけた妄想を
打ち砕いてくれました
とこんなことを書くと
「そうでしょう
銭金の問題じゃないんですよ」
と理解のない一部の行政の人に
言われるんだろうな
今日出会った素敵な言葉
「比べるな
隣の芝は
合成芝」
11月1日(土)
探究活動『街プロ』発表会
「MAJI で WAJI活」
が本校を会場に開催されます
どんな発表があるか
少しずつご紹介します
(1)「らくして防災 〜防災 × AI〜」
明石の青楓館高等学院さんとの共創
AIを使った防災アプリを開発しました
災害への備えって
大切だとはわかっていても
何から始めていいのかわからなかったり
ついつい億劫になりがちですよね
あなたのライフスタイルを
AIが分析して
手間をかけずに
最適な備えを提供する
そんなアプリを
実際の被災経験を踏まえて
開発しています
(2)「猫も人間も食べられるお菓子」
先輩の探究を引き継ぎました
本校が避難所として運営されていた頃
一部屋をペットと同居ができる部屋
としていました
しかし全国的に見ると
動物も一緒に入れる避難所への
理解は進んでいません
そんな中
例えばネコは
小麦粉を食べることができません
避難所にパンしかなく
ペットフードがなかった頃
ペットたちがお腹を空かせていたのです
それをなんとかしたいというのが
このグループの
テーマ設定のきっかけです
水の記憶
地震から 652 日目
豪雨から 388 日目
大阪・関西万博
フィナーレを迎えました
本校2年生 正角心音さんが
櫻井翔さん
河瀬直美監督
有働由美子アナウンサーとともに
未来へのメッセージを語りました
被災地からの復興を誓い
世界中に感動を届けました
櫻井翔さんが
気さくに話しかけてくださいました
今回お繋ぎくださったのは
能登半島の太鼓から始まる
オープニングの演出も手がけていた
芸術家 大志さんです
素敵なプレゼントありがとうございました
一酸化二水素
様々な物質を溶かす性質を持ち
金属すら腐食させてしまう
毎年多くの方が
これにより命を奪われている
この恐るべき物質
一酸化二水素
すなわち H2O にまつわる話です
この物質により
昨年9月に甚大な被害を受けた
珠洲市大谷地区へ行って来ました
こちらは地域の避難所となっていた
馬緤(まつなぎ)地区の公民館
大切なお神輿もこちらに避難
壁には所狭しと
当時の写真が貼られています
そして当時入所者へ
連絡事項を伝えていた張り紙が
時系列順に並べられていて
当時の極限状態が
臨場感を持って迫ってきます
さながら建物まるごと
被災を伝える一級資料となっています
こちらはボランティアさんが
寝泊まりしていた段ボールベッド
兵どもが夢の痕
「一期一会に感謝
令和6年の能登半島地震に際しまして
温かい励ましのお言葉や
お心遣いをいただき
厚く御礼申し上げます
1月2日に開設した
馬緤自主避難所は
住民の支え合いのみならず
多くの方々による
様々なご支援を受けながら
運営を続けて参りましたが
地区内での仮設住宅の整備や
生活インフラの復旧に伴い
その役割を終え
12月をもって閉所いたしました
振り返れば
炊き出しや物資支援
土砂撤去
災害ゴミの搬出作業等
様々な形で助けていただきました
こいのぼりの下での餅つき
黄色いハンカチプロジェクト
砂取節祭りや秋のキリコ祭りなど
様々な行事ができたのも
皆様からのご支援のおかげと
感謝申し上げます」
(ご挨拶の看板文章より)
命を脅かす恐怖の物質 H2O
一方で全ての命の源H2O
これにまつわる感動の話が
ここにはありました
待てど暮らせど水道が出ない中
ここの住民がいかにして
大切な水を手に入れて
命を繋いできたのか
一冊の報告書に
まとめ上げられています
「地震で全てを失った小さな集落
そこには
名もなき男と女たちの
水を手に入れるための
壮絶なドラマがあった」
「風の中のすばる〜
砂の中の銀河〜」
被災者が集まった避難所
しかしそこは断水したまま
復旧の目処すらありません
「うちのライナープレートに水あるぞ!」
ひとりの避難民のアイデアから
物語は始まりました
ライナープレートとは
縦井戸の形をした集水井
地滑りの原因となる地下水を抜き
地盤を安定させる装置です
その地下水を水道水に利用すべく
協力が始まりました!
平時であれば
井戸内に溜まった地下水は
ボーリングを通して
外に捨てられるのですが
それを利用しようと考え
住民自らの力で
簡易水道をこしらえたのでした
なんという生命力でしょう
繋いだパイプからは
とめどなく水が滴り
それを受けるタライは
満々と水を湛えるのでした
その後も定期的に
水質検査を繰り返し
飲料としても充分な水質であることが
確認されています
被災地における水源確保の技術として
先進的いや昔へ遡っての
素晴らしい事例であると思います
未来と過去
その捉え方に関する
面白い話があります
昔の人は
「サキの戦は苦しいものであった」
この『サキ』は
『サ』にアクセントがありますが
過去のことを指しています
現代人は
「そんなサキのことはわからない」
この『サキ』は
『キ』にアクセントがあり
未来のことを指しています
同じ『サキ』なのに
時代によって使い方が異なるのは
時間の流れに対する
捉え方に違いがあるからなのだそうです
現代人は未来に向かって
前向きに進んでいる時間感覚を持ち
なので視線のサキにあるのが『未来」
一方昔の人は
未来は見えないが過去は見える
過去を見つめながら
後ろ向きに進んでいる時間感覚を持つので
視線のサキにあるのが『過去』
なんだそうです
後ろ向きに吸い込まれていく
ジェットコースターに乗っているような
イメージなんでしょうね
明日でいよいよ
地震から 651 日目
豪雨から 387 日目
小松市でどんどん祭りが
開催されています
本校生徒と
岡山の興陽高校さんを結んで
商品開発してくださった
環太平洋大学のみなさんがお越しになり
バスソルトとジェラートを
販売しました
さあさあ予想を遥かに超える
盛り上がりを見せ
「なんで年間パスポート買うたのに
入れへんねんな」
という大阪マダムたちの
怒りのボルテージも最高潮の
大阪・関西万博
輪島塗の地球儀も
多くの方にご覧いただいたり
被災地から生まれた商品の
販売をさせていただいたり
我々被災者としても
たくさんの元気をいただいた万博
いよいよ明日閉会式が行われます
14時〜15時10分
NHK総合テレビで全国生放送されます
また
大阪・関西万博の
公式YouTubeチャンネルにて
ライブ配信されます
https://www.youtube.com/@Expo2025Japan
ぜひご覧ください
今はまだ言えませんが
素敵な演出があります
未来の図書館
地震から 650 日目
豪雨から 386 日目
3年生の普通コース理系の生徒を対象に
国語科の松本昭子先生による
「論理国語」と外国語科及び理科との
教科横断的な授業を実施しました
テーマは
「まちづくりの拠点として
輪島に公立図書館を作るとしたら
どのような図書館が良いか」
です

これまでに
「人とともにある図書館の未来は明るい」や
「図書館と『ものがたり』」を学び
前回の授業で
発表用のスライドを作成し
さらに新聞記事を活用しながら
多様な角度から図書館に関する話題に
触れてきました
本時は
スライドを用いて
グループ内で発表を行いました
そして次の時間は
グループ代表を決めて
代表全体発表を行う予定です
生徒たちは
「説得力とは何か」
という問いを意識しながら
質問やコメントを通して
互いの意見を深め合っていました

以下に生徒の発表内容と
聞き手のコメント質問の一部を示します
生徒Aは
これからの図書館のあり方について
発表しました
図書館が必要である理由として
「憩いの場があれば
住みやすくなるのではないか」
と述べ
これからの図書館として
「全ての人に
知識や情報へのアクセスを
提供することが大切であり
飲食スペースや
話し合いに使える会議室も必要」
と提案しました
聞き手であった生徒Bは
「輪島にある図書館の課題が
書かれていてよかった」
とコメントしました
生徒Cは
誰もが利用しやすく
魅力的な図書館作りについて
発表を行いました
「キッズスペースや
飲食可能なスペースを
設けるとよい」
「日本語の本だけでなく
他国の本を置くことで
外国や言語への関心を高められる」
「誰もが気軽に立ち寄れる
場所にしたい」
と提案しました
聞き手であった生徒Dは
「図書館の大きさは
どれくらいを想定しているのか」
「フリースペースを設けたほうが
よいのでは」
とコメントしました
生徒Eは
幅広い年代が利用できる図書館のあり方
特に中高生も利用しやすい
図書館づくりについて発表しました
データを活用し
高齢者が利用が多い割に
中高生の利用が少ないことを指摘し
その要因として
「高齢者は余暇がある」
「中高生はスマホを使う」
などを挙げました
その上で
「中高生も通用しやすい環境にするには
本を借りるだけでなく
雑談や飲食
参考書利用
カフェなどの機能を併設するとよい」
と提案しました
構造としては
「1階に児童コーナーやカフェ
2階に自習スペースを設けた二階建て」
を構想しました
生徒Fは
理想の図書館の具体例として
武雄市図書館を紹介しました
図書館とTSUTAYA書店が併設され
気に入った本を
その場で購入できる点や
親子で楽しめる絵本コーナー
スターバックスが併設されている点など挙げ
寄り道がてら立ち寄りやすい図書館
として紹介しました
また輪島で建設する場合を想定し
敷地面積や延床面積
建設費や運営費についても
具体的に提示しました
そのほか
教科書から文章を引用して
考えを補強する生徒
データを元に考察を行う生徒
輪島の現状を踏まえて
図書館は必要ないと主張する生徒
聞き手を引きつける「つかみ」について
工夫する生徒
図書館の存在意義を考えながら
高齢者や子供など
多様な立場から
図書館のあり方を考える生徒などなど
それぞれが主体的に
意見を表現していました
全体発表が終わると
生徒たちは自らの
発表原稿やスライドを見直し
より説得力のある
プレゼンをするための方法について
意欲的に意見交換していました
今日のレポートは
新採の櫻庭先生が
まとめてくださいました
めんそ〜れ沖縄最終日
地震から 649 日目
豪雨から 385 日目
楽しかった修学旅行も最後の日
食事の後は
ホテルの方が片付けやすいようにと
自分たちで食器をまとめるグループ
ご家庭でのしつけでしょうか
それとも避難生活で身についた
助け合いの心でしょうか
いずれにしても
美しい日本の心を見ました
最後の見学地
首里城に行きました
昨年来たときよりも
はるかに復興が進んでいます
輪島塗の職人さんも
復興作業に関わっています
今年の夏には
本校和太鼓部が
演奏させていただきました
そんなゆかりのある場所です
復興をお祈りしております
最後にガイドさんから
教えていただいた
素敵なことば
「誠(まくと)そ〜ち〜ね〜
なんくるないさ〜」
(誠実に一生懸命生きていれば
必ず道は開かれる)
いろんな思いを抱き沖縄を後に
ただいま
送り出してくださったご
ご家族のみなさま
おかげさまで
たくさんのことを学んで
つらい環境の中でも
明るく強く
未来を夢見て生き抜く力を
さらに強くして帰ってきました
ありがとうございました
めんそ〜れ沖縄3日目
地震から 648 日目
豪雨から 384 日目
日本のほぼ最西端
沖縄の夜明けは遅いです
6時でもこんなに真っ暗
少しずつ東の空に陽がさしてきました
陸上部はビーチでトレーニングです
私は昨日3つのオンライン会議があり
夕食も一緒に摂ることが
できなかったのですが
夕食後カラオケ大会で
盛り上がったそうです
実はこのカラオケ大会
行程にあったものではなく
生徒が直接ホテルに掛け合って
追加料金なしで
急きょ実現したものです
誰ひとり帰らず
終了時刻もきちんと守って
自分たちの力で
自分たちの旅行を盛り上げています
自分たちの力で
世界は変えられます
こちらは守り神シーサー
阿吽の「あ」
つまり口を開けているのがメス
「うん」
口を閉じている方がオスだそうです
今日のプログラムは
2組に分かれ
ジャングリアコースと
マリンスポーツコース
ジャングリアコースは
路線バスを乗り継いで向かうため
ひと足先に出発
マリンスポーツコースは
それに遅れること30分
貸切バスで走っていると
あれ?
先発したはずの
ジャングリアコースの生徒が
まだ停留所に!?
どうやら路線バスが遅れているよう
大ピ〜ンチ!
急きょ貸切バスを停めて
送迎することにします
バスの中では
ガイドさんが三線で
「てぃんさぐぬ花」
を歌ってくださいました
『てぃんさぐ』は
ホウセンカのこと
「ホウセンカで指先を染めるように
人としての教えを
伝えていきましょう」
そんな曲です
ジャングリア組を無事送り届けました
マリンスポーツ組は
午前中は「美ら海水族館」です
ここは4階から1階に降りていくにつれ
浅い海から深海へと
海の中を潜っていくように
展示されています
一番浅い海をイメージした水槽では
人工で水面を波立たせています
それは観客が上を眺めた時
水槽のバックヤードや飼育員を
見えないようにするためです
水分子は赤い光を吸収する性質があります
ですので浅い海の中は赤以外の光
つまり透き通った青色に見えます
さらに潜ると黄色い光も吸収され
透明な青から深い藍へ
やがて真っ暗な世界へと
深海で暮らす魚たちに
光のストレスを与えないよう
住む環境に合わせてあげます
しかしそれだと
今度は人が魚を観察することが
できません
そこで赤い光で照らしてあげるのです
なぜなら赤い光は
水に吸収されてしまい
深海までは届かないため
深海魚の目はそれを感じないように
進化してきたからです
身の回りにある科学でした
お昼はソーキそば
パワーをつけたあとは
午後はマリンスポーツ
ジャングリア組は

ヒューマンアロウ(人間矢)
田中選手が挑戦です
飛べ〜!
こちらは恐竜と気球をバックに
ナルトダンスを踊る新谷選手
そして夕飯後は「うたバス」
ガイドさんたちが歌と踊りで
楽しませてくださいました
本校の吹奏楽部のパーカッショニスト
髙橋惺(さとい)さんが
沖縄の民族楽器「三板(さんば)」を
飛び入りで奏でてくれました
抜群のリズム感です!
11月1日の「街プロ」発表会の
案内ができました
ぜひお越しください
めんそ〜れ沖縄2日目
地震から 647 日目
豪雨から 383 日目
いい天気
2日目の朝です
バイキングの朝食でスタートです
こちらは朝からモリモリ漫画ごはん
バイキングっていうのは
北欧の海賊の食事スタイルかと
思ったらさにあらず
日本以外の人には
伝わらない言葉です
昭和32年
新しいレストランを模索していた
帝国ホテルの社長が
デンマーク・コペンハーゲンを訪れた際
好みのものを自由に食べる
スカンジナビアの伝統料理
“スモーガスボード” に出会い
それに着想を得た
日本初のビュッフェレストラン
をつくりました
当時流行っていた
映画のタイトルから
「バイキング」と名付けたそうです
キャッチーなネーミングって
重要ですね
出発!
男性は「ハイサーイ」
女性は「はいたーい」
男性と女性で使う言葉が違うんですね
「ありがとう」を
男性は「コップンクラップ」
女性は「コップンカー」
というタイ語に似ていますね
もしかして
太平洋西南にある位置する国に
共通してみられる
言語の特徴なのかもしれません
今度研究してみることにします
ガイドさんが
対馬丸の話をしてくださいました
対馬丸は沖縄から本土への疎開船
当時の子どもたちは
修学旅行にでも行く感覚で
親元を離れて
楽しそうに船に乗り込んだそうです
それが永遠の別れになるとも知らずに
本土に到着する直前に
アメリカの潜水艦からの魚雷を受け
多くの幼い命が失われたのです
生徒たちはその話を
のめり込んで聴いていました
なぜならこの子たちは
令和の時代に
疎開を実際に経験しているからです
高校受験を間近に控えた
大切な時期に家を失い
集団で親元を離れて
暮らす経験をしたこの子らにとって
決して人ごとではないのです
自分の体験そのままなのです
「戦争は人を人でなくする」
「戦争はこの世で最も醜いもの」
こんな話に涙しながら
あの時焼け野原だった場所を
バスは走ります
「ぬちどぅたから(命こそ宝)」
ひめゆりの塔で祈りをささげました
バスの中では
カリスマガイド「ちばりな」さんが
バスを劇場に仕立てて
歌で踊りで素敵な旅を
演出してくださいます
「右手をご覧ください
一番高いのは
中指でございます」
「掌に人という字を書いて舐めると
人を舐めてかかるということで
人前で緊張しないおまじないがあります
車に酔わない方法をお教えします
掌に車と書いて舐めてください
もっといいのは
直接車を舐めることです
窓ガラスを舐めてください
ありがとうございました
窓がきれいになりました」
などが昭和のガイドさんの定番でしたが
コロナ禍を超えて
令和にアップグレードされています

お昼は瀬長島ウミカジテラスで
透き通るような海を見ながら

バスの中ではガイドさんが占いを
「左手で右手の指を1本
握ってみてください」
親指を握った人は
シャイで引っ込み思案
人差し指を握った人は
せっかち
中指を握った人は
おしゃべり
薬指を握った人は
クールで控えめ
小指を握った人は
甘えん坊
添乗員の丸山さんが握ったのは
人差し指
顔を見合わせて笑いました
午後に訪れたのは
「おきなわワールド」
エイサーを鑑賞したあとは
琉球文化体験
まずはレザークラフト
そしてシーサーの絵付け
「決して覗かないでくださいね」
機織り体験に
琉装着付け体験のお嬢様方
いろんな思い出ができました
でもこれ
よくよく考えてみると
本当に沖縄オリジナルかというと
そうではないんですよね
レザークラフトにしても
機織りにしても
実は日本中どこにでもあるもの
でもそこに琉球の香りをつけることで
一生の思い出に残るような
思い出を織りなしているんですね
輪島の復興への
大切な視点になりそうです
次に訪れたのは普天間基地
東京ドーム400個超のこの広大な敷地
日本であって日本でない
この不思議な場所
先日訪れた
韓国と北朝鮮の国境にも似た
なんとも言えない
不気味さを感じました
学校の方では昨日
富山県立小杉高等学校の
生徒のみなさんと
オンラインで
震災学習及び交流会を実施しました
実際の能登半島地震の写真や説明から
小杉高校の生徒さんたちは
「防災・減災として本当は何が必要なのか
高校生の自分たちには何ができるのか」
自分事として考えたようでした
地域の子どもの支援について
考えている生徒からは
「もっと震災後の子どもの気持ちを考える」
という意見が出てきました
”自分たちがしたいこと”ではなく
”被災者の気持ちに寄り添った支援のあり方”
に気がついたようでした
次回は
輪島高校の生徒たちも加わり
活発な学習会になればと思います
めんそ〜れ沖縄1日目
地震から 646 日目
豪雨から 382 日目
今日から修学旅行
3泊4日沖縄の旅
みんな元気に出発です
高松パーキングで休憩
悪路のため酔ってしまい
もどしてしまう生徒も
この先の道は真っ直ぐだから
きっと大丈夫!
小松空港に着きました
これから沖縄に向かってフライトです
那覇空港に到着
いきなり南国の香りがします

モノレール「ゆいレール」で国際通りへ
国際通りという名前は
戦後「アーニーパイル国際劇場」
という映画館があったことに由来します
終戦後いち早く復興を遂げたこと
通りの長さがほぼ1マイルであることから
別名「奇跡の1マイル」とも呼ばれています
今では名前の通り
国際色豊かな店舗が
軒を連ねています
ウチナーンチュの台所
第一牧志公設市場に行ってみました
こちらは夜光貝
もともと屋久島でとれる貝で
幕府への献上品でもありました
「屋久貝(やくがい)」が訛って
「夜光貝」に
刺身で生食できるそうで
独特の食感と豊かな旨味を楽しめます
身が硬いので
薄くスライスして
内臓(ワタ)を茹でて添えます
バター炒めやアヒージョなど
加熱すると身が柔らかくなり
違った食感を楽しめるのだとか
そのほか南国情緒たっぷりの魚たち
青いのはゲンナーイラブチャー
ナンヨウブダイです
白身魚で味は淡白で独特の香りがするそう
刺身やあんかけでいただきます
赤いのはアカジンミーバイ
スジアラです
表面の皮はゼラチン質で軟らかく
引き締まった身が甘く
高級魚とされています
塩煮が一番美味しいそう
今回も平和学習
「ひめゆりの塔」や「ガマ(防空壕)」
を訪れます
地震からほぼ2年
私自身
これまで前向きに生きてこれたのは
発災の数ヶ月前に引率した
修学旅行の
「ガマ」での経験があったからです
糸数アブチラガマは
沖縄本島南部の
南城市糸数にある
自然洞窟(ガマ)です
もともとは糸数集落の防空壕でしたが
やがて日本軍の倉庫として使用され
戦場が南下するにつれて
陸軍病院の分室となりました
ガマ内は600人以上の負傷兵で
埋め尽くされました
日本軍は兵力不足を補うため
沖縄県民を「根こそぎ動員」しました
中学生や高校生まで戦場に動員しました
「沖縄師範学校女子部」と
「沖縄県立第一高等女学校」からも
生徒・教師240名が
看護要員として動員されました
2校の愛称は「ひめゆり」
戦後彼女たちは
「ひめゆり学徒隊」
と呼ばれるようになりました
2週間くらい辛抱すれば
学校に戻れるだろう
そんな彼女たちの淡い期待は
無惨にも打ち砕かれます
最初は食事や水を運んでいましたが
戦禍が悪化するにつれ
麻酔なしで手術する患者を押さえつけたり
排泄物や切断した手足を外に棄てたり
悲惨な仕事に従事するようになりました
真っ暗で悪臭の立ち込めるガマの中
出口の見えない作業に
追われるのでした
やがて軍から「解散命令」が出されます
「あとは自分の力で生きていけ」
砲火飛び交う野外へと
放り出されるのです
生徒たちは親元に帰ることもできず
爆撃や米兵との遭遇に怯えながら
海岸や壕をさまよい
逃げ惑い死にゆくことしか
できませんでした
こんな状況に比べたら
地震で全てを失ってしまっても
自分たちには未来と希望が見える
そんな思いになれたのでした
11月1日
「街プロ」発表会のチラシができました
今日は中秋の明月記
地震から 645 日目
豪雨から 381 日目
日本三大なんちゃらを集めてみました
いくつご存知ですか?
そしていくつ行ったことがありますか
(1)日本三景
(2)日本三名園
(3)日本三大夜景
(4)日本三大花火
(5)日本三名泉
(6)日本三大朝市
(1)日本三景
宮島(広島県)天橋立(京都府)松島(宮城県)
(2)日本三名園
兼六園(石川県)後楽園(岡山県)偕楽園(茨城県)
(3)日本三大夜景
函館山(北海道)摩耶山(兵庫県)稲佐山(長崎県)
(4)日本三大花火
大曲の花火(秋田県)
土浦全国花火競技大会(茨城県)
長岡まつり大花火大会(新潟県)
(5)日本三名泉
有馬温泉(兵庫県)草津温泉(群馬県)下呂温泉(岐阜県)
(6)日本三大朝市
勝浦朝市(千葉県)
呼子朝市(佐賀県)
館鼻岸壁朝市(青森県八戸市)
閖上朝市(宮城県)
など資料によってまちまちです
しかしながら全ての資料に
名を連ねているのが
宮川朝市(岐阜県高山市)
そして輪島朝市です
こうしてみると
改めて我々は大切なものを
燃やしてしまったんだなと
そしてここで絶やしてはならぬものだと
実感します
先日閖上朝市を視察して来ました
pdf 資料にあるように
必ずしも閖上にあるものだけでなくて
全国あるいは世界から出店できる
仕組みがあるようです
輪島朝市の復興には
伝統を残しつつ
どれだけ新しいものを取り入れていくか
ポイントとなりそうです
箱物ができたけど
出店する人がいなかったということは
避けなければいけません
「街プロ」で
朝市復興をテーマに掲げるグループが
市の協議会にも参加して
高校生ならではのアイデアを
提案しています
時間をかけて
しっかり議論をしてほしいです
三大なんちゃらを世界に広げてみると
「 世界三大がっかり」なんてのもありますね
マーライオン(シンガポール)
人魚姫の像(デンマーク)
小便小僧(ベルギー)
ネーミングが失礼ですが
期待が大きすぎて
実物が思ったよりこじんまり
な名所たちですね
「日本三大こじんまり」
(あえてがっかりとは言わない)
ってのもあって
はりまやばし(高知)
時計台(北海道)
オランダ坂(長崎)
だそうです
小さくてもそれぞれに物語のある
素敵なスポットですね
今日は中秋の名月
県庁の最上階に行って
夜景と名月のツーショット
ところが室内の灯りが明るすぎて
うまく撮れませんでした
中秋というのは旧暦の8月15日
これは年によって大きくずれたりします
ちなみに来年は9月25日になるそうです
そしてもひとつ意外な事実
今日は満月ではありません
明日の月が満月です
このように
中秋の名月と満月は
1日ずれることの方が多いのです
さて名月にちなんで
「明月記」という書物を紹介しましょう
これは
鎌倉時代の公家 藤原定家が書いた
56年間にわたる克明な日記です
自筆日記としてはもとより
歴史書としても価値あるものです
例えば1巻には
建久10年(1199)正月から3月までが
書かれています
この年の正月11日には
鎌倉で源頼朝が亡くなっています
そのことが日記に記されているのが
正月18日
この時代の鎌倉と京都の距離感が
これによってわかりますね
さらには科学的資料としても
大きな価値があるのです
「後冷泉院 天喜二年 四月中旬以降 丑時
客星觜参度 見東方 孛天関星 大如歳星」
「觜」と「参」は
当時の中国で作られた星座
今の牡牛座のあたりです
「客星」は、突然現れた見慣れない星のこと
そして「歳星」は木星のことです
つまり
「天喜ニ年(1054年)4月中旬以降の夜中に
東の空おうし座のあたりに明るい星が現れ
その明るさは木星と同じだった」
現代の研究では
この年に超新星爆発が
起こったことがわかっています
「超新星爆発」というのは
星が一生を終える時に起こす爆発です
最近では
オリオン座のベテルギウスが
急に暗くなっていることから
超新星爆発を起こすのではないかと
言われています
ベテルギウスまでの距離は640光年
つまり実際に爆発しても
地球でそれを観測できるのは640年後
つまりすでに死んでいる可能性もあるのです
ベテルギウスはオリオン座の左上
腕を振り上げたオリオンの
脇の下にあります
ベテルギウスはアラビア語で
「脇の下」という意味です
優里さんの素敵な曲があります
知らなかった方がよかった
豆知識でしたね
すみません
コオロギ温度計の秘密
地震から 644 日目
豪雨から 380 日目
航空自衛隊「小松基地航空祭」
あいにくの天候でしたが
展示されていた戦闘機などを
見て来ました
こちらはロッキード製の戦闘機『F-35A』
高いステルス性能を持つ
最新鋭の主力戦闘機です
25mm機関砲
空対空レーダーミサイル
空対空赤外線ミサイル
などを搭載し
最大速度マッハ1.6です
さあさあ生徒の皆さん
日常のいろんなところに
探究のタネが転がっていますよ
マッハとは何でしょう?
マッハとは速度を表す数値で
音速の何倍かで表してあります
つまりマッハ1.6 は音速の 1.6 倍
物理の授業で
空気中の音速は気温によって変化し
0℃でおよそ 331.5m/s
1℃上昇するごとに
0.6 m/sずつ増加すると学びましたね
V = 331.5 + 0.6 t [m/s]
(V:音速 [m/s]、t:気温 [℃])
気温15℃では約 340 m/s となります
これは1秒(second)で340m 進むので
最近ようやく道路が整備されて
2時間を切るようになった
私の朝の通勤時間が
『F-35A』を使うと
3分ちょっとに短縮されます
いいな
1機欲しいな
日常のいろんなところに
物理や数学が潜んでいますよ
季節に因んだこんな公式はいかが?
T = 5(n+8)/9
/ は ÷ のこと
ところでこの ÷ を使うのは
世界中で
イギリスとアメリカと日本だけ
なんだそう
あとの国は全て / を使います
さてさっきの式が意味するものは
n はコオロギが15秒間に鳴く回数
それに8を足し、5を掛けて9で割ると
温度T(℃)が求められる
ということです
例えば15秒間に28回鳴いたとしたら
28+8 = 36
36 × 5 = 180
180 ÷ 9 = 20
その時の気温は20℃です
このコオロギ
古くは秋鳴く虫の総称でした
古名をキリギリスと呼んだり
その鳴き声から
ちちろ虫などと呼んでいたようです
次のうち
コオロギを表す漢字はどれ?
① 蟷螂
② 飛蝗
③ 紅娘
④ 蜥蜴
⑤ 蟋蟀
⑥ 螽斯
⑦ 蜻蛉
⑧ 蝙蝠
⑨ 鳳蝶
⑩ 天牛
答えは後ほど
さて話をマッハに戻しましょう
このマッハ
飛行している空間の
音速との比率で決まります
つまり同じ速度で航行していても
離陸したて
低空飛行をしている時と
高度が上がって
対流圏上部 - 成層圏下部を
巡行するときでは
マッハの表示が異なります
例えばボーイング787の巡航速度は
およそマッハ0.85とされ
具体的な時速は
明示されていません
ということは宇宙空間を飛ぶ
人工衛星のマッハは?
空気のないところは音が伝わらないので
人工衛星の速度を
マッハで表すことはできません
漢字クイズの答
① 蟷螂(カマキリ)
② 飛蝗(バッタ)
③ 紅娘(テントウムシ)
④ 蜥蜴(トカゲ)
⑤ 蟋蟀(コオロギ)
⑥ 螽斯(キリギリス)
⑦ 蜻蛉(トンボ・カゲロウ)
⑧ 蝙蝠(コウモリ)
⑨ 鳳蝶(アゲハチョウ)
⑩ 天牛(カミキリムシ)
で正解は⑤でした
こちらは戦車や対空迎撃機などの特殊車両
こんな車両
震災後に所狭しと
高校グラウンドに並んでいたな
決死の救助作業をしてくださっていたこと
思い出しました
HESOに行って来ました
地震から 643 日目
豪雨から 379 日目
HESOセミナーに行って来ました
金沢大学附属幼・小・中・特支・高の5校園
が展開する
附属学校園将来構想〈金沢モデル〉
= PROJECT HESO(プロジェクト・ヘソ)
そのセミナーです
講師としてお迎えしたのは
教職員支援機構理事長の 荒瀬 克己 氏
どうすれば
児童生徒が学び学びあえるか
教職員が学び学びあえるか
学校は何のためにあるのか?
真剣に学びあって来ました
素敵な言葉を教えていただきました
「楽しんどい(たのしんどい)」
まさに本校が取り組む『街プロ』に
ピッタリ当てはまる言葉だなと
「楽しいけどしんどい」
では長続きしません
これをいかに
「しんどいけど楽しい」
に変えていくか
教師の力が求められます
今
生涯にわたって
能動的に学び続ける力が求められています
◯自分のよさや可能性を認識する
◯あらゆる他者を
価値のある存在として尊重する
◯多様な人々と協働しながら
様々な社会的変化を乗り越える
◯豊かな人生を切り拓く
◯持続可能な社会の創り手となる
『街プロ』では
これらのことを段階的に体験できるよう
取り組んでいます
自己肯定感を高めます
◯自分はたいせつなひとりだ
◯いまの自分が自分のすべてではない
◯人間は学ぶことを通して成長する
◯目の前の世界が世界のすべてではない。
◯少し動けば世界は変わる
こんな気持ちが高まりますように
自分には何ができるのだろうか?
何かの役に立っているだろうか?
自分はここにいていいのだろうか?
こんなこと自問自答しながら
周りが気づかせるたり支えたり
自分で気づいて考えて行動しています
興味深い事例も
紹介していただきました
学びの環境づくりです
教室のうしろには
採択していない他社の教科書を
教卓の上には教師用の指導書を
置いておいて
生徒に自由に活用させるのだそう
いいアイデアです
さっそく真似しようと思います
個別最適な学び
協働的な学びを充実させるために
校長にとって
従前より求められている資質に加え
① アセスメント
様々なデータや
学校が置かれた内外環境に関する情報について
収集・整理・分析し共有すること
②ファシリテーション
学校内外の関係者の相互作用により
学校の教育力を最大化していくこと
が求められる
ということを学びました
今日出会った素敵なことば
「ヒトが成長する順番
① 知る
② 覚える
③ 動く
④ 考える
知 覚 動 考
ともかくうごこう」
動く前にあれこれ考えると
結局動けなくなりますもんね
小指と薬指の思い出
地震から 642 日目
豪雨から 378 日目
昨日「話し方教室」を開いてくださった
原田幸子アナからこんなお便り
原田さんは東日本大震災で
被災した経験がおありです
3月11日
片づけずに置いてあった
娘さんが幼稚園で作ったおひなさま
地震で顔が傷ついたけど
捨てられなくて持って来たのだそう
誰にも
どうしても捨てられないものって
ありますね
【今日の学びウィーク】
受け身な学習姿勢を脱却し
自ら学ぶ意欲を育むために
中間考査の代わりに導入した取り組み
〈電験三種講習会〉
輪島沖に洋上風力発電を誘致しています
先日三菱商事が
秋田沖と銚子沖3ヶ所の撤退を表明しましたが
現在日本では
業者選定済みの促進区域が
長崎や新潟など7か所
これから業者を選定する有望区域が
北海道を中心に9か所
そして準備区域が
富山や福井など11か所あります
輪島沖が準備区域に入れば
そこに大きな雇用が生まれます
必要となる資格が
まずは電験三種です
かなりの難関ではありますが
希望者が勉強をしています
〈コア輪島〉
授業の内容を超えた深い知識を身につけ
輪島高校の自主学習の核(コア)となり
自分自身も難関大学合格を目指す
発展的講座
今日は英語で開講しました
【今日のDeep Purple】
教科を超えた授業実践を紹介し
深い教科横断型授業を作り出すコーナー
今日は数学と英語の教科横断です
音楽が世界共通の言語であるように
数学も世界共通の言語です
情緒的な日本語に対し
論理的な英語は
数学の証明問題と
親和性が高い気がします
Question 1
Show that if n is even,then n2 is even.
たまに英語を
キーボードでタイピングすると
気付かされるのですが
一見でたらめに並んでいるように
見えるキーボードの配列
滅多に登場しない "q" や "z" が
端っこにあったり
登場頻度の多い "e" や "t" が
真ん中にあったり
たいていの単語のつながりが
右手←→左手と
交互にタイピングできるように
並んでいて大層都合がいいですね
日本語入力だと不都合がチラホラ
特に苦手なのが
我が県庁所在地「金沢」です
"kanazawa"
"k" と"n" 以外は全て左手の小指
特に最後は5連打
打ちにくいったらありゃしない
手の指にはそれぞれ
神経が1本ずつ通っていますが
薬指と小指は
まとめて1本しかないそうです
小指を動かそうとすると
一緒に薬指もついて来がちなのは
そういう理由だそうです
だから楽器をやる人は
薬指と小指を別々に動かす訓練が必要だよ
と昔ギターの師匠に教わりました
両手の中指を折り曲げて
第二関節の背同士をくっつけて
残りの4組の指先の腹同士をくっつける

その時
親指 人差し指 小指は
離すことができるけど
薬指だけは離すことができないんだよ
だから結婚指輪は薬指にするんだよ
って話がありますが
こういう身体的カラクリが
あるのですね
さて話を戻すと
数学の 宮下 琢磨 先生と
英語の 矢田 勇 先生で
英語で数学の証明問題を考える
教科横断型の授業を展開しました
学びウィークでいろんな学び
地震から 641 日目
豪雨から 377 日目
【今日の学びウィーク】
受け身な学習姿勢を脱却し
自ら学ぶ意欲を育むために
中間考査の代わりに導入した取り組み
今日はアナウンサーの原田幸子さまをお招きし
2年生を対象に「話し方講座」の第2回(応用編)です
第1回(基礎編)は
ワークショップ「声の道」をしました
目をつむった人に対して
いろんな方向を向いて
名前を呼びます
すると目をつむっていても
自分の胸に向かって呼んだときだけ
心に響くのです
まずはみんなで発声練習
縦に2本指が入るくらい口を開いて「あ」
口角上げて「え」
プレゼンテーションの語源はプレゼント
つまり贈り物なのです
相手に贈る気持ちが大切です
「何を話すのか考えるのが難しい」
「つい一定のテンションで喋ってしまう」
など生徒からの悩みにも
一つひとつ丁寧に答えていただきました
前回いただいた宿題
「2分間で推しのプレゼン」
3人の生徒が披露しました
①どんな言葉で
どんな雰囲気で始めるか
プレゼンには導入が大切です
「私は〇〇です」
「今日は◯◯について話します」
とか無難に入りがちですが
それではつかみになりません
奇をてらう必要はありません
みんながわかっていて
それでいて「おっ」と思わせる
導入が大事です
自分しか話せないこと
自分にとっては当たり前のことを話すと
聴衆が引き込まれます
②どこが一番話したいことなのかを意識します
話のヤマはどこなのかをしっかり意識します
一番時間をかけて話します
具体的な例を挙げるとよいです
③話の着地点をしっかりさせる
終わりよければ全てよし
④そして何より声に表情を乗せること
続いては
「いろんな〇〇」のワークショップ
まずは「いろんなありがとう」
①今一番欲しいものをもらった時の『ありがとう』
②ずっと欲しかったけど
たまたま昨日自分で買っちゃったものを
もらったときの『ありがとう』
ペアになって使い分けて伝え合ってみました
続いては「いろんなヤバい」
「ヤバい」はヤバい言葉ですよね
どれだけヤバいかというと
たとえば
『かわいい』を意味する
「愛くるしい」「チャーミング」「甘美な」「綺麗な」「可憐な」
『かっこいい』を意味する
「粋な」「見目良い」「洒脱な」「洗練された」「ハイブロウな」
『すき』を意味する
「心惹かれる」「目がない」「愛する」「愛おしい」「慕わしい」
『すばらしい』を意味する
「崇高な」「究極の」「至高の」「神聖な」「珠玉の」
これ全部『ヤバい』のひとことで済んでしまいます
同義語に『わかる~』や『それな〜』があります
「これヤバい」
「わかる〜」
「こっちもヤバくね?」
「それな〜」
完全に会話として成立しています
聞かれたことに答えない
政治家の答弁より
ある意味ヤバいかもしれません
続いて「街プロ」の時間
大成建設さんやURさん
そして青年会議所のみなさんはじめ
多くの方が伴走に入ってくださっています
今日は生徒のミーティングが終わってから
伴走の大人のミーティングも開かれました

いくつかの伴走団体様が集まって
生徒が帰ったあとも喧喧諤諤
すりあわせを行いました
先日「阪神淡路復興研修ツアー」でお邪魔した
「人と防災未来センター」の方に
教えてもらった大切なことは
復興がうまくいっているコミュニティーは
当初喧嘩するほどやりあった場所で
「このへんでいいんじゃない?」
と適当なところで妥協した場所は
30年後の今になって
さまざまな問題が沸き上がっている
ということです
そう考えると
高校生も大人も真剣に議論している
今のスタイルは理想的ですね
「大人がうまく誘導して成功に導こう」
ではなく
「失敗してもいいから高校生主体で動かそう」
に着地しました
今日出逢った素敵な言葉
人生で大事な「あ い う え お」
愛 命 運 縁 恩
ユダヤの法則と学びウィークと
地震から 640 日目
豪雨から 376 日目
世の中には不思議な法則があります
「ユダヤの法則」もそのひとつです
人間がどうあがいても
曲げることのできない宇宙の大法則
ユダヤ人はその法則に則って商いを行います
「78対22の法則」とも呼ばれます
例えば地球
海が78%で陸地が22%
例えば人間の体は水分が78%
例えば空気は窒素が78%
この法則に則って
コカコーラのボトルは
縦と横の比が78:22になるように
デザインされました
ワンコインで食べれる
マックのサンキューセット
390円とお釣りの110円が78:22
他にないか探してみました
このブログの
地震から◯日目
豪雨から◯日目
のカウント
78:22になるのはいつか調べてみました
そしたらなんと
地震からちょうど1年
今年の1月1日が
地震から367日目
豪雨から103日目
で78:22になっていました
背筋がゾクっとしました
本校では昨日より
「学びウイーク」が始まっています
一昨年より中間考査を廃止し
その代わりに
生徒が自らの学びを設計する力をつけるための
さまざまな仕掛けを準備しています
まずは
【今日のDeep Purple】
教科を超えた授業実践を紹介し
深い教科横断型授業を作り出すコーナー
今日は公民と数学の教科横断です
まずは公民科の 竹田 悠月 先生
今年の参議院選を題材に
「比例代表」や「ドント式」などの
選挙の仕組みについて学び
さらには「当確」についても学びました
今回 20時 の時点で
香川 山口 大阪 などで「当確」が出ましたが
石川選挙区には出ませんでした
それはどうしてか?
次に数学科の宮下 琢磨 先生の出番です
統計で学んだ「母比率の推定」を用いて
石川で「当確」を出すには
どのようなデータが必要だったか?
など考察しました
次に
【青楓館さんいらっしゃい】
学校の枠を超えての部活動
「AI部」で伴走してくださっている
明石の青楓館高等学院さんが
遠路はるばるお越しくださり
1年生と交流しました
まずは
「AI部」の生徒さんが
今取り組んでいらっしゃる
メタバース空間や
オンライン校舎設計PBLなどの活動について
プレゼンしてくださいました
そしてクイズ大会で盛り上がります
第1問:オリジナルAI を作成できるサービスは次のうちどれ?
① Apple Intelligence
② Google Intelligence
③ ChatGPT
④ Genspark
第2問:機械学習の説明として、正しいものは次のうちどれ?
① データからパターンやルールを自動で学習すること
② AIやコンピューターを教えして人間が学ぶこと
③ 脳のように自動で学習すること
④ 人間の専門知識を学習させ専門家のように回答させること
第3問:メタバースと言う言葉が登場した年は次のうちどれ?
① 1992年 ② 2003年 ③ 2010年 ④ 2021年
第4問:メタバースで再現された市場は次のどれ?
① 豊洲市場 ② 築地市場 ③ 輪島朝市 ④ 函館旭市
正解は
第1問 ③
第2問 ①
第3問 ①
第4問 ③
なんと全問正解が2人
商品をかけてジャンケンです
次にグループになって
最近の困りごと
つまりAIに叶えてほしいことを
ピックアップします
最適なトレーニングメニュー
食事のメニューとレシピ
その日の気候にあったファッションコーディネート
などを提案するAIが欲しい
といったアイデアが集まりました
青楓館のTERU学院長がおっしゃいます
「AIアプリの製作は簡単ですよ」
実際に青楓館の生徒さんが
輪島高校から出たアイデアを解決するアプリを
即興で作って見せてくださいました
輪島高校は
半島の最先端の場所にありますが
こんな場所からでも世界につながる
そして世界の最先端に触れることのできる
学校を目指しています
こちらは先生方のミーティングです
今年の「街プロ」発表会の企画会議です
これから詳細決まり次第
本ブログでお知らせします
今日は日程のみお知らせします
11月1日(土)
保護者のみなさん
小中学校の生徒及び保護者のみなさま
これまで伴走してくださった企業のみなさま
輪島市で復興に携わっている全てのみなさん
輪高生が被災した中
力強く立ち上がっていく様子を
ぜひご覧ください
11月1日(土)
絶対に空けといてください
英語俳句に挑戦!
地震から 639 日目
豪雨から 375 日目
秋晴れの気持ちのいい朝です
校門に立っていると
生徒のみなさんが
気持ちのいい挨拶をしてくれます
玄関前では「青春」の像が
迎えてくれています
昭和44年度の卒業生のみなさんから
寄贈されたものです
1月1日の午後4時10分を指さしています
おや
よく見ると
誰かがペディキュアを塗ってくれたようです
昔なら
「誰だ!名乗り出なさい!」
とか言って叱りつけていたものですが
私自身
震災でかなり心の持ちようが変わったようで
塞ぐみんなの心を明るくしようとしたのかな
とか
破壊したのならともかくオシャレにしてくれたから
まいっか
とか
その時の生徒のイタズラ心を
微笑ましく感じるようになっています
とはいえ生徒の皆さん
公共物にこれはいけません
昨夜の「Qさま」で
一度は訪れたい世界遺産に
「マチュピチュ」が選ばれていましたが
それ以外のインカ文明は
スペインに破壊されています
自然災害で
人の造ったものが壊されるのは
仕方がないけど
人の手で他の人の心のこもったものを
傷つけたり破壊するようなことは
断じてなりません
門前高校へのオンライン授業が行われています
山上佳織先生による『家庭基礎』
〈健康な住生活〉について考えました
動画の視聴含めて
知識を画面越しに伝えます
グループワークも遠隔で指示できます
受信側の教室の様子
コッソリ〇〇している生徒の様子も
送信側の画面にバッチリ映っていますし
教室の後ろでボソボソ喋っている私語も
バッチリ聞こえています
だんだん慣れてきて
画面越しに生徒が
リアクションしてくれるようになると
もっといい授業になってくると思います
ゴールデンウィークのポルトガル研修
夏休みのアメリカ研修に参加した4人
東陽中学校の生徒さんに報告会
その前に
災害復興らFM「まちのラジオ」にお邪魔して
出演して来ました
肉が好きな 崖 顕 さん
エビが好きな 髙橋 惺 さん
オムライスが好きな 山村 百華 さん
味噌おにぎりが好きな 岩﨑 月希乃 さん
「ホッとする瞬間」をテーマに
トークを楽しみました
今日の放送は「ポッドキャスト」でも
お聴きいただけます
ぜひどうぞ!
そのあとは東陽中学校で
ポルトガルでのスクールクラスター
アメリカでの災害医療
それぞれ学んできたことを
プレゼンしました
そしてグループトークです
活発な交流ができました
最後に現地での発表の様子を
英語でプレゼンしました
先日より紹介していた
生徒による夏の想い出俳句
ALT(外国語助手)のマイケルさんに
俳句のリズムに乗せて英訳してもらいました
『英語の俳句』です
「蝉の声
追いかけるよう
泣く子かな」
"A cicada's cry
A child's cring follows soon
Echo back and forth"
ちゃんと五七五の調べに乗った
「才能有り」です!
ごちゃまるティーンラボさんが
校内カフェを開いてくださいました
ひとぼう
地震から 638 日目
豪雨から 374 日目
【30-55 時間の旅】vol.5
30年前 55年前と時を遡った復興研修旅行
生徒の学びを紹介するコーナー
「人と防災未来センター」
阪神・淡路大震災の経験を語り継ぎ
その教訓を未来に生かすための施設
防災に詳しい方は
「ひとぼう」と略して呼んでいます
実際に被災した生徒たちが見ても
それでも大きな衝撃が走りました
〔中野舞星〕~「ひとぼう」で学んだこと
まず目に飛び込んだものは
南海トラフが来た時の
津波の最大の高さを想定した表です
もし南海トラフが起こってしまうと
ほとんどの建物が津波に飲まれてしまいます
改めて南海トラフの恐ろしさを感じました
次に収蔵庫に行ったら
そこには約20万件の震災資料がありました
今輪島にあるなんでもない物でも
数年経てばそれは能登半島地震の
大切な資料になるかもしれないので
残して置くのも大事だと学びました
そして神戸ではこの資料達を
未来にどう繋ぐのかが
今後の課題だと言っていました
震災当時を再現した映像を見ました
ほとんどの建物が倒壊して
高速道路のように頑丈そうなものでも
自然災害の強さには抗うことは出来ず
車も次々にぶつかり合って
逃げたくても逃げられない状況になってしまい
無力さをまざまざと見せつけられました
瓦礫に埋まってしまったお姉ちゃんは
「逃げて」という言葉を最後に亡くなってしまったり
状況を理解できないまま
ちゃんとしたお別れもできずに
身内の方を無くしてしまうのは
とても辛く苦しいものだと感じました
神戸市では
地区のみんなで助け合うことを
大切にしています
地震で無くなってしまった場所も
新しい場所だからできることをして
前と同じにするのではなく
さらに街をよくしていました
輪島もさらに
街を良く快適にする計画を立てて行くのが
大事だと思います」
〔橋浦 千秋〕~「ひとぼう」で学んだこと
「震災当時はゴミでも
時間が経てば経つほど貴重になる」
ポリタンク
折れた街灯の頭
商店街の看板など
様々な震災資料がありました
特に印象に残ったのは
被災者の実際の言葉やメッセージなどでした
「助けを呼ぶ声が耳に残って…」
「死を覚悟して…」
「早く逃げて!」
私は特に「『解体後』花だけは咲いている」
という言葉が殴り書きされたメモと
「応急手当をして貰ってから
遺体安置所にほっておかれた」
という言葉に胸を打たれました
今まで住んでいた家
いつも通っていた道路
穏やかに流れていた川が
全て壊れてぐちゃぐちゃになってしまったのに
花だけは咲いている
いつもは花に対してなんとも思わないのに
今だけはとても「呑気に咲いてるな」と憎く思える
そんな思いが詰まったメモ
遺体安置所にほっておかれた
どれだけしんどい言葉でしょうか
「もう生きていけないだろうから
ほうっておいたら死ぬだろう」
ということなのでしょうか
憎しみと共に悲しさも垣間見える言葉でした
実際に見てみて
とても胸が痛みました
災害を完全に阻止することは不可能
ですが「減災」という言葉があるくらいです
人間は頑張れば何でもできるのだから
なにもわからない
でも自分でできることも探して行動する
そんなことを学ぶことができました」
〔濵高 一朗〕~「ひとぼう」で学んだこと
能登地震が阪神淡路大震災に比べて
大きく減災ができていたということに気づきました
能登半島地震が起こった時
私は阪神淡路や東日本から
何も学んでいないじゃないか
また同じ事を繰り返しているじゃないか
と思っていました
しかしそれは大きな勘違いでした
阪神淡路大震災の時と比べて
建物 人の意識 国の援助 物資の搬入など
たくさんの点において
大きな成長を遂げている事を
映像や写真をみて理解しました
そして私が今注視しているのは
どうやってまた町を盛り上げていくかという点です
その点においては
まだ足りない部分もあると感じました
讃岐うどんの極意
地震から 637 日目
豪雨から 373 日目
大成建設さんのご協力のもと
災害ゴミを転生させてこしらえたベンチ
中庭から生徒玄関へ移動させました

これまでは休日朝早く
部活動の遠征に登校した生徒が
地べたに座って待っていたのですが
これからちゃんと座って待つ場所が
できましたね
輪島高校の避難所で
足湯ボランティアとして
寄り添ってくださった
藤井節子さまはじめ
四国ボランティアネットワークのみなさん
今日は本番讃岐の手打ちうどん教室を
開催してくださいました
特製レシピを伝授します
ぜひお試しあれ
塩:水の加減は
夏は 1:9
春秋は1:11
冬は 1:15
粉は中力粉を使います
粉に対する食塩水の割合は
夏〜冬で 42〜46%
中力粉をボールに入れ
両手で下から空気を含ませるように
混ぜながら
食塩水を3回に分けて加えます
しっかりこねていると
初めてボソボソだったのが
やがてひとつの玉にまとまります
ビニール袋に入れて寝かします
夏は 1時間
春秋は2時間
冬は 3時間
ビニール袋に入れたまま
足の裏全体で踏みます
1分半
薄く広がった生地を
縦横にそれぞれ3回
9層に折りたたみ
足踏みを3回繰り返します
生地を麺棒で薄く伸ばして
それを蛇腹に折りたたんで
4mm幅に切って出来上がり
茹でる時間は15〜16分です
29日(月)10:00より
南志見公民館でも開催されます
予約は不要
無料です
手ぶらで起こしください
【30-55 時間の旅】vol.4
30年前 55年前と時を遡った復興研修旅行
生徒の学びを紹介するコーナー
2日目の午前中は
青楓館高等学院さんを訪れました
学校を超えた部活動「AI部」で
一緒に活動しています

〔中野舞星〕〜青楓館で学んだこと
「みんな自分のやりたいことをすぐ行動に移し
学校の環境を
自分たちが過ごしやすい場所にしていました
自分達の活動を発表する場があって
素晴らしい発表をした人を投票して壁に貼って
みんな互いに高めあっていました
そして部活動は
どれも社会で活用していくことができそうなものでした
生徒一人ひとりの能力を育てて
挑戦する意欲を引き出しているとわかりました
私は何かに挑戦していくことはすごいと思います
自分で何か起こすのは難しい
そしてなかなか上手くいかないことも知りました
けれど諦めずに改善していくのをみて
私も何か挑戦する時は
失敗しても諦めずに改善を重ねて
成功に繋げて行く姿勢にしていきたいと思いました」
〔宮腰花歩〕~青楓館で学んだこと
たくさん質問をしました
Q.遠くにいる生徒が実際に来る時に
金銭面の支援はありますか?
A.高いランクのバッジを持っている生徒には支援が出ます
最高ランクバッジはプラチナバッチです
Q.修学旅行はどこへ行きますか?
A.基本みんな自由人なので
修学旅行でまとまって行くより
個として友達と一緒に旅行に行くほうがいい!
という人が多い
生徒さんについて私が感じたことは
話が止まりそうになったら
こっちに話題を振るなど
会話を回すのがうまいということです
また発表テクニックとして
スライドに書いてあることだけではなく
自分の意見を交えて笑いを取る
というのは自分を含め
輪島高校の生徒にはできていないことです」

〔浅野琉衣〕~青楓館で学んだこと
「青楓館のPBL型の授業は
主体性や積極性
社会的な立ち回りなどを学ぶ面が
輪島高校の「街プロ」と似ていると感じました
さらには単純に高等学校の探究活動の延長ではなく
本格的に社会参加する準備期間としての
カリキュラムや制度が整えられていて
他にも校歌・制服の制作など幅広い活動があり
生徒一人ひとりの主体性や行動力の高さを
改めて感じました
フレックスタイム制のような働き方改革を取り入れ
就職やその後まで見据えた体制が斬新でした」
〔森下正幸〕〜青楓館で学んだこと
「青楓館の生徒たちはGoogleスライドではなく
キャンパというアプリを使って
プレゼンしている人がほとんどでした
普段
活動やイベントなどで
県外に行くことが多いらしく
場数をふんでいて
共同作業や発表が上手でした
コミュニケーションスキル
主体性
チャレンジ精神など
社会に必要なスキルが養われ
海外企業系への推薦も多く
即戦力になりそうな教育をしていました」
この教室内のロフトも
生徒さんが手造りしたそうです
釣瓶落としの謎
地震から 636 日目
豪雨から 372 日目
【今日のDeep Purple】
教科を超えた授業実践を紹介し
深い教科横断型授業を作り出すコーナー
今日は国語と理科の教科横断です
3日間にわたった
阪神淡路復興研修ツアー
帰りのバスの中
夕暮れ空を見ながらこんなこと考えました
「秋の日は釣瓶落とし」
他の季節に比べて
秋は急速に日が暮れる
ということを表すことわざです
釣瓶とは
井戸で水を汲み上げるための道具で
桶を縄の先にとりつけたものを
滑車に掛けて使用します
井戸に落とすと素早く一気に落ちる様子に
秋の日暮れを例えています
これは単に
「日が短い」ということを表しているのではなく
「一気に暗くなる」ということを表しているようです
言われてみれば確かに
日が沈むと容赦なく暗くなる気がします
薄明るい時間が短いような気がします
科学的に検証してみる価値がありそうです
以前にこのブログでも紹介した
「天高く馬肥ゆる秋」
の科学的な根拠
夏の小笠原高気圧に比べ
秋の移動性大陸高気圧の
空気中に含まれる水分の違いから
実際に秋の雲の標高は高い
と言う事実
このことに関係があるのではと
考えてみました
空気中の水分量が多いと
そこを通る多くの光が散乱します
つまり明るく輝いて見えます
震災による停電で真っ暗なときに得た智恵ですが
懐中電灯を立てて
その上に水を入れたペットボトルを立てると
光が散乱されて
ランタンのように照らしてくれます
つまり空気中の水蒸気量が多い春や夏は
日が水平線に沈んでも
しばらくは散乱した光によって
空全体がぼーっと明るく見えるけど
空気が乾燥している秋はそれがなく
太陽が水平線に沈むと同時に
あたりが真っ暗になる
という仮説を立ててみました
単なる気のせいかと思い
実際に日没後の明るい時間帯の長さについて
調べてみました
すると
上空の大気が太陽光を散乱して光り
日の入後もしばらくは暗くならない現象をさす
「薄明」ということばがあることを知りました
「薄明」の長さを調べたサイトを見つけました
それによると
最も長いのは6月で1時間49分
それに対して
9月のそれは1時間25分
30分近くの違いがありました
どうやら仮説はある程度合っていそうです
実際に
湿度と「薄明」時間を測定して
調べてみるとおもしろそうです
温度によって差が出るのか?
緯度によって差がでるのか?
興味は尽きません
以前こんなこと研究している生徒がいました
「二階から目薬」
本当にそんな難しいのか?
実験と計算により検証しました
こうした諺や古くからの言い伝え
これらを科学的に検証する教科横断型の学習は
ものごとを複眼的に捉える力を育てます
「それがいったい社会の何に役立つのか?」
いいんです
本人がおもしろければ
「災害復興は現状復帰が原則」
としか言わない
頭の固い役人のようなこと言わないでください
日本人として5人目となるノーベル化学賞を受賞した
海洋生物学者である下村 脩 氏は
子どもの頃に見た光るクラゲが不思議で不思議で
その発光の仕組みを生涯追い続けました
そして「GFP」とよばれる光るたんぱく質を発見したのです
「それがいったい社会の何に役立つのか?」
のちに医学の発展に大きな役割を果たすことになるのです
細胞を生きたまま観察するための「光る目印」として活用され
がん細胞をマーキングしたり
難病治療のための新薬開発などに大きく貢献するのです
基礎研究とはこういうものです
そのときは何の役にもたたないように見えても
その後思わぬところで
大切な何かに結びつくのです
だから
基礎研究に関わる国家予算を
ふんだんに研究機関に回していただきたいと思います
日本の失われた30年を取り戻すために
長い目で復興のことを考えている毎日を送っていると
コスパやタイパばかり追い求めず
目に見える成果ばかりにとらわれず
真に大切なことは何なのかを
本気で考える大切さを日々感じています
【30-55 時間の旅】vol.3
30年前 55年前と時を遡った復興研修旅行
生徒の学びを紹介するコーナー
〔辻 姫花〕〜2025 万博会場にて
ポルトガルパビリオンに行きました
パビリオンのテーマは「海洋:青の対話」
海が私たちに話しかけるような口調で話している様子が
スクリーンに映し出されてました
海の氷を溶かすと海は私達の家を沈め
ゴミを流せば海は私たちにそれを返し
資源を奪い尽くせば海はもう
私たちは資源をもたらすことはない
海は決して危険な存在ではなく
真に危険なのは人間である
私はその動画をみて
自分たちが環境にしたことは自分たちに返ってくる
と改めて知り
環境を大切にすることの重要性を実感しました
復興は極めて重要ではあるが
環境を思いやって進めていくことが
真の復興だと思いました
〔濵高一朗〕〜2025 万博会場にて
国が
大阪府が
私たち輪島の特色である輪島塗を
全国または世界各国に伝え
輪島への興味関心が薄れないよう
輪島という町の価値を再確認してもらうよう
努めてくださっているということが
心に残りました
「夜の地球」輪島塗で作られた地球儀に対し
多くの方が足を運ぶ様子が
輪島市がまだ忘れられていないことを
強く象徴していると感じました
復興研修最終日
地震から 635 日目
豪雨から 371 日目
今日は阪神・淡路災害復興研修最終日
最後にとっておきの危機対応研修を
準備していました
題して「初めての置いてけぼり」作戦
出発時刻に遅刻した生徒を待たずに
バスを出発させるのです
途中で追いつくのか
それともあきらめて帰宅するか
自分でルートを設定させて
行動させる訓練です
この子たちがいずれ親元を離れて
一人暮らしになったとき被災したら
自分で考えて行動しなければなりません
そんな思いも込めての作戦だったのですが
さすがみなさん時間厳守で集まりました
帰り道
北陸自動車道が交通事故のため
通行できなくなりました
運転手さんのとっさの機転で
8月31日に開通したばかりの
東海環状道を通って
東海北陸道経由で
帰ることとしました
さすがの危機管理能力です
さて問題です
実際に知り合いが体験した
北陸新幹線がまだない頃の話
東海地区に近づいてきた台風のため
午後2時頃
新幹線が運転を見合わせました
東京にいた彼は
夜の9時までには
大阪に入らなければいけませんでした
航空機をとろうとしましたが
その日の東京大阪便は全て満席
レンタカーだと
ぶっ通しで運転してギリギリ
渋滞でもあれば確実アウトです
ましてや台風に向かって運転するのは危険です
とっさの機転で
彼は夜の9時までに
大阪に入ることができたのですが
どんな方法を使ったのでしょう?
答えは次のコーナーのあと
【30-55 時間の旅】vol.2
2025 大阪・関西万博で未来の姿を
1995 阪神淡路大震災の姿を
1970 未来を夢見た大阪万博の姿を
30年前 55年前と時を遡る今回のツアー
今日は最終日
「万博記念公園」を訪れました
先々日
今年の万博のレポートより
〔大北 琉絆〕〜2025 万博会場にて
ポルトガル館での展示
「あなたは水から生まれたが
あなたたちが海や川に資源を捨てるなら
私達もあなたたちに
水として襲い掛かるだろう」
復興をする際に雨や地震による水害をよく考えたり
海辺や川などの整備をし
ゴミを拾うなどの清掃をして
その場所を大切にするようなところ
そんなまちづくりをしようと思いました
〔北村篤太郎〕〜2025 万博会場にて
防災に地域コミュニティは切っても切り離せない存在です
そして万博は「コミュニティの形成」に最も適しています
「コミュニティの形成」には交流が不可欠であり
このようなイベントに防災を盛り込んだら
様々な国の人達の防災意識が高まると考えました
〔小住 優太〕〜2025 万博会場にて
輪島塗の「夜の地球(Earth at Night)」を見ました
沢山の人が来てくださっていました
子供が楽しめるような遊び場が多くありました
定期的に地面から霧が出たり
トランポリンを置いたりして
遊ばせていました
輪島にもそういう場はありますが
全て買い物できるとこからは少し離れており
親が安心していられる場所ではありません
復興させる時は
商業施設の一部に
遊び場を作れたらいいなと思いました
先ほどの答え
羽田空港から千歳空港を経由して
伊丹空港に入ったのでした
【夏を詠む】最後の句
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナーの最終回
最後の一句は
「朝焼けに 染まる君いて 言葉なく」
我が家の公費解体が終了しました
高校で国語を教えていらっしゃる
大工髙志先生より
こんなメッセージをいただきました
「解体してありましたね。
大火を塞き止めた家でしたね。
お疲れ様でした。
ウチも倒壊を免れた家でしたから
地震の後
いろいろ会話できたんですよ。
家と。
1月に地震があって、
家と会話したけど
3月頃から
声が聞こえなくなって。
家って
少しずつ死んでいくのだなと
思いました。」
これを読んで
生まれて初めて
本当に人生で初めて
嗚咽
ってものを経験しました
「あさやけに そまるきみいて ことばなく」
復興研修2日目
地震から 634 日目
豪雨から 370 日目
昨日の万博では
多くの学びがありました
《本手 蒼瑶》
ROBOT&MOBILITYSTATIONブースで見た
不整地の荷物搬送などに活用可能な
六脚ロボット「ハルモニウム」
それからAIスーツケース
「人に優しい」をテーマにした
こうしたロボットを
積極的に取り入れることで
被災地復興に
新たな可能性が生まれると思いました
《宮下 ほのか》
多くの国のパビリオンが
その国の文化や自然を活かしていました
能登でも豊かな自然や観光地を活かして
世界に伝えられたらいいと思います
コモンズパビリオンでは
1つの国ではなくコモンズで協力しよう
という考え方を知りました
これは能登でも同じで
他の地域と協力することで
復興につながると感じました
他の地域とのつながりを大切にしていきたいです
《中野 舞星》
アラブ首長国連邦のパビリオンで
とある文を見つけました
「再生可能エネルギーと先駆的技術を
戦略的に採用し活用することで
気候変動に対応できる
未来の創造を目指した取り組みを続けています」
「環境変化に対応できる
未来の創造と革新を目指し
伝統に根ざした取り組みは
地球とそこに暮らす人々
そして将来の世代のために
生命を守る原動力となる
私たちはそう信じています」
輪島の復興も
このような思いを持って
そこに暮らす人々や将来の世代の生命を
守る行動をしていくべきだと思いました
《橋浦 千秋》
阪神淡路大震災から30年、
前回の万博から55年
とても長い時間が経って
ようやく神戸や夢洲などの地域が
元に戻ってきて開催できた万博
長い時間が経って戻ってきたのは
道路や水道などのインフラ
ビルやマンションなどの建造物だけでなく
人と人との心の繋がり
国外の人との交流関係
新しい出会いや経験を身につけるきっかけなど
様々なことが戻ってきたのだと思います
輪島は未だ復興途中
30年前の阪神・淡路と同じような状態
万博に行った身として
輪島の復興に少しでも貢献できるような
考え方や見方で成長していきたいと思いました
《宮腰 花歩》
入場した瞬間
テレビで見た時とは違う
物凄い迫力に圧倒されました
ヨーロッパなどの人気のパビリオンには
入れなかったけど
コモンズなどの
小さな国々がたくさん入っているパビリオンや
ロボットの展示をしてるパビリオン
大屋根リングなど
万博でしか出来ない体験ができたことを
とても嬉しく思いました
輪島と大阪で違うと思ったことは
ふたつありました
ひとつ目は観光客の数です
今の輪島には外国人観光客
日本人の観光客すらほぼいません
観光客を呼ぶこと=輪島全体の活性化
に繋がるのではないかと思いました
ふたつ目は
観光資源が震災前と比べて
圧倒的に少なくなったことです
朝市は焼け
千枚田は割れ
窓岩は崩れてしまいました
《浅野 琉衣》
ポルトガルパビリオンで
海洋資源や排他的経済水域など
海に関する記録の展示を見ました
巨大なスクリーンに映し出された
海から人間に対する
強いメッセージが印象に残りました
また万博会場では
外食パビリオン「宴」や
各地に点在するキッチンカーのように
全国から来るたくさんの企業や飲食店が
交代制で出店するブースがいくつか見られました
このシステムは地域活性化にもつながります
調べてみると
歴代開催された万国博覧会でも
災害を取り上げた国がいくつかありましたが
どちらかといえば防災・減災が目的であり
日本のように
復興支援として万国博覧会で災害を取り上げる国は
珍しいのだと気づきました
日本の手厚い災害支援は
捉え方を変えれば「チャンス」になります
そのためには
今日実際に見てきたパビリオンのように
強いメッセージ性が必要なのだと思います
みんなそれぞれに思うところがあって
期待していた以上に
いろんなことを吸収しています
今回のツアーで生徒が学んだこと
明日からシリーズ化してお伝えします
「AI部」の活動でご一緒している
明石にある青楓館高等学院さんを訪ねました

通信制の学校で新しい時代の教育を
実践されています
例えば「AI部」の他には
「起業部」
「デザイン部」
「投資部」
など特徴的な部活動
青楓館高等学院は
「子どもの未来を守る」ための高等学院で
①社会と学校とのギャップがあること
②子どもたちの未来か真っ暗なこと
を変えるために生まれました
そのあとは
「人と防災未来センター」を訪れました
背景の建物
写真では切れている
さらに上方に
「南海トラフで予測される
津波の高さ→」
の表示があります
衝撃の高さです
何もかもひとたまりもありません
こちらの様子も少しずつ
お知らせしていきます
【夏を詠む】無題
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
それぞれの想いをのせて夏が過ぎ行きました
今日はいろんな夏を集めてみました
ただ想像力の乏しい私にとっては
どんな情景を詠んだ句かわからなかったので
みなさんで味わってみてください
「掌に ビー玉ひとつ 月を抱く」
「氷山や かき氷めく 地の悲鳴」
「夏夕べ 君と竿振る 肩ぬくし」
復興に向けて学ぼう!
地震から 633 日目
豪雨から 369 日目
阪神・淡路復興研修に出かけています
今回の研修はとにかく自分たちで動くこと
お客様じゃなくて自分たちで旅を組み立てる
これが大きな目標です
バスの中も自分たちで順番にもりあげます
トップバッターは2年生の辻姫花さん
万博にまつわるクイズ大会です
第1問ジャカジャン
世界初の万博開催地は?
① パリ
② ニューヨーク
③ ロンドン 答は最後に
続いては1年生の宮腰花歩さんと橋浦千秋さん
イントロクイズです
とっても進行が上手でアナウンサーみたいです
震災復興FM「まちのラジオ」に
出演しませんかと
思わずオファーしました
それから1年生の
本手蒼瑶さんと宮下ほのかさんと中野舞星さんによる
水平思考クイズ
第2問ジャカジャン
「4人は仲が良いだけでなく
結婚や家を買うタイミングも
全て同じだった なぜ?」
『4人は家族?』
「いいえ」
『4人は就職のタイミングも同じ?』
「はい」
『4人は車も同じ?』
「はい」
2年生の浅野琉衣さんのスピーチ
今日はこのあと万博を訪れますが
彼女は実は万博2回目
「ネコにあげれる避難食」を商品開発し
以前その販売実習をしました
ネタバレにならない程度に
万博見学のポイントを
レクチャーしてくださいました
2年生の谷内陽斗さんと正角奏音さん
大阪について調べて来てくれました
第3問ジャカジャン
新世界百周年公式キャラは?
①キン肉マン
②サザエさん
③グリコマン
第4問ジャカジャン
次のうちハミゴは?
①イモ
②アメ
③いなり
2年生の小住優太さん
昨年の東北復興研修に続いての参加です
その時得た防災に関する知識を教えてくれました
第5問ジャカジャン
地震が起こった時
とりあえず避難するのに適切な場所は?
①デパート
②木造家屋
③ガソリンスタンド
ファシリテーターの北村篤太郎さんが
満を持しての登場です
全員がオンラインで参加できる
早押し型のクイズを企画しました
今どきの高校生の修学旅行の形ですね
みんなで力を合わせて盛り上げてくれました
午後からは大阪万博
何かヒントになるものがないか
復興の視点で見てきてねと
送り出しました
大屋根リング
閉幕後一部を残すそうですが
撤去する部分を
能登半島地震被災地に
分割して設置してくれないかなと
思っています
輪島では朝市に生まれ変わります
大阪・関西万博を飾った輪が
能登半島を大きく囲む希望の輪となって
残るのです
どうでしょう?
この案
【今日のDeep Purple】
教科を超えた授業実践を紹介し
深い教科横断型授業を作り出すコーナー
2年生の普通コース物理選択者を対象に
物理の岡田成満先生が
「数学」とコラボした
教科横断型授業を行いました
前の授業で
気柱共鳴の実験を行いデータを測定し
今日の授業は
そのデータを処理・分析し検証するものでした
データを分析する上で
「数学I」で学んだ用語を
全員で思いつくままたくさん挙げました
その中から
今日のデータの分析では
「偏差」「分散」「標準偏差」
などを使いました
数学で学んだ内容を確認するとともに
一つひとつの用語の意味を
丁寧に振り返り
データ分析の意義を深く理解します
続けて測定誤差をオーダー(桁数)で検証
3~5名のグループでデータを処理・分析し
①実験で得られた近似値と誤差により
自分たちの実験の成否を評価し
②実験結果とチューナーを用いた測定結果を比較し
誤差が大きくなった場合にはその原因を考察しました
途中で煩雑な計算がありましたが
Chromebookを活用すると
計算処理はスムーズでした
データ処理はChromebookに任せて
人の頭脳で考察・検証することが
生きる力につながります
【夏を詠む】晩夏の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
どうしてこんなにせつないのでしょう
今日は夏の終わりの句を集めてみました
「夏休み 補習の窓に 秋の風」
「すず風の 知らせに夏を 惜しみけり」
「青空に 音なき風が 心ほどく」
クイズの答え
第1問 ③ ロンドン
第2問 4人で人生ゲームをしていたのでした
第3問 ① キン肉マン
第4問 ② アメ
ハミゴとは仲間はずれのこと
おいもさん おいなりさん
アメちゃんだけちゃん付け
第5問 ③ ガソリンスタンド
そもそも危険なガソリンスタンドは
厳しい基準をクリアして造ってあるから
ものが落下してくるなどの恐れがない
イグノーベル賞と春夏コレクション
地震から 632 日目
豪雨から 368 日目
人を笑わせ
そして考えさせる
ユニークで独創的な研究に送られる
イグノーベル賞!
「不名誉な」という意味の「ignoble」と
ノーベル賞(Nobel Prize)を組み合わせた造語です
ネーミングからして洒落てます
「洒落」の「洒」は「酒(さけ)」ではありません
ついでに「祟り(たたり)」も「崇(たかし)」ではありません
もひとつ「柿落とし(こけらおとし)」も
「柿(かき)」とは別の字です
それはさておき
今年のイグノーベル賞に
日本人チームが選ばれました
パチパチ!
賞金はなんと10兆ドル!
今日の為替相場は1ドル148円だから…
と興奮してたら
ドルはドルでも
ジンバブエドルだそうです
全く笑かしてくれます
さて注目の受賞研究はというと
「牛の毛を染めてシマウシにすると
ハエにたかられない」
だそうです
「しょーもな」と笑うなかれ
牛はハエにたかられると
体重が増えにくかったり
お乳の出が悪くなったり
その経済的損失は
かなり深刻なのだそうです
さて高校生諸君
批判的思考力を高めましょう
ここまで読んで
この実験
問題点はないですか?
「ハエは縞模様を嫌ったのではなくて
染料の成分を嫌ってよりつかなかったのでは?」
と気づいた君
素晴らしいです!
実はこの研究グループ
同じ成分の黒染料を使って
見た目縞模様には見えないシマウシも
同時に実験に用いていたのです
これを「対照実験」といいます
これによると
白黒のシマウシはハエにたかられなかったけど
黒黒のシマウシはたかられまくったそうです
明らかにハエは縞模様を嫌っているようです
さてさて高校生諸君
ここで新たな仮説を立ててください
「水玉模様ならどうだろう?」
「縦縞と横縞の違いは?」
などと気づいた君
これまた素晴らしいです!
ところでシマウマって縦縞なの?それとも横縞?
正解は横縞!
えっ?てなりそうですが
シマウマの立場に立って
ボーダーのシャツを着ている気分になると
確かに横縞ですね
もひとつところで
縦縞ボーダーと横縞ボーダー
太って見えるのはどっちだと思いますか?
横縞は太って見える
よく言われていましたが
全く逆ですよ
どうです?
下の横縞の方が
引き締まって見えませんか?
これは
「ヘルムホルフ」の正方形といいます
正方形の中に横縞を入れると
縦長に見えるというものです
これはこれまで平面にのみ言えることと
思われていたのですが
ヨーク大学の研究チームが
立体においても成り立つことを
実験により示しました
これを受けて今年の夏
プラダ
ルイ・ヴィトン
シャネルに
クリスチャン・ディオール
2025春夏コレクションには
全てのブランドに
ボーダーが取り入れられました
【夏を詠む】星祭の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
夏は夜 いとをかし
今日は夜空に輝く句を集めてみました
「夏の夜 空に咲きたる 紅の夢」
「汗ひかる 頬をなぞれる 夜の火花」
光った瞬間
照らされた好きな人の頬の汗が
見えた一瞬を捉えた句ですね
それにしても花火そっちのけで
好きな人の顔ばかり
見つめていたんですね
可愛い句です
「手をつなぐ 音にまぎれて 好きと言う」
これも可愛いですね
面というのは恥ずかしくて
花火の音にまみれて
聞こえるか聞こえないか
言ってみたのかな?
昔聴いた小話を思い出しました
「好きな男を膝枕していた若い娘
気を許した瞬間ぷっ
恥ずかしくて恥ずかしくて
目をつむっていた男が
寝てくれていたらよかったけど
ちょっと試してみよう
『ねえねえおまえさん
さっきウグイスが鳴いたよ
聞こえた?』
『いや聞こえなかったなあ』
よかった寝てたんだ…
『ところでウグイスが鳴いたってのは
屁の前かい?後かい?』」
せっかくの素敵な句なのにごめんなさい
ムードもヘチマもないですね
後生畏るべし
地震から 631 日目
豪雨から 367 日目
タイトルの言葉は
『論語』に出てくる孔子の言葉で
「自分より若い世代は
将来どのような人物になるか計り知れないので
決して侮らず畏敬の念を持って接するべきだ」
という意味の言葉です
若者が持つ無限の可能性を称えるものです
最近は昔の教え子に会うごとに
この言葉の意味をかみしめています
懐かしいお客様
二本松市立東和中学校の 鈴木 直樹 先生です
私の町野高校赴任時代の教え子で
町野高校が第1回の21世紀枠
最終選考全国9校にまで残ったときのエースです
廃校直前たった11人の部員でそこまで残って
絶対選ばれると勝手にワクワクして
甲子園球場に行くときは
大型バスじゃなくてワゴンで充分ですね
ワゴンで甲子園横付けする出場校なんて
これまでないでしょ
なんて妄想ふくらましていました
大学卒業後は福島県で教員をしながら
好きな野球の研究をずっとされていて
多くの論文も残されています
「野球における投手の投球に関する運動技術史的研究」
ーオーバースローにおける「胴体の動き」を中心にしてー
ーオーバースローにおける「バックスイング」を中心にしてー
ーオーバースローにおける「フォワードスイング」を中心にしてー
ーオーバースローにおける「下肢の動き」を中心にしてー
「野球における投手のオーバースローの運動技術史」
ー競技規則との関係からー
「日本におけるアンダースローの運動技術史」
「野球の投手におけるコントロールのコツに関する一考察」
ー技術の定立に向けてー
「野球における投手のオーバースローの構造体系化」
いずれも「スポーツ教育学研究」や
「スポーツ運動学研究」などに掲載されたものです
彼自身高校時代に
オーバースローからサイドスローに転向し
その中で探究の芽が育まれていったのですね
好きなことをとことん突き詰める
これからの時代に大切な力です
生徒にぜひ身につけさせたい力です
【GIS不自由研究】第5回
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に分析する手法を学ぶこのコーナー
今回は「知を作る!」
重ねるレイヤーを自分で検索して探します
「浸水深想定」「浸水推定」「標高」
などをキーワードに洪水災害について
「土砂災害」「警戒区域」
をキーワードに土砂災害について
それぞれ活用可能なデータを作ります
【夏を詠む】夢眠の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
夏の昼寝は至福のひととき
今日は夢見の句を集めてみました
「昼寝して 夢の中まで 夏休み」
夢占いで検索してみました
夏休みの夢を見るということは
自由になる時間を求めているそうです
退屈な日々からの逃避願望の可能性も
日頃から勤勉な人であれば
働き過ぎの赤信号が点滅しています
怠けがちな人であれば
手つかずに放置している課題を片付けるように
と夢が警告しています
「夏休み 呼ばれてもなお 夢のなか」
起きたいのになかなか起きれない夢は
人間関係の変化を暗示しているそうです
嫌々付き合っている人がいるケースが多いとか
何かに対して不満を持っている
ということを暗示している夢でもあるそうです
「気にしない」或いは「知らんふりでやり過ごす」
そうすることで運気が上昇することもあります
「夏の夜 布団に沈み 秒で寝る」
部活動の練習で疲れてバタンキューでしょうか
昼間に思いっきり汗をかくと
暑い夜でもぐっすり眠れていいですね
ところで若い人はバタンキューって
わかりませんよね
「死語の世界は存在する」
モロこの句のような状態を表します
モロも死語か?
気になって調べてみたら
名古屋の方言なのだそうです
未だに「写メ」って言ってる人いませんか?
若い人に「なにそれ?」って言われますよ
芸術の秋スポーツの秋
地震から 630 日目
豪雨から ちょうど1年目
【芸術の秋】
中部航空音楽隊のみなさんが
はるばる静岡からお越しくださり
復興応援演奏会を開いてくださいました
「心の中の一番綺麗な風景と
大切な人のことを思いながら聞いてください」
とアンコールで演奏してくださった
Danny Boy には
込み上げる思いでいっぱいになりました
アイルランド民謡に詩をつけた Danny Boy は
第一次世界大戦中
「生まれ育ったこの場所へ
きっといつか帰っておいで」
出征する我が子への思いを綴った曲です
発災以来
傾いた体育館にずっと寝泊まりして
救助に当たってくださっていた
隊員のみなさんのこと思い出しました
それからその頃にもらった
東日本大震災を経験したお母さんからの
こんなメッセージ
「東日本大震災に襲われたとき
当時2歳だった娘には
その時の記憶がありません
ただひとつ覚えているのが
『真っ暗なお風呂の中に
黄色いアヒルちゃんが浮かんでた』
自衛隊のみなさんが準備してくださった
お風呂の思い出です
壊れた建物
慌てふためく大人たち
そんなものじゃなくて
暖かい思い出を
娘の心に残してくださった
自衛隊のお姉さんたち
本当にありがとうございました」
今日の演奏会も
きっとみなさんの心の中に
残っていくものと思います
【スポーツの秋】
バレーボール部が体験入部を行いました
輪島市内の中学校から
6名の3年生が参加してくれました
輪島中学校には
女子バレー部はありますが男子バレー部がありません
輪島高校には
男子バレー部がありますが女子バレー部はありません
ですので男子は全員初心者からのスタート
女子は続けたくてもできません
そんな中ひとりの女子部員が
マネージャーとして3年間
頑張ってくれました
きっとプレイしたかったろうと思います
でも影でみんなを支えてくれました
本当にけなげで立派な姿でした
とってもセンスあるので
男子に混じっても
決してひけを取らなかった
というより下手すると
一番うまかったかもしれません
40年ほど前
リベロの制度がない時代
全日本女子で広瀬選手っていう
小さな選手がいました
アメリカのハイマンやクロケット
中国の郎平らが放つ強烈スパイクを
とにかく拾いまくっていました
確か男子の中に混じって
レシーブの練習をして
技を磨いたと聞いています
今日は女子バレー部のない東陽中学校から
女の子がひとり参加してくれたので
そのマネージャーの子も
受験勉強の合間を縫って
お手伝いに来てくれました
少子高齢化が進み
部活動の存続が危うくなってくるこれからは
吹奏楽に大編成と小編成があるように
男女混合大会もひとつの選択肢かもしれません
この模様の秘密は明日書きます
キーワードはイグノーベル賞
【GIS不自由研究】第4回
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に分析する手法を学ぶこのコーナー
今回は「データ」
ArcGISのアプリ「Survey123」を用い
重ねたレイヤー上のさまざまな地点において
どんな情報が欲しいかリクエストする
「調査票」をつくります
「調査票」によって集められたデータは
一覧表となって管理されます
【夏を詠む】香味の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
いっぱい食べて元気な夏を
今日は美味しい句を集めてみました
「種飛ばす 黙して笑う 夏の午後」
スイカの種の飛ばしっこですね
スイカを切る時は
皮の縞模様の濃いところに沿って
包丁を入れるといいですよ
種はその線に並んでいるので
切り口に一列に並んで取りやすくなります
「かき氷 食べて後悔 また一口」
ダイエットしてるのかな?
冷たいと甘みを感じにくくなっているので
摂取過多になりやすく
注意が必要ですね
「夏の午後 残る胃の奥 祭味」
お祭りに行って
屋台のおいしいもの
いっぱい食べたんですね
創造的復興サミット in 神戸
地震から 629 日目
豪雨から 365 日目
「創造的復興」
この言葉が生まれた神戸のまちで
今日はサミットが開催されています
会場はポートピアホテル
Portopia, the city of light and waves
ゴダイゴが歌っていましたね
3本の国旗からわかるように
本日はトルコとウクライナからも
発表にいらっしゃいます
朝一番からリハーサル
司会は武庫川女子大付属高校3年生
竹内 舞桜さん
どこかで聞き覚えのある
お名前ではないですか?
夏の甲子園の開会式の司会を務めた方です
素敵な響きの声でした
齋藤 元彦 兵庫県知事からのご挨拶です
「創造的復興」
という言葉を生んだこのまちでは
震災から30年が過ぎ
その記憶を風化させないため
今年から「つなぐ」という
キーワードを追加したそうです
兵庫県立舞子高校のみなさんです
各学年で1週間に8時間ほど
防災に関する授業を行っています
宮城県多賀城高校の災害科学科さん
防災に特化した独特なカリキュラムで
計問的に防災について学んでいます
神戸学院大学のおふたり
阪神・淡路大震災の震源地に
最も近い大学なんだそうです
兵庫県立大学学生災害支援団体LAN のおふたり
先日の新潟での「ぼうさいこくたい」で
ご挨拶させていただきました
東北学院大学 地域総合学部のおふたり
本校からは中村輝人さん
自ら取り組む居場所づくりと
ガイド活動について発表しました
そのあとは発表者全員で
パネルディスカッションを行いました
午後からはサミットです
神戸市立御影北小学校のみなさんによる
『しあわせ運べるように』の合唱で幕を開けます
「傷ついた神戸を もとの姿にもどそう
支えあう心と 明日への 希望を胸に
響きわたれ ぼくたちの歌
生まれ変わる 神戸のまちに
届けたい わたしたちの歌
しあわせ 運べるように」
涙がとめどなく流れてきます
学生からの行動宣言が行われました
防災教育とは
単に学ぶことではなくて
行動に起こすこと
力強い宣言が行われました
石川県から馳浩知事も参加されました
発災時
当時の岸田総理から
「金の心配はするな!
できることは全てやれ!」
との指示を受け取り組んでこられたことを
お話されました
【GIS不自由研究】
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に分析する手法を学ぶこのコーナー
第3回は「ラベル」と「シンボル」
地図上に重ねたレイヤーに
文字を表記させるのが「ラベル」です
例えば「耕作地」レイヤーの
「ラベル」をオンにすると
『田』や『畑』といった
耕作地の活用状況が表示されます
そしてレイヤーの色味や透過度を
調整するのが「シンボル」です
「ラベル」と「シンボル」を
うまく調整して
一目でわかるデータに仕上げるのです
【夏を詠む】空蝉の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
空蝉とは蝉の抜け殻のこと
今日は虫を詠んだ句を集めてみました
「蝉の声 追いかけるよう 泣く子かな」
小さい弟さん妹さんがいるのかな?
それにしても今年はあまりセミが鳴かないなと
勝手に感じていましたが
どうも全国的な傾向であったようですね
急激に暑くなったことと
空梅雨で地面が乾燥し固まって
羽化しにくかったことが原因と
考えられています
「蝉の羽 数えて落ちる 風の中」
過去の文献にも蝉の鳴かない年が見られます
1923年夏は神奈川県橘樹郡登戸村で
1707年は伊勢国萩原で
蝉がまったく鳴かなかった
という記録が残されています
1923年は関東大震災の年で
1707年は宝永地震の年
「蝉が鳴かない年には大地震が起こる」
などと短絡的に考えずに
しっかりデータを集めて
科学的に分析する必要がありそうです
GISの出番ですね
「夜もふけて 蚊に囲まれて 香にまみれ」
これはお見事!というほかありません
なんてテンポのいいリズムでしょう
香(か)とは蚊取り線香の香ですね
蚊取り線香の有効成分はピレトリン
除虫菊(シロバナムシヨケギク)
の花から抽出されます
昆虫の神経系に作用しますが
人に対する毒性は低いです
ただ魚や猫には高い毒性を示すため
飼い主は注意が必要です
震災前の輪島朝市の魚売りも
独特な虫除けの香を焚いていました
その匂いも含めて
懐かしい思い出です
越後を後に山を越え
地震から 628 日目
豪雨から 364 日目
今日は新潟での「商業研究大会」を終え
明日の「創造的復興サミット」のため
山を越え神戸へと来ました
サミットは明日ですが
今日は
「人と防災未来センター」を訪ねました
来週生徒たちが復興研修で訪れることになっていて
その事前研修をオンラインで行いました
副センター長様からご講義をいただいたのですが
生徒の「なんで校長がそこにいるんだ?」感が
おかしかったです
お話の中で心に残ったのは
「災害が起こると時間が10年進む」
今能登半島で起こっている出来事は
もし地震がなかったとしても
10年後には起こっていたこと
という意味です
人工流出や地価下落
10年後の日本の姿を映し出しているのが
今の能登半島です
今
目の前のことに一生懸命取り組んでいる
能登半島の高校生たちは
きっと10年後には
このノウハウを活かして
日本中で活躍しているはずなのです
それを目指してさまざまなことに
挑戦しています
学校では昨日より
地理情報システムGISを用いての
不自由研究が始まっています
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に分析する手法を学びます
イントロダクションに続く第2回は
『マップ』
地図上にさまざまな情報(レイヤー)を
重ね合わせる手法を学びました
重ねる基礎となるベースマップには
「地形図」
「衛星画像」
「起伏図」
「キャンバス」
などがあります
「マップ」アプリでお馴染みですね
さてそこに重ねるレイヤーとして
農林水産省による「耕作地」
基盤地図による「建物」や「標高10m」
国土数値情報による
「河川」やその「流域界」
「学校」やその「校区」
「バス停」や「バスルート」
さまざまなものがあります
地図に情報を重ねるだけで
いろんなことが見えてきて楽しいです
【夏を詠む】灼炎の候
五七五に込めた生徒の夏を
紹介するコーナー
補習も終わりいよいよ夏真っ盛り
今日はそんな頃を謳った句を集めてみました
「夏の風 肌にまとわる 熱の息」
今年の夏も暑かったですね
多くのお嬢さんが持っていた
ハンディ式の扇風機
あれすら熱風が当たるだけから危険
とまで言われていました
「炎天を 食べて笑って 越えにけり」
夏になると無性に食べたくなるものって
ありますよね
子供の頃の夏休みの思い出と
リンクしているものが多いです
みなさんの夏の思い出の食べ物は何ですか?
私は『しただめ』です
「かき氷 勝負のあとに 歯がうなる」
歯に染みるし頭もキーン
この頭キーンは
顔の感覚を司る三叉神経が
冷たさを痛みと勘違いするからです
三叉神経はよく勘違いする神経で
お酒を飲むと
赤くなる人と青くなる人
頭が痛くなる人とそうでない人がいますが
これも三叉神経の勘違いに関係しているといいます
アルコールは体内でアルデヒドに変わります
アルデヒドには血管を拡張させる作用があります
血管が拡張すると顔が赤くなると同時に
三叉神経を刺激します
三叉神経はそれを氷キーン同様痛みと勘違いします
アルデヒドを分解する酵素を持つ人には
それが起こりません
そのかわり次の作用がより大きく現れます
アルコールが脳下垂体後葉に作用すると
バソプレシンというホルモンの分泌が抑制されます
バソプレシンには
血圧を上げる作用があります
分泌が抑制されると血圧が下がり
顔が青ざめることになります
またバソプレシンは抗利尿ホルモンとも呼ばれ
腎臓での水の再吸収を促進して
尿量を減らす作用があります
お酒を飲むとトイレが近くなるのは
これができなくなることによります
ところでかき氷の頭キーン
天然氷よりも人工氷の方が
起こりやすいんだそうです
人工氷は一気に冷やして作るのに対して
天然氷はゆっくり冷やされてできます
すると不純物が入りにくいのです
不純物が混じると凝固点降下という現象が起こり
0℃より低くても溶け始めます
つまり人工氷は
温度が低いまま一気に削らないと
すぐに溶けてしまうのです
このため人工氷から作ったかき氷は
天然氷から作ったものに比べて
温度が低いのです
俳句から
生物や化学への教科横断に繋がりましたね
夏を詠む
地震から 627 日目
豪雨から 363 日目
夏休み俳句コンテスト開催中
生徒玄関に作品を展示してあります
一人ひとりにいろんな夏があったようです
毎日少しずつ紹介します
夏のはじまりに胸躍る
今日はそんな句を紹介します
「夏の海 きらめく先に 七ツ島」
七ツ島は輪島の沖合の小島です
輪島市名舟町に属します
北の島群(大島 狩又島 竜島)と
南の島群(荒三子島 烏帽子島 赤島 御厨島)
からなります
もともとは能登半島と陸続きでしたが
1万4千年前に別れたと考えられています
7つの峰を有し南西部に噴火口のある
大きなひとつの火山であったようです
「天高く馬肥ゆる秋」
夏の湿った太平洋高気圧とは異なり
秋の移動性高気圧は大陸から来る乾いた空気なので
雲のできる高さが高くなります
夏は雲底が2000m程度の積乱雲が中心ですが
秋は5000m付近でようやく高積雲
8000mを超えて巻雲ができるなど
実際に雲の高さが違うのです
それを昔の人は「天高く」と表現したのですね
さらには空気中の水蒸気が少ないと
青い光が散乱されず地表に届くので
空自体の青が深く澄んで見えます
ところでこの
「天高く馬肥ゆる秋」
美味しいもの食べて馬も太るよ
などと呑気な諺ではなく
本来は古代中国で
「北方騎馬民族が肥えた馬に乗って
秋に侵攻してくる」という
敵襲への警戒を促す意味合いで
使われていた物騒なものです
講談社の近藤大介氏は
著書『ほんとうの中国』の中で
多くの国に囲まれ
常に周辺異民族との侵略に晒されていた中国人と
周りを海に囲まれ
侵略から守られてきた日本人では
考え方がまるで違うと指摘なさっています
「常に周りに気を遣って同調しなければならない」
日本社会と
「周りはいつ敵になってもおかしくない」
中国人は
どうも相性が悪いような気がしますが
日本にやってくる多くの中国人は
社会保障制度やセーフティネットが脆弱で
政府や周囲の人間を信用できない
カネだけが唯一の拠り所である
そんな社会に疲弊しているそうです
【科学と歴史】vol.4
20世紀のマッドサイエンティストを紹介し
科学の発展と人類の幸せを考えるコーナー
実は日本にもマッドサイエンティストが存在します
名前は伏せます
先日とあるテレビ番組で
ある歴史上の人物を批判的に描いたところ
その子孫の方から名誉を貶められたと
局が訴えられていたからです
第二次世界大戦中
生物兵器の研究に携わっていた
陸軍731部隊の初代隊長が
捕虜に対して細菌を注射する
生きたまま解剖して感染細胞を取り出す
手足を切断するなどの
人体実験を繰り返したという
記録が残っています
このことは
中国で本日封切りとなる映画
「421」にも描かれているそうです
中国では政権が不安定になってくると
反日感情を煽って国民の目を逸らすのが
常套手段ではありますが
中国が「抗日戦争勝利80年」を謳う今年は
記念式典や軍事パレードが大々的に行われるなど
これまでとは違って穏やかではなさそうです
そんな中
南京での日本兵の残虐を描いた映画「南京大虐殺」
が7月25日に公開されるや空前のヒットとなり
8月15日にはアメリカとカナダでも上映され
中国国民のみならず
全世界に拡がりを見せているそうです
さらには8月8日公開の「東獄島」に続き
本日封切りの「421」
反日三部作ともいうべき作品が揃います
本来7月に封切りされる予定でしたが
中国共産党の意向で
本日に延期されています
9月18日は満州事変の発端となる
柳条湖事件が起こった日で
中国はこの日を「国恥日」としています
「421」のキーワードは
『馬路大』
「マールーター」と読みます
人体実験の実験台にする中国人を
「木材のような扱い」ということで
隠語で「丸太」と呼んでいたそうです
その中国語読みが『馬路大」です
戦争が落とした傷跡は大きいです
80年経っても癒えません
それでも世界中の人が
お互いを認め合って暮らせる社会の実現に向けて
歩みを止めてはいけません
北信越地区商業教育研究大会のため
先々週に引き続き
新潟の朱鷺メッセに来ています
イベント告知
地震から 626 日目
豪雨から 362 日目
本校男子バレー部が体験入部を行います
輪島市の小中学校には男子バレーのチームがないので
全員が初心者です
それでも
Aきらめない
Aいさつできる
Aいされる
みっつのAをモットーに
県ベスト8以上を目指して
頑張っています
9月21日(日)13:00~16:00
本校体育館で行います
希望者は
チラシのQRコード
あるいはこちらのリンクから
お申し込みください
お申し込みのデータをもとに
こちらで傷害保険に加入します
もひとつ耳寄りな情報です
私の尊敬する『口田 圭』氏による
トークライブ「なんやかんやで」
が開催されることとなりました
10月26日(日)15:00 より
金沢市湯涌温泉はCafé Lente において
かつて「ナンチャッテ教師」として
高校で英語の教鞭をとられ
今や
「口だけおじさん」として名を馳せる
口田 圭(くちだ けい)氏による
笑いながらなぜか元気になる
渾身の30分授業が繰り広げられます
ワンドリンクオーダー制ですが
「『おこらいえ』見てきたよ!」
と言っていただけると
店員さんの「怪訝な顔」のサービスがつきます
竹久夢二が生きていたら
きっと最愛の人と訪れたであろうトークショー
秋の湯涌温泉へぜひどうぞ
【科学と歴史】vol.3
20世紀のマッドサイエンティストを紹介し
科学の発展と人類の幸せを考えるコーナー
ハンガリー系アメリカ人数学者
『ノイマン』
ナチス時代にドイツからアメリカに渡りました
現代のコンピュータにつながる
多くの業績を残しましたが
彼が発見した
「爆弾による被害は
地上に落ちる前に
爆発したときの方が大きくなる」
という理論は
広島と長崎に落とされた原子爆弾にも応用されました
また投下の目標地点を選定する際には
「日本国民にとって最も大きな痛手を与えるために
深い文化的意義をもっている場所に落とすべき」と
京都への投下を進言しました
このような側面を持つ彼は
スタンリー・キューブリックによる映画
『博士の異常な愛情』の
主人公のモデルとされています
本当に京都に落とされていたら
今頃の日本はどんな世界だったでしょう
三谷産業さまのお力添えで
本校を会場に
卓球イベントを開催していただけることとなりました
企画運営は
石川県のプロ卓球チーム『金沢ポート』様
本日挨拶に来てくださったのは
執行委員で経営企画部長の 堀 祐巳 様
なんと私の七尾高校時代の教え子でした
久しぶりの再会に驚きです
慶応義塾で化学を学ぶ彼が
教育実習で来たときに
慶応の実験書見せてくれと頼んで
それを参考に
ハイレベル実験書を作ったのを
思い出しました
陸上部が新人戦に向けて出発しました
世界陸上に負けない熱戦を
繰り広げてくれるでしょう
明日から3日間
西部緑地公園陸上競技場で繰り広げられます
ぜひ応援にお越しください
学校では明日〜明後日と
GISを用いての探究学習が行われます
全15回の『不自由研究』の第2〜5回です
GIS(地理情報システム)とは
位置情報に様々なデータを地図上で統合し
視覚的に表示・分析するシステムです
地図上に複数の情報を重ね合わせることで
これまで見えなかったデータ間の関係性や傾向を把握し
効率的な情報管理や業務の最適化を可能にします
商圏分析やインフラ管理など
幅広い分野での応用が可能です
いよいよ明日から実践編です
高校生と一緒に学んでみたい方は
ぜひお越しください
18日(木)は14:00から2時間
19日(金)は 9:30から2時間行います
受講料は無料です
お気軽にお越しください
レモン彗星の日
地震から 625 日目
豪雨から 361 日目
朝日新聞の記事から
AI開発や活用で世界に遅れをとっていることは
政府も認めるところです
総務省の調査によると
個人的に生成AIを使ったことのある人の割合は
日本では27%なのに対し
中国では81%にのぼります
またスタンフォード大の調査では
2024年のAI分野への投資額は
米国が1091億ドルなのに対して
日本は9億ドルと
100分の1にも届きません
経済産業省の推計では
このままでは
海外のデジタルサービスに伴う日本の赤字が
30年後に原油の輸入額を超えるとしています
しかしながら
AIに対する認識が
「AIを使いこなす」から
「AIをパートナーとしてみなす」
に変わってきているところから
日本のAI技術が世界のモデルになる時代が
これからやってくるように思います
さて本日
和歌山大学から
くわ 将倫 客員准教授
此松 昌彦 教授
太田 和良 アドバイザー
のお三方が学校を訪れてくださいました
和歌山大学災害科学・レジリエンス共創センターでは
孤立集落における情報発信システムについて
研究なさっています
和歌山県は半島に位置する
少子高齢化が進む地域として
能登と同じ条件下にあることに加え
近い将来発生が懸念される
南海トラフ地震により
孤立集落が多く発生する危険性があります
今回我々が得た知見をお伝えさせていただきました
また和歌山大学さんでは
内閣府の主導のもと
「Q-ANPI」
の活用にも携わってこられました
これは衛星安否確認システムです
阪神淡路大震災の頃は
ちょうど携帯電話が
東日本大震災の頃は
電子メールが
熊本地震の頃は
インスタなどのサービスが
それぞれ普及し始めた時でした
いずれもその活用が期待されたのですが
電波がなければただの箱
結局最後は避難所を回って安否確認したといいます
今回の能登半島地震も同じ
最も有効な手段は
紙とマジックそしてガムテープでした
「ANPI 」のような安否確認システムの
普及が待たれます
ところでレモン彗星がやってきていますね
今年1月3日に
アメリカ・アリゾナ州の
マウントレモン天文台で発見されました
緑色をした彗星で
10月後半に向けて接近しています
北斗七星のひしゃくの柄を伸ばしていくと
アークトゥルスという
オレンジ色に輝く全天で4番目に明るい星に
ぶつかりますが
その近くに現れます
4等星ぐらいに輝くそうですが
その頃は新月と重なり
観測には最適なようです
さらには流星群とも重なり
1時間に数十個の流れ星も見られるそうなので
天文ファンでなくても
ワクワクなイベントになりそうです
マウントレモンは植物学者のレモンさんが
初めてその山に登頂したことにちなんでいるそうです
なんとも可愛い
そしてちょっとお間抜けなネーミングです
可愛くお間抜けといえば
最近全国的に
可愛くお間抜けな名前の幼稚園が
増えているようです
これは幼稚園の風紀を乱すような子の親は
えてしてそんな名前の幼稚園にやりたがらず
結果として落ち着いて活動できる雰囲気を
保つことができるからだそうです
空気からパンをつくる
地震から 624 日目
豪雨から 360 日目
【科学と歴史】vol.2
20世紀のマッドサイエンティストを紹介し
科学の発展と人類の幸せを考えるコーナー
前回は第二次世界大戦中に活躍した
原子力開発に関わる3人の科学者を紹介しました
今日はもう少し遡って
第一次世界大戦の頃の話をします
ドイツの物理化学者
『ハーバー』
人口増加に伴う食糧危機が叫ばれていた
19世紀末期のヨーロッパでは
アンモニア合成が喫緊の課題でした
カリウム・リンと並んで
植物の成長に欠かせない3元素のひとつ
窒素を含む肥料が不足したからです
特にドイツにおいてそれは深刻でした
それまで窒素肥料は硝石から作っていたのですが
硝石の輸入国チリとの関係が悪化し
手に入らなくなっていたからでした
1902年に同じくドイツのオストワルトが
アンモニアからの硝酸の合成に成功しました
その時用いた白金(プラチナ)の
触媒としての有用性も確認できました
硝酸さえできてしまえば
そこから窒素肥料を作るのは簡単です
あとはアンモニアをどうするか?
アンモニアは窒素と水素の化合物
窒素は空気中にたくさんあります
そこに水素をくっつける方法を
ハーバーは探ります
オストワルトに倣い
白金を触媒として鉄製の装置を用いて
その合成に成功します
しかしその実験には再現性がありませんでした
つまり他の科学者が同じように
白金触媒で実験してもうまくいかないのです
しかしその後ハーバーは
国家予算を受けて数千にも及ぶ触媒を試し
ついにその触媒を探し当てるのです
その触媒とは…
鉄
つまり最初に成功した実験に用いられた
実験装置そのものが触媒だったのです
鉄を触媒にして高温高圧にすると
空気中の窒素から
アンモニアを作ることができるのです
ところがその実験結果に
ネルンストが「測定値がおかしい」と酷評します
ハーバーが行った条件では合成できない
成功させるにはさらに高温高圧条件が必要である
そうすると費用対効果が低く
とてもじゃないが実用化はできない
ちょうどその頃
東京大学を卒業してハーバー研究所に入った
日本人研究者がいました
田丸節郎です
「死ぬほどはたらく人」
とハーバーに言わしめた田丸は
アンモニアの生成熱と反応ガスの比熱を正確に測定し
ハーバーの正しさを証明しました
田丸はハーバー研究所に入る前は
ネルンストの研究所にいましたので
恩師の反論を見事論破したことになります
こんなところにも日本人の繊細で根気強い
研究の成果が生かされているのですね
かくして空気中の窒素をアンモニアに変えて
それを硝酸そして肥料に
つまり空気からパンを作ることに成功したのでした
そのはずでした
ところが硝酸は肥料の原料となると同時に
爆薬の原料ともなるのです
ハーバーの理論が実用化され
実際に硝酸の大量生産が開始されたのが1913年
その翌年1914年にドイツが
フランスやロシアに宣戦布告しているところを見ると
ドイツ国家は国民の飢えへの対策ではなく
軍事への応用を
最初から狙ってのものだったのでしょう
ハーバーがその後
塩素ガスを用いた大量虐殺の研究に手を染めていることを見ても
そのことは明らかです
科学の発展は人々を豊かにします
しかしそれを用いる者が
「命」を蔑ろにした瞬間
それは破滅の道を転げ落ちることを意味します
科学と歴史
地震から 623 日目
豪雨から 359 日目
小松末広球場で高校野球秋の大会です
春の選抜につながる大会です
先発は森 晃大 くん
先制を許しますが…
3回の表23塁のピンチを
渾身のストレートで
4番打者を三振です
その裏
田屋くんのタイムリーで同点に追いつくと
坂本くんのライトオーバーの長打で
さらに2点追加です
スタンドでは
小さな応援団長が大活躍
1年生冨水選手の弟さんたちです
輪島高校にとって
給水タイムの後の6回表は
どうも鬼門のようで
夏の大会に続いての失点で
追いつかれてしまいますが
その裏すかさず
水口くんのタイムリーで突き放します
その後リードを許し
9回にはライトの坂本くんがマウンドに
4番の山田くんに特大ホームランを浴びます
3塁を回るところで
サードの水口くんが
「ナイスバッティング!」
拍手で見送りました
敵味方関係なく
素晴らしいプレイは讃える!
部活動の本来の姿です
あとになって相手の浅井監督から
伺った話です
私はスタンドから
目にすることができなかったのですが
その時冨水監督も
ベンチから拍手を送っていたのだそう
勝利至上主義に走り
生徒を傷つける言葉を浴びせる指導者が
最近問題になっていますが
ぜひ見てもらいたいものです
龍谷 100 002 211 7
輪島 003 001 001 5
グラウンドの修繕は終わりましたが
防球ネットがまだ立たず
打撃練習が全くできていません
それでもできることを
ひとつずつやってきて
私立の強豪相手にここまで戦えました
守備は鍛え上げられていて無失策
素晴らしいプレイが
そこかしこに見られました
未来の授業をつくる力をつけるため
教科横断型の授業を
全員ひとり1回は実施してください
と先生方にお願いしています
科学と歴史は特に親和性が高く
というより
科学の発展そのものが人類の歴史です
今日はそんな科学の歴史の中でも
20世紀が産んだモンスター
マッドサイエンティストについて
まずはユダヤ系アメリカ人物理学者
『オッペンハイマー』
「原爆の父」と呼ばれます
広島長崎に投下する直前の実験では
その成功に満足気だったと伝えられています
戦後に態度を一変させて
核兵器廃絶を熱心に唱える
ようになったところをみると
自らの研究が人殺しに利用されることを
もしかしたら知らされていなかったのかも
しれません
ユダヤ系ハンガリー人物理学者
『テラー』
ナチス時代に
ドイツからアメリカに亡命しています
「アメリカ水爆の父」と呼ばれます
水素爆発を5回起こして掘削し
巨大港湾を建設する
「チャリオット作戦」を計画しましたが
実現には至りませんでした
ソ連のロケット開発指導者
『コロリョフ』
1957年に世界初の
大陸間弾道ミサイル「R-7」を開発し
アメリカを直接攻撃できるようにしました
この技術を現在北朝鮮が利用しています
InterContinental Ballistic Missile(ICBM)です
また彼はこんなことも考えます
「もっと速度を上げれば
もっと遠くに届くはず
もっともっと遠くに飛ばして
ミサイルが落下する時に描く弧が
地球の球面に沿うくらいになれば
永遠に地球の周りを墜ち続けるはず」
世界初の人工衛星「スプートニク1号」
の開発に繋がりました
人工衛星は飛び続けているのではなくて
地球の重力によって
実は墜ち続けているのですね
【科学と歴史】
しばらくシリーズ化して連載します
桃毛
地震から 622 日目
豪雨から 358 日目
チコちゃんが
チョー難しい早口言葉を募集しています
うちの晴れ女が
「今あるので充分難しいわ
生グミ 生ゴミ 生桃毛」
とスラスラとのたまっていました
一個も合っていません
さすが
「親に向かって歯応えするな!」
の豊かな言葉の使い手です
がんばれAI!
地震から 621 日目
豪雨から 357 日目
新しいプロジェクトの名前を
AIに考えてもらいました
さすがAI
瞬時に素敵なネーミングを
いくつも考えてくれました
出してくれたアイデア全てがスマートなのですが
と同時に全てが頭に残りません
ここがAIの限界ですね
どこかで聞いたことのあるような
耳障りのいいフレーズばかりで
新しいものがないのです
やはり時間をかけて自分の頭で考えないと
新しいものは生まれないのだなと思いました
三菱商事などの企業連合が
採算悪化を理由に
国内3海域からの
『洋上風力発電』撤退を表明しています
実は輪島沖にも震災前から設置計画を進めています
半島の先っぽにおいて
海上から安定した電気供給を受けれることは
大変魅力的です
本校では「電検三種」の資格取得を目指して
講座を設けています
このあと設置計画がどうなるかわかりませんが
勉強したことはきっと役に立つはずなので
がんばりましょうね!
NPO法人 RISE様のご協力により
GISシステムを学ぶ講座が
1年生全員を対象に実施されています
全15回のこの講座
今日はその第1回です
復興で終わることなく
世界をリードしよう
ご指導くださる京都大学の林春男先生から
オンラインで力強いエールをいただきました
GISによるデータ共有と相互作用によって
問題解決能力の向上を図る
「総合的な探究の時間」と
「地理総合」の教科横断型の学びです
1年生主任の山本宏行先生より
名人芸のガイダンスです
「GISとは
Geographic Information System
概念そのものは決して新しいものではないのですが
従来の単独目的利用モデルから
相互利用モデルへの転換が図られています
例えば昔の事例
Case1:パソコン素人の店主はじめ社員2名
個人経営のたこ焼き屋 2003年の事例
①たこ焼きができる間に来店客に郵便番号を書いてもらう
②データを委託会社に渡す
③結果から来客の地域を割り出す
Case2:三重県のある温泉旅館
①アンケートは取っていたが集計していなかった
②高評価を市町村別に集計して色分けして地図で見ると
はっきりと地域的傾向が見えた。
③ターゲットエリアを決定し集中して広告を打った
Case3:北海道のある自動車ディーラー
①新型が発表された際には
同じ車種の旧型に乗っている顧客を
GISで検索する
②同車種に乗っている顧客の多いエリアに
集中的に営業をかける
③営業マンが集めてきたお客様の反応を
再度GISにフィードバックする
現在ではマップの上に
お店の情報として
価格やメニューなどのほか混んでる時間帯など
さまざまなデータが重ねられ
あまりにも日常的になりすぎて
どこにその技術が使われているのか
わからないほどです
大谷選手の部屋に張ってあった
武田信玄の言葉です
『真剣だと知恵が出る
中途半端だと愚痴が出る
いい加減だと言い訳ばかり
本気でするからたいていの事はできる
本気でするから何でも面白い
本気でしているから誰かが助けてくれる』
なんでもおもしろがって本気でやろう!」
さよなら いろは橋
地震から 620 日目
豪雨から 356 日目
燃えた朝市通りと
夕市の立つお宮さんを結んでいた
『いろは橋』
昔は緑色の鉄骨の橋でしたが
あるとき
輪島塗りの黒と朱に塗り替えられました
以来多くの観光客が渡り
NHK連続テレビ小説「まれ」では
土屋太鳳さんが自転車で駆け抜けた
市民に親しまれているこの橋
架け替えられることが
先日の市議会で明らかになりました
橋のたもとには
『まれ』記念館がありましたが
火事で焼失してしまいました
奇跡的にスイーツのモニュメントが
残っています
スイーツといえば
大阪万博において
本校生徒が企画した
スイーツの販売が始まりました
ご協力くださったのは
(株)日本旅行様とまねき食品様
私立神戸野田高等学校様と
コラボしました
商品化してくださったのは
神戸を代表する洋菓子店の
(有)菓子工房ボックサン様
期間限定で出品したものが
好評によりレギュラー販売となったものです
現在販売されているものは
輪島高校が作った
「まいもんブルーベリー大福」
野田高校が作った
「淡路レモンの輝きカップスイーツ」
のセット商品です
24日からはメニューが一新され
輪島高校の
「栗とチョコのまいもん大福」
野田高校の
「マスカットの煌めきカップスイーツ」
セットです
輪島高校の商品には
「うま味の塩 能登 わじまの海塩」
野田高校の商品には
「淡路島の藻塩」
がそれぞれ使用されています
それぞれの地方の海の香りの違いを
感じてみてはいかがでしょう
こうして生徒たちはそれぞれ
未来に向けての歩みを
けなげに着実に始めています
ところが・・・
先日発売された『女性自身』に
ショッキングな記事を見つけました
被災地にいると自分の生活で精一杯で
意外と被災地のことを知ることができずにいて
自分自身も初めて耳にしたのですが
石川県の医療費の免除が
6月末で突如打ち切りになっていた
というものです
能登半島地震から1年半
いまだ仮設住宅に住み
生活困窮や病気にあえぐ高齢者に
非情な仕打ち
発災以降
自宅が半壊以上の被害を受けた人には
医療費の窓口負担などが免除される
特別措置がとられていました
国は9月末までの財政支援の継続を決めていますが
免除の継続については
保険組合が決定することになっています
富山県や福井県では
いまも免除が続いているようですが
石川県は財政が逼迫して
継続が困難だと判断したようです
患者アンケートでは
「受診せず我慢する」と28%の方が答え
「がん治療をあきらめる」といった声もあるそうです
東日本大震災の際には
いったん打ち切られた医療費免除が
住民の強い要望を受けて
再開された事例もあるそうです
【ぼうさいこくたいでのであいそのよん】
「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティアのみなさんを
紹介するコーナー
北九州市にある明治学園高等学校
防災減災班のみなさん
"Disaster Prevention Of Meijigakuen”
『DPOMs』さんは
地域の防災意識の向上を目指し活動しています
特にこどもたちに防災意識啓発活動を行っています
輪島高校の『街プロ』グループと
何かいっしょにできるといいね
きゅうきゅうきゅう命
地震から 619 日目
豪雨から 355 日目
多くの方に助けていただいて
今を生かせていただいている
そのことを一日たりとも忘れたことのない日々ですが
今度どこかで何かがあったら
自分に何ができるのか?
問い続けています
まずは防災士の資格を取ろうと考えています
そのためには救急救命講習の受講証明書が必要
私のそれは期限切れになっているということで
講習を受け直してきました
(1)安全を確認します
〇 傷病者の救助の前に自らの安全の確保が第一です
車が通って来ないか
煙が立ちこめていないか
(2)反応を確認します
〇 肩をやさしく叩きながら大きな声で
「大丈夫ですか?」「わかりますか?」
(3)119番通報してAEDを手配します
〇「誰か来て下さい!人が倒れています!」
大きな声で応援を求めます
〇 協力者が駆けつけたら
「あなたは119番へ通報してください」
「あなたはAEDを持ってきて下さい」
と具体的に指示します
〇 119番に電話したら
① 消防か救急か?
② 場所はどこか?
その2点をまず伝えます
傷病者の容態などはあとでいいです
その2点さえ伝えればその時点で
出動できるからです
場所がわからないときは
電柱に町名の表示があります
あるいは自動販売機にも貼ってあります
〇 次に携帯電話をスピーカーモードに切り替えます
両手をフリーにすることで
電話の指示を聞きながら次の処置ができるからです
(4)呼吸を確認します
〇 胸と腹を見て「普段どおりの呼吸」をしているか
10秒以内に判断します
〇 よくわからない場合は心停止と判断します
〇 しゃくりあげるような途切れ途切れの呼吸は
「死戦期呼吸」といって「普段どおりの呼吸」ではありません
(5)胸骨圧迫をします
〇 心停止ではない傷病者に胸骨圧迫をしても
重大な障害が生じることはありません
〇 胸骨圧迫がうまくいかなくて助からなくても
罪に問われることはありません
ですので勇気を持ってしましょう
とはいえ私自身経験がないので自信はありませんが
〇 1分間に100回~120回の速さで30回
両手を重ね両胸の真ん中を
5cmくらい沈むように強く圧迫します
「そうだ おそれないで みんなのために
あいと ゆうきだけが ともだちさ
あ あ アンパンマン やさしいきみは
いけ みんなのゆめ まもるため」
これを歌いながらすると
ちょうどのテンポで32回になります
〇 人工呼吸の技術と意思があれば1秒ずつ2回
これもさっきのアンパンマンのマーチに合わせ
「ちゃーらっ ちゃーらっ ちゃらちゃかちゃんちゃん
ちゃっちゃかちゃんちゃん ちゃっちゃかちゃらちゃん」
間奏部分にぴったりはまります
(6)AEDが届いたら使います
〇 スイッチをオンにさえすれば
あとは機械の指示に従います
ひとりでやるとパニックになりそうですが
何人かで協力しながら行えば
誰にでもできそうです
今回受講した研修は
前もってオンラインで講義部分を受講し
その修了書を持って
実技に臨みます
まさにこれからの教育のヒントになりそうです
知識の伝達はオンラインで充分できますし
いやむしろ
その方が自分のペースで学べて
一時停止や繰り返し再生も自由なので
一斉講義よりも効果がありそうです
学校は
個々がそうやって知識を学んで集まって
それらを融合させて新しいものを産み出すための
場所となっていきそうです
【ぼうさいこくたいでのであいそのさん】
「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティアのみなさんを
紹介するコーナー
株式会社 JX通信社の 井戸 健介 様
市民参加型ニュースアプリ
地域密着型ニュース速報アプリ
AIリスク情報配信サービス
AIビッグデータリスクセンサ
などを開発され
多くの自治体で活用されています
本校の「街プロ」でも取り組んでいる
アプリ開発グループにご助言などいただけると
うれしいです
ことりのさえずりなぜピーチクパーチク?
地震から 618 日目
豪雨から 354 日目
被災地では
住むところをなくし
引っ越さざるを得ない教員が多くいて
全国的に教員の成り手が不足している中
一層教員不足が進んでいます
そんな状況を遠隔授業で解決すべく
県教委では機材を導入してくださいました
家庭科の山上佳織先生が
門前高校と繋いで
輪島高校から授業の配信です
今日は
「命を守るためには
どんな住まいがいいのだろうか」
家の模型を造り
揺れを確認したあと
地震に強い家について
グループでアイデアを出し合いました
門前高校の教室の様子を
モニターで確認でき
高性能のマイクで
教室の後ろの方の生徒のつぶやきも
しっかり配信側まで聞こえてきます
半島の最先端の小さな取り組みが
今後全世界で起こってくる
教員不足の問題への解決策の
糸口となります
まさに世界の最先端
そして未来を見据えています
今日は2回目の授業でしたが
1回目の問題点を踏まえ
格段に良くなっていることを実感できます
私は配信側で視聴していましたが
生徒のつぶやきが英語に聞こえました
マイクの機能または設定に
課題がありそうです
もしかして英語の特性に特化した
設定になっているのでは?
英語は「cap」「cat」「desk」など
子音で終わる単語が多いのですが
日本語で発音すると
「キャッpu」「キャッto」「デスku 」
のように必ず最後に母音がつきます
このことにより
はじめて英語を聞いた江戸っ子たちは
「p」「t」「k」の子音が
やたらと耳についたそうです
「なんでぇ!なんでぇ!毛唐め!
ptkptk
訳のわかんねぇことさえずりやがって」
『さえずる』という言葉は
現在は小鳥の鳴き声に特化して使われますが
当時は訳の分からない言葉を話す
人間に対して使われる言葉でした
ところが江戸っ子は
慣れない子音だけの発音がうまくできず
どうしても母音をつけて発音してしまうのでした
本人はptkptkと
英語っぽく発音しているつもりでも
ピーチクパーチク
と発音してしまいます
これが
小鳥のさえずりを
ピーチクパーチクと表現する
語源となりました
今回使用した機材はアメリカ製です
つまり子音を中心に聞き取り
子音を強調して再生する
おそらくそのように
開発されたのではないかと思います
母音が多くアクセントの少ない平坦な
日本語に特化したシステムが
開発されるといいなと思います
【ぼうさいこくたいでのであいそのに】
「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティアのみなさんを
紹介するコーナー
難民を助ける会 ARR Japan の
山形 真紀 さま
注目すべきは外国人被災者支援です
実は輪島高校避難所にもひとりいました
日本語も英語もできないベトナム人青年
さぞ心細かったことと思います
ポツンとひとり避難所の隅っこに
うずくまっていました
ときおり私も
翻訳機を持って行き
ベトナム語でお話したのですが
そんなに時間を割けるわけもなく・・・
どうなったんだろう?
ずっと気になっています
本校卒業生で早稲田大学名誉教授の 木棚 照一 様
奥様のまり子さまより
書籍の寄贈をいただきました
「80日間世界一周 80万円」
という新聞広告から始まった
世界一周クルーズ
ご自身の船旅の生活を
正確かつ詳細に記録したもので
今後の人生を考えさせてくれる一冊です
照一先生は高校時代
修学旅行をキャンセルして
大学入試の参考書を買われ
自己研鑽に励まれたそうです
後輩たちへの
「能登の復興と勉強に邁進せよ」
というエールとともに
贈っていただきました
図書室や学級文庫そして移動図書館にも
置かせていただきます
またご希望の方には差し上げますので
学校までご連絡ください
芸術の秋 落語の秋
地震から 617 日目
豪雨から 353 日目
ちゃかちゃんりんちゃんりんでんでん
てなわけで
今日は
チャリティー落語の会を催しました
桂 空治 師匠が来てくださいました
落語は想像の芸だそうです
演者が手にするのは扇子と手拭い
それだけで脇差と大太刀を演じ分けたります
それを補うのが観客の想像力
演者と観客が一体となって創り出す
日本の伝統芸能なんですね
もともと落語はお寺の講話だそうです
説法だけだと退屈して
しまいに誰も聞かなくなってしまうところを
あそこんちの熊さんがこんな面白いことしたよ
はっつぁんもこんな間抜けなことを言ってたよ
どんどん膨らんで面白くなったのだそう
教会でみんなが楽しめるゴスペルが生まれたのと
よく似ていますね
本当は月亭方正師匠も
いらっしゃる予定だったのですが
大雨警報のため急遽お越しになれませんでした
お詫びの方正師匠の手拭い
大争奪ジャンケン大会で幕を開けました
まず演じられたのはご存知
「寿限無寿限無五劫の擦り切れ
海砂利水魚の水行末雲来末風来末
食う寝るところに住むところ
やぶら小路のぶら小路
パイポパイポパイポのシューリンガン
シューリンガンのグーリンダイ
グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの
長久命の長助」
私自身フルバージョンで聞いたのははじめて
かと思いきや
実は被災地用にアレンジしてあったのだそうです
子どもを名付ける「お七夜」を「初七日」と間違えるくだりや
長い名前を「お経みたいだねチーン」とやるくだり
古典落語には本来ブラックな笑いがつきものなのですが
そういったものを一切排除して演じてくださいました
細やかな心遣いに感謝です
先日の「ぼうさいこくたい」でお逢いした
林 信太郎 先生から
興味深い情報を教えていただきました
「秋田城址という遺跡がありまして
そこからは平安時代の古文書が発掘されます
漆にゴミが入らないように
入れ物に反古で蓋をした紙は漆付きの紙になります
それが発掘されて
赤外線を当てると字が読めるのだそうです
漆のたいへんな保存性がわかります」
【ぼうさいこくたいでのであいそのいち】
昨日の「ぼうさいこくたい」で出逢った
素敵なボランティア団体の皆さま
一日で紹介しきれなかったので
今日からシリーズで紹介します
兵庫県立大学学生復興支援団体
LANのみなさま
2011年に東日本大震災を機に発足しました
今回の能登半島地震にも
のべ50名以上の学生さんたちが
支援に入ってくださいました
国際商経学部
社会情報学部
理学部
工学部
環境人間学部
看護学部
それぞれの学生さんたちが
それぞれの専門性を活かして
総合的な支援をしてくださっています
また大学院には
減災復興政策研究科が設置されており
誰ひとり取り残さない
社会を作る人の育成を目指し
災害に強い社会づくりに貢献されています
ぼうさいこくたい2025
地震から 616 日目
豪雨から 352 日目
地震 津波 豪雨 台風 噴火 豪雪 竜巻
様々な自然災害の影響を受けやすい環境にある日本
近年の自然災害は激甚化・頻発化しており
南海トラフ地震の発生も懸念されています
これまでに災害が発生するたびに
課題を洗い出し
経験と教訓を踏まえて
災害対応を進化させてきました
行政による「公助」
自分の身は自分で守る「自助」
地域で助け合う「共助」
能登半島地震においても
様々な支援の手を差し伸べていただきました
地域コミュニティやボランティアなど
人的物的両面での事前の備えや連携が重要であることを
身をもって知ることができました
そんな過去の教訓を未来へ伝えるべく
新潟において「ぼうさいこくたい」が開催されています
これまで日本各地で展開されてきたこの大会は
今回で10 回目を迎えます
多くの能登地区支援に入っておられた方々にお逢いして
お礼を申し上げてきました
災害支援団 Gorilla 代表理事の 茅野 匠 様と
環境防災総合政策究機構の 松本 健一 様
行政に止められても突破して支援に入ってくださった
力強い民間のボランティアの方です
https://npohoujin-gorilla.com/
日本ラクテーション・コンサルタント協会の
近藤 望 さま
被災地における
母乳で赤ちゃんを育てる必要のある
ママさんの支援をしていらっしゃいます
日本災害リハビリテーション支援協会の
堂井 真理 さま
高齢者や体に不自由がある方への
災害のフェーズに合わせた
リハビリ支援をしてくださっています
株式会社 Cell-En の代表取締役 COO
山口 直美 さま
環境に優しい自然エネルギー
「微生物発電」を開発なさっています
ぜひ『街プロ』のエネルギーグループに
伴走していただけるとうれしいです
日本地球惑星科学連合の
林 信太郎 様
自然現象 地殻変動 環境変動を研究対象とされており
防災教育小委員会を立ち上げていらっしゃいます
秋田大学の名誉教授でもいらっしゃる林先生は
「世界一おいしい火山の本」を書かれています
https://www.kodomo.go.jp/guide/kids/read/book/book_2012_03.html
昨年度の東北復興研修旅行以来
交流を深めている多賀城高校さん
今回も発表に参加です
生徒さんはテスト期間中ということで
津守先生と石山先生が
来ていらっしゃいました
関西大学 KANDAI DPE の
松井 芳樹 様
次世代を担うこどもたちへの
双方向型でワクワクできる
防災教育を実現しています
本校の「みつばちプロジェクト」に
教えていただけることがありそうです
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/about/pr/topics/2024/10/post_80323.html
災害時に子供を守る最低基準 様
まさかこんなところでお会いするとは!
「ごちゃまるクリニック」の
小浦詩先生と一緒に活躍してくださったみなさんです
https://sites.google.com/view/cpmsnetwork-japan-com/
続きはまたあした
愛子さまが手を振ってくださいました
香川漆器と輪島塗と
地震から 615 日目
豪雨から 351 日目
香川県のお土産やさんを巡ると
漆器が目につきます
輪島同様
漆器の名産地でもあります
AI先生に訊いてみました
「香川漆器は
江戸時代後期に玉楮象谷が
中国や東南アジアの漆技法を研究・融合させて確立した
日本の伝統工芸品です
漆を塗り重ねた上から線彫りして色漆を埋め込む
蒟醤(きんま)をはじめ
存清(ぞんせい)
彫漆(ちょうしつ)
後藤塗(ごとうぬり)
象谷塗(ぞうこくぬり)の5つの伝統技法が特徴です」
なるほど
蒔絵(まきえ)沈金(ちんきん)螺鈿(らでん)が
中心の輪島塗とは
また一味違った魅力がありそうです
漆で絵や紋様を描き
漆が乾かないうちに金粉などを蒔く技法を「蒔絵」
乾いた漆に紋様を彫り
その溝に金粉などを押し込む技法を「沈金」
漆で描いた絵に
貝殻を砕いたかけらなどを貼り付ける技法を「螺鈿」といいます
「漆」はウルシノキの樹液からつくります
化学的には「ウルシオール」 と呼ばれる物質です
採取した樹液を濾過(ろか)したばかりの
「生漆(きうるし)」は
乳白色をしていますが
それを撹拌して水分を飛ばすと
透明な飴色をした
「素黒目漆(すぐろめうるし)」
に変わります
これに鉄粉を加えて
未反応の鉄粉を取り除くと
それこそ漆黒の「黒漆」となります
漆が空気にふれると
その中に含まれるラッカーゼという酵素と
酸素のはたらきによって
網目上の強固な構造の膜に変わります
この膜は
防腐性が高く
酸やアルカリにも強く
さらに抗菌性や抗ウイルス性もあります
この反応は
多湿の状態でよく進むので
雨や雪の多い輪島は
うってつけの環境であるといえます
漆は何層にも塗り重ねられます
30〜40の過程を経て完成します
輪島塗が特に堅牢なのは
さらに秘密があります
それは魔法のパウダー「地の粉(じのこ)」です
下地漆に混ぜ込んで木地に塗り込みます
「地の粉」は
珪藻土を粉砕したものです
珪藻土とは藻類の一種である
ケイソウの殻が堆積してできた岩石で
能登半島は主にこの珪藻土でできているのです
今回の地震で崩落した見附島
あるいは輪島の鴨ケ浦海岸
さらには珠州七輪の産地など
たいへん脆い岩石ではありますが
ガラス質であるため粒子そのものは硬いです
そして微小な孔が無数に開いているため
漆が入り込むと極めて堅牢な下地となるのです
日本ではなんと7000年も昔から
漆を使っていたと考えられています
驚くべき知恵です
この文化を地震なんぞによって
絶やされてたまるかと
輪島塗職人の皆さんは立ち上がっています
四国巡礼
地震から 614 日目
豪雨から 350 日目
四国災害ボランティアネットワーク様主催の
「情報共有会議 in かがわ」
にお招きいただき
災害発生に備える体制の構築について
講演及びパネルディスカッションを
させていただきました
会場は「かがわ国際会議場」
駅前にある複合施設『サンポート』
の6階にあります
窓からは美しい瀬戸内海を望む
素晴らしいロケーションです
講演の後はパネルディスカッションです
パネラーのみなさんは
ヒューマンシールド神戸代表
吉村 誠司 様
阪神淡路大震災から活動を始め
災害支援NGOを立ち上げられた後
全国各地で支援活動を行っていらっしゃいます
今日のステージの最中にも
静岡県で起こった竜巻の支援に来てくれと
依頼が入るほど活躍中です
能登半島地震では
翌日に輪島市に入り
自衛隊と協力して
救助・救援活動をしてくださいました
本校野球部と一緒にも
活動してくださいました
「いい奴らだった!」
とベタ褒めでした
公益財団法人日本財団
寺田 歩 様
ヒューマンシールドさんのような
実働ボランティアに対して
資金的な援助をしてくださっています
香川県議会議員
山本 悟史 様
基本のんびり時々頑固だそうです
香川県では
防災マップの被害想定の見直しを
図っているそうです
高松市議会議員
中村 秀三 様
能登半島地震の経験を活かした
法改正の必要性を訴えてくださいました
高松市社会福祉協議会
兵頭 大祐 様
自分たちの暮らしの復興は自分たちで…
決意の大切さを語ってくださいました
夜には情報交換会も行い
多くの方と交流を深めることができました
災害支援TEAM B-DASH の
藤丸 剛 様
ご自身17歳の時に阪神淡路で被災
以来活動を続け
能登半島地震でも
輪島高校の生徒玄関前に陣を構え
空き家の水道の元栓を全て閉めて回るなど
水道関係の支援をしてくださっていました
遅刻指導の冨水先生の毎朝の
「3分前〜!」
の声が忘れられないと…
私が知らないところで
本当にいろんな方の助けがあってのことだったんだなと
改めて感謝です
南海トラフ地震が起こったら
四国は陸の孤島となり
外部支援が期待できない懸念があります
国の支援や自衛隊は
まずは被害の甚大な大都市に入り
地域には手が回らない懸念があります
自分たちの町は自分たちで
その意識が大切であると
「四国災害ボランティアネットワーク」様は
考えていらっしゃいます
東日本大震災の数日後に
石巻消防署長に任命された星氏による
就任訓話の一節を教えていただきました
「一.当たり前のこと。と判断したものは、報告だけでよい。
一.今一番やってはいけないこと。それは、考えすぎて何もしないこと。
一.想定以外のことばかりの事象ですが、今いる署員で、
何か方法がないか、それぞれ知恵を絞って行動してみてください。
行動を起こしての失敗は、私なり組織で責任を取ります。」
探究から研究へ
地震から 613 日目
豪雨から 349 日目
今日は
関西国際空港とディズニーシーが
誕生した日です
同じ誕生日だったんですね
同じ誕生日パラドクス
AさんとBさんの誕生日が異なる確率は
364/365で99.7%ぐらいです
まず同じ誕生日にはなりません
ではもう一人Cさんが加わり
3人の誕生日が全て異なる確率は
364/365×363/365で
99.1%となります
このように考えていくと
23人になった時点で
その確率は50%を切ります
さらに40人のクラスで全員が違う誕生日になる確率は
およそ11%となります
つまり逆に言うと
40人のクラスで同じ誕生日の組がいる確率は89%
9割方誰かと誰かが同じ誕生日ということになります
意外な感じがしますね
今日は石川県立看護大学で開催された
「探究から研究につなげる初年次教育学会」
に参加しました
今回のシンポジウムの目的は
高校で本格化している探究学習を
大学ではどう捉えるべきか
このことを考えることです
探究学習の目指すもののひとつに
『創造性』『独創性』を育むこと
があります
このことについて
医療関係の方から以前に
このようなことを言われたことがあります
「医療は
過去の知見あるいは臨床データに
基づいて行われるべきものであり
“この薬とこの薬を組み合わせれば
効きそうな気がする"
といった思いつきに基づいた
『創造性』や『独創性』を持った学生は
迷惑この上ない」
実際のところどうなんでしょう?
ドイツの医師ドーマクにまつわる話です
彼は細菌の化学療法を研究していました
レンサ球菌を殺傷する能力を持つ染料を発見しました
レンサ球菌による感染症は当時死に至る病でした
そんな時ドーマクの娘がレンサ球菌感染症に罹患します
他の治療がすべて効果を発揮しない娘に
その染料を投与することを決心します
平たく言えば
死を待つ娘に絵の具を飲ませて治そうという決意です
ただ投薬によって逆に死期を早めることもあります
どんな思いだったでしょう
結果娘は完治するのです
この知見が現在処方されている
サルファ剤の製薬へとつながりました
午後からは
高校生による活動報告がありました
本校からは
「地震被災後における
高齢者の人身の健康支援と
地域のつながりづくり」
2年生の
髙橋惺さん
岩崎月希乃さん
山村百華さんが発表しました
石川県立看護大学さんのご協力のもと
今夏アメリカ医療研修に参加した3人です
たくさんの方に話を聞いていただき
アドバイスや意見をいただきました
奨励賞をいただきました
今朝あんなに高く飛んでいたツバメが
今は低く低く飛んでいます
台風が近づいて来た証拠ですね
昔から「ツバメが低く飛ぶと雨が降る」
と言われます
これは餌になる虫たちが
気圧が低くなると
高く飛べなくなるからです
ちなみに蚊なんかは
気圧の高い秋晴れの日であっても
3階の高さぐらいまでしか
飛べないそうです
ということは
飛行機が飛ぶ時も
雨の日よりも晴れの日の方が
燃費が良いということでしょうか?
石川県の高松から
香川県の高松に向かっています
明日は14:00よりかがわ国際会議場において
「情報共有会議 in かがわ」
にお招きいただき
講演をさせていただく予定です
お世話くださっている
代表の藤井節子さまはじめ
四国災害ボランティアネットワーク様は
本校の避難所においても
足湯のボランティアサービスをしてくださるなど
今回の能登半島地震に
ずっと寄り添ってくださっています
NEVER ENDING SUMMER
地震から 612 日目
豪雨から 348 日目
この暑さホントに終わるんかい
と突っ込みたくなるような毎日ですが
それでも朝の日差しと夜の虫の声に
夏の終わりを感じます
夏の終わりに聴きたい曲は何ですか?
私は杉山清貴&オメガトライブの
NEVER ENDING SUMMER Ⅰ〜Ⅳ です
3枚目のアルバム
NEVER ENDING SUMMER のB面まるごと
(当時はLPというレコードでした)
同じタイトルの4つの曲
1曲ずつ聴いても
それぞれ魅力的な曲ですが
4曲が組曲仕立てになっていて
第1楽章から第4楽章まで
順に聴くとひとつのストーリーになっているのです
ぜひ聴いてみていただきたいです
まずはプロローグ
「きみの肩抱くように街に秋の風」
このメロディーライン覚えておいてください
第1楽章
夏の回想シーンです
ふたりの出逢いそして
ふたりの夏物語
屈託のない笑顔の彼女に惹かれていくのです
第2楽章
夏の終わりとともに
ふたりの関係に微妙な風が…
彼女の笑顔の裏側には
忘れられない過去の恋の傷が・・・
このまま甘えるわけにはいかない
彼の元を去る決心をするのでした
第3楽章
あれから半年が過ぎ
彼の元に彼女からの手紙が届きます
あのときどうして
無理にでも引き留めなかったのか
胸が痛みます
そして最終楽章
ふたりの恋のゆくえは?
そして
エピローグに流れるメロディーラインの意味は?
https://www.youtube.com/watch?v=4gf_6QOB30M
こちらのYouTube 動画が
途中CMが入らなくておすすめです
ただ20分近い曲ですので時間のある時に
スキップや早送り再生をせず
ぜひじっくりと聴いてください
地震に引き続き豪雨災害の大きかった町野地区
災害復興ラジオでみなさんに
安らぎのひとときと情報の提供を
おこなっていらっしゃいます
先日町野出身の宮腰さんといっしょに
出演させていただきました
次回は9月30日出演の予定です
実はこの日
町野地区にある東陽中学校において
高校生がこれまで行ってきた
海外研修の報告会をする予定で
その足でスタジオにお邪魔しようと考えています
今回の出演はポッドキャストにも公開されました
仮校舎の建設もピッチが上がってきました
グラウンドの3分の1を使って建てています
部活動の練習は空いたスペースで行っています
道路に面していますので
球が出て行かないように
野球はバッティング練習を行っていません
何とかしたいということで
防球ネットを建てていただけることとなりました
電柱を立てる関係で
桜を切らなければなりません
枯れかけているものを中心に何本か切ります
せっかくの桜を
というお気持ちもおありかと思いますが
生徒の活動のため
震災後におけるやむを得ない対応ということで
ご理解ください
OECDとの共創で
いつもお世話になっている草野みらいさんが本日
品川区の荏原第五中学校で震災講話をされました
本校卒業生の細谷彩香さんが助太刀いたしました

細谷さんはお正月に遊びに行っていた
おばあちゃんちで被災
道路が寸断され電波もなく孤立状態でした
本校の中で一番最後まで安否がわからなかった生徒です
おばあちゃんちに行ったという友達情報があったので
大丈夫であってくれと望みをかけていたところ
7日目に自力でいくつもの山を越えて学校に顔を出し
なお孤立していたおばあちゃんたちへの
救助のヘリを要請したという
とんでもない経験をもっています
フリートークがとっても上手で
どんな質問にも臨機応変に答えたようです
中学生も飽きずに最後まで聞いたとか
震災を経て強くなったね!
生物の子育て戦略
地震から 611 日目
豪雨から 347 日
定期的に『はなし方講座』を開催していただいている
原田幸子アナさんから
またまた素敵なメールをいただきました
原田さんは小さな生き物がお好きなようで
繊細な観察眼で見つけた
なにげない日常を
ときおりこっそり教えてくださいます
「この1ヶ月くらい
庭に巣を作っている
ニホンヒメグモという
4ミリくらいの小さなクモの
観察をしています
子育てするクモと言われ
子グモがかえった後も
一緒に住んで面倒を見るんです
先日
役目を終えた母さんグモが天に召され・・・
子どもたちが
小さな小さな巣を近くに張って
頑張ってます
子グモは1ミリに満たないので
携帯にマクロレンズを取り付けて撮影します
こんな小さな中にも宇宙がある
そんなふうに感じます
写真は
オレンジ色の母ちゃんグモが
獲物(黒い虫)を捉え
それを隠れ家の葉っぱから見守る
子グモ達(黄色いつぶつぶ)
可愛いです」
「ファーブル姉さん昆虫記」
よければ連載化しますので
また情報お待ちしています
さてさて学校の方はというと
新学期が始まりました
まずは始業式
蒸し風呂のような体育館に集まるのもな
って感じでオンライン始業式です
カメラに向かって
「みんなどんな夏休みだった?
校長先生は韓国へ行ってきたよ」と
お土産をひとつひとつ紹介して
抽選で希望者に配ることにしました
生徒玄関に応募BOXを設置したら
あっという間に満杯に
ノリのいい子たちです
夏休み中
いろんな方が訪ねて来てくださいましたが
みなさん口を揃えておっしゃるのが
「生徒さんが元気に挨拶してくれて気持ちいい」
そして12年生は課題テストです

3年生は課題テストなんかなくても
勉強するだろうということで
さっそく授業の開始です
伊奈岡先生の生物にお邪魔しました
伊奈岡先生は魚が大好き
輪島高校の「さかなくん」です
とっても面白くて思わず教室に乱入しました
生存曲線の話です
生物には「早死形」「平均型」「晩死型」の3つがあるとか
生まれてすぐに他の生物に捕食される「早死型」
魚類や両生類がこの型です
生まれた個体がほとんど捕食されず
多くが天寿を全うするのが「晩死型」
大型哺乳類や社会的昆虫がこの型です
そしてその中間が「平均型」です
ここで伊奈岡先生からいい問いが…
「ネズミはどれかな?」
生徒らはディスカッションの上
自分たちはなぜそう判断したのかも含め
発表し合います
ネズミは一度に5〜6匹の子を産みます
そこに妊娠期間の長さなどの
データを組み合わせると
どの型なのか正解に近づけそうです
単に「ネズミは平均型です」
と知識の一方的な伝達ではなく
生徒の思考のプロセスを大切にする
最近の授業スタイルでした
ではさっきの原田さんの
ニホンヒメグモの生体曲線を描いてみなさい
こんな質問もありですよね
さらに伊奈岡先生の授業では
シュモクザメの話に
ニモにも登場する
頭がトンカチみたいなアレです
魚のくせに卵じゃなく赤ちゃんを産みます
一度に30匹くらいの赤ちゃんを産みます
痛くないんかな?
鼻から地球が出るくらい痛そう
実際には頭の出っ張りは
柔らかいようです
しかも尻尾から出てきます
人間でいうと「逆子」です
タツノオトシゴも独特です
メスがオスのお腹の中に
卵を産みつけます
オスはそこに自分で精子をかけて受精させ
お腹の中で子を育てます
「イクメン」ならぬ「イクギョ」です
「する」「やる」問題 続編
地震から 610 日目
豪雨から 346 日目
先日議論した「する」「やる」問題
うちの三女から新しい知見が
「やる気」とはよく言うけど
「する気」とはあまり言わないから
本人の意思の強さの問題では?
なるほど確かに
否定文にするとさらに明らかに
「やる気が出ない」ですが
「する気がしない」ですもんね
マイケル君からも新たな知見が
スポーツは全て play を使えばいいものではない
観客を楽しませることに主眼をおく種目は play だが
自己を高めることを主眼とするものは do だ
play baseball と do karate
なんだそうです
楽器の場合
play the guitar
なぜtheが入るのか尋ねると
play guitar
も言うよと
ただし
the が入るとまさに実際に演奏するイメージ
入らないと
「ギターやってます」みたいな
たしなんでます感があるそうです
「引き寄せ」の法則
地震から 609 日目
豪雨から 345 日目
藤井節子さまはじめ
四国災害ボランティアネットワーク様の
お招きにより
今週末に高松で講演会をさせていただきます
金沢から高松まで4つの列車を乗り継ぎます
乗り継ぎが4回を超えると
インターネットでの購入ができないみたいで
金沢駅へ直接購入に
するとそこで出会ったのが
昨日まで文化祭に来てくださっていた
Global Bishow Academy の
庄司真由美さま
佐藤ひろ美さま
沼田祐子さま
気功ヒーリングをしてくださっていました
昨日は本当にたくさんの支援の方に入っていただいて
みなさんにご挨拶することができませんでした
この場を借りてお礼申し上げます
こんな場所でこんな時間に
ピンポイントでお会いできるなんて
「引き寄せ」でしょうかね
なんて話をさせていただきました
復興ガイドツアーの
ボランティア活動に参加しています
今日は自主練習会が行われました
メンバーは20名ちょっと
今後現地でのリハーサルのあと
実際にお客様の受け入れが始まります
私がここに顔を出している理由はふたつ
(1)高校生によるインバウンドガイド
(2)防災学習を兼ねた修学旅行受け入れ
本校からは岡本夕佳先生も参加しています
校長の野望をよく理解してくださってます
【見ようによっちゃ写真展】のコーナー
『お母さんとお父さんに甘える赤ちゃん犬』
ようこそ!りんちゃん
地震から 608 日目
豪雨から 344 日目
野々市明倫高校のみなさんが
文化祭に来てくださいました
マスコットのりんちゃんも
一緒です
倫高と輪高
「りんこう」繋がりです
輪高が初任だった池田先生
昨年一年間助けに来てくださった坂下先生が
連れてきてくださいました
みなさん希望して参加してくださったそうです
被災地に心を寄せてくださる
優しい生徒さんたちです
ありがとうございます
そのほか文化祭情報はこちら
「輪高生の活動記録」をどうぞ
スクールサポートスタッフの福谷さんが
心を込めて作ってくださっています
「する」のと「やる」のとどう違う?
地震から 607 日目
豪雨から 343 日目
8月26日付けのブログでご紹介した
万博会場で販売していた
オリジナルスイーツ
本来100食の限定販売だったのですが
大好評のため
期間中のレギュラー販売が決まりました
「まいもんブルーベリー大福と
淡路レモンの輝きカップスイーツ」
第2弾が販売開始される9月24日の前まで
まねき食品さんが運営している
「MANEKI FUTURESTUDIO JAPAN」
で継続販売されます
どうぞお買い求めください
Assistant Language Teacher(ALT)
のマイケル先生から
Why Japanese?な質問が…
「する」と「やる」の違いは何ですか?
考えたこともなかったけど
確かに言われてみれば…
少し考えさせてくれと宿題にしてもらいました
どちらも英語で言うとdo
でも英語では日本語ほど頻繁にdoは登場しません
例えば
「勉強する」は do を使わず1語でstudy
「野球をする」は do を使いもせず play
英語ネイティブの方にとって
確かに謎ですね
そこで徹底研究です
「勉強する」は言うけど
「勉強やる」はあまり言いません
「運動する」と「運動やる」も同じです
学校での行為が「する」?
「宿題」は?
「宿題でもやろっかな?」
「やる」の方が自然です
でも親の立場だと
「宿題しなさい!」
疑問文だと「宿題やったの?」
ますますわからん
視点を変えましょう
「する」は使うけど「やる」は使わない言葉
◯会話する × 会話やる
◯約束する × 約束やる
◯旅行する × 旅行やる
◯食事する × 食事やる
◯休憩する × 休憩やる
圧倒的に「する」派が多いですね
では逆は?
あんまり思いつきませんが…
あった!
◯クスリをやる × クスリをする
非合法的なのが「やる」か?
◯人殺しをする × 人殺しをやる
ダメだこりゃ
△盗みをする △盗みをやる
盗みははたらくものです
Why Japanese?
マイケル先生が言うには
「する」よりも「やる」方が
強い意志を感じるのだそうです
では
「する」「やる」
どちらも使える言葉でニュアンス比べ
「掃除する」と「掃除やる」
先生は「掃除しなさい」
友達同士だと「掃除やろうぜ」と言うと
すすんでする感が出ますが
「掃除しようぜ」だと
言われて渋々やる感が出ませんか?
自主性の違いか?
「ゲームする」と「ゲームやる」
こちらも友達同士だと
「ゲームやる」の方が何だか自然
「する」はフォーマルな感じで
「やる」はくだけた感じ?
「音楽やってます」はどうでしょう
たしなんでます感がありますね
「お茶やっています」は
お茶を習っていますになりますが
「お茶しています」は
喫茶店で休んでいますになります
結局こねくり回した結果
ますますわからなくなっただけでした
明日マイケルになんて説明してあげよう?
困った
明日文化祭では模擬店をしています
明日文化祭では模擬店をやっています
前者はスイーツ屋さんぽくて
後者はたこ焼き屋っぽいですね
お上品派と庶民派か
本校では今日から文化祭をやっています
その様子は
「輪高生の活動記録ブログ」
のコーナーに掲載やってあります
是非チェックやってみてください
被災者を一番苦しめているものは?
地震から 606 日目
豪雨から 342 日目
「国が認めないなら腹を切る!」
時は平成の時代
火山活動が数年続き
40名を超える死者が出た
雲仙・普賢岳の災害対応での
当時の鐘ヶ江島原市長の言葉です
火砕流の恐れがあるとして
法に基づき立入を禁止する
「警戒区域」を全国で初めて導入しました
「出て行け」と命じられた住民に対して
何の保障もありませんでした
国は「自主再建が原則」の一点張り
思い詰めた市長が実際に口にした言葉
県幹部があわててその場は諌めましたが
その後市長が戦い続けて
それでようやく
国が財政的に支援するしくみが
つくられたそうです
国が出て行けと言っておきながら
何の保障もないというのは
どう考えてもおかしなことです
そのおかしなことが
輪島でも現在実際に起こっています
地震で土砂崩れのある稲舟地区は
立入禁止区域となっています
「いつになったら水道が復旧するのですか?」
「立入禁止なので復旧の予定はありません」
「私の家は一部損壊で何とか住めるので
水道がなくても帰ります」
「立入禁止なのでそれはできません」
「では仮設住宅を申し込ませてください」
「仮設住宅は半壊以上の方でないと入れません」
「ではどうすれば…」
「ご自分でアパートを探してください」
「このへんにはありません」
「金沢の方に行けばあるでしょう」
「家賃の補助などはあるのでしょうか?」
「みなしアパートの補助は2年間なので
それ以降は自己負担となります」
これは実際のやりとりです
復興を最も妨げているのは『法律』
被災民を今でも苦しめ続けているのも『法律』
こんな話をさせていただく機会を
ある大学さんからいただきました
同じ石川県内であっても
「もうだいぶ復興進んだんでしょ」
という認識の方が多い中
県外の大学なのに
このような取り組みをしてくださり
そしてそこにわざわざ
聴きに集まってくださる方がいらっしゃることに
感謝の気持ちしかありません
精一杯準備をして臨んだ講演
後ろの方の席に
ずっとうつむいている学生がひとり
「私の講義スタイルは壇上からではなく
聞いてくださる方と同じ目線で行います」
と適当なことを言って客席に降ります
徐々にその学生との距離を詰めますが
一向に前を向く気配もなく
ついに彼の目の前にたっても
ゲームをやめる気配はありません
「ゲームをしたければ外でやってください」
退出を促しましたがそのまま
壇上に戻りましたが
その時頭の中に浮かんできたのは
傾いた校舎の中で
それでもしっかり前を向いて
授業に取り組んでいる
輪島高校の生徒の姿
そしてこれまでこのブログには
決して書くまいと決めていた負の側面
不誠実な一部行政の対応
被災地の生徒を番組作りに利用する一部マスコミ
そういったものが一気に押し寄せてきて
10分ほど壇上で黙り込んでしまいました
時間にして数分だったかもしれません
でも自分にはそれだけ長い時間に感じました
これまでに何人も
居眠りする生徒や内職する生徒
しまいには教室を飛び出す生徒など
山ほど相手してきました
だけど今回は特別でした
その後の講演で何を話したか
パネルディスカッションで
どんなやりとりをしたのか
全く覚えていません
「6秒我慢すれば怒りは通り過ぎる」
アンガーマネジメントでよく言われますが
嘘です
そんなもんじゃ本当の怒りは収まりません
いや収まってあの程度だったのかもしれません
せっかく招いてくださった大学さん
集まってくださったみなさんに
本当に申し訳ないことをしました
役目を終え
帰ろうとすると
さっきの学生さんがわざわざ待っていて
「すみませんでした」
と頭を下げてくれました
自分のしたことの意味をしっかり受け止めて
誠実に謝罪できる彼の姿に
この国の明るい未来を見ることができました
私は常日頃先生方には
「授業中寝る生徒は悪くありません
寝たくなるような授業しかできない
教員が悪いのです
授業の技術を磨いてください」
と言っています
今回も彼は悪くありません
ゲームよりもつまらない話しかできなかった
私の未熟さです
私の命の講義はゲームに負けたのです
私の怒りの本質はそこにあるのです
頼まれごとは試されごと
地震から 605 日目
豪雨から 341 日目
タイトルの言葉は
本校野球部監督
いつも真っ赤っかの服を着ている
燃える男冨水諒一先生から教わった言葉です
ちなみにニホンザルの学名は
「マカカ ファスカタ」といいます
お猿のお尻は真っ赤っかだから?
「マカカ リョーイチ」の言う
「頼まれごとは試されごと」とは
誰かにお願いをされた時は
「面倒くさいな」と思うのではなく
自分が試されていると思うことです
「おっ!今頼み事をしましたね!
おいらを試してますね!
よっしゃ!そんなら
頼まれている以上のことをして差し上げて
驚かせてやりやしょう!」
この心意気です
今被災した奥能登公立高校5校では
創造的復興に関する探究活動に
力を入れています
探究アドバイザーを派遣してくださるなど
県教委も全面的に
バックアップしてくださっています
探究アドバイザー派遣事業の主旨に関する文書が
県教委から送られてきて
全職員に配布の上読み上げるように
との指示です
それだけ重要な文書です
さあさあ来ましたよ
「頼まれごとは試されごと」
「上から降ってきた復興計画には
そのまま乗っかるな!」
常日頃生徒に伝えている立場上
そのまま伝える訳にはいきません
「そのまま乗っかるな」
のアクセントは
「乗っかるな」ではなく
「そのまま」にあります
県教委の真意は何か?
「全員に周知徹底せよ」
であって
「棒読みせよ」
ではないはずです
読み上げはやめました
時間の無駄です
本校の探究活動を推進している
ふたつの部署の4人の女性教諭
通称「四人官女」のひとりが
AIに読み込ませて音声データを
作ってくれると同時に
要約文も作ってくれました
これを全員に配信し
朝礼では
県教委からの文書の行間を
校長自らの言葉で語りました
もともと話すのが苦手でしどろもどろでしたが
一生懸命であることだけは伝わった
と勝手に思うことにしています
実はこれは
若い担任の先生に見せたかった姿であって
つまり毎朝の伝達事項をただ伝えるだけではなく
そこに担任としての自分の思いを込めて
伝えて欲しいということです
それこそがAIにはできない
新しい時代の教師像だと思うのです
三重県津市にある
高田中・高等学校の柔道部の生徒さんが
尋ねてきてくださり
本校の野球部員と交流会を行いました
久居ライオンズクラブの皆様が
橋渡しをしてくださいました
① マカカ・リョウイチより震災当時のお話
② 久居ライオンズクラブの池田様からのお話
③ グループを作り野球部員からの震災当時のお話
④ 学校施設の見学
高田高校の生徒さんからは
「震災後に避難した人の家に盗みが入ることなど
想像していなかったお話をたくさん聞かせていただいた
自分が経験したわけではないが
もし災害に遭ったらこのお話を生かしていきます」
という感想がありました
輪島高校の生徒からは
「今まで自分が被災した経験を
人に話したことはありませんでしたが
自分の経験したことを人に伝えていくことが
防災や減災に繋がるのではないかと
感じることができました
今後もこのような機会があれば
積極的に関わっていきたいです
それが支援してくれた方々に対する
恩返しにもなると感じました」
という感想がありました
細かなご案内いっぱい・・・
地震から 604 日目
豪雨から 340 日目
【軽トラ市】
8月31日(日)
昨年本校の文化祭にもお越しくださった軽トラ市さん
今年も輪島市に来てくださいます
ただし会場は本校ではありませんので
お気をつけてください
「復興輪島朝市×全国軽トラ市in輪島」は
マリンタウンにて開催です
「災害対策車」も出店されます
【木陰の物語展】
8月29日(金)~30日(土)
本校文化祭において
家族心理臨床家で漫画家でいらっしゃる
団 士郎 氏の漫画の掛け軸が
1階生徒玄関前にて展示されます
【万博でのスイーツ販売】
8月27日(水)~28日(木)
「まねき食品」さんのご協力のもと
神戸野田高校さんと共同開発した
オリジナルスイーツの販売を
万博会場にて行います
「未来社会の創造」を目指して
復興30年目の神戸の高校生と
復興半ばの輪島の高校生とが
オンライン交流しながら企画開発してきました
第1弾は
「まいもんブルーベリー大福と
淡路レモンの輝きカップスイーツ」
会場内の
「MANEKI FUTURESTUDIO JAPAN」において
27日14:00よりプレス発表
28日 9:00より販売を開始します
販売するのは
2年生の浦さん 前川さん 小岩さん 竹内さんです
提供される器は
田谷漆器店さまの輪島塗が使用されます
日本旅行様のご協力をいただいております
【オンライン授業の準備】
2学期より
本校と門前高校との間で
オンライン授業の実証実験が行われます
今後
全国そして全世界において
深刻化してくる教員不足の問題
その解決のためのひとつとして
オンラインによる授業実践があります
世界に先駆けて行います
県教委の協力のもと
機材が運び込まれまれ設置されました
門前高校との間で通信テストです
音声もクリアだし
ズームや資料提示のオプションも豊富です
あとは使う側
つまり教員と生徒がいかに活用するかに
フォーカスされます
本当に指導力のある優秀な教員が
厳選された教材を用いて行えば
全国一斉に地域格差なく
レベルの高い
しかも個々の習熟度に応じた授業を
地震などの自然災害時においても
学びを止めることなく提供できる
未来のコンテンツとしての
可能性を大いに秘めています
しかしながら
受ける生徒の意識が低いと
受け手側に生活指導力のある
教員を配置する必要が生じ
本末転倒となります
100年を超える高校野球の歴史の中で
甲子園で最も多い球数を投げたのは
ハンカチ王子こと早稲田実業の斎藤佑樹投手です
948球をひとりで投げ抜きましたが
そのときのことをこう語っていらっしゃいます
「この集中力は部活動だけではなかなか身につかない
学校の勉強を頑張ることで身につけることができた」
早実だから自分は成長できたのだと思います」
早実の授業には
「野球部だから授業を適当に受けてよい
野球さえしっかりしていればいい」
という空気は全くないそうです
大会直前のテスト期間中であっても
他の生徒と同じで練習は禁止
そうして迎えた大会で
大会直前までテストだろうが関係なく
ガンガン練習していたチームを
撃破したわけです
どれだけ恵まれた機材で
すばらしい授業を配信しても
それを受ける側の生徒が
目の前に先生がいないからといって
いい加減な受け方をしていたのでは
部活動においても
どんなに恵まれた環境とスタッフで練習できても
大事な試合で力を発揮することは到底できません
リスクマネジメント
地震から 603 日目
豪雨から 339 日目
今日は
保護者対応に関する職員研修を
行いました
主催してくださったのは
リスクマネジメント推進機構様
学校危機管理に特化した唯一の専門機関です
会員になると
ありとあらゆる学校が直面する危機に
適切なアドバイスと支援をいただけます
私自身も会員で
これまで何度となく助けていただいています
安全安心で明るい学校を実現するために
学校や先生方を支援してくださいます
まずは学校で生じる可能性のある危機の
「発生頻度を少なくすること」
そして危機が発生してしまった後の
「ダメージを少なくすること」
を専門知識と経験でフォローしてくださいます
今回はオンラインで
保護者対応について学びました
いじめや不登校
解決したいのは保護者も教師も同じ
しかし学校側の初期対応がまずいと
保護者の不信感を募らせます
そうならないための
保護者との対応の仕方を学びました
一般企業では
クレームは宝の山と言われます
誠意を込めて対応すれば
その方は最大の協力者になってくださるからです
とは言え
悪意のあるクレーマーも
存在するのは事実です
総会屋にように
会を扇動し炎上させ
学校を攻撃の的とするのです
そんなとき防波堤の役割も
推進機構さんは果たしてくださいます
防波堤と言えば
先日訪れた仙台大学の帰りに立ち寄った
松島海岸
大小様々な島々が
天然の防波堤となって
松島を守ってくださったそうです
講演の最後に髙橋教頭先生から
「困った親というのは
実は困っている親なんだ」
との言葉がみなさんに送られました
旅はみちづれ
地震から 602 日目
豪雨から 338 日目
旅にはアクシデントがつきもので
昨日仙台大学での生徒発表を見た後
今日少し観光をして
戻るつもりではあったのですが
東北新幹線の故障により
仙台駅で足止めされています
いろいろあるもんです
現在16時ですが
復旧の目処が立っていません
ポルトガル研修旅行での
大規模停電による
シャルル・ド・ゴール空港での一件を
思い出します
あの時5時間ほど飛行機の中で缶詰
結局欠航が決まり
全員冷静に飛行機を降りたのですが
その時パリで流行ったジョークです
「乗客は全員日本人だったらしいぞ」
ヨーロッパでこんな事故が起こると
必ずと言っていいほど暴動になるのが
この時奇跡的に何事も起こらなかったことへの
パリ市民の驚きを込めたジョークです
東日本大震災の時に見せた
みんなが整然と物資を受け取り
そして分け合っている姿が
世界中における日本人のイメージなのです
あの時に比べれば
今回は言葉も通じるし
他のお客様も冷静に待っているし
のんびり復旧を待つこととします
今回の旅行記でも書いて待ちましょう
昨日生徒の発表を見届けたあと
蔵王まで足を伸ばしてみました
蔵王は
山形県と宮城県の県境に位置する
「蔵王連峰」の総称です
美しい景観が楽しめる山岳観光道路
「蔵王エコーライン」
そこから分岐して
ダイナミックな風景を楽しみながら
頂上を目指す観光有料道路
「蔵王ハイライン」
乗り継いでたどり着いた『御釜』は
エメラルドグリーンに輝く神秘の湖です
噴火の際には湖底の温度が
100℃以上になるそうです
14:57発のはやぶさ22号東京行きが
17:20に出発する目処が立ちました
現時点で2時間23分遅れ
こんな混乱の中でも
冷静に運行ダイヤの変更を行い
整然と乗客を誘導する職員の皆さん
その判断力・実行力・チームワークに
心から敬意を表します
日本人って本当に素晴らしいなと
ひとり勝手に感動しています
続いて
15:44発のやまびこ146号東京行きが
17:54に出発します
各駅停車に変更しての運行です
この時点で2時間10分遅れ
自分が乗る予定だったのは
16:31発のこまち28号
秋田から来て
はやぶさ28号に接続する予定でしたが
それが来ません
仕方ないのでデッキに立っているつもりで
はやぶさ28号に飛び乗りました
同じことを考えている人が大勢いらっしゃって
それでも乗り切れない方もたくさん
飛び乗った車両はグランクラス
入口でそれ以上の進入を制されました
ホームで乗せてくれと叫ぶ乗客と
グランクラスでゆったりと寛ぐお客様
その狭間にいた私は
被災地で苦しむ人と
それに関心を示さない一部の人に重なって見え
井上陽水さんの「傘がない」が
頭の中を巡るのでした
結局駅員さんは
グランクラスの通路に立たせてくださる
決断をしてくださいました
非常時における適切な判断だったと思います
ただ高い運賃を支払っていらっしゃる方にとっては
さぞ不愉快であったことと思います
「グランクラスの意味がねえじゃねえか!」
と文句を言う人
「この貧乏人めが」
といいたげな目で睨む人も実際に
ただそんな中で
「大変ね」と優しく声をかけてくださる方も
ご自分の肘掛けに腰かけていいよとまで
おっしゃってくださいました
さすがにそこまではと遠慮しましたが
非常時に本当の人間性が見えるものだと
再確認できました
JRの方々も一生懸命でした
非常時にはみんなが少しずつ我慢すれば
ひとりでも多くの人が
少しずつしあわせになれます
どうかクレームを言うことは
やめていただければと思います
後になって分かったのですが
秋田新幹線『こまち』が来なかったのは
故障とは別の理由で
クマをはねたからだったようです
今日は珍しい新幹線事故を
ダブルで同時に体験できたわけです
何だかとんでもなく
いいことが起こりそうな気がします
今日も全国のあちこちで
地震から 601 日目
豪雨から 337 日目
今日も生徒たちは全国を飛び回って
被災地の現状を伝えています
【高校生ボランティア・アワード2025全国大会】
主催は「風に立つライオン基金」様
若き日の柴田紘一郎医師をモデルに
「風に立つライオン」を作曲したさだまさしさんは
2015年に映画化された際に映画のロケに同行し
初めて踏んだケニアの地での
献身的に活動する日本人女性医師との邂逅を機に
「途上国や被災地で頑張る
『偉大な志=風に立つライオン』を応援したい」
と同基金を設立されました
今回は
全国から108団体の応募があり
その中で本校が選ばれ
「ブース発表」させていただけることとなりました
中村輝人さんと
左手(さて)ナタコーンさんが発表します
高校を休学してオーストラリアで暮らしていた
中村さんは今回の震災を機に急きょ帰国して復学
その後高校に籍を置きながら
被災地復興のために
自ら被災地視察ツアー団体を立ち上げ
被災地の現状を発信し続けています
左手さんも中村さんに賛同して
幼少時代に故郷のタイで見た
海辺の野外映画館が忘れられず
被災地のみんなを励まそうと
自ら映画会を開催するなど
活動を続けています
ふたりは23〜24日の両日
新宿住友ビル三角広場において
ブース発表をしています
ぜひお越しください
【SDGs防災セミナー】
主催者は仙台大学さん
昨年「震災復興東北研修」で生徒が訪れたとき
学校あげてお迎えしてくださり
激励して送り出してくださった
多賀城高校さん
そちらで長年教鞭をとられた後
退職され仙台大学に移られた
小野敬弘 元校長先生が中心となって
企画運営された
地域防災人材育成プログラムの一環です
今回は輪島高校と多賀城高校さんのほか
阪神淡路大震災を経験された
兵庫県立舞子高校さんも参加され
災害の教訓を伝承していくことの大切さを
再確認しました
本校からは川口はるひさん 小住優大さんが参加
◯ 長期化している復旧の様子
◯ 復興への取り組み
◯ そして未来に目を向ける『街プロ』
についてプレゼンしました
会場で目立ったのは
おじいちゃんおばあちゃんの姿
東日本大震災の教訓を後世に伝えていく
何年も過ぎているにも関わらず
その意識の高さに驚きました
出来杉くんからのび太の時代へ
地震から 600 日目
豪雨から 336 日目
新しい時代の教育とは?
大切になってくるそのひとつは
学校の外に出て社会といかに関わるか?
AIはそのためのツールです
IQ( Intelligence Quotient )から
SQ( Society Quotient )へ
出来杉くんから
のび太の時代へ
テクノロジーの進化に対して
それを楽しめる人と恐怖を感じる人がいます
時代に求められる方はどちらか?
答えは明白です
そんな人材を育成すべく
OECD(経済協力開発機構)の支援のもと
明石にある青楓館高等学院さんと協力して
学校をまたいだ部活動『AI部』を展開しています
そこでは学校が社会や企業の協力を得ながら
① 原体験をつくること
② 持続できる環境を整えること
③ 目標を持たせること
を目指しています
防災分野でのAI活用について
衆議院第一議員会館で開催された
『教育AIサミット2025』において
発表をしてきました
テーマは「防災とAI」
青楓館高校さんからは
過去の教育から学び最適な防災を実現するために
『防災ナビゲートAI』が提案されました
このアプリでは
家庭内での話し合いを活発化するために
次のふたつの機能を持たせています
① 防災すべきトピックの選択
「備蓄や準備について」
「被災後の行動について」
家族内で話し合っておくべき内容が
整理されています
② AIによる要約とリマインド機能
話し合った内容をAIが要約して保存します
実際に被災すると電波事情が悪くなり
ケータイがただの箱となりますが
オフライン状態でも利用できるようになっています
本校からは
2年生の辻 姫花さんと山瀬 大貴さんが
AI備蓄品支援アプリ『そなれこ』を提案しました
「備える」×「レコード」で『そなれこ』
被災体験に基づく
実際のニーズを踏まえた機能設計になっています
まずは家族構成やライフスタイルを分析して
必要な備蓄品とその数量を提案します
それはそのままオンラインで購入できます
さらには購入品の賞味期限を管理し
ローリングストックを実現するための
レシピの提案もしてくれます
『AI部』では
これらを単なる提案で終わらせず
自分たちで開発して社会実装させます
野球の甲子園
サッカーの国立競技場
それぞれの部活動には憧れの舞台があります
AI部にもその舞台が準備されています
来る10月10日
大阪・関西万博Expo2025メッセ「WASSE」において
全国大会が行われます
『AI部』がない学校でも
個人でも
出場できます
本校も予選突破を目指してがんばっています
【ソルトレイクより愛をこめて】
災害医療と命の尊さを学ぶアメリカ研修の報告
日本時間21日(木)深夜11時
現地時間同日朝8時
乗り継ぎのロサンゼルス空港に到着いたしました
生徒はみな元気に空港でショッピングをしています
これから羽田空港行きの飛行機に搭乗します
PTA全国大会
地震から 599 日目
豪雨から 335 日目
PTAの全国大会が三重県で開催されています
全国からPTA役員の皆さんが
一堂に会します
震災前に石川県で開催され
その時お手伝いしましましたが
何だか遠い過去の出来事のような気がします
本来PTAの役員の皆さんで
参加すべきところではありますが
現在本校では役員の人選すらままならず
会長さんも
災害復興で手が回らない中無理を言って
お名前だけ入れさせてもらっている状態です
ですので今年は校長ひとりで参加してきました
本校PTAはそういう状態ではありますが
お母さま方で知恵を出し合って
炊き出しなどのできることを
楽しんでできる範囲で活動しています
文化祭にも出店していただく方向です
お手伝いを希望される方は
ぜひ学校までご連絡ください
一日目の日程終了後
伊勢神宮まで足を運んでみました
伊勢神宮には内宮と外宮があります
内宮は天照大神を
外宮は豊受大神を祀った神社です
豊受大神は天照大御神に食事を捧げる「御饌都神」
祭祀の順序に従って
外宮から内宮へ参拝するのが一般的です
伊勢神宮では20年に一度
式年遷宮が行われます
社殿と神宝を新調して
大御神にお遷り願う
神宮最大のお祭りです
これは天武天皇のご発意により始まり
次の持統天皇4年(690年)に
第一回が執り行われました
以来約1300年の長きにわたり伝えられています
次回は令和十五年に第六十三回式年遷宮
その最高潮『遷御』の儀が
執り行われることになっており
すでにその準備が始まっています
輪島高校でも今年秋に
仮設校舎への『遷舎』の儀が
執り行われることになります
不便な仮設校舎への移動であっても
こう言えば何となく厳かな感じがして
新しい時代への期待が高まりますね
『式年遷宮』で取り壊された神殿
そこに用いられていた心柱などの木材は
次の二十年間は神宮へ渡る橋と鳥居
その次の二十年間は伊勢街道に並ぶ神社の鳥居
さらにその後は全国に散らばるお社の改築材として
末永く活用していくのだそうです
【ソルトレイクより愛をこめて】
災害医療と命の尊さを学ぶアメリカ研修の報告
日本時間20日(水)午前9時
現地時間19日(火)夕方6時
ユタ州での生活の最終日が終了しました
今日もBYUに訪れ
午前中は職員の方に
キャンパス内を案内してもらいました
キャンパス内にある建物は
ほぼ人物の名前になっており
大学やキリスト教会に
大きな影響を与えた人だそうです
BYUのオープンキャンパスに来た様な雰囲気でした
その後は学食でランチをとり
BYUの中の売店でお土産を購入しました
学食も売店もビックスケールでした
売店の中には日本のお菓子も売られていました
午後からは
farewell(お別れ) partyを開くための
準備をしました
焼きそば 牛丼 お好み焼きをみんなで作って
お世話になったホストファミリーに振舞いました
明日
飛行機の時間の都合で
家を出るのが早朝4時になります
そのためホストファミリーとお別れをするのが
今晩ということになります
みんなお世話になった宣教師やホストファミリーに
手紙を書いたりプレゼントを用意したりして
最後の別れを惜しみました
またアメリカに行って
みんなと再会することができますように
生徒たちは英語力が向上しただけでなく
率先して自ら行動する力も身につきました
本当に頼もしい限りです
魅力的なアプリを開発するには?
地震から 598 日目
豪雨から 334 日目
夏季補習後半戦が始まっています
9月1日にいきなり学校に来いと言われると
なかなか足が向かなかったりします
そう言った意味で
このアイドリング期間はいいですね
学校に行くのに苦痛を感じている生徒さんは
この期間にとりあえず一回出ておいで
いきなり授業が始まると思うと
気が重くなるけど
友達と顔合わせるだけで
スッと気持ちが軽くなるよ
文化祭の準備に来るだけでもいいから
地震で校舎が傾き使用できない部分が
全体の3分の2を占めるため
現在教室を仕切るなどして
3分の1の校舎で工夫しながら
授業をしています
「北陸SDGs総合研究所」から
武田幸男様と皆口みちこさま
併せて
「株式会社IRODORI」から
谷津孝啓様が訪れてくださり
生徒によるアプリ開発支援に関する
ご提案をいただきました
アプリ開発に携わると
自分が開発したアプリで
多くの人が喜ぶことを実感できます
自己肯定感の高まりを期待できます
よいアプリを開発するための必要条件は
「周りの人を観察する力」だそうです
独りよがりの人に
良いアプリを開発できるはずがありません
人格の形成といった視点でも
大きな成果を得ることができそうです
【ソルトレイクより愛をこめて】
災害医療と命の尊さを学ぶアメリカ研修の報告
日本時間19日(火)午前9時
現地時間18日(月)夕方6時
今日は旅の目的であるBYUに訪れました
まず看護学部の棟に向かいました
BYUの看護学部は教員の数が多くて
学生への指導が手厚いだけでなく
最先端の実習道具や環境が整っていました
銃乱射された現場を想定した
大規模シュミレーション実習が行われました
60人くらいの傷病者役としてボランティアを募って
体や床などに血のりをつけて学生たちが処置をしていきます
学生が看護師になった際にも冷静に対応できるよう
常にリアリティを求めながら行っているそうです
血や吐瀉物にはスプレーで匂いをつけてあります
階段で倒れている患者さんを学生たちで運んだりします
その後は
イエス・キリスト教会の十二使徒定例会のメンバーである
ゲリット・W・ゴング長老の講演を聞きました
現地の方は生涯学び続けることにも一生懸命で
会場はライブ並みに混んでいました
MTCといって宣教師たちを育成する施設を
特別に見学をさせてもらいました
今回の旅にもふたりの宣教師の方に
案内や言語通訳など協力してもらっています
今日も学びが多い一日となりました
明日でユタの生活も最後となりました
生徒たちも私もアメリカロスになりそうです
のと里山海道で「何それ!?」
地震から 597 日目
豪雨から 333 日目
生成AIに関する教員研修を実施しました
SoftBank さんから
5人の講師の先生をお招きしました
実際にAIを活用しての
実践的な研修となりました
昨日『のと里山海道』を走っていて
目を疑うようなものを目撃してしまいました
路肩にパトカーが数台
「事故かな?」と様子を見ながら
横を通り過ぎると
数人の警官に取り囲まれて
身柄を確保されていたのは
猪より大きく牛より小さい
白と茶色のケモノ
バクかアルパカか
そんな感じの
なぜそんなところに?
どこかから逃げ出したのでしょうか?
おとなしい草食動物でしょう
草食動物は
目が顔の両側に
人間で例えるとこめかみあたりに
離れてついています
これは360°ほぼ全方向に視野を確保して
肉食動物に襲われないよう見張るためです
そのため正面から見ると
のほほんとした顔をしています
それでも運悪く襲われた際には
首の筋肉を硬直させて
肉食動物の牙が入っていかないようにする
そんな術も持っています
ヒトにもその名残があって
「危ない!!」と叫ばれた時
思わず首をすくめる動きがそれです
その時の瞬間的な硬さは
牙を折るほどだそうです
それに対して肉食動物の目は
ほぼ正面向きにふたつくっついています
猫の顔を想像してみてください
キティちゃんやひこにゃんは正面から見ても
ふたつの目が同時に見えます
獲物までの距離を瞬時に見分け
正確に狩りをするためです
ひこにゃん恐るべし
さて草食動物と肉食動物の目の位置の違いは
そのまま昆虫の世界にも当てはまります
アブラムシやカメムシなど
草食昆虫はアルパカのように
正面から見るとのほほんとした顔
対してそれを食べるカマキリやクモは
獲物を狙うチーターのように
正面から見ると
なんとも恐ろしい顔をしています
人間にとって
作物を食い荒らす害虫は優しい顔
作物を守ってくれる益虫は怖い顔
考えさせられますね
ところでヒトから見ると害虫のカメムシ
私は生まれつき匂いに鈍感なので
わからないのですが
とても臭いんだそうですね
カメムシの匂いの成分は
ヘキサナールなどのアルデヒド類です
さあ化学選択者たちに課題です
ヘキサナールの構造式を答えなさい
たとえばエタンC2H6 から
Hが2つ抜けて代わりにOがくっついた
CH3CHO(アセトアルデヒド)を
エタナールといいます
ではヘキサンC6H14 からできた
ヘキサナールの構造式は?
別名へクソムシともいわれるカメムシの
匂いの素がヘキサナールだなんて
カメムシはこの強烈なヘキサナールを
脇の下から噴射するのだそうです
人間でいうとワキガですね
しかもまれに自分の匂いにびっくりして
死んでしまうこともあるそうです
憎めないやつです
ここでもうひとつ化学選択者へ課題
ヘキサナールは水に溶けますか?
疏水基 C5H11 と親水基 CHOの
大きさから推測してみてください
であるならば
カメムシの匂いは水で洗って取れますか?取れませんか?
わかりますよね!
このように教科書で学んだことは
実は使いようによっては
生活のあらゆる面で役に立っているのです
「数学なんて日常生活にとって何の役にも立たない」
と豪語されているあなた
自分が勉強したくない
言い訳をしているだけではありませんか?
「数学はスコップです」
誰かが言っていました
それそのものには何の面白みもないのですが
使いようによっては
宝を掘り出すことができるのです
学校で学ぶ全てのことはスコップです
多くのアイテムを高校生活で身につけましょう
【ソルトレイクより愛をこめて】
災害医療と命の尊さを学ぶアメリカ研修の報告
日本時間19日(火)午前9時
現地時間18日(月)夕方6時
今日はまず
福祉広場のWelfare Squareを訪問しました
ここはイエス・キリスト教会(LDS教会)が
所有運営している施設で
食料・衣料・雇用などを通じて
地域社会への支援と自立支援を
提供している施設です
職員と沢山のボランティアで
成り立っています
教会を訪問した際にも思いましたが
現地の人々は自分だけでなく
相手のことも大切にするために考える
献身的な人が多いです
他にもテンプルスクエアに訪問し
オルガニストの演奏を聴かせていただいたり
現在工事中でしたが
ソルトレイクシティ神殿を見ることができました
その後は
アメリカの開拓時代の生活を
観察することができる施設を訪問して
開拓者への理解を深めることができました
本日は本当に多くの施設を
視察させていただきました
明日はいよいよ
目的のBYUを訪れる予定です