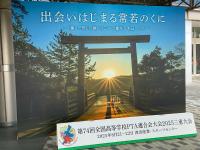校長室より「おこらいえ」
PTA全国大会
地震から 599 日目
豪雨から 335 日目
PTAの全国大会が三重県で開催されています
全国からPTA役員の皆さんが
一堂に会します
震災前に石川県で開催され
その時お手伝いしましましたが
何だか遠い過去の出来事のような気がします
本来PTAの役員の皆さんで
参加すべきところではありますが
現在本校では役員の人選すらままならず
会長さんも
災害復興で手が回らない中無理を言って
お名前だけ入れさせてもらっている状態です
ですので今年は校長ひとりで参加してきました
本校PTAはそういう状態ではありますが
お母さま方で知恵を出し合って
炊き出しなどのできることを
楽しんでできる範囲で活動しています
文化祭にも出店していただく方向です
お手伝いを希望される方は
ぜひ学校までご連絡ください
一日目の日程終了後
伊勢神宮まで足を運んでみました
伊勢神宮には内宮と外宮があります
内宮は天照大神を
外宮は豊受大神を祀った神社です
豊受大神は天照大御神に食事を捧げる「御饌都神」
祭祀の順序に従って
外宮から内宮へ参拝するのが一般的です
伊勢神宮では20年に一度
式年遷宮が行われます
社殿と神宝を新調して
大御神にお遷り願う
神宮最大のお祭りです
これは天武天皇のご発意により始まり
次の持統天皇4年(690年)に
第一回が執り行われました
以来約1300年の長きにわたり伝えられています
次回は令和十五年に第六十三回式年遷宮
その最高潮『遷御』の儀が
執り行われることになっており
すでにその準備が始まっています
輪島高校でも今年秋に
仮設校舎への『遷舎』の儀が
執り行われることになります
不便な仮設校舎への移動であっても
こう言えば何となく厳かな感じがして
新しい時代への期待が高まりますね
『式年遷宮』で取り壊された神殿
そこに用いられていた心柱などの木材は
次の二十年間は神宮へ渡る橋と鳥居
その次の二十年間は伊勢街道に並ぶ神社の鳥居
さらにその後は全国に散らばるお社の改築材として
末永く活用していくのだそうです
【ソルトレイクより愛をこめて】
災害医療と命の尊さを学ぶアメリカ研修の報告
日本時間20日(水)午前9時
現地時間19日(火)夕方6時
ユタ州での生活の最終日が終了しました
今日もBYUに訪れ
午前中は職員の方に
キャンパス内を案内してもらいました
キャンパス内にある建物は
ほぼ人物の名前になっており
大学やキリスト教会に
大きな影響を与えた人だそうです
BYUのオープンキャンパスに来た様な雰囲気でした
その後は学食でランチをとり
BYUの中の売店でお土産を購入しました
学食も売店もビックスケールでした
売店の中には日本のお菓子も売られていました
午後からは
farewell(お別れ) partyを開くための
準備をしました
焼きそば 牛丼 お好み焼きをみんなで作って
お世話になったホストファミリーに振舞いました
明日
飛行機の時間の都合で
家を出るのが早朝4時になります
そのためホストファミリーとお別れをするのが
今晩ということになります
みんなお世話になった宣教師やホストファミリーに
手紙を書いたりプレゼントを用意したりして
最後の別れを惜しみました
またアメリカに行って
みんなと再会することができますように
生徒たちは英語力が向上しただけでなく
率先して自ら行動する力も身につきました
本当に頼もしい限りです
魅力的なアプリを開発するには?
地震から 598 日目
豪雨から 334 日目
夏季補習後半戦が始まっています
9月1日にいきなり学校に来いと言われると
なかなか足が向かなかったりします
そう言った意味で
このアイドリング期間はいいですね
学校に行くのに苦痛を感じている生徒さんは
この期間にとりあえず一回出ておいで
いきなり授業が始まると思うと
気が重くなるけど
友達と顔合わせるだけで
スッと気持ちが軽くなるよ
文化祭の準備に来るだけでもいいから
地震で校舎が傾き使用できない部分が
全体の3分の2を占めるため
現在教室を仕切るなどして
3分の1の校舎で工夫しながら
授業をしています
「北陸SDGs総合研究所」から
武田幸男様と皆口みちこさま
併せて
「株式会社IRODORI」から
谷津孝啓様が訪れてくださり
生徒によるアプリ開発支援に関する
ご提案をいただきました
アプリ開発に携わると
自分が開発したアプリで
多くの人が喜ぶことを実感できます
自己肯定感の高まりを期待できます
よいアプリを開発するための必要条件は
「周りの人を観察する力」だそうです
独りよがりの人に
良いアプリを開発できるはずがありません
人格の形成といった視点でも
大きな成果を得ることができそうです
【ソルトレイクより愛をこめて】
災害医療と命の尊さを学ぶアメリカ研修の報告
日本時間19日(火)午前9時
現地時間18日(月)夕方6時
今日は旅の目的であるBYUに訪れました
まず看護学部の棟に向かいました
BYUの看護学部は教員の数が多くて
学生への指導が手厚いだけでなく
最先端の実習道具や環境が整っていました
銃乱射された現場を想定した
大規模シュミレーション実習が行われました
60人くらいの傷病者役としてボランティアを募って
体や床などに血のりをつけて学生たちが処置をしていきます
学生が看護師になった際にも冷静に対応できるよう
常にリアリティを求めながら行っているそうです
血や吐瀉物にはスプレーで匂いをつけてあります
階段で倒れている患者さんを学生たちで運んだりします
その後は
イエス・キリスト教会の十二使徒定例会のメンバーである
ゲリット・W・ゴング長老の講演を聞きました
現地の方は生涯学び続けることにも一生懸命で
会場はライブ並みに混んでいました
MTCといって宣教師たちを育成する施設を
特別に見学をさせてもらいました
今回の旅にもふたりの宣教師の方に
案内や言語通訳など協力してもらっています
今日も学びが多い一日となりました
明日でユタの生活も最後となりました
生徒たちも私もアメリカロスになりそうです
のと里山海道で「何それ!?」
地震から 597 日目
豪雨から 333 日目
生成AIに関する教員研修を実施しました
SoftBank さんから
5人の講師の先生をお招きしました
実際にAIを活用しての
実践的な研修となりました
昨日『のと里山海道』を走っていて
目を疑うようなものを目撃してしまいました
路肩にパトカーが数台
「事故かな?」と様子を見ながら
横を通り過ぎると
数人の警官に取り囲まれて
身柄を確保されていたのは
猪より大きく牛より小さい
白と茶色のケモノ
バクかアルパカか
そんな感じの
なぜそんなところに?
どこかから逃げ出したのでしょうか?
おとなしい草食動物でしょう
草食動物は
目が顔の両側に
人間で例えるとこめかみあたりに
離れてついています
これは360°ほぼ全方向に視野を確保して
肉食動物に襲われないよう見張るためです
そのため正面から見ると
のほほんとした顔をしています
それでも運悪く襲われた際には
首の筋肉を硬直させて
肉食動物の牙が入っていかないようにする
そんな術も持っています
ヒトにもその名残があって
「危ない!!」と叫ばれた時
思わず首をすくめる動きがそれです
その時の瞬間的な硬さは
牙を折るほどだそうです
それに対して肉食動物の目は
ほぼ正面向きにふたつくっついています
猫の顔を想像してみてください
キティちゃんやひこにゃんは正面から見ても
ふたつの目が同時に見えます
獲物までの距離を瞬時に見分け
正確に狩りをするためです
ひこにゃん恐るべし
さて草食動物と肉食動物の目の位置の違いは
そのまま昆虫の世界にも当てはまります
アブラムシやカメムシなど
草食昆虫はアルパカのように
正面から見るとのほほんとした顔
対してそれを食べるカマキリやクモは
獲物を狙うチーターのように
正面から見ると
なんとも恐ろしい顔をしています
人間にとって
作物を食い荒らす害虫は優しい顔
作物を守ってくれる益虫は怖い顔
考えさせられますね
ところでヒトから見ると害虫のカメムシ
私は生まれつき匂いに鈍感なので
わからないのですが
とても臭いんだそうですね
カメムシの匂いの成分は
ヘキサナールなどのアルデヒド類です
さあ化学選択者たちに課題です
ヘキサナールの構造式を答えなさい
たとえばエタンC2H6 から
Hが2つ抜けて代わりにOがくっついた
CH3CHO(アセトアルデヒド)を
エタナールといいます
ではヘキサンC6H14 からできた
ヘキサナールの構造式は?
別名へクソムシともいわれるカメムシの
匂いの素がヘキサナールだなんて
カメムシはこの強烈なヘキサナールを
脇の下から噴射するのだそうです
人間でいうとワキガですね
しかもまれに自分の匂いにびっくりして
死んでしまうこともあるそうです
憎めないやつです
ここでもうひとつ化学選択者へ課題
ヘキサナールは水に溶けますか?
疏水基 C5H11 と親水基 CHOの
大きさから推測してみてください
であるならば
カメムシの匂いは水で洗って取れますか?取れませんか?
わかりますよね!
このように教科書で学んだことは
実は使いようによっては
生活のあらゆる面で役に立っているのです
「数学なんて日常生活にとって何の役にも立たない」
と豪語されているあなた
自分が勉強したくない
言い訳をしているだけではありませんか?
「数学はスコップです」
誰かが言っていました
それそのものには何の面白みもないのですが
使いようによっては
宝を掘り出すことができるのです
学校で学ぶ全てのことはスコップです
多くのアイテムを高校生活で身につけましょう
【ソルトレイクより愛をこめて】
災害医療と命の尊さを学ぶアメリカ研修の報告
日本時間19日(火)午前9時
現地時間18日(月)夕方6時
今日はまず
福祉広場のWelfare Squareを訪問しました
ここはイエス・キリスト教会(LDS教会)が
所有運営している施設で
食料・衣料・雇用などを通じて
地域社会への支援と自立支援を
提供している施設です
職員と沢山のボランティアで
成り立っています
教会を訪問した際にも思いましたが
現地の人々は自分だけでなく
相手のことも大切にするために考える
献身的な人が多いです
他にもテンプルスクエアに訪問し
オルガニストの演奏を聴かせていただいたり
現在工事中でしたが
ソルトレイクシティ神殿を見ることができました
その後は
アメリカの開拓時代の生活を
観察することができる施設を訪問して
開拓者への理解を深めることができました
本日は本当に多くの施設を
視察させていただきました
明日はいよいよ
目的のBYUを訪れる予定です
万博でのプレゼン動画
地震から 596 日目
豪雨から 332 日目
【ソルトレイクより愛をこめて】
災害医療と命の尊さを学ぶアメリカ研修の報告
日本時間18日(月)午前9時
現地時間17日(日)夕方6時
今日は教会で日曜礼拝に参加しました
一緒に讃美歌を歌ったり
ホストファミリーのベイビーの
祝福を行ったりしました
人々のそれぞれのキリストに対する思いや
命の尊さを感じることができました
昼食はホストファミリーの家で
トルティーヤパーティーをしました
その後、Japanese partyでカレーを作り
用意したプレゼンを発表しました
特に能登の地震の被害を伝えると
現地の人々から驚いたリアクションがありました
早いもので
今日でユタの生活での日程の
半分が終了いたしました
生徒も元気で何よりです
HAB北陸朝日放送で先日紹介された
本校生徒の万博での発表の動画です
https://www.youtube.com/watch?v=QJp4Y6eFfXo
ぜひご覧になってください
ソルトレイクシティの日曜日
地震から 595 日目
豪雨から 331 日目
【ソルトレイクより愛をこめて】
災害医療を学ぶアメリカ研修の報告
日本時間17日(日)深夜1:00
現地時間16日(土)午前10:00
とても良い天気で気持ちが良いです
今日はジップラインとショッピングを
これから楽しむ予定です
ホストファミリーとの交流
とても楽しそうです
ホストファミリーの中には
日本語を勉強している人もいて
日本語で交流しているとのことでした
ツアーに参加している他校の生徒と
これから楽しみます
日本時間17日(日)正午
現地時間16日(土)夜9:00
ジップラインは山の標高が高いところで行い
景色もとても綺麗でした
日本にはない山や自然の景色を堪能することができました
ショッピングはTRADER JOE'Sという
アメリカのスーパーマーケットに入りました
夕食はホストファミリーとBBQを楽しみました
みんなでBBQの準備も行いました
夕食後は明日のプレゼン発表の原稿を読んで
サポーターのカーターさんに
発音などを教えていただきました
みな積極的に現地の方と
交流や会話を楽しんでいて本当に頼もしいです
明日は教会に行き
キリスト教の文化を理解する活動をします
ソルトレイクシティの教育は
この地区で最も進んでいます
1847年先駆者のジェーン・ディルウォースが
キリスト教会会員とその家族のために
開拓者のテントで行った教育が基になっています
現在でも中高生の多くが
何らかの形式の宗教教育を受けているとともに
多くの企業が学校に寄付をするなどして支援しています
教会のあとはJapanese partyを行い
能登の紹介や震災の影響などを
現地の方にプレゼンします
みんなで作ったカレーも振る舞う予定です
ソルトレイクシティはユタ州の州都で
塩湖であるグレートソルト湖に
その名が由来しています
3つの河川から流入しますが
流出河川がなく湖面からの蒸発のため
塩分濃度が高い場所で海水の10倍くらいになります
あまりに高い塩分濃度のため
ブラインシュリンプと呼ばれる
エビの一種しか生息していません