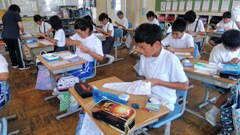好天に恵まれ,8名全員揃って,七ツ島へ出かけました。国土交通省の「のとかぜ」で,1時間程かけて到着しました。入江には,たくさんの漂着物があり,はじめにそれらを回収する作業を行いました。漂着物調査を通して,国外から流れてくる物もあるけれど,6割は国内から出たゴミであることを学びました。その後,水着に着替え,磯で海水浴を楽しみました。アメフラシを見つけて触れている子,船の先からの飛び込みにチャレンジする子,浮き輪でのんびりする子など,思い思いに楽しみました。とても充実した体験学習ができました。金沢港湾整備事務所の皆さん,ありがとうございました。(相神)



輪島沖50kmに舳倉島があります。七ツ島は,ちょうどそのルートの中間地点にある無人島です。この島は,オオミズナギドリなど,海鳥の集団繁殖地となっており,環境省レッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類に指定されているヒトクロウミツバメ,カンムリウミスズメ,ハヤブサなども生息しています。鳥獣保護区に指定されている国有地で,北陸財務局の許可がないと上陸できない島ですので,通常であれば,私たちがこの島に行くことはできません。児童にとって,そういう意味でもいい機会となった,今回の体験でした。ちなみに,この島の鳥ですが,以前人間が放し,その後大繁殖したうさぎに住処(岩場の穴)を奪われ,数が大幅に減ってきているとか。うさぎに罪はありませんが,空しい話です。