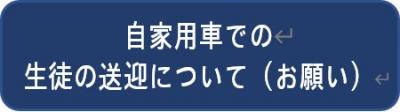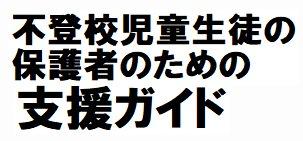924-0864 石川県白山市馬場1丁目100番地
TEL(076)275-2242 / FAX(076)275-9082
学校や生徒の様子を紹介します
優良PTA表彰おめでとうございます!!
本校PTAのこれまでの活動が評価され、優良PTAとして石川県教育委員会から昨日表彰を受けました。これまでのPTAの皆様の本校の教育活動へのご協力・ご支援に改めて感謝申し上げます。また引き続き、生徒のよりよい教育活動の推進のために何卒、ご協力をお願いいたします。
11月5日の表彰式には、PTA会長が出席され、教育長より表彰を受けました。PTA役員・会員の皆様、受賞おめでとうございます!
11月1日(土)学校説明会を行いました
11月1日(土)、本校、第2会議室にて、中学生及び保護者向け対象の学校説明会を行いました。
本校生徒会の生徒による、学校紹介プレゼンをし、その後、校舎施設見学及び部活動見学を行いました。
本校生徒の話を、熱心に聞いていただき、ありがとうございました。
11/1 JR西日本 白山総合車両所 一般公開 イベントに松任高校も出店!
白山総合車両所 一般公開に出店し、松任高校の様子がわかる行事の紹介や部活動の紹介を展示しました。
「こんなものも高校生が作れるんだ。」(3Dプリンターによる本校キャラクターまつのねくんフィギアやパズル)
「この機械、使ってみたい!」
「これ、すっごくかわいい!(美術の授業:ハンバーガーの模型・UVプリンタを利用したトートバッグ)
「これ美術部や写真部ではない生徒の作品?!すごいね!」(映像表現の授業作品)
レーザーカッターを使った松任高校特製キーホルダーやコースター、木製コースター試作で生まれた切粉を使ったサシェ(防臭・湿気取りに使えます!)が当たるガチャガチャも大人気!
また、展示に足を止め、「懐かしいねぇ。」「がんばって!」とたくさんの同窓生が声をかけてくださいました。本当にたくさんの先輩が松任高校を応援してくれているんだなぁと感じる一日でした。


車両所の一般公開のページはこちらです。
いしかわ教育ウィーク:講演「地域とともに考える防災~東日本大震災の経験から~」
いしかわ教育ウィーク期間中の行事として、本日教育講演会が行われました。「地域とともに考える防災~東日本大震災の経験から~」と題し、金沢大学附属特別支援学校長の中澤宏一先生にご講演をいただきました。今回の講演会は、生徒・教職員だけではなく、保護者・地域のみなさまにも公開し、松任高校で一緒に防災・減災について考えてみたいと企画されたものです。中澤先生がご経験をもとにお話しされた大震災とその後の復興に取り組んだ高校生や教職員、地域の方のお話に、生徒も教職員も心を打たれ、会場一同、静かに聞き入った90分でした。講演後の生徒の感想からは、「中澤先生のお話を聞いて人の思いはどんなに小さくても伝染していくんだなと思いました。高校生が地域を励まして活気が戻っていったことを聞いて、高校生から身近な大人にそして地域に気持ちは通じることが分かりました。私たち松任高校生も中澤先生の体験からたくさんの思いをもらうことができて、本当に貴重な体験になりました。震災以外にもこのことは他人事ではなく自分事として活かしていきたい。」「高校生が周りを笑顔にしようという行動力や言動がとてもすごいなと思いました。震災を経験した後だからこそ、この(宮城県の高校生の)行動は本当に印象に残りました。わたしも見習いたいと思いました。」等の感想もあり、わたしたち一人一人が防災を自分事として考える貴重な機会となりました。
11月行事予定
令和7年度第52回県高文連商業部新人競技大会ワープロ競技に参加しました
令和7年10月30日(木)、小松市民センターにて、令和7年度第52回県高文連商業部新人競技大会ワープロ競技に、ビジネス研究部が参加しました。
団体では、参加9校中7位という結果でした。生徒にとって、良い経験となりました。
次年度の県総文大会に向けて、練習を積み重ねていきたいと思います。
いしかわ産業教育フェア2025に参加しました
10月25日(土)、イオンモール白山にて、いしかわ産業教育フェア2025が開催され、本校のビジネス研究部及び2年次総合的な探究の時間観光ゼミの生徒が、商業部会のVR観光動画体験コーナーを担当しました。
生徒は、VR観光動画体験をしてくださった方に、説明しながら、VR観光動画体験をしてもらいました。
生徒も、良い経験になりました。これからも、様々な取り組みにがんばっていきたいと思います。
この取り組みに伴い、パナソニック教育財団、日教弘石川支部、アクサユネスコ協会の助成から、VRゴーグル、360度カメラを購入させていただきました。ありがとうございました。
まっとうまちなか商店街の秋祭りに参加しました
10月12日(日)に行われました「まっとうまちなか商店街 秋祭り」に
2年生総合的な探究の秋祭りゼミが参加しました。
割り箸銃で的を狙う射的を行いました。当日は家族連れで多くの子供たちが
ブースを訪れ、遊んでくれました。本校生徒も子供たちと接し、ブースの運営を
行うことで、学校の中では味わえない様々な学びがありました。
本校のブースを訪れて下さった皆様には、感謝申し上げます。
交通安全教室が開かれました!
プロのスタントマンの方々による交通安全教室が開かれました。
なかなか無なくならない「自転車での事故」を減らすためにも、危険な運転の実演から振り返りたいと思います。
また、自転車に乗ったときには車道を通ることやブレーキをかけたときにすぐに停まれるスピードで運転する大切さを実感しました。
車の運転手からは見えない「死角」に自分がいて車から気が付かないケースや、大型車の内輪差(前輪と後輪の通る道の違い)など、交通事故を誘発させる要因についても理解し、今後の生活で活かせるようにしていこうと感じました。
最初はアトラクション?のように感じた生徒もいましたが、徐々に自分事に考えることができ、交通事故の怖さを実感し、ルールを守ることの大切さを自覚できたのではないでしょうか。
皆さんも、この機会に自分の交通安全感覚を高めるようにしましょう!






本校の防災に関する取り組み
本校では今年度、防災・減災について保護者や地域の皆様と一緒に考える行事を企画しております。
第1弾は、10月18日(土)の文化祭内での催事です。2年生の総合的な探究の活動と連携し、防災ゲームや防災カフェ、起震車・VRゴーグル等が体験できるブースを準備します。
第2弾は、11月1日(土)の教育ウィーク期間中に実施する教育講演会「地域とともに考える防災~東日本大震災の経験から~(講師:中澤 宏一氏)」です。講演会を保護者・地域の皆様にも公開し、みんなで防災について考える機会にできたらと願っております。詳細は添付のチラシをご覧ください。
皆様のご来校をお待ちしております。(参加ご希望の方は、事前のお申込みが必要となります。)