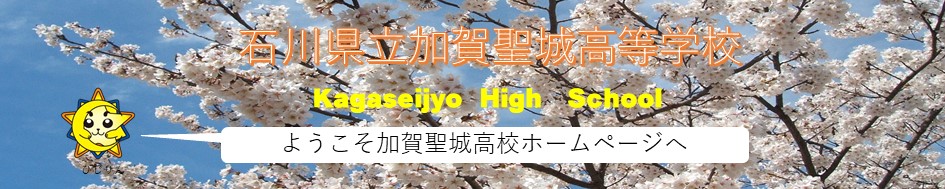2018年6月の記事一覧
第1回事例検討会が開催されました
今年度第1回目は、講師の金沢大学准教授の原田克巳先生をはじめとし、加賀市内の小・中・高・特別支援学校、関係機関等から23名の参加をいただき、活発な質問・意見交換が行われました。
今年度初顔合わせであり、まず自己紹介や簡単な情報交換を行い、その後PCAGIP法による事例検討を行いました。初めてPCAGIP法に参加する方にやや戸惑いもありましたが、次第に参加者の質問が、事例報告者の気づきに優しく迫っていく実感が会場に漂い始めました。
今回は、授業中に他の生徒たちにからかわれたことから、「自分への視線に耐えられない、周囲の視線や言葉全てが自分に向けられているように感じてしんどい」と訴える生徒の事例でした。
支援のアイデアについては、
・「本人の思い込み」なのかしっかりと確認すべき。もし、そのような状況がないとしたら、本人は気持ちを強く持つべきで、他の生徒達と歩み寄ることができない。
・「本人の思い」をどう受け止め、どう対応すべきか。「本人の思い」は主観であり、本人にとっては「事実」であるので、先ず共感し受け止めてから状況を整理してあげると良い。話すだけでなく、文字や4コマ漫画などで表現させると良い。落ち着いた中で客観的に分析して、共に凌ぎ方を考えると良い。
・その相手と接する場面を少なくする。相談室との関係を大切にする。しんどくならないような想像をする、つまり認知の仕方を変えるとよい。
・授業では発表する場面などで配慮できるよう教科担任の情報交換や連携も大切。
最後に原田先生からは、
本人が主観的にそう思っていることが事実で、それを分かってもらえないということになり、相談しなくなりしんどさを自分だけで抱えてゆくことになるので、しっかりと受け止めてから、「でもね・・・」と訊いてあげる。想像の産物と思うことができると楽になる。結局「それで損をすることが無いような想像の仕方をやってみると良いね・・・」と、本人が納得感を持てるように、担任・SCなども関与していくと「信頼性が増す」ので本人もそのように思うようになる。いろいろな考え方があるな、と思ってもらえるようになる。周囲の生徒に(このように)関わっている私の人生しょうもないな、と思えると良いとの助言がありました。
参加された皆さん、ありがとうございました。