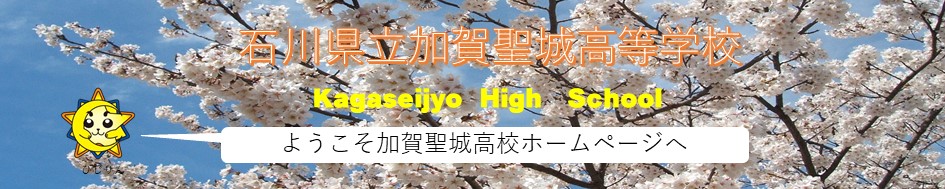2019年1月の記事一覧
第4回事例検討会を開催しました
今回は、昨年度より欠席気味だったが今年度に入り欠席が増えている、高校2年生の男子生徒の事例です。学校では登校時には授業に参加し部活動にも楽しそうにしており、特に困り感はない様子ですが、家庭では何かと本人の気が休まらない状況のようでした。一つは祖父が認知症のため家庭が落ち着かないことがあったようです。しかし、祖父が入院してからも欠席は続き、本人も家庭も努力しているのですがなかなか改善が見られないようです。多くの質問から生徒の様子や家族のことが見えて来て、皆さんから支援のアドバイスが沢山出されました。
・家庭で本人を認めるように、エネルギーを充電できるようにするとよい。本人なりに考えている様子も見え、本人の中にエネルギーが溜まってくると登校できるようなので、家庭で充電ができるような関わり方をしてもらう。きつい言葉を言うと溜まりかけたエネルギーも一挙に消えてしまうので、使わないようにしてもらうと良い。
・本人が前向きになっていることを評価して伝えると良い。その際、可視的データなどで分かり易くしてあげる。家族にもそうしてもらうように伝えると良い。
・前向きになっていることを評価してあげることが大切。自分でどのくらいキャッチ出来ているのか気になる。本人が、自分がどのくらいできるようになっているのかを知ることが大切。何が効いたと思うか、どこを頑張ったのか訊いてみるのも良い。
・中学校でSCと関わったことを良い経験として、今も生かしているのが良い。
・担任が上手に関わっている、SCとの関わりも良い。家庭への支援という点でSSWの活用もして欲しい。母や祖母もSCと関わっていくこともよい。
・中学校との連携も必要、未然防止のためにも中学校時の情報を活用すると良い。
最後に事例提供者からの、「今回祖父のことに気づくのがとても遅くなってしまった。もっと早い段階でどうかできなかったのか(と残念だ)。違和感はずっとあったが、気づけなった。」という感想に対して、
講師より
・何も聞かずに気づくのは無理。学校の先生が家庭のことを聞くことに抵抗があることはよく理解できる。SCとしての経験から、本人に何かあったら、「最近、何か変わったことはありませんか?」と、普段と違うこと、気づいたこと、良いことも(含めて)悪いことも拘わらずに訊いてみると良い。
・「違和感」を感じたその時が契機である。前年度の担任や中学でのこと、家庭のことなど情報を仕入れるとよい。との助言を頂きました。
参加された皆さん、ありがとうございました。

どんどん読んで!!
一部を写真に撮ってみました、気になる本があったら、どんどん手に取ってみて下さい。もちろん、今までの蔵書も沢山あります。


ゆっくりできます!
やすらぎ加賀教室は今年度ここ加賀聖城高校に移転しましたが、以前のような広いスペースが無く、リラックスできる場がありませんでした。そこで、先月学習室にソファを購入しました。一個ずつ外せるタイプなのでレイアウトも変えられます。それに、何といっても「ゴロっと横になることもできる」タイプのものです。
通ってくる皆さんにくつろいでいただけると思いますので、どうぞご利用下さい。