瑞穂小の日常
校長室だよりNO.12アップしました
プール開き
6月12日(火)の3限目に、体育館でプール開きを行いました。
プール開きの式では、校長先生の話の後、プール使用のきまりについて確認し、6年生がプールサイドに出向いて安全を祈願しました。
天気が良ければ、5,6年生がきれいにしてくれたプールにみんなで入って、「水泳シーズン到来!」を実感したかったのですが、気温、水温とも低く、おまけに雨模様。プールに入れないことを知らされた子どもたちは、とても残念そうにしていました。
気持ち良く水泳できる日が早く来ますように。



プール開きの式では、校長先生の話の後、プール使用のきまりについて確認し、6年生がプールサイドに出向いて安全を祈願しました。
天気が良ければ、5,6年生がきれいにしてくれたプールにみんなで入って、「水泳シーズン到来!」を実感したかったのですが、気温、水温とも低く、おまけに雨模様。プールに入れないことを知らされた子どもたちは、とても残念そうにしていました。
気持ち良く水泳できる日が早く来ますように。



校長室だよりNO.11アップしました
プール掃除
6月7日(木)の5・6限目に、5・6年生はプール掃除を行いました。
夏を思わせような暑さの中、額に汗しながら懸命に掃除に取り組んでくれました。
最初は汚かったプールが、見違えるほどきれいになり、6月12日(火)のプール開き以降、気持ち良く水泳ができそうです。
5・6年生のみなさん、ありがとう!



夏を思わせような暑さの中、額に汗しながら懸命に掃除に取り組んでくれました。
最初は汚かったプールが、見違えるほどきれいになり、6月12日(火)のプール開き以降、気持ち良く水泳ができそうです。
5・6年生のみなさん、ありがとう!



老人会、老人クラブの皆様、除草作業ありがとうございました
6月6日(水)、富永地区、鹿島路地区、越路野地区の老人会、老人クラブの皆様に除草作業を行っていただきました。
今回の作業は、例年の植え込みの中や遊具広場に加え、運動場まで範囲を広げていただき、おかげで校舎周辺はとてもすっきり、そして大変美しくなりました。
ご参加いただきました老人会、老人クラブの皆様に心より感謝申し上げます。




今回の作業は、例年の植え込みの中や遊具広場に加え、運動場まで範囲を広げていただき、おかげで校舎周辺はとてもすっきり、そして大変美しくなりました。
ご参加いただきました老人会、老人クラブの皆様に心より感謝申し上げます。




校長室だよりNO.10アップしました
英語番組の視聴開始
本校では、英語教育の推進、英語の日常化を目的として、今月より朝自習の時間に、NHKから配信されている番組を視聴することにしました。低学年は月曜日に「えいごでがんこちゃん」、中学年は木曜日に「世界英語ミッション」、高学年は火曜日に「えいごリアン」を視聴します。
本日、本校トップを切って低学年が番組を視聴しました。視聴後、みんなで中心フレーズを確認し、朝の活動を終えました。


本日、本校トップを切って低学年が番組を視聴しました。視聴後、みんなで中心フレーズを確認し、朝の活動を終えました。


第18回羽咋市小学生陸上競技大会
6月2日(土)、志賀町陸上競技場において、第18回羽咋市小学生陸上競技大会が開催されました。
大変暑い中ではありましたが、本校より参加した4年生以上の34名の子ども達は、自己ベスト記録を目指して頑張ってくれました。
応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、本当にありがとうございました。
3位以上の入賞者は、下記の通りです。
【男子の部】
4年100m 2位 堀越、3位 松生
5年100m 1位 船本
6年100m 2位 多々見、3位 山本
80mハードル 2位 立中
ジャベリックボール投げ 2位 折田
400mリレー 1位 多々見、山本、船本、立中
【女子の部】
4年100m 1位 奥本
5年100m 3位 鈴木
6年100m 2位 堀田
80mハードル 2位 備後、3位 杉浦
走り高跳び 3位 西山
400mリレー 1位 濵名、松生、堀田、西山
校長室だよりNO.9アップしました
校長室だよりNO.8アップしました
校長室だよりNO.7アップしました
校長室だよりNO.6アップしました
校長室だよりNO.5アップしました
校長室だよりNO.4アップしました
校長室だよりNO.3アップしました
校長室だよりNO.2アップしました
校長室だよりNO.1アップしました
卒業式
3月16日(金)
この日は、雨模様の寒い日になりましたが、たくさんのご来賓やご家族の方々にお越しいただいて第12回瑞穂小学校卒業式が行われました。
式では、『威風堂々』の曲に合わせ、卒業生が入場すると体育館全体に温かな拍手が湧き起こりました。立派な態度で卒業証書をもらう卒業生と、それを後ろから見守る在校生が心を一つにして思い出に残る卒業式になるようにがんばっていました。全校が言葉や歌で、思いを伝え合う「門出の言葉」では、在校生からは運動会や絆コンサートなど6年生とともに取り組んだ思い出の数々や、瑞穂小学校の伝統を受け継ぎ、よりよい学校をつくっていくという誓いの言葉が贈られました。また、卒業生からも、明るく笑顔いっぱいの学校にしていってほしいという願いや、これまで支えてくださった見守り隊や地域の方々、そして家族への感謝の思いが伝えられました。
寒い日ではありましたが、 「伝えよう 感謝の思い 見えるよに」をスローガンに、全校で練習を重ねてきた卒業式は、厳粛な中にもそれぞれの思いのこもった温かな式となりました。

この日は、雨模様の寒い日になりましたが、たくさんのご来賓やご家族の方々にお越しいただいて第12回瑞穂小学校卒業式が行われました。
式では、『威風堂々』の曲に合わせ、卒業生が入場すると体育館全体に温かな拍手が湧き起こりました。立派な態度で卒業証書をもらう卒業生と、それを後ろから見守る在校生が心を一つにして思い出に残る卒業式になるようにがんばっていました。全校が言葉や歌で、思いを伝え合う「門出の言葉」では、在校生からは運動会や絆コンサートなど6年生とともに取り組んだ思い出の数々や、瑞穂小学校の伝統を受け継ぎ、よりよい学校をつくっていくという誓いの言葉が贈られました。また、卒業生からも、明るく笑顔いっぱいの学校にしていってほしいという願いや、これまで支えてくださった見守り隊や地域の方々、そして家族への感謝の思いが伝えられました。
寒い日ではありましたが、 「伝えよう 感謝の思い 見えるよに」をスローガンに、全校で練習を重ねてきた卒業式は、厳粛な中にもそれぞれの思いのこもった温かな式となりました。

学校だより3月号アップしました
6年生から伝統を受け継ぐ!(5年生)
卒業式の練習も始まり、いよいよ6年生が卒業するのだなあと実感する日々です。
5年生も6年生を送る会を終えて、また一つ自信をつけ、6年生への階段を着実に上っています。
委員会の企画や全校のお知らせなどでも、5年生が全校の前で話すことも増えてきました。
そんな5年生に、先日、瑞穂小学校の伝統である「先あいさつレンジャー隊」の参加記録用名簿と、委員会活動用のファイルが6年生から託されました。
6年担任の山岸教諭から励ましの言葉をもらい、5年生の子どもたちは「いよいよ来たな。」「よし、がんばるぞ!」と意気込んでいる様子でした。
翌日、児童玄関には、早速ファイルを持って児童玄関前で元気にあいさつをする5年生の姿が見られました。
進んで参加する「先あいさつレンジャー隊」のこれからに、ますます期待が高まります!

5年生も6年生を送る会を終えて、また一つ自信をつけ、6年生への階段を着実に上っています。
委員会の企画や全校のお知らせなどでも、5年生が全校の前で話すことも増えてきました。
そんな5年生に、先日、瑞穂小学校の伝統である「先あいさつレンジャー隊」の参加記録用名簿と、委員会活動用のファイルが6年生から託されました。
6年担任の山岸教諭から励ましの言葉をもらい、5年生の子どもたちは「いよいよ来たな。」「よし、がんばるぞ!」と意気込んでいる様子でした。
翌日、児童玄関には、早速ファイルを持って児童玄関前で元気にあいさつをする5年生の姿が見られました。
進んで参加する「先あいさつレンジャー隊」のこれからに、ますます期待が高まります!



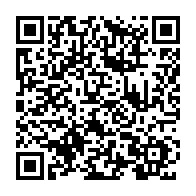 上のQRコードを
上のQRコードを